
『灰のもと、色を探して。』第18話:再創世
もがいている。
気づくのが遅れるほど、ヒューから返ってくる力は弱かった。
慌てて、アッシュは顔を離した。唇の余韻に、心が波立つ。
息を忘れていたらしい。途端に、荒々しい呼吸の音が、躰の内側から聞こえる。
ヒューの顔を、ようやく見る。その表情から、憑き物が落ちている、とアッシュは思った。それは精神に巣食っていた魔だけではなく、躰にまとわりついていたものも、剥がれるように取れていた。
「ヒュー? わかる?」
眼を見つめる。光が宿り、潤っていた。同時に、わずかばかり朱に染まったヒューの頬に、なにかこそばゆさを感じてしまう。
「わかります、アッシュさん」
「そっか」
ヒューの口調に、懐かしさに似た感情を覚え、眼がしらが熱くなってしまう。
「よかった」
安堵が、心に拡がっていく。それから、手をヒューの頭に乗せた。よく戻ってきてくれたと、万感の意を覚えながら、アッシュは頭を撫でた。髪はごわついたままだったが、血が通ったように、色は鮮やかさを増していた。
「ごめん、変なことして」
「いえ、なにも、謝るようなことは」
少し困ったように、ヒューは笑みを浮かべる。こういう表情を、どれだけ望んでいたか。ヒューそのものだ。
「本当なら、再会を喜びたいんだけど、それは後で、だね」
祝うには、人が足りていない。ミリアとギマライは、今もなお戦っているのだ。
「アッシュさん、治癒を」
「俺は大丈夫。それより、ヒューの治癒魔法は、どこまで届く?」
「どこまで?」
「ギマライさんを、回復してほしいんだ。どう? 届く?」
「やります。やってみせます。しかし、ミリアさんは」
「頑丈だから、ミリアは」
気休めだった。あちらの情況はわからない。両方治癒できるのなら、そうしたかった。だが、優先順位をつけるなら、ギマライが先だった。指揮系統の乱れ、といった話ではない。
ギマライは、ミリアのためにきっと無茶をするからだ。
「ミリアは獣属性だし、多少の損傷はなんとかなる。明らかに危ないのは、ギマライさんだ。それに」
片方の眉を、アッシュはあげた。
「ミリアには、ちゃんと近づいて治癒しなよ。困ったことに、ヒューのせいでずっと怒ってるんだから」
アッシュの軽口に一拍遅れて、ヒューは微笑み頷いた。そして、その眼に強い光が宿る。
「いきます」
緑色の燐光が、ヒューから生じていく。
「任せたよ。俺は俺で、やることがあるからね」
何度か、詠唱は切れていた。穴の開いた衣服を縫うように、その都度唱え直しては、繕っていった。一度だけではない。鉄を叩き、剣を作っていくように、ひたすら多重に詠唱を繰り返した。唱え終えた魔法を放たずに保持しておくことも、本来はよくないことなのだろう。その代償か、高熱を額に感じる。
気づけば、塔の頂上にいた。かなり潜っていたはずだから、今いる高さを考えると、とてつもなく上昇したことになる。
方角を見定めようとした矢先、近くの空から閃光が走った。いや、雷だ。それがミリアの戦技であるとわかる。ほかに、こういう現象が起こる原因はない。
あそこに放てばいい、とアッシュは思った。
やるべきことは、やった。あとは、ミリアとギマライに任せる。
火を扱うことで、人間はほかの動物から圧倒的な差をつけ、世界を支配するに至った。熱への恐怖を前にして、なお火炎を自らのものとしたその欲求は、どれだけ高い山に登っても届かない、燃え続ける星に対する情景だったのかもしれない。
太陽は時代によっては神と呼ばれ、万物に平等に、恵みをもたらす光熱を発し続けている。それをこの手で作れたのなら、神以上の存在になることも、きっと容易いのだ。
中には失敗もある。天に届きかけるも、墜落する火が。
「熄岩王の落胤」
吸い取られる。そう思った。発した言葉が見えないなにかとなり、上空へと昇っていく。その飛びゆくものを燃料として、自分の力が奪われていく。
固まる。雲か、と最初は思った。それは勢いよく大気を絡めとり、そして赤く燃えあがる。火炎と呼ぶには、規模が大きすぎる。かつて地に降ったと言われる、隕石のようだった。
不意打ちを狙っていた。だから、合図は出さなかった。
ミリアなら、問題ない。
ミリアは、自分を犠牲にするかもしれない。姉だから、とかではなく、そういう人格なのだと思う。だから不測が生じやすい。
しかし、今は隣にギマライがいる。
「大丈夫だよ、ヒュー。ミリアは大丈夫だ」
ギマライは、ミリアに最悪の結果が起こるようなことは、決して許さない。
火が、ゆっくりと落ちていく。遠くで見るからそう感じるだけで、実際は速いのかもしれない。周囲の風景が、大火を前に赤を映し出す。雷と合わさり、とてつもなく眩い。
「はい、わたしもお二人を信じています」
ここからでは、どうなったかまではわからない。むかいたくとも、ここを離れては再創世が止まってしまうかもしれなかった。もとより、今からむかったところで、なにができるわけでもない。
弾け、鬩ぎ合う音が轟く。自分の魔法ではあるが、その威力に驚愕を隠しきれなかった。まだ、未修の高次的な魔法はある。それらは、いったいどこまでの効果を生じ得るのかと、アッシュは少し震える思いだった。
やがて暴風のような音はやみ、光もなくなり、もとの曇天に戻った。その治まりいく様子を、アッシュはぼんやりと眺めていた。
「ゾヴは、消滅しました」
瞳を、ヒューは閉じていた。
「わかるの?」
「わたしは眷属で、彼は天使ですから。繋がっているものが、途絶えています」
「そっか」
そういうものなのか、と思う。どことなく、ヒューは声の響きに寂しさを滲ませていた。その理由を訊くことはしない。ヒューにとってのゾヴは、敵ではないのだ。仲間であるアッシュたちを優先する。彼女は、そう決断したにすぎない。
今になって思えば、斃せるのか、という迷いはずっとあった。ヒューの言葉を聞いてさえ、本当にゾヴが消えたかどうかわからない、と疑ってしまう。
それでも、ゾヴはもういないのだろう。信じられないことだが、いないのだ。
ふと、右腕に違和感ができていた。痛みが引き、動かせるようになっている。
知らぬ間に、ヒューが治癒魔法を使ってくれていた。
「さすがだなあ、その治癒は」
「いえ、それよりも」
「待った。その先は言わなくていい」
手で、ヒューを遮った。
「ヒューは、なにも悪くない。あえて言うならゾヴのせいだけど、きっとあいつには、あいつなりに思うところがあったんだと思うよ」
ヒューの眼から、涙が溢れていた。その粒は、とめどなくて大きい。
「なんで、泣いてるんでしょう、わたし」
「さあ。泣くことに、理由はいらないんじゃないかな」
「なんですか、それ。言っていることが、わかりません」
「俺も、自分で言っていて、よくわからないや。そうだ、ヒュー、お願いがあるんだけど」
頬の濡れを気にせず、ヒューはこちらを見てくる。
「敬語をやめてくれないかな?」
「急に、なんの話ですか」
「急じゃないよ。ずっと考えていたけど、言う機会がなかっただけで」
「なら、なぜ今になって」
「唯一、魔物のヒューにもいいところがあって、それは敬語じゃなかったこと」
「そう、でしたか?」
「うん。だから、そこは戻さなくていい」
アッシュは、不服そうな顔を作ってみせた。風が、わずかに時間を流す。塔の上ではあったが、不思議と風は強くなかった。風だけではない。世界全体が、止まってしまっているような感覚があった。
まるで、嵐の前であるかのように。
「はい。いや、うん。わかったよ、アッシュ」
二人で笑った。
「各座標に信号の送信完了。大気調整、問題なし。再創世」
大地全体に鳴るような声が聞こえる。力が抜けそうになっていた自分を、アッシュはかろうじて引き留めた。
「注意。使徒は、離脱を推奨します。強制的な帰還は、思わぬ事故の可能性を高めます」
「アッシュ、もう大丈夫だよ。世界は変わる。もう一度、やり直せるんだ」
遠くを見ながら、ヒューは呟く。砕けた口調が、うれしかった。
「終えるべきことを、終えられた。けど、わたしが思っていたより、感慨はないものなんだね」
「俺も、まだ疑っている自分がいるよ。でも、なにかやりたいことを終えた時ってのは、案外その程度なのかもしれない」
ヒューを助けて、再創世もできた。しかし、達成感のような感情があるかと言えば、なかった。自分を縛っていたものが、解けたような思いがひとつあるだけだ。
「ミリアに、会いに行かないと」
「ううん、その必要はないよ、アッシュ」
「なんでさ」
「また、会えるから」
なにを言っているのか、わからなかった。問おうとした時、ヒューの視線の先に、小さな筋が見えた。地上から少しずつ拡がり、灰色の雲にまで達している。
その筋が、みるみる太くなっていき、その輪郭を露わにする。
渦巻く気流だった。
「竜巻、なのか?」
「あれは、再創世のひとつの過程。この世界を構築するすべてのものを、一度回収して、それから、適切に配置していくんだ」
気流は、自然災害のように、遠方の山を削りはじめていた。通りすぎたあとには、なにも残っていない。悪夢に似ながらも、その光景はどこか神々しさを含んでいた。
木々のざわめきと、折れていく音。そして気流の唸りが、次第に増していく。
そして気づく。気流は雲を吸いこみ、空を曝け出していた。
朱に染まる空。なんのことはない、アッシュの世界では日常として見あげる、夕焼けだった。
しかし、美しかった。
ヒューが、こちらを振りむく。その背に、赤い光が当たる。
「空って、こんな色なんだ」
感動か落胆か判然としない、ひたすらにまっすぐな声だった。
「夜になる前は、こういう色になる」
ヒューの躰が、わずかに浮いていた。嫌な予感に、アッシュは思わずヒューを抱きとめた。
「アッシュ、これじゃ、空が見えないよ」
「ヒュー。あの気流はヒューも」
「いいんだよ、アッシュ。わたしだって、この世界の一部なんだから」
気流の方へ引っ張られていくように、ヒューの躰は浮かびあがる。抱いていなければ、すぐにでも空へ飛んで行きそうだった。
「ミリアのところまで、連れて行く」
声に涙が滲む。
「間に合わないって」
「駄目だ。それじゃあ駄目なんだよ」
悪あがきだと、わかっている。それでも、腕を離すことができなかった。
「アッシュ、よく聞いて?」
耳元で、ヒューが囁く。
「わたし、本当にうれしかった。みんなに会えて、旅ができて。みんなで危ない目に遭って、おいしいものを食べて。魔物になっても、みんなはわたしを救ってくれた」
「うん」
「これは、村にいたままのわたしでは、絶対に経験できなかったこと。そして、ほかのだれでもない、自分だけのもの」
「うん」
「でも、満足はしてない。全然ね。だからアッシュ」
寄せていた顔を離し、見つめ合う。
「また会おう」
きれいな笑顔だった。跡はあっても、涙ひとつ流れていない。
「うん」
アッシュも笑顔を作り、そして腕を離した。涙は、流してはいけない。
「会おう。また、みんなで」
柔らかい感触を、後頭部に覚える。色丸が、背中の羽根をはためかせながら、その顔を当ててきていた。怪我はなくなっているようだ。
「お前、ちゃんと飛べるのか」
鳴く代わりとでもいう風に、色丸はアッシュの頬を舐める。
「泣くなよ、小僧」
声ではないが、そう色丸に言われたような気がした。
「別に、泣いてないだろ」
ひとつ、色丸はうれしそうに吼えた。
「ありがとな、色丸」
色丸はアッシュをくるりと周り、そしてかすかに上昇したかと思うと、凄まじい勢いで気流の方へと飛び去っていった。
「わたしも、色丸に続かなくちゃ。じゃあね、アッシュ」
最早気流は颶風と化し、視界の一面を埋める壁となっていた。
突如、腕輪が淡い光を帯びる。自分たちもそろそろ時間切れのようだ。
ヒューの手が、頭に置かれる。撫でられていた。
「本当に、あなたの髪は、この空の色なのね」
手が離れた。アッシュはその手を、掴むことはしなかった。
しばらくの、別れでしかない。
遠くなっていくヒューは、手を振ることも、またアッシュを振り返ることもなかった。

ーーーーーーーーーー
こちらのイラストは、朝日川日和様に描いていただきました。
改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
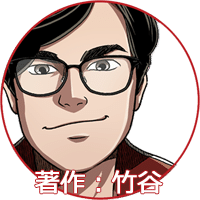
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
