
『灰のもと、色を探して。』第9話:少女二人
やわらかさとあたたかさを、背中から感じる。
来た時に比べれば、いくぶん空は暗がりを見せていた。
「寝ていいからね、ヒュー?」
「はい。ありがとうございます。重くないですか?」
「まったく。やわらかくて気持ちいいくらいよ」
彼女の眼は、閉じているようだった。いかにも眠そうな声が、耳裏から届く。もとの世界の自分だったら、いかに女の子で軽いとはいえ、背負った状態で悠長に歩くことなどできなかった。灰の国ならそれも容易なのだと、身をもってわかる。
斧は置いてきていた。捨てた、と意思表示をしない限り、斧は手元にいつでも戻るのだと、ヒューは言っていた。確かに、見えない糸で繋がっているような妙な感覚が常にある。
西方へと、歩いていた。廃墟はもう遠くにあり、大きな道を進んでいる。慣れてしまってはいるが、道の整備は当然なされておらず、灰が積もって荒れるに任せている。かろうじて道と判別できるのは、街灯らしきものが等間隔にあるからだ。それも、柱が曲がっていたり、先端が取れていたりして、夜を照らしてくれるとは思えなかった。
結局ヒューは、廃墟から少し離れたところにいた。ギマライの言った通り、魔物と遭遇することを恐れて、平坦な場所に移動していたのだ。
ミリアたちが獣と呼んでいたものは、灰の国では魔物と呼ばれている。動物とは異なり、使徒に仇なす禍々しい存在。大きさも種類も多様で、使徒を手助けする眷属とも、当然に敵対している。
「ギマライさん、次はね、あの鳥を操ってみて」
弟は先ほどからずっとあんな風だ。ギマライとともに、ミリアの少し先を歩いている。色丸は、短い脚を懸命に動かしながら、ミリアの隣を維持していた。
「ちょっと待って、あれだね。よし、いくよ」
右手を開いて前面に押し出すと、ギマライはなにかを引っ張るように、掴んで戻した。
「できた。それ」
鳥が、こちらを見る。飛んだかと思うと、弟の肩にとまった。
「すごい。これ、本当にギマライさんがやってるの?」
「そうだよ」
弟の顔へ近づくと、鳥は素速く鼻を突いた。痛がる弟を見て、満足そうにギマライは笑う。
「攻撃も可能、と」
「ひどいなあ。俺で試さなくとも」
「頼みを聞いてるんだから、こっちの頼みも聞いてくれないとね」
拘束していた縄が解けたかのように、鳥が飛び立つ。
「でも、ギマライさんは本当にすごいと思います」
「あまり褒めない方がいいと思うわよ、ヒュー」
「数ある魔法のなかでも、操作魔法を先天的に扱える方は、ちょっと異常です」
ギマライの魔法は、操作と言い、文字通り生命を操ることができるらしい。石や風といったものは対象外で、動物や魔物、練達すれば眷属も意のままに動かせる。
使徒を操ることも、魔法の極致として習得できる。ヒューはそう説明した。
「まだ、小さい動物しか従えられないけどね。重さみたいなものを、操る対象に感じるんだ。持ちあげるのと、同じなのかもね。鳥や魚は軽めだけど、ミリアは重い」
「はあ? 操ろうとしないでよ」
「冗談だって」
心なしか、ギマライは息があがっているようだった。旅路を進めながら、少しでも鍛錬を積むために、道中のさまざまな動物に魔法を放っている。
「それにしても、さっき教えてもらったように、色丸にはまったく通じないんだね」
「はい。色丸さんは、操作魔法を使用する使徒に対する、歯止めですので」
使い魔、とヒューは呼んでいた。どんなに魔法の技術が向上しても、決して操れない存在。それが常時近くにいることで、使徒は自らの操作が万能ではないと再認識するらしい。
「使い魔ね。みんな、こいつと同じかたちなのかい?」
「いえ、使徒に合わせて、十人十色に変わります。ギマライさんの心理をなにか読み取って、使い魔は羽の生えた犬になりました」
「なんだって。ううん、これも誤作動なんじゃないのか」
納得いかない表情で、ギマライは色丸を見据える。その視線が気に入らないのか、色丸は顔をそむけた。その様子に、ヒューはくすくすと笑う。
ヒュー見つけた時を、ミリアは思い出す。彼女は両足を揃えて曲げ、ただ座っていた。頭から足先まで、灰を積もらせたままで。まるで石像が、雪の一晩を越えた姿のようだった。
正確には、会話していたのだ。
「ゾヴは、違うと言っています」
ヒューにだけ、話しかける声。それをヒューはゾヴと紹介してきた。そのゾヴと、ミリアたちが元の世界に戻ったあと、ヒューは一睡もせずに質疑応答をしていた。降灰への対策もせず、躰をわずかたりとて動かさず。
灰の国に生じている問題を知悉し、使徒を導き、現状を打開するために。
「ヒュー、道が分かれてるよ。どっち?」
先を行く弟が、こちらを見返り大声を立てる。生まれてから旅をしたことがない弟にとっては、楽しくて仕方がないようだ。
もっとも、それはミリアにとっても、同じことだ。
「右です」
「右だってさ」
気張れないヒューの代わりに、声を張る。近寄ってもミリアたちに気づかないほど、あの時のヒューは集中していた。弟が眼前で騒ぎ、やっとのことでゾヴとの会話を終わらせた。その後、ヒューはミリアたちがいることにひとしきり驚き、それから自らの躰に積もった灰をはたいて落としていた。寝ずに夜が明けてしまったことも、わからなかったようだ。
「観光気分だなあ、アッシュは」
ギマライのことを、この一大事に使徒は多ければ多いほどよい、とヒューは快く受け入れてくれた。ゾヴも同意している、と言い添えて。そして、西にむかうことを、頼んできたのだ。
遠く西にある、造物主の石庭。
ゾヴが声を発している場所であり、使徒がそこに行くことで、灰の国に充満してしまった誤作動を元に戻せる。
この世界を再創世し、誤作動は正されなければならない。そのために、ミリアたち使徒が必要だ。
再創世、という言葉を、ヒューは用いた。
ただ闇雲に調査を進めるより、なにか目的があった方がいい。また、灰の国が完全な状態でないのなら、それを回復することは、発掘者として当然すべきことだ。ギマライはそう判断を下し、ヒューに応じた。そして、躰が固まり、眼に隈を作ってしまったヒューを、ミリアは背負った。
「空から、明るみが消えてきたわ」
「ヒューの寝床を、そろそろ探すべきだね。アッシュ、止まってくれ。今日はここまでだ」
ミリアの呟きを、ギマライが受ける。立てた仮説が正しければ、日没の近づく今、そろそろ灰の国から離れなければならない。
「アッシュと二人で、整えてくれない? わたしはほら、両手が塞がっているし」
手をあげ、ギマライは了承の意を示す。そのまま、弟のもとへ歩いていった。
「今日は、ちゃんと寝るのよ、ヒュー?」
「はい。ゾヴに寝かせてくれるよう、お願いします」
「迷惑な話。ねえ、わたしの声はゾヴに届かないの? 寝かせなさい、と言いたいんだけど」
「伝言することは、できるのですが」
ヒューは、申し訳なさそうに苦笑する。ゾヴが上で、ヒューが下となっていると感じるのが、どことなく嫌だった。
「ゾヴの声は魔法ではなく、天使と眷属間の連絡網を利用しているので。彼も、ミリアさんたちの来訪は感知できても、話しかけることはできないみたいです」
「迎えに来ればいいのに」
「すみません。彼は天使であるため、役割も大きなものとなります。造物主の石庭を管理する彼は、そこから動けるようには作られていません」
「ヒューが謝ることじゃないでしょ」
「そうですね」
「ひとつ、訊いてもいい?」
「なんでしょうか?」
「ヒューはどうして、あんな廃墟にいたの?」
言葉に詰まるのが、わかった。尋ねてはいけないことだったのかもしれない。
「答えたくなかったら、いいんだけどね。ただの興味本位だし。でも、なんだろう、話したかったら聞くよ? 男たちも払ったし、女同士の秘密ってことで」
おそらく、ギマライは勘づいている。ヒューと話したいことがある。それを察して、なにも言わずに寝床を探しに行ったのだ。
街の女性から人気が高いのも、こういう気配りが要因のひとつなのだろう。
「簡単に言えば、わたしも誤作動を起こしていたんだと思います」
ぽつりと、ヒューは言った。喜怒哀楽は感じられず、ただ静かだった。
「わたしの住んでいた村は、貧しくて。食べ物も満足になく、住居は脆く、服も毎日同じものを着ていました」
やはり、悲しみはない。どちらかというと、故郷を語るヒューの声は、あたたかな響きを帯びていた。
「ほかの眷属たちのように、このまま老いて、消えていくものだと思っていました。そういうものだと、思っていました」
「うん」
「きっかけは、結婚でした」
耳慣れない単語に、ミリアはむせてしまう。自分より幼い少女から、結婚の話が出てくるとはまったく考えていなかった。むせる振動が、ヒューに伝わっているのだろう。彼女は少し笑った。
「ミリアさんの世界では、早いのかもしれませんが、わたしの村では、わたしくらいが適齢とされます。親が持ってきた話でした。隣村の裕福な青年で。よい条件だったと思います。なぜ、その彼がわたしとの縁談に乗り気だったのかは、わかりませんが」
かわいいからに決まっている、とミリアは内心で口にする。
「結婚すべきだと、そうしなければならないと、思いました。彼の財力は、村を潤すのに充分でしたから。周囲の、なにより、親の期待に応えなければと、言い聞かせました」
「でも、できなかったのね」
「はい」
ヒューは、深く呼吸をした。
「婚前に、互いの家族が集まって食事をするのが、村の習わしです。その前日の夜、眠れなくて外に出ました。真っ暗な灰の空を見あげて、ふと思ったんです」
ミリアは、つられて空を仰ぐ、月や星々のない夜は、ミリアが想像するより暗いのだろう。日没とともに帰らざるを得ない自分には、実際の暗さはわからない。
「灰のない空を、見てみたいって」
したたかな意志を秘めた、声だった。
「太古、天に灰はなく、日月の輪、そして星々の流転が空を賑やかす。おとぎ話のように、聞かされていました。忘れてはならない、と昔の眷属たちは考えたんでしょうね。どこか遠くへ行けば、いつかはそんな空を眺められると思いました。まあ、今となっては、世界全体が灰の下にあると、ゾヴから知らされてしまったわけですが」
「それは、残念ね」
「その夜に、家出をしました。食事会のため、と親が用意した食糧を盗み、隣村の方向とは逆に。どれくらい歩いたのかわかりませんが、ある日、前方に廃墟が見えたんです」
「じゃあ、きっと今ごろ、ご両親や村の人たちは」
「探しているかもしれません。わたしは、あの村の歴史上、最も迷惑な村人ではないでしょうか。申し訳ないことをした、と謝りたい気持ちでいっぱいです」
そんなことない、とは言えなかった。多分、ヒューはただミリアに聞いて欲しいのだ。
「ですが、悔いはありません」
ヒューも、空を見ているようだった。
「正直、恐怖はありました。村の外に出たことのないわたしが、どこまで行けるのか。魔物に襲われて、襤褸のように果てる。大自然に囲まれ、ひとり孤独に躯となる。村を出てから、これまでの自分がいかに安全に生きてきたのか、嫌というほど知りました」
なにか、胸に深く刺さるものが、ヒューの言葉から発せられていた。眼じりに浮かんだ涙で、ミリアはあげた顔を戻せない。
「でも、死んでしまったとしても、よくない事態になってしまっても、それが自分で選んだ生き方だったと、胸を張れる気がしたんです。自分で決めて、生きたのだと」
この小さい躰で、ヒューは自ら覚悟を決め、判断をしている。ミリアは、少女と自分を比較して考える。数年前、ミリアはスミスに促されるまま、発掘者として働きはじめた。
言われたから、やっただけだ。
そこには、覚悟も決断もない。本当にやりたいことはこれではない。もっと違う自分があるのではないか。だれかから与えられてばかりなのに、不満ばかり持っていた。
過去形ではない。今もそうだ。
「いったん、降ろすね?」
同意を得ないままミリアが屈むと、ヒューは降りた。振り返ると、不思議そうな表情で、ヒューは首を傾げてミリアを見ている。そのまま前へ進むと、ミリアはヒューを抱き締めた。あまり強くしないよう、包みこむように。

「ミリアさん、どうしたんですか」
慌てた声を、ヒューは出す。
「なんだろう、わかんない。こうしたくなっちゃった」
突然、思いもよらないところから、気づかされることがある。自分の甘さ、そして弱さを。本来、それは身悶えるような苦しみがあると思っていたが、なぜだか、少女に対する愛おしさが、ミリアに満ちていた。
「ありがとう。ヒューはすごいね」
自然と言葉が紡がれる。愛おしさは、気づかせてくれたことに対する感謝だった。それを、ヒューにしっかりと伝えたかった。そして、敬意を表したかった。
「いや、わたしはなにも。ただ、無謀なだけです」
腕の中で、ヒューは照れたように微笑む。ミリアも自然と、笑みが浮かんでしまう。そっと頭を撫でると、ヒューはますます恥ずかしそうにした。指に繊細な金色の髪が絡む。弟の髪はやはり硬いんだなと、妙なことを思った。
背後に気配がした。
「ミリア、近くに魔物が。と、それはどういう状況?」
「いいところだったのに。ギマライ、あなた案外そういうところがあるのね」
ギマライの声に、ミリアはヒューを抱いたまま振り返った。宙に足が浮き、回るヒューから変な声が漏れる。
「見てわかると思うけど、ヒューの抱き心地は最高なの。で、魔物の数と方角は?」
「複数。方角は」
瞬間、斜め前方に赤い光が出る。炎だった。距離としては少し離れている。
「退け、とアッシュには言ったんけどね」
弟が魔法を使ったようだ。困ったように、ギマライはこめかみのあたりを指でさする。ただ、交戦状態に入ったことで、その声色には緊張が含まれていた。
「ギマライは、ヒューを見てもらっていい?」
「わかった。申し訳ないけど、俺の魔法は、まだ実戦に耐えない。アッシュは任せたよ」
「ええ。ヒュー、ちょっと待っててね」
腕を解くと、わずかに寒さを覚えた。ヒューは、先ほどまでと変わり、その表情に翳りを見せている。
「あの、ミリアさん」
「大丈夫」
遮るように、ミリアは返した。ヒューは今、先日の光景を思い出しているのだろう。ミリアが魔物に倒され、いいようにされていた場面を。彼女に怖い思いをさせ、不安の種を残してしまった。
不甲斐ない。悔しい。高まりゆく負の感情を、ミリアは好きにさせた。すべてを力へと注ぎこむために。
繋がっている感覚を意識して、念じる。斧は右手に現れ、握られていた。強く、ただ強く握る。重さが気持ちよかった。
「もう、負けないから」
脚を曲げると、ミリアは大きく跳躍し、弟がいるところへむかう。
学べ。そう言い聞かせる。知っているだけでは駄目なのだ。技の組み合わせを考えろ。敵の反応を想定しろ。
上段からの斬りおろしは、重力を味方にしている分、敵に与える損傷は大きい。しかし、避けられやすく、その時こちらは無防備になる。対して横薙ぎは、比較的躱されない。上へ跳ばれたら、そのまま斬りあげればいい。回転を増やせば威力も増すが、斬りおろしと同じく、はずした場合の危険性は高い。時と場合を考慮し、使い分けるべきだ。
戦いは、動きの連続性を意識することで、まったく別のものとなる。ミリアは己のなかで、急速に視界が拡がっていく感覚を覚えた。
「アッシュ」
着地と同時に、魔物の注意を惹くためにも、ミリアは大声を立てる。
前面に、魔物の群れと弟がいた。
数える。五体。うち、人骨のみで立ち、瞳が怪しく紫色に光っているものが四体。スミスの背丈の三倍はありそうな巨漢を、一層肥え太らせたのが一体。苔むしたような緑色の体躯で、お世辞にも、この世のものとは思えなかった。ミリアの声に反応したのか、五体の視線はこちらに集中していた。
人骨は剣と盾を、巨躯はその身と同等ほどの棍棒を、得物としているようだ。
別に、三体の人骨が炎に包まれ焼かれている。弟がやったのだろう。
「姉ちゃん、遅いよ」
弟は近くの木の枝に立ち、両手から炎を出していた。
「ギマライの指示を無視して、勝手に戦ったんでしょうが」
言いながら、ミリアは前へ出る。すかさず人骨が二体、走り寄ってきた。剣を振りかぶったのを見て、短く息を吐き、ミリアは斧を横に振る。二体とも、胴体から二つに分かれていた。その勢いのまま回転し、ミリアは高く飛んだ。次の一体へ、斧を放り投げる。当たり、砕ける音とともに人骨はその場に斃れた。斧は、なお直線に空間を貫き、ミリアの着地に少し遅れて地面に刺さる。
「姉ちゃん、斧が」
「わたしはいいから、この大きいのを攻撃して」
巨躯が、棍棒を構えていた。斜めから振りおろされる。横に跳んで、ミリアは避けた。衝撃で大地が割れる。しかし、速くはない。人骨に比べると、動作は緩やかだった。
いくらか俊敏な人骨は、ミリアが相手すべきだと思った。残す一体は、巨躯の裏側にいる。
ミリアは巨躯の眼前に出る。飛ぶと、渾身の力で、巨躯の顔に拳を数発放ち、そして蹴った。
硬い。
損傷は、与えられていないと思った。姿こそ人間に近いが、皮膚はまったく別ものだった。しなる鉄を、蹴ったような感覚だ。
巨躯が、憎悪を宿した眼でミリアを見る。棍棒を握っていない手で、ミリアは掴まえようとしてきた。それでいい、とミリアは思った。
ミリアは、巨躯の頭に手を乗せると、そのまま飛び越えた。眼下に人骨を捉える。右手をあげると、手もとに斧が現れた。両手で握り締め、上空から人骨を断ち割る。斧は、深く地面に刺さった。
「残すは、そいつだけだね」
斧を引き抜くと、ミリアは距離を取った。
「アッシュ、なにもしてないじゃない。しっかりしてよ」
「え、ああ、ごめん」
話しながら、横に歩く、予想通り、巨躯の眼はミリアを追いかける。先ほどの打撃に、腹が立っているのだろう。好都合だった。弟を巨躯の死角に入れた。
斧で斬れるかどうか、半疑だった。ただ硬いだけなら両断できるかもしれないが、あの皮膚の質が厄介だった。摩擦が減り、滑れば、与える損傷は小さくなってしまう。
「飛べ、火尖剣」
巨躯の肩が燃えあがる。呻きながら、巨躯は叩いて火を消した。
弟の魔法、火尖剣は、投擲の動作を必要とする。枝の上という不安定な場からでは、満足に投げられない。そして、人骨と異なり、巨躯には効果が薄いのだろう。炎で包むには、躰が大きすぎる。
「火尖剣は、こいつには通じないわ」
巨躯は、苛立ちを発散するように、棍棒を振り回す。その膂力により生じる風が、ミリアまで伝わってきていた。喰らえば、ただでは済まないと思った。
理想は、まず武器の破壊だ。次に、足に損傷を与えて倒れさせる。満を持して、頭部を斬り飛ばすべきだろう。
そのためにも、弟の炎は欠かせない。先ほどの反応から、巨躯が火を嫌うことがわかったからだ。そして、あの皮膚に火傷を負わせられる、ということも。
皮膚が焼けていれば、斬撃は容易に通る。ただ、それには火尖剣では不足していた。
手数か威力か。どちらかが必要だ。
「姉ちゃん。ちょっと時間が欲しい。大きな炎は、長く詠唱しない駄目だ」
「了解。頼むわよ」
巨躯との距離を詰める。どこからでも斬りかかれる間合いではあるが、自分が相手だと、示しておきたかった。応じて、巨躯はこちらを見てくる。心なしか、にやついているように見えた。情欲めいた視線に、ミリアは這いずってくる不快感を隠せず、眉をひそめる。
左前方に跳ぶと、棍棒を斬った。浅いが刃は通る。そこらへんの木を抜き、枝を削いで幹だけにしたような、無骨な棍棒。鉄製でなくてよかったと、ミリアは思う。何度か斬撃を叩きこめれば、破壊できるだろう。そうすれば、ほぼ勝てたも同然だ。しかし、予断を許してはならない。
常に、相手が自分より強いと考える。結果が確定するまで、気を緩めてはならない。だれしも、奥の手を持つものだ。
巨躯の、体型に比すれば短めの足が動いた。蹴りが来る。ミリアは斧の刃を立て、その場に伏せた。上を、風圧が過ぎる。立ちあがる。斬れたと思ったが、巨躯の足に傷はなかった。
「腹立つなあ、もう」
時間稼ぎとはいえ、少しは損傷を与えておきたかった。その思いを嘲るように、巨躯は笑みをこびりつかせている。
もう一度、足があがった。しかし、蹴る動作ではなく、真横に、自らの頭よりも高くあげていた。そのまま、まるで地面を蹴りつけるかのように、足を落とした。
轟音。直後、大地が隆起した。踏まれた位置から同心円形に拡がると、土が剣のように突き出てきた。真上に飛ぶ。土の剣は強度がないのか、すぐに崩れてなくなった。
視界の左側に、影が来ていた。それが、棍棒だとわかる。
飛ばせて打つ。これが、巨躯の本当の戦い方か。ミリアは、斧の柄で棍棒を受け止めようとする。多少の痛みを覚悟し、息を吸い、止めた。棍棒の描く流線が、とても緩やかに見えた。
いや、実際に遅いのだ。かと思うと、巨躯の右腕は動かなくなり、棍棒がその手から落ちる。
ミリアは着地し、巨躯は左手で顎を掻きながら、怪訝そうに棍棒を見つめていた。
右腕は、主人を失ったかのように、だらんと巨躯にぶらさがる。
なにか視線を感じる。見やると、色丸がいた。今までどこにいたのか、と思い、そして息を呑む。
普段は線のような眼が、円のように見開かれていた。その眼球は、赤黒く染められ、まっすぐに巨躯へとむけられていた。
「打ち据えろ、散尾火」
弟の声に呼応して、巨躯のまわりに火炎が生じる。火尖剣よりも、激しく大きな炎だった。巨躯は、突如現れた火炎に驚き、呻き声を立てる。
炎が細く分かれる。十をゆうに超える数となった炎は、それぞれが弧を描くようにまとまり、素速く巨躯を打ちはじめた。
尾撃のようだった。消そうにも、焼かれたと思えば離れる。絡まった炎は、縄が解けるようにはずれる。火炎の鞭が、巨躯を翻弄していた。
ミリアは跳び、旋回する。巨躯にまとまりつく炎ごと、足に斬撃を加えた。斬った、という感覚を得る。巨躯は一際大きな声で吼えると、這う火炎をそのままに、ゆっくりとその場に倒れこんだ。
合図をしたわけではなかった。それでも、弟の呼んだ炎は、巨躯の頭部に集中する。高く飛び、回転を足して斧を振りおろす。
「断ち切れ、四漣」
斬撃を四つ与える技。初撃の威力が強いほど、効果は増す。首を飛ばした。そう思った時、巨躯は全身から蒸気を出して、溶けゆくように消えていた。
斧を背中にかける。弟が木から降りて、寄ってきた。
「姉ちゃん、強すぎる」
「そう? それよりアッシュ、いい魔法だったわ」
「どうしても、時間を取っちゃうなあ。練習すれば、ある程度短縮はできるんだろうけど」
気づけば、色丸は弟の隣に座っている。機嫌よさそうに、尻尾を振っていた。
「きみ、なにかしたね?」
屈んで、ミリアは色丸の顔を撫でる。たまらない、といったふうで、色丸は細長く鳴いた。
「ミリアさん、アッシュさん、お怪我は? 治癒します、治癒」
大声をあげ、ヒューが忙しなさそうに走ってきた。やや遅れて、ギマライも続いている。どこかから、戦闘が終わるのを見ていたのだろう。
「大丈夫よ、そんなに慌てなくても。今回はかすり傷ひとつもらってないわ」
「よかった。治せるとはいえ、傷ついたお二人を見るのはしのびなくて」
「姉ちゃん、ギマライさんが鼻血出してる」
「あれ、本当だ。なんでだろう」
指摘されたギマライが、自覚なさそうに呟く。片側から、血が滔々と流れていた。少し焦りを見せながら、ギマライは手で鼻下を拭う。
「姉ちゃんの見すぎ?」
「そこまで見てないよ」
「操作魔法の、超過詠唱ですね」
「ええと、ちょうか?」
ヒューの言葉を、弟は繰り返そうにもできない。
「自身の技量を超えた魔法を唱えると、その反動が返ってきます。本来は、放てない魔法は自然にわかり、歯止めがかかるものなのですが、無茶な人はそこを飛び越えるようで。アッシュさんも、詠唱できるものとそうでないものは、躰が知っているのでは?」
「わかるよ。今の俺に使える魔法は、二、三しかない」
「ギマライさんは、その箍をはずしたんですね。鼻血が代償となるのは、手足などを用いず、対象の脳にはたらきかける操作魔法だからかもしれません」
いったいなんの魔法で無茶をしたのか、と思い、ミリアは気づく。赤く染まった瞳を。
「右腕。色丸」
色丸の瞳が開かれ、巨躯の腕は動きをやめた。
「色丸は、媒体も兼ねるようですね。彼のいるところであれば、多少遠くとも操作魔法をかけられます。もちろん、高度な魔法でしょうから、ギマライさんへの負担は一段大きいものとなりますが」
「こんなにつらい思いをして、右腕一本、止めただけだけどね。それにしても、頭が痛い」
血は止まったようだが、乱暴にこすったため、小鼻から頬にかけて赤黒い痕が伸びていた。
「操れる対象を感じ取るだけで、色丸の視界を借りられるわけじゃないから、情況はわからないし、ちょっと不便なんだよね。でもまあ、役には立てたのかな、ミリア?」
「ええ。一応は」
「そうかい。なら、よしとしよう」
ギマライは、やや俯いて笑みを浮かべた。普段は見ないような表情だ、とミリアは思った。
「敵は、もういないようね」
「そのようです」
「結局、寝床は見つかったの、あなたたち?」
「見つけたら、見つかったんだよ」
「わかるように言って」
「多分、罠を張っていたんじゃないかな。ここなら獲物がかかるぞっていう。そこに、ギマライさんと二人まんまと入っちゃった」
「木造だけど、壊れていない住居があってね。床も、抜けるほど腐ってはいない。逆に言えば、罠を仕掛けた奴らはもういないんだから、今となっては休息にうってつけだと思うよ」
「じゃあ、そこにしましょう。わたしたちが戻る刻限も、そろそろでしょうし」
振り返ると、ヒューは大きく瞬きをしていた。
「どうしたの、ヒュー?」
「いや、ええと、その、こんなによくしていただいていいのかなと」
「なに、くだらないこと言ってるのよ。このままだったら危ないじゃない」
「家の周囲に、簡単な罠を作っておくよ。本来は狩猟用だし、魔物がかかるかわからないけど、逃げる時間くらいは作れるかも」
「ギマライさん、俺も手伝うよ」
手を挙げ、弟は去ろうとするギマライに付く。
「ギマライ」
呼び止めていた。そのあとを、特に考えていない。
「なに?」
弟と二人で、ギマライはこちらを見ている。
「あなたの魔法がなければ」
無事ではなかった。いや、回りくどいことを言おうとしている。
違う。言いたいことは、そんなにないのだ。
「ありがとう」
平静に言ったつもりだったが、そう聞こえているだろうか。ギマライは、眉を少しあげて、止まっている。
「それだけ、言っておきたくて」
「ああ。どういたしまして」
ギマライは、どこか不器用そうに返してきた。その理由はわからない。弟と、木々の中に消えていく。
「ミリアさんは、ギマライさんが苦手なのですか?」
裏表のない問い方は、ヒューの特性のひとつだろう。はじめて訊かれたが、別に嫌な気分には襲われなかった。
「苦手という言い方が合ってるかは、わからないけど。昔、ちょっとね」
「ということは、今は、違うのですね」
「さあ、どうだか」
肩をすくめる。本当に、自分でもわからないところだった。
「みなさん、本当にすてきな人たちです。まっすぐなアッシュさんに、ちょっと素直じゃないミリアさん。ギマライさんも、頭脳明晰で、ゆえに立ち回りを優先的に考えてしまう方だと思いますが、根は多分、お二人と変わらない」
「それは、褒めてくれているの?」
「もちろんです。当然じゃないですか」
「ゾヴとかいう天使の伝言でもなく?」
「まったく。怒りますよ、ミリアさん」
わざとらしく、ヒューは腰に手を当て、怒った仕草を作る。
「ごめんなさい」
両手を合わせて、ミリアは謝るそぶりを見せた。なんだかおかしくなり、二人同時に噴き出して笑った。
「明日、また来るから。待っててね」
「はい。待っています」
「それで、造物主の石庭だっけ? そこに行こう」
「はい。なんとしても」
ヒューは口を真横に結び、しっかりと頷く。正直なところ、彼女にももっと感謝を伝えたかった。
自ら責任を負い、自ら行動に移し、自ら覚悟を決める。ヒューは、あれこれと理屈を楯に腐り、己こそが悲劇の主役だと思っていた自分の甘さを、見事なまでに殴り飛ばしてくれた。
痛みではない。心に吹く、ひと筋の爽やかな薫風をヒューはくれた。
「ヒュー、明日もたくさんお話しよう」
そしてその少女は、やりたいことがあり、自分の協力が必要だと言っている。
ならば、できるできないではなく、やる。そう決意するだけだった。
ーーーーーーーーーー
こちらのイラストは、トキ兄様に描いていただきました。
改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
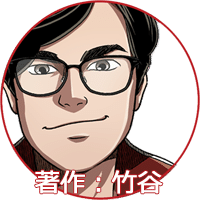
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
