
『灰のもと、色を探して。』第12話:ギマライ
祈ることが、生きることだった。
日々、神を模したと言われる像を父は愛おしそうに見つめ、生命の感謝を述べる。母もできる限り父に寄り添い、結果、ギマライも祈りに同席することが多かった。
祈るとはいえ、父から出る言葉は願望や希望ではなく、謝恩と決意だったように思える。
今日も素晴らしい一日をありがとうございます。日々の繋がりを意識し、欲に溺れず、人を愛し愛されるように生きます。そんなような内容だ。
教会は、人々が祈るために建てられたものだった。そこの牧師の息子として生まれ、厳格な父母のもと、清廉であることを躾けられた。また、それが当然のことだとギマライは思い、生きていた。
その年は、疫病が猛威をふるっていた。信仰心の篤い罹患者とその家族は、教会に集まり平癒を祈る。災害や病は、人間の神に対する献身が足らないからだ。しっかりと祈念し、それが神に通じれば、なにも災いは降りかからない。
もっと神に寄与しなければ、とギマライは思う。わずかな食糧を分け与え、皆等しく死にむかっていく感覚。時折空虚に思うこともあったが、満たされた気分だった。
食事以外の時間、父はひたすら患者たちのもとを回っては話を聞き、信仰の尊さを説き、彼らと一緒に祈る。母は街へ行き、家財を売り払って信者たちの衣食を揃えた。ギマライも遣いに出されたが、次第に、自ら進んで手伝うようになっていた。そんな自分たちによくない感情を抱くひともいたみたいだが、この忠勤を笑いたければ勝手にすればいい、とギマライは思った。
それでも、神の怒りは鎮まらない。人は死に寝床は空き、そしてまた埋められる。
家財も尽きかけていたが、父はそれを気にしないどころか、献身の証拠だとでも言うかのように、幸せそうだった。父は神に祈り、母は人に頼む。寝食を忘れて両親は励み、特に母が街を回り、なんとかして金銭や食物を手に入れようとするさまは、執拗であった。近寄るなと、話しかけた住人に蹴られることもあった。
やがて疫病は去り、忘れかけた土産を持ち帰るかのように、最後に父を連れていった。死に臨んでもなお、父の表情は泰然として揺るがなかった。神に迎えられることに、なんの憂いがあるのかと言い遺した。
今思えば、父は神ばかりでなく、母のこともしっかりと愛するべきだったのだ。
父の死を契機に、母は気が抜けたようになり、生きる力を失った。なにをするにも、ただ惰性で過ごしているように見えた。動くこれだけ他者を恵み、自らを犠牲にしても、母は父を失ったのだ。
そして、高熱に苦しむ人がひしめき合っていた教会は閑散とし、寒々しく感じるほどだった。人々の信仰心は、自らが苦境にある時だけ篤くなるものだった。
祈り、尽くした日々は、まったくの無駄だった。
神を信じて、なにになる。
その母の背を見ながら、ギマライは固く拳を握った。
他人に幸を分けて、どうなったか。家族が壊れただけではないか。
もう信じない。分け与えない。譲らない。自分で得たものは、自分で使い、大切にする。
取り戻すのだ。失われた、家族のものを。
建物こそ教会だったが、機能はもうなくなっていた。父と違い、母にもギマライにも、牧師の教養はなく、また信仰を広めようという精神も消えていた。がらんとした堂内で、在りし日の父が説法をする時に立っていた壇に立つ。疫病の蔓延により傍聴席は撤去され、簡易な寝床が用意され、病人たちで溢れかえる病室となっていた。
その病人たちも、もういない。ここは父の死と一緒に、死んだのだ。
違う働き方をしたいと思った。神や信仰から、とにかく離れていたかった。
しかし、職は見つからずに、日々は続いた。
学校へは行っておらず、体力に自信もない。まして自分は、廃れてしまった教会の息子として知られていた。祈り、頼む以外に、やることを知らない。求人を出している人々の中には、信仰心の薄さを父に非難された人もいれば、食べ物を分けるよう母にしつこく説得された人もいて、怨嗟の視線で見られたことも少なくなかった。
教会へ来る信者たちを保護するために、どれだけの迷惑をばら撒いたのか。ギマライの心中に疼くものは、人々に対する憎悪ではなく、両親へむけた敵意だった。死なれてからこそ、父を嫌いそして呪った。
そんな折、発掘者という仕事を知った。遺跡や秘跡を探査し、失われた技術や価値を再発見する。結果を出しただけ、報酬に反映される。
これしかない、と賭ける思いだった。過去を取り戻すような仕事。そんな大義名分が、家族を台無しにされた自分にとって必要だった。たくさん成果を出し、金を集めて家を建て替える。あの教会は、早く壊してしまった方がいい。
発掘協会の本部で、面談をした。スミスと名乗ったその会長は、組織の長には見えないほど、鍛えあげられた体躯をしていた。常に前線にいて、太陽と危険にその身を晒している、といった鈍く光る眼で、こちらを見てくる。どことなく好きになれそうになかったが、些細なことだった。そんな彼から訊かれたことは、雇用されたいがため熱意をひたすら述べるギマライとは対照的に、ただひとつだった。
自分の未来にとって、この仕事は必要だと思うか。
その内容に少し面食らってから、ギマライは頷き、返事をした。
そう思うなら、やってみるといい。
両親の状態、自らの過去、また適性などを判断されるのかと思ったが、特にそんなこともなく、発掘者の契約は終わった。
欲していながらも、ずっと手に入れられなかった職。無関心や蔑みの中、平静を装って臨んでいた面談。そこに自らが投じた時間や、受けざるを得なかった苦難の量だけ、雇用されるとなった時は、もっと喜ばしく感じるものだと思っていた。しかし、妙なあっけなさだけが、ギマライに残っていた。
渇望していたものが満たされても、意外と心は揺れないのかもしれない。
帰り道を歩いていると、路傍に少女が佇んでいた。年齢は、十五歳前後くらいだろうか。自分よりはいくつか下だ。小さいその少女は、暗鬱そうに表情を曇らして、うつむいている。
教会では、こういう顔はよく見ていた。
「どうしたの?」
思わず話しかけてしまい、舌打ちをしそうになる。自分のためだけに生きると決めても、長年染みついていた生き方は、なかなか変えられないのだろうか。少女の眼は、充血して真っ赤だった。腫れた頬から、泣いていたのだろう、と思った。
「おかあさんが、死んじゃった」
少女は、かろうじて声を絞りながらも、ギマライを見あげてきた。大きな瞳と、灰色の髪。この子も、疫病に家族を連れ去られたのか。こみあげてくる同情の波に、ギマライは眼が歪んだ。
「おとうさんは?」
「とっくにいない。まだ弟も小さいのに、わたし、どうしたらいいのかな」
鼻を震わせながら、少女は少しずつ言葉にしていく。両親を失い、幼い弟がいる少女。生きていくには、塗炭の苦しみしかない。住居はあるのだろうか。ギマライの教会には、寝るところもあれば、多少の食糧もあった。
まずは、一緒にご飯でも食べよう。きみの話を聞かせてくれないかな。
そう言おうとして、ギマライは踏みとどまる。
これでは、父母の二の舞ではないか。仁愛や施しでは、幸せになどなれない。自ら、思い直したことだったではないか。
慣習を、当たり前だと思いこんでいた価値観を、完膚なきまでに打破しなければならない。そして、自らの人生を豊かにするのだ。
今までの俺は、黙っていろ。
「そうか」
短く返し、ギマライは道の先を指さす。つられて、少女はそちらを見た。

「あの先を曲がってしばらく歩くと、確か娼館があるよ」
助言であることに、変わりはない。
「きみなら、たくさん稼げるんじゃないかな。弟さんにも、きっといい暮らしをさせてあげられるよ」
軽く、笑みを作った。この少女は、自分になんの関係もない。あしらうべきだった。理屈で言えば、発掘者よりも娼婦の方がよい給金を貰えるのだから。
少女は、なにも言わず、黙って道をぼんやりと眺めていた。衝撃を受けているのか、不満を抱いているのか、わからない。しかし、興味を持つことも、ギマライは自らに禁じた。
「じゃあね。また、どこかで」
言い放ち、場を後にする。
「間違っては、いない」
言い聞かせるように、呟いた。
数日後、はじめての出勤だった。朝礼だった。多くの発掘者が集まり、報告や情報の交換をしている。どことなく漠然と、緩んだ空気のようなものをギマライは感じた。病人が敷き詰められていた教会しか知らないから、そう思えてしまったのかもしれない。
ほかの会員たちに紹介するからと、スミスに呼ばれて前へ出る。
息を呑んだ。
「同期だからな、お前たち。仲良くするように」
少女が立っていた。戸惑う自分をよそに、ギマライは紹介を進める。
お互いに眼が合い、逸らした。少女の瞳からは、以前あった弱々したが消えていた。その代わりであるかのように、静かで、なにか諦めたような疲れた顔をしている。
少女の名は、ミリアと言った。両親を亡くして、スミスが後見人をしているとのことだった。つまり、彼の私情によって、発掘者として働くことになったのだろう。
そう思った途端、ギマライは言いようのない不快感を覚えた。
仕事にありつきたくとも、そうできない人々は多い。疫病の流行していた時、衣食住の不確かな家族に、街を歩きながら食糧を分け与えたこともある。戦や生まれつきで、四肢が満足でない人もいれば、頭脳に障碍を持った人もいた。この少女は、会長という格別な後ろ楯がありながら、境遇に不満を抱いていたのか。
恵まれている、と気づかない人がいる。新たな発見だった。
数年が経ち、ミリアとは普通に話すようになっていた。しかし、天気や安っぽい噂話など、表面的である。それも、お互いにわかった上で、気にしていないようだった。
極力、視界にはミリアを入れないようにしていた。気持ちを入れずに働いている姿勢か、不満そうにスミスに従う表情か。とにかく、見ると妙に心が騒ぐのだ。
発掘は、よい仕事だと思った。当然、運に左右されるが、発掘できた時や未踏遺跡を見つけた時の感慨は、ギマライがこれまでに味わったことのないものだった。
とにかく経験を積もうと、熟練の発掘者たちにひたすら随行を願い出て、時には疎まれながらも、着実に技術や勘を磨いていった。教会で老若男女の相手をしてきたことが、役に立った。先輩からは一目置かれ、後輩からは慕われる。今では、ギマライのことを新人だと馬鹿にする人もいなくなり、どちらかといえば、若き出世頭と思ってくれているようだった。
だからこそ歯痒く、怒りを覚える。
作った業績が、全体のものになる。自分の出した成果が、結局他人と共有されてしまう。長く勤めているだけの凡人が、若く才ある者を食い物にしている。それだけではない。挙句の果てには、狡猾に眼を盗み、働かず報酬だけを得ているような連中もいるのだ。
各々がひとりで発掘するのだ。なら、自分だけがその富をもらうべきではないか。これでは、教会となんら変わらない。
その思いは、日に日に強まる。なにか大きな業績を残した時ほど、分配されゆく自らの手柄を見て、悔しい気持ちが抑えきれない。
雪が、降った日だった。
「珍しいな、ギマライ」
振り返ったスミスと、眼が合う。会長という点を除いても、この直視される威圧は耐え難いものがあった。ただ無為に年を取るのではなく、自らとむき合い、努力し、きちんと年齢を重ねてきた者のみが出せる気迫。責任と覚悟をどれだけ経れば、こうなれるのだろうか。
スミスが協会から出てくるところを、狙っていた。建物の中では、発掘者や工房の連中の視線があり、正直なところ鬱陶しい。
「相談が、あります」
鼓動を抑えるように、息を長くつく。その息は白く、今日がいかに寒いかということを暗に示していた。
スミスはなにも言わず、こちらを見ている。続けろ、と言われているようだった。
「発掘に従事してから三年、手前味噌ながらいっぱしの発掘者となり、協会内でも優秀な者として他者より名を挙げられるようになりました。なにもなかった子どもが、困らずに生活できているのは、スミスさんのお蔭です」
「そういうのはいらん。本題を言え」
「しかし、拾っていただいた御礼も申しあげずにおりましたので、一度」
「いらんと言っている。確かに機会は与えた。だが、それを転機とできるかは、そいつ次第だ。俺に感謝する必要などない」
「そうですか」
多分、スミスならそう言うだろうと思っていた。本来の人格なのか、会長としての最適な振舞いを模索した結果なのかは、わからない。
逆に言えば、育てたのはだれだ、と恩を楯に、論点を封じてくることもしないだろう。
「具申は、ひとつです」
眼は、逸らさない。
「成果を、分配するのをやめていただきたいのです」
顔が熱い、と思った。発掘者になって以降、意見をする時は細心の注意を払っていた。賛成でも反対でも、だれかの機嫌を損なわないよう、振舞っていた。ここまで直接的に、反意を示したことはない。
「もちろん、長所はわかっているつもりです。体力の衰えや不慮の事故などにより、以前のように働けなくなった人たちが、一定の収入を得られる。その保証による安心感は、ほかの職では類を見なく、スミス会長の手腕によるものだと理解しています」
だから、賭けだった。ギマライらしくないことを、敢えてする。意表を衝くつもりはないが、言葉を飾らないことで、本心を伝えられるはずだ。
「しかし反面、あぐらをかいている連中がいることも事実です」
スミスは、眼を閉じた。思案しているようでも、話に集中するようでもあった。
「働いているふりをして、その実なにもしていない。遺跡ではなく酒場に赴き、酔いつぶれて路上で眠る。しかしそのお金は、ほかの発掘者たちの血と汗から作られたものです」
そういう連中は、多くはないが少なくもない。保証の話を聞きつけて、その旨さを味わいたいがために、発掘者を志願してくる者もいると聞いていた。
「真摯に仕事へ取り組む者が、馬鹿を見る。スミスさん、あなたのやり方では、本当に幸せになるべき人が不幸になります」
雪が、互いの服に積もってきている。ひと気は感じなかった。寒く、雪の降る時間に、外へ出ようとは考えないのだろう。人が来てしまっては、この話はできない。方法であれ制度であれ、新しいもの、つまり改革を好む者は多くないのだと、ギマライは考えていた。
スミスは眼を開け、ギマライを見据えてくる。その表情からは、肯定も否定も読み取れなかった。
「ギマライ、いくつになった」
「先日、二十三に」
ただ、静かにスミスは訊いてきた。
「会員の中で、新古含めて考えても、お前ほどに協会のことを真剣に考えている奴はいないだろうな」
言いながら、スミスは頭を掻く。がりがりと、音が聞こえてきそうな勢いだった。
「若いのに、大したものだと思う。言っていることも正しい」
「では」
「監視を厳しくする。しかし、分配はやめない」
駄目だった。ギマライは、手を強く組み合わせる。
「さっきも言ったが、お前の言うことは間違っていない。才と努力のある者が、相応の報酬をもらえる。それは、よい世の中だろう。しかし、俺はやり方を変えない」
「なぜですか」
一歩、スミスは近づいてきた。わずかに、見あげる恰好となる。
「ギマライ、お前は得た金をどうしたい」
「どうって」
「うまいものを食べたい。いい家に住みたい。年頃の男なら、洒落た服を着たい。綺麗な女を抱きたい。そんなところか」
失ったものたちを、取り返したい。それは言えなかった。
「そういった欲は、人間として当然だ。だが俺は、もっと別のものを大切にしたい。だから金は、少しあればいい」
「別のもの。それは、なんですか」
「愛」
知らず、眉をひそめ固まってしまう。その様子を見てか、スミスは小さく笑い声をあげた。ギマライにとって、スミスの砕けた顔は、はじめて見るものだった。
「なんてな。まあ、どうしてもと言うなら、ギマライ、お前が次の会長になれ。そうして、思うことを実行していけばいい」
「そんな、あまりに突飛なことを」
返事に窮していると、スミスに肩を叩かれた。彼はギマライを過ぎ、場を立ち去ろうとする。消化不良もよいところだった。実質、なにも変えることができなかったのだ。はぐらかされた、という思いさえある。怒りと悔しさで、唇が震えた。
「ああ、そうだ」
歩きを止め、背をむけたまま、スミスは横顔を見せた。
「俺に、面とむかってものを言ってくる奴は、ここのところ見なかった」
なにか言葉を返さなければ。そう思っても、ひとつとして出てこない。
「老人めいた説教をするとな、考えの正しさの隣には、いつも思いの大きさがある」
「なんだよ、それ」
敬語を使えなかった。咎められると思ったが、スミスは口元を綻ばせていた。
「今はそれでいい。けどな、いつか、理屈だけではどうしようもないものに出会えよ」
理解できなかった。その状態をスミスに肯定されていることも、業腹だった。
「できれば人間がいい。お前の場合、できれば女がいい。せいぜい狂え、ギマライ」
スミスは、歩いていく。その姿を、ただ見ていることしかできなかった。
確信した。スミスのことは、やはり好きになれない。
しかし、忘れようと思っても、干満に負けない錨のように、スミスの言葉は脳裡にしつこく居座り続けていた。
「俺は、間違っていない。間違っていないんだ」
ひたすらに、言葉にする。
翌日、スミスは普段通りの硬い顔だった。あの時、本当に笑ったのかと一瞬疑うほどだ。ギマライも、協会のいち発掘者として過ごす日々に戻った。
諦めるつもりはない。もっと結果を出して、だれからも信頼され、組織の中での影響力や発言力を高めなければ、と思った。頂きを変えるのが無理なら、麓から手をつけていけばいいのだ。時間はかかるが、やむを得ない。
あの時のことは、とにかく頭から追い払った。ただただ、不要なものだ。
「おはよう、ギマライ」
「ああ、おはよう、ミリア」
ミリアが通り過ぎる。挨拶以上の会話を、求めていないことが明白だった。
だいぶ、ミリアは背が伸びた。髪もより長くなり、灰色にも艶があるようだ。彼女の後ろ姿をぼんやりと見ながら、ギマライを思った。なぜ、そんなことを思っているのか。その理由は考えたくなかった。
ーーーーーーーーーー
こちらのイラストは、西藤様に描いていただきました。
改めまして、この度はご協力いただきありがとうございました。
ーーーーーーーーーー
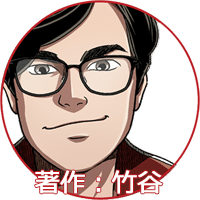
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
