プラスαのインターネット活用術32
Medical Tribune 2000年9月28日 22ページ ©︎鈴木吉彦 医学博士
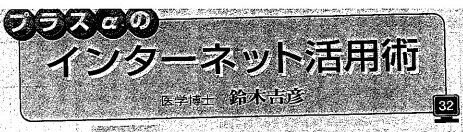
学会ハイライトをインターネットで入手
情報のデジタル化が加速
海外で開かれる学会では発表内容もスライドからPowerPointを利用したプロジェクター方式に急速に変わりつつあります。日本でも,多くの学会で演題登録システムのネット化が進み,情報のデジタル化は加速しています。今後,学会資料の入力から発表までの一連のプロセスはすべてデジタル化され,旧来のプロセス(手書き,紙,スライドなど)は淘汰されてゆくことでしょう。
学会内容をデジタル媒体で配布
かつては海外の医学会に参加すると,講演内容がCD-ROMに納められ,販売されていました。分厚い抄録集よりも,CD-ROMのほうが簡単に持ち帰ることができます。しかしマック版か,Windows版(95,98,2000,NT)か,などとOSに振り回されるくらいなら利用しないということで,現在ではCD-ROMの人気は落ちているそうです。
しかし,ネット上で学会情報を保存する流れが早まれば,抄録のみならず,発表内容のすべてがインターネット上で閲覧できる時代が来るでしょう。学会員は,そこにアクセスするためのパスワードあるいはIDなどを取得しておくだけですむようになります。一方,学会側では会員限定空間の確立,つまり会員にターゲットを絞ってアクセスを許可するための認証システムの構築が急務になってくるでしょう。
ターゲットの絞り込みがかぎ
2000年7月26日の日本経済新聞(朝刊)に,「ネットで医療情報。武田薬品,SCN(ソニーコミュニケーションネットワーク(株))と提携」というタイトルの記事が掲載されました。「学会開催後24時間以内に日本語に翻訳して掲載。2週間は会員のみが閲覧できるようにし,その後は会員外にも内容を公開する」という仕組みが注目されたのだと思います。武田薬品工業やノボノルディスクという大手製薬企業が主役となって活動したこと,また,MyMediproのOne-To-One技術でサービスコードという閲覧者を限定できる仕組みを利用し,会員だけにターゲットを絞ったシステムを構築できたことなどがサービスの価値を高めました。
これまで多くの製薬企業は,コンテンツをできるだけ多くの人に見てもらいたいという発想が主流でした。利用者を限定せず,できるだけ範囲を広くして公開し,それによってアクセスを伸ばすという考えです。利用者を限定することは,製薬企業の情報提供という本来の目的には反した行為と,これまでは考えられてきたわけです。しかし,上記両者の発想は,その先入観を打ち破りました。従来型の発想を180度転換させ,会員やサービスコードを持つ人だけに限定する,という仕組みにしたからです。それによって,サービスを受けられる人をターゲッティングしてしまったのです。その結果,サービスの提供を受けた医師には感謝されるサービスを提供でき,逆にサービスの提供を受けられない医師にとっては,提供された医師がうらやましい,と思われるサービスを提供できたことになります。
ここから先は
¥ 500
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
