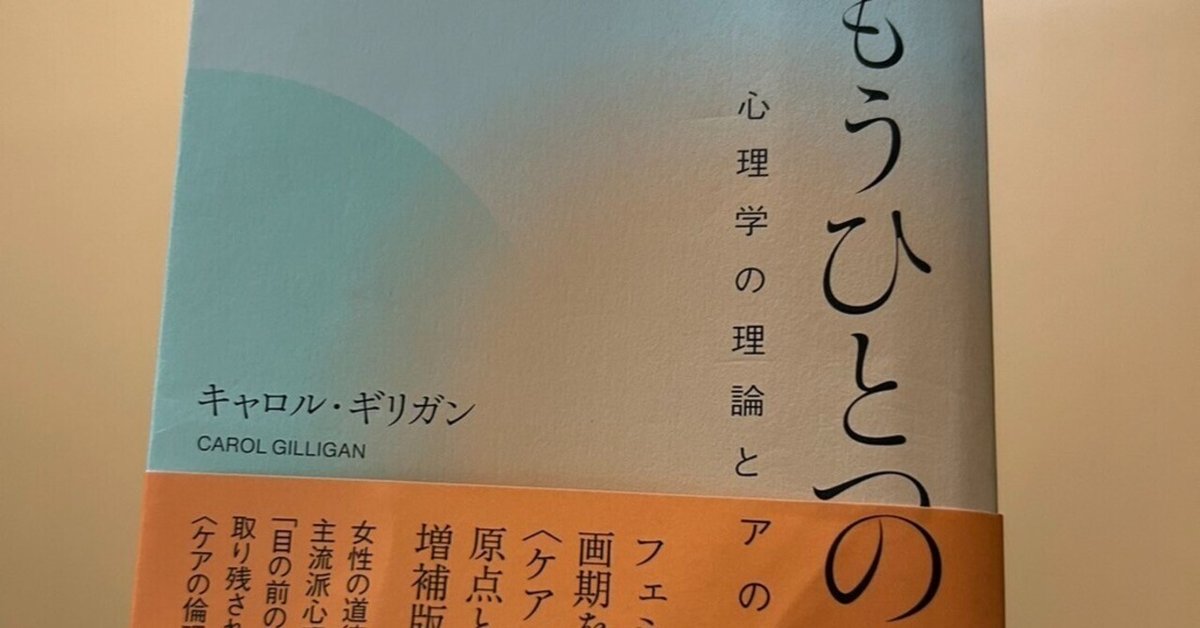
キャロル・ギリガン『もうひとつの声で』|読書記録 08
読書記録、8冊目。
今回は前回に続いてキャロル・ギリガンによる『もうひとつの声で』について書こうと思う。
概要
本書は心理学者のキャロル・ギリガンが、コールバーグやエリクソンによる発達理論は男性のみを対象として作成されていて、それを女性に照らし合わせると、女性の発達が遅れていると不当に評価されてしまうということに疑問を呈した。そこで女性の声を聴く研究を進めた。
ハインツのジレンマ問題、女性の人工妊娠中絶における語り等のインタビュー調査を実施する。
そこで、女性の声の響きは男性と異なっていて、それは<ケアの倫理>としての響きを持っていたことに気づく。
男性は発達を通して、自己と他者を分離して、自律した主体として、権利の優先順位をつけられるようになる<正義の倫理>の響きを持つが、
一方で女性は自己と他者を分離せずに、関係性の中で捉えて、誰に応答するか、誰に対しての責任を取るかを決められるようになる<ケアの倫理>の響きを持つ。
ギリガンによれば、<ケアの倫理>は家父長制が根強いこの社会では<女性の倫理>として響くが、実際には<人間の倫理>である。
<人間の倫理>として取り戻すためにも、まずは女性の声を聴かなければならない。
女性の発達理論
女性の道徳的判断は、
**********
STEP1. 生存
STEP2. 善
STEP3.ケア
**********
へと移行としていく。
移行の際には、利己心と責任との間の葛藤を批判的に解釈し直す過程が含まれている。
そして、女性の道徳の定義域の中核には、責任とケアの概念がある。
生存の段階では、まずは自分自身へのケアが第一である。自分が生きることが最優先される。
善の段階では、すなわち他者に対してケアをすることと考えられる。この段階では、しばしば自己犠牲的な判断が下される。
そこで、関係性が円滑に行かなくなることで、
ケアの段階で、自分と他者に応答し、責任を取る態度を求めていくようになる。
感想
1.「女性の声をいかに学問上にあげられていないか」
コールバーグやエリクソンによる発達理論が、男性のみを対象にした研究から作成されていたとは純粋に驚いた。
まさにman=menではないか。
仮にそれが女性にも当てはまるとしても、女性の声を聴いていない理論である、ということに課題は当然残るだろう。
理論ありきで女性に当てはまることが示された、としてはならないはずだ。
発達段階の途中で女性がとまってしまうことを、ギリガンが理論に課題があるのでは?と考えた点が優れていたと言えるだろう。
一方で、では人種・障害・性などの、多様さの軸は様々であって、それらを考慮しているのか、という疑問も残る。
2.「ケアの倫理と正義の倫理が統合された状態とは」
結果的に、ケアと正義の倫理が統合された自己像、かつ、社会像はどのような状態なのかわからなかった。
ケアの倫理が言う、個別具体的で文脈依存的な判断は、望ましいとは言え、制度設計や政策への反映をしようと思うと、いちいち個別具体的な事例を洗い出して、そのすべてに答えをだすことは難しい。
そのため、まずは正義の倫理が先行することになってしまう。
すると、今の社会の在り方と何ら変化はないのではないか。
はたして女性の声を聴いた先にどんな社会があるのか、想像し得なかった。
3.個人的にはとても納得する。
何よりギリガンが提唱した発達理論が、自分に照らし合わせたときに、納得する点ばかりで感動してしまった。
「あー私がずっと悩んでいたことは学問上で蔑ろにされてきただけで、当然のことであったのか」と。
どの責任を引き受けるのか、誰も傷つけずに生きることはできないのか、
他者に対して誠実であるために自分に誠実であり続けることはできないのか。
ずっと考えてきたことが皆考えていることなのだ、それが当然あることを知れて、私はとても心が軽くなった。
以上、読書記録!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
