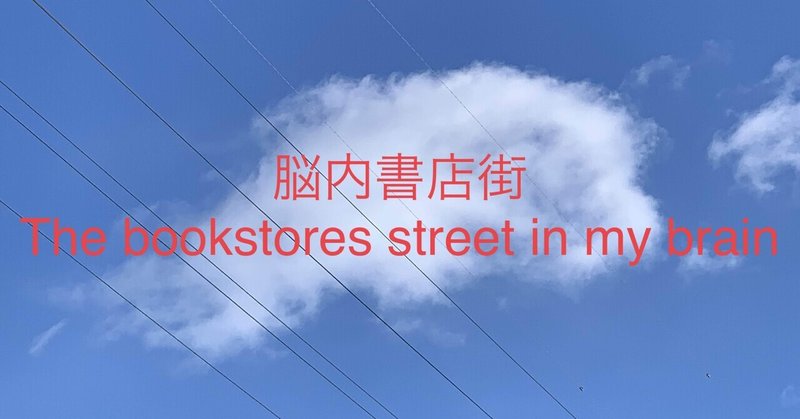
7. It was a bookstore school for me.
小学生の時に、地区の名前が付いた本屋さんが新規開店した。
パン屋系お菓子屋が併設されていたけれど、その本屋さんは、まさに私のための本屋さんだった。
なにしろ、家から歩いて子どもの足でも10分ぐらい。
両親に頼んで連れて行ってもらわなくても、明るいうちなら1人で本屋さんへ行けるのである(昔は子どもが1人で出歩いても、明るいうちなら割と大丈夫という平和さがあった)。
店内の雑誌棚以外、書籍やマンガ、児童書、文庫本の棚は白くて明るく、小学校が近かったからなのか、児童書の棚も幅広くとってあり、店に入る瞬間もそうだが、中にいるだけでワクワクした。
そして!
この本屋さん、なによりも魅力的だったのは、ラップフィルムを巻かれることが主流になるまでは、店長さん公認でマンガの立ち読みOKだったのである。
漫画雑誌はおそらく閉店するまで自由にできたと思う。
コロナ前の某大型古書店並みの気前良さだった。
時折、数人の中学生が横並びになって、通路を塞ぐようにして床で座り読みしてる時は注意されていたけれど。
立ち読みしても満足せず、結局は欲しくて買ってしまうことが多かったから、店長さんはそこまで見込んでいたのかもしれない。
また、当時の小学生は放課後出かける時には、学校の名札を付けていたので、いつも行っている私は店長さんに名前を覚えられていて、行くたびに「富原さん、いらっしゃい」と笑顔で迎えてもらっていたから、余計に嬉しかった。
今思えばマニアック過ぎで私以外買わないような欲しい本を、お小遣いが貯まるまで別の本の後ろに隠したこともあったし、お気に入りマンガのコミックスを全巻集めたり、発売日にダッシュで買いに行ったり、流行りの角川文庫(ほぼ赤川次郎)を買い漁ったり、同じ本でも高い本(単行本や児童書)と安い本(文庫本)があることを知ったり、いろんな本を注文や予約したり…、本屋さんとの付き合い方はすべて学ばせてもらった。
私にとっては、本屋さん学校だった。
大人になったらここで働きたいなぁ…と密かに思っていたけれど、「あの店長さんはお客さんには優しいけど、働いてる人にはすっごく厳しいんだって」という噂を聞いて驚いた。
そういえば一度だけ、お店の人が怒られてるのを見たことがあったかも。
そんな厳しい店長さんだからだろう。
他地区に、同じ名前の店を「〇〇ブックセンター他地区店」という支店や、同じ地区内に「2号店」を開店する凄腕も見せていた。
その2店舗ももちろん脳内にあるけれど、本店とは全然違う状況だった。
それはまた別の日に。

子どもの頃、その本屋さんで買った本です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
