
2023年よく聴いた音楽【年間ベストアルバム】
今回は年間ベストアルバムということで、2023年に私が特によく聴いた作品を20枚、紹介していきたいと思います。
20. The Hives 『The Death Of Randy Fitzsimmons』

ストロークスやホワイト・ストライプスらとともに、00年代初頭のガレージロック・リバイバル・ムーヴメントを牽引したスウェーデンの雄、実に11年ぶりとなる6th。冴え渡るソングライティングで高い評価を得た2004年の傑作3rd『Tyrannosaurus Hives』を上回り、全英チャート2位を記録するなど絶好調。音楽的に何か新たな要素を持ち込んでいるわけではないものの、持ち前のポップセンスと、テンションMAXで勢い十分なロックンロールサウンドにとにかく磨きをかけ、復活を印象付けた爽快痛快な全12曲。
19. Mr.Children 『Miss You』

ここ数年、徐々にメインストリームから降りつつある印象だったミスチル。2020年の前作『Soundtracks』は、あくまで楽曲フォーマットとしてはJ-POPの範疇内でありながらも、華美なアレンジを避けたミニマルな味付けで、曲そのものの良さを引き立てることに成功した傑作だった。本作ではいよいよ、楽曲フォーマットに関しても王道的なJ-POPから脱却してきたなという印象。次世代バンド達の台頭もあり、自らの立ち位置が変化してきていることに対しては明らかに自覚的。全14曲が事前タイアップ無しの新曲ということもそうだし、セルフプロデュースということもそう。装飾は更に削ぎ落とされ、桜井和寿の類稀なるソングライティングをよりダイレクトに味わえる作品となった。『Soundtracks』がJ-POPとしての集大成だとしたら、本作は新たなフェーズの第一歩目で、まだまだ進化は続いていく。そんな展開に大いに期待したい。
18. Arlo Parks 『My Soft Machine』

2021年リリースの『Collapsed In Sunbeams』で鮮烈なデビューを果たしたロンドンの若きSSW、2年ぶりの2作目。デビュー時の騒がれ方を思えば、本作はほとんど無視されていると言ってもいいくらい反応が薄いし、実際、チャート的にも後退している。確かに、ソングライティングの完成度や、空間・隙間を使う巧みさでは前作があまりに圧倒的だったので、その点においては見劣りすると言わざるを得ない。ただ、前作とはまた違ったテイストを提示してきた点は見逃せない。R&Bを軸としつつも、前作以上にインディーロック・ネオソウル側へ寄ってきており、アナログとデジタルを鮮やかに共存させた、瑞々しいサウンドメイクが印象的。中でも#3 Devotionは出色の出来。音楽性を更に変化させる意欲も見せつつ、しっかりと一定のクオリティを超えてきているところは流石と感じた。
17. Andy Shauf 『Norm』

カナダのSSWによる通算8作目。今年度Myベストするめアルバム。最初はガッカリから始まって、最終的にはお気に入りに。第一印象が良くなかった原因は、サウンド面の変化にある。これまで彼の楽曲の軸を担ってきたのはアコースティックギターとクラリネット。それに対し本作ではシンセが主体に。意図してのことだと当初から分かってはいたものの、どこかぼやけたような、輪郭が不鮮明な音像がどうにも馴染めなかった。今となっては、このシンセこそが幻想的な世界観を作り出す上で欠かせないと感じている。全体的に非常にスローテンポで、リズム的な動きは少ないが、優しいポップセンスに溢れた作品。先日の来日公演キャンセルは本当に残念だったが、また来てくれることを心から願っている。
16. Jonah Yano 『Portrait of a Dog』
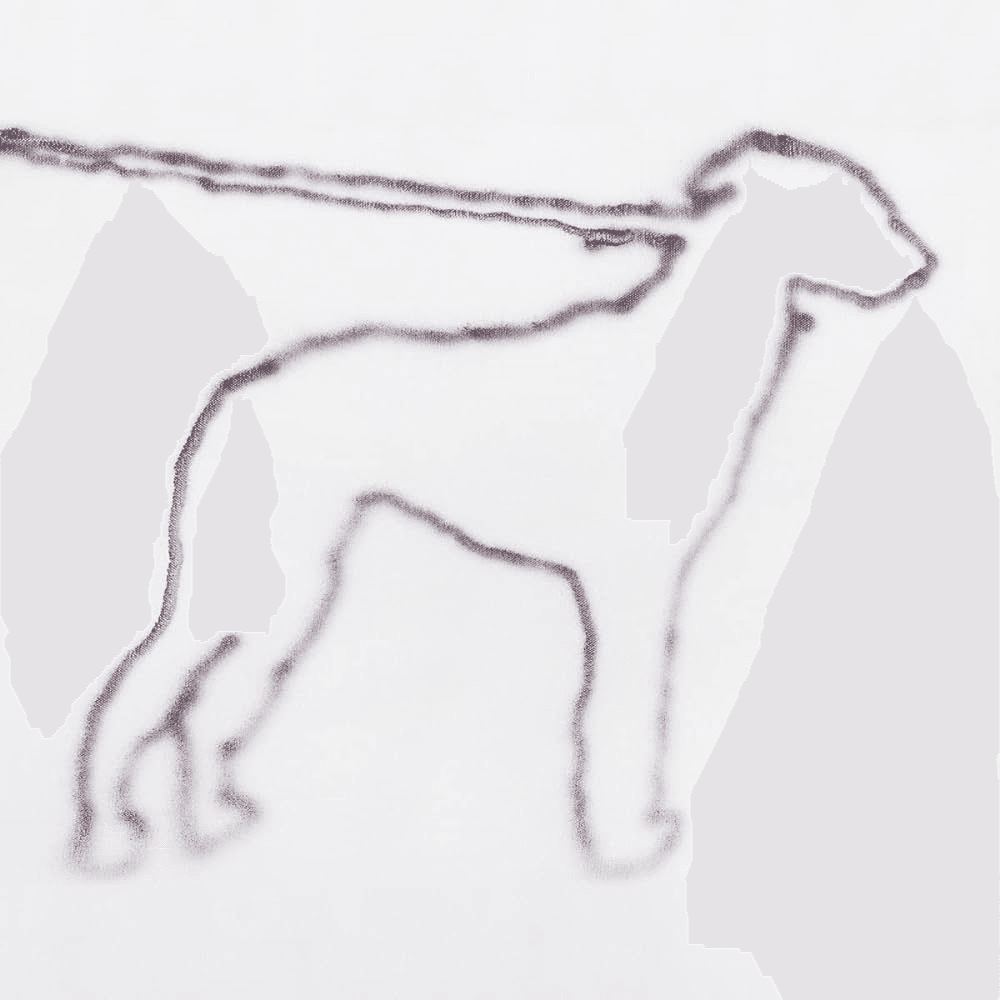
広島出身でトロント在住の日系カナダ人SSW、ジョナ・ヤノの2ndアルバム。2020年リリースの前作『souvenir』では、フォーク、ネオソウル、サイケ、ジャズといった要素を巧みにブレンドしたモダンなサウンドが高い評価を受けたが、本作ではそれらの要素を下敷きにし、ジャズの要素を大胆に打ち出してきた。同じトロントを拠点とするジャズバンド、BADBADNOTGOODが全曲にわたって作曲・アレンジ・演奏で参加しており、ほとんどジャズアルバムだと言ってもいい。より自由度を増した楽曲展開と、鍵盤やサックスの煌びやかなサウンドで新境地を示した。ジャジーでドリーミーな音響に、彼の淡く伸びやかな歌声もよく合っている。素朴だが、独特の魅力に溢れた歌声だ。次作でこのジャズ路線からどう展開していくのか、非常に興味深い。
15. Wilco 『Cousin』

USインディーのベテラン、通算13作目。個人的には、フォーク・カントリー色の強い作品よりも、ネルス・クラインによる長尺ギターソロが聴ける2007年の『Sky Blue Sky』のようなオルタナ全開な作品の方が好みなのだが、本作ではそのどちらとも異なる新たなサウンドが鳴らされている。その仕掛け人は、自身もアーティストとして活動するプロデューサーのCate Le Bon。長らくセルフプロデュースを続けていたWilcoが外部から起用するのは7th以来、実に6作ぶり。従来はモノトーンな音像のイメージが強いWilcoだが、本作には色彩豊かで上品な華やかさがある。収録曲10曲はキャリア最少だが、決して淡白ではない。緻密に幾つも音を重ね、コンパクトな中に濃密な内容を凝縮している。それでいてリラックスした自由なムードも健在。Jeff Tweedyのソングライティングの良さも光る会心の作品。
14. cero 『e o』

今年5月に本作がリリースされて以降、沢山の高評価を目にしたことで、つい先日、初めてceroの音楽を聴いた。それと合わせて、前作『Poly Life Multi Soul』も予備知識として聴いたのだが、ceroの音楽性を一言で言い表すような言葉が全く浮かんでこない。そして、そんな掴みどころが無い音楽なのにも関わらず、非常にキャッチーさを感じている。この感覚はなかなか味わったことがない。アフロビート的で複雑なリズムに、エレクトロ・ネオソウル・ジャズ…と様々なキーワードが思い浮かぶが、結局そのどれでもないような、混沌とした電子音が鳴らされている。ハイトーンな歌声が紡ぐ日本語には明瞭な響きがあるが、まるで楽器が鳴らす音の一部のように自然に溶け込んでおり、耳に滑らかに入り込んでくる。実験音楽的でありながら、同時にポップス的でもある。全貌が掴めないまま何度も繰り返し聴いてしまう、中毒性の高いアルバムだ。
13. Yo La Tengo 『This Stupid World』

USインディーロックシーンの重鎮による通算16作目。私にとっては本作が初めてのヨラテンゴ体験。遡るようにして過去作も幾つか聴いてみたが、長いキャリアの中でも本作はかなり優れた部類に入るのだろうなと感じる。9曲49分という、このバンドとしてはかなりコンパクトな尺で1曲ごとの強度が高く、どこを切り取っても彼ら特有のノイジーなギターが存分に味わえる濃密さが良い。1曲あたりの尺は長めだが、不思議と冗長さは感じない。張り詰めるような緊張感を保ちつつも、それに反するような緩さ、浮遊感が常に漂っている。ノイズと静寂が互いにぶつかり合いながら均衡を保っており、決して混ざり合ってはいないが、それでもバランスは取れている。楽曲はラフな作りで掴みどころが無いが、じっくり最後まで聴かせる力がある。ベテランならではの職人的な作品だと感じた。
12. Slowdive 『Everything Is Alive』

マイブラ、Rideと並ぶシューゲイザー界のレジェンドによる6年振り5作目。2017年リリースの前作は、バンド名を冠した堂々の自信作であったのと同時に、22年振りの新譜リリースとして再出発となる見事な復活作だった。それから6年、フジロック2023での来日に今回の新譜リリース、そして来年3月の単独での来日と、再び精力的な活動を行っている。本作でも、持ち前のメロディの美しさと、浮遊感溢れるサウンドというSlowdiveの個性がよく表れている。加えて、エレクトロニックな音像を強めている点は過去作からの変化と言える。リバーヴの効いた、より没入感のあるサウンドを展開しており、期待に違わぬ内容を見せてくれた。
11. カネコアヤノ 『タオルケットは穏やかな』

2021年の前作『よすが』から2年ぶりとなる通算6作目。アルバムタイトルから、何気ない日常を描いた素朴な雰囲気を連想するが、実際には人間の内なる不安や葛藤、人と人との繋がり、あるいはすれ違いが描かれており、どこかシリアスな一面も秘めた作品となっている。それはサウンドにも表れており、#1 わたしたちへや#5 予感では、轟音のような重厚なギターサウンドが掻き鳴らされる。ただ、そうした音楽的変化はあれど、彼女本来の素朴さや、丁寧なソングライティングが失われたわけでは決してないし、やはり、彼女の歌声が持つ力には凄いものがある。ピュアさと、捻くれた感じを両方持ち合わせた個性的な歌声だと思う。繊細さよりもまずスケールの大きさ、パワー、生命力を感じるような、泥臭く人間臭い作品。
10. Måneskin 『Rush!』

イタリアから一気にスターダムを駆け上がった4人組。華のあるビジュアルとド派手なライブパフォーマンスだけでなく、楽曲の質の高さも本物であることは既に広く知れ渡ったことと思う。人気を獲得したことで音楽性がブレてしまうこともなく、相変わらず00年代初頭のガレージロックからの影響を前面に出しており、なおかつ、よりメロディアスでよりスケールの大きい楽曲を展開。正統派バラードも有り、バラエティに富んだ内容となった。ただ、曲数がやけに多いのと、先行シングル曲を終盤に固めた曲順には疑問符がつく。正直、中盤〜後半にかけての3〜4曲は削ってもよかったと思うし、曲順もしっかり練ってくれれば文句無しの大傑作だった。それでも、そんなモヤモヤを蹴散らせるだけの圧倒的な勢いとパワーがこのバンドにはある。是非ともこのまま自分たちらしく突き進んでほしい。頼もしい存在。
9. Buck Meek 『Haunted Mountain』

Big Thiefのギタリストによるソロ通算3作目。過去2作のリラックスした雰囲気、インディーフォーク・カントリー的な内容を軸としつつ、シンセなどの新機軸を取り入れたり、バンドサウンドを前面に押し出したりと、新たな試みの多い意欲作。過去作と比べて、明らかに色彩豊かな音像へと変化している。ただ、あくまでサウンドが派手になり過ぎることはなく、淡い煌めきを帯びたフォーク・ロックといったところで、そこの味付け加減の丁度良さは流石の一言。シンセが印象的な冒頭の"Mood Ring"、バンドサウンドが前面に出た表題曲の#2 Haunted Mountain、歪んだエレキギターが軽やかに鳴り響く#4 Cyclades。過去2作を凌駕し、ソロとしての存在感も格段に増した一枚。
8. Blur 『The Ballad Of Darren』

先日、デーモン・アルバーンが再びブラーとしての活動を休止すると発言。解散というわけではないが、やはり今年これだけ精力的な活動を見せてくれたことは奇跡的だった。成熟に成熟を重ねてきた、2023年のブラーが鳴らしているからこそ良さを感じられる、あまりにも渋いサウンド。主役は歌メロで、ギターは引き立て役。かつての尖りは無いが丸くなり過ぎもせず、絶妙な枯れ具合といったところで、これまでにはない味わい深い響きがある。過去作すべて50分超だったのに対して本作は36分という潔さも良い。ハイライトは先行シングルにもなった#6 The Narcissist。軽やかなギターと、シンプルなグッドメロディが印象的な楽曲。今年一年間のブラーとしての活動も全部ひっくるめて、あらためてバンドの素晴らしさを教えてくれたアルバム。
7. Phum Viphurit 『The Greng Jai Piece』

タイ・バンコク出身のSSWによる2作目。2023年の個人的激プッシュ枠。インディーフォークを軸として、ファンクやソウルも包括した多様な音楽性が魅力。タイの伝統的な楽器を取り入れ、どこか祝祭的かつ神秘的でエキゾチックなムードを漂わせつつも、小気味の良いギターワークや、大胆な打ち込みの導入など、洗練された都会的なサウンドも自然にブレンドさせている。このバランス感覚が絶妙で、ありそうでなかなか無いサウンドを提供してくれている。昨今は、台湾や韓国、東南アジア諸国も含め、アジアのインディーシーンには優れたアーティストが沢山いるが、中でも彼のセンスには感服させられる。タイとアメリカをルーツとするSSWのHugoや、以前から交流のある日本のトラックメイカーSTUTSと共作した楽曲も収録した、充実の2ndアルバム。もっともっと飛躍してほしい。
6. 羊文学 『12 hugs (like butterflies)』

まだリリースから3日しか経っていないが…滑り込みでランクイン。前作『Our Hope』から僅か1年半ほどのスパンで、またしても素晴らしい作品を届けてくれた。前作での覚醒が一時的なものではないことをあらためて証明。大きなタイアップも付き、メインストリームへと進出する中で、いかにオルタナ・シューゲイザーの要素を残せるかに注目していたが、まさか今まで以上にオルタナ全開なギターロックを展開してくれるとは。前半から怒涛のギターサウンドを連発。#4 GO!!!はこれまでに無くグルーヴ感を強調したナンバー。後半はテンポを抑え、落ち着いたトーンながらも少しずつ表情に変化をつけている。欲を言えば、後半にもインパクトのある楽曲、前作で言うところの『OOPARTS』的な存在がもう1曲あると更に良かった。アルバム全体に一貫して流れる空気感はよく統一されていて、12曲が丁寧に整列されている。サウンド面、アレンジ面の洗練具合には目覚ましいものがあり、頼もしさを感じる一方で、少々荒削りだった頃もそれはそれでまた違った良さがあったなと再確認させられた。
5. Mitski 『The Land Is Inhospitable and So Are We』

三重県出身で、現在はNYを拠点に活動するSSW、という説明ももはや不要な存在になってきたMitskiの通算7作目。ノスタルジックでレトロな雰囲気漂う80'sシンセポップを展開した前作『Laurel Hell』から約1年半。前作も彼女にとって新境地のサウンドだったが、今回もまた違った新境地。厚みのあるシンセサウンドから一転、本人が「これまでで最もアメリカ的な作品」と語る、カントリー/フォーク/ゴスペルの要素が色濃い音楽性へと変貌を遂げた。大胆なオーケストラの導入、フル合唱団の参加など、静謐で幻想的な世界観を提示してくれている。そこに、従来のドラマティックなメロディセンス、彼女自身の芳醇な歌声が加わり、まさに盤石の仕上がり。毎回スタイルを変えながらも常に進化を繰り返し、次は一体どこへ向かうのか。注目し続けていきたい。
4. Sufjan Stevens 『Javelin』

稀代のSSWによる2年ぶり通算10作目。前々作『The Ascension』ではエレクトロポップに傾倒し、前作『Convocation』ではスペーシーなアンビエントを展開し150分に渡る超大作となった。近年はそんな実験性の強い作品が続いていたが、本作では久々に原点のインディーフォーク路線へと回帰している。ギターとピアノを軸としたシンプルな構成ではあるものの、細部まで緻密に描き込まれたスケールの大きい楽曲が並んでおり、たった一人で作り上げたとは思えない凄みがある。そこはやはり彼の真骨頂。サウンドのテイストとしては、ストリングスやクワイアを大胆に導入した賑やかな『Illinois』というよりは、ほぼギターとピアノのみの静謐な『Carrie & Lowell』に近いのだが、『Illinois』を彷彿とさせるような壮大さが顔を覗かせる瞬間もある。『Carrie〜』は亡き母を含めた両親に捧げる作品であったが、本作もスフィアンの亡きパートナーへ捧げる作品ということで、喪失を描いた作品という部分に共通点が見出せる。悲しみだけでなく、その先にある温かみ、希望も感じられるのが良い。
3. boygenius 『the record』

2023年のインディーシーンを最も盛り上げてくれたグループの一つ。感情豊かに力強く歌い上げるJulien Baker、繊細な歌声で美しく囁く Phoebe Bridgers、聴き手を優しく包み込むように語りかける Lucy Dacus。既に各々がソロとして大きな成功を収めている3人の女性SSWによるスーパーユニットの1stフルAL。個々の才能がしっかりと発揮されつつも、ぶつかり合うことなく上手く調和しているのは、絶妙なコーラスワークと美しいハーモニー、そして3人の絆があってこそ。この1年間、boygeniusとしてのツアーに力を注ぎ、より結束力が強固になった印象も。#6 Not Strong Enoughは多くの人々に強烈なインパクトを与えるであろうアンセム的楽曲。エネルギーに満ち溢れた美しき傑作。
2. Foo Fighters 『But Here We Are』

先日フー・ファイターズの全11アルバムを一通り聴いたが、本作はキャリア全体でも間違いなく3本の指に入る屈指の名作だ。個人的には最高傑作と思っている。本作は、2022年にこの世を去った、テイラー・ホーキンスと、デイヴの母の2人に捧げられた作品だが、その背景と楽曲自体の良さを切り離して語ることはできない。アーティスト自身の経験や感情が作品に色濃く影響を与えることは多々あるが、本作はそれが大きくプラスに作用した好例だろう。過去最高にピュアでストレートでエモーショナル。MåneskinやThe Hivesもそうだが、気を衒ったり技巧に頼ったりせず、泥臭くロックをやり続けるバンドが好きだし、これからもそういうバンドを聴き続けていきたい。
1. Paramore 『This Is Why』

間違いなく今年一番聴いたアルバム。00年代の初期3作ではポップパンク/EMO路線だったのが、10年代の2作ではシンセポップの要素やダンサブルなアプローチを取り入れ、20年以降はHayley Williamsのソロ作2枚で更に音楽性を深化させるなど、これまでの軌跡が本作で結実したように思う。まず目を引くのはミニマルなサウンドプロダクション。分厚いギターサウンドに頼らず、余白を巧みに使った引き算的なアプローチで、奥行きを感じさせる洗練されたサウンドに仕上げている。もう一つ見逃せないのは、ルーツであるポップパンク/EMOの精神溢れるフィジカル的躍動感。成熟した音楽性を見せつけつつも、根底にあるロックバンドとしてのアイデンティティも感じさせてくれる。全曲がハイレベルで、バンドのキャリアを総括する堂々の最高傑作。
以上の20枚です。
来年も素敵なアルバムに出会えますように。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
