
Kings Of Leon全アルバム聴いてみた
The Nationalなどもそうだが、キングス・オブ・レオンもまた、海外での人気と日本での知名度が最も大きく乖離しているバンドの代表格だろう。
かく言う私も、その乖離を作り出すのにしっかりと貢献しており、アルバム単位はおろか、曲単位でさえ彼らの音楽を聴いたことが全くなかった。
先日リリースされたばかりの新作『Can We Please Have Fun』を機に、全作をレビューしてみようと思う。
1st『Youth and Young Manhood』(2003)

USのバンドだが、まるでUKガレージロックのようだ。歌唱も演奏も前のめり気味に疾走し、サウンドは無骨で飾り気が無い。だがよく聴けば、『印象的なギターフレーズで一撃必殺』という安易な発想ではなく、あくまで全体のバンドアンサンブルで魅せようとする姿勢が感じられる。凡百のガレージロックバンドにありがちな、一本調子で勢い任せなスタイルとは明らかに異なり、アレンジ・楽曲展開が巧みだ。ファストな曲が中心だが、小休止的なスローな曲も甘ったるいバラードではなく、あくまで緊張感を保ったロックナンバーとなっているところも良い。アルバム全体を通じて、澱みなく一定のテンションを保ちながら一気に聴かせるハイレベルなギターロックアルバム。
2nd『Aha Shake Heartbreak』(2005)

無骨で飾り気の無い1stのサウンドが軸ではあるが、そこに鍵盤を加え、やや丸みを帯びた感がある。相変わらずファストな曲が中心ではあるものの、どうも勢いが落ちたように聴こえるのは、前作でキレッキレだったソングライティング、バンドアンサンブルに今一つ目立つものが感じられないからだろうか。どの曲も爆発寸前の期待感は抱かせてくれるものの、結局不発のまま最後まで行ってしまうようなもどかしさがある。終盤にフックの効いた楽曲があり若干持ち直すものの、1stの強烈なインパクトからすると地味な印象は否めない。
3rd『Because of the Times』(2007)

冒頭の"Knocked Up"からただならぬ緊張感が漂っており、明らかにスタイルを変えてきていることが分かる。前2作のスカスカぶりから一転、音の構造は格段に重厚さを増し、最初から最後まで途切れることなくシリアスで濃密な空気感が支配している。1stで見せつけたバンドアンサンブルの妙を更に成熟させたかのような演奏はもはや圧巻で、特に4曲目の"McFearless"、5曲目の"Black Thumbnail"で展開される静と動のコントラストはあまりにも見事だ。1stからの理想的な進化系。
4th『Only By The Night』(2008)

前作が素晴らしかったので一体どのように展開するのかと思ったが、本作もまた文句のつけようが無い傑作。ここがキャリアにおいて最も脂の乗った黄金期なのだろう。重厚で濃密な前作の路線を継承しつつ、よりドラマティックな響き、味わい深さがある。また、コンパクト感を意識しているのか、ギュッと凝縮してサッと終わる潔さがあり、それが功を奏しているように思う。一曲単位でのインパクト・爆発力なら前作に軍配を上げるが、アルバム単位での総合力・安定感では圧倒的に本作を推したい。
5th『Come Around Sundown』(2010)

2曲目"Radioactive"で小気味良く掻き鳴らされるギター、これまでになく強調されたシンセの心地良い音が、本作のムードを象徴している。重厚で濃密な空気感を封じ込めていた前2作とは異なる、開放的なムードだ。時に軽快でスタイリッシュなポップナンバー、時に哀愁漂うドラマティックなミディアムテンポナンバーを展開。フィジカル面での爆発力や瞬発力を期待し過ぎると肩透かしを食らうかもしれないが、ソングライティングは丁寧で堅実さがあり、これはこれで悪くはない。長いキャリアにおいて、こういう作風のアルバムがあっても良いとは思う。ただ、前2作の流れの良さを考えれば、もっと歳を重ねてからでも遅くはなかったのでは…等と考えたが、バンド側からしてみれば、リスナーが勝手に思い描くキャリアビジョンなど知ったことではないだろう。
6th『Mechanical Bull』(2013)

開放的でリラックスしたムードは前作から引き継がれている。前作と明らかに違うのは、アグレッシブさ、泥臭さ、男臭さだ。このバンドの音楽を言い表す際にしばしば用いられる、"サザン・ロック"や"サーフ・ロック"といったキーワードが最もよく当てはまる作品な気がする。それはいいとして、アップテンポな曲にしてもスローな曲にしても、やたら高らかに歌い上げる傾向がある。無理やり褒めるのであれば"雄大なスケール感がある"ということになるのだろうが、どうしても大雑把で捻りが無いように聴こえてならない。バンドの規模が大きくなったのは分かるが…。彼らのライブを観にスタジアムへと足を運ぶ観衆の多くがどんなセットリストを望み、バンドがどのようにして応えているのか私はまるで知らないが、本作の曲に負けじと初期の曲も躍動していてほしいと願う。
7th『Walls』(2016)
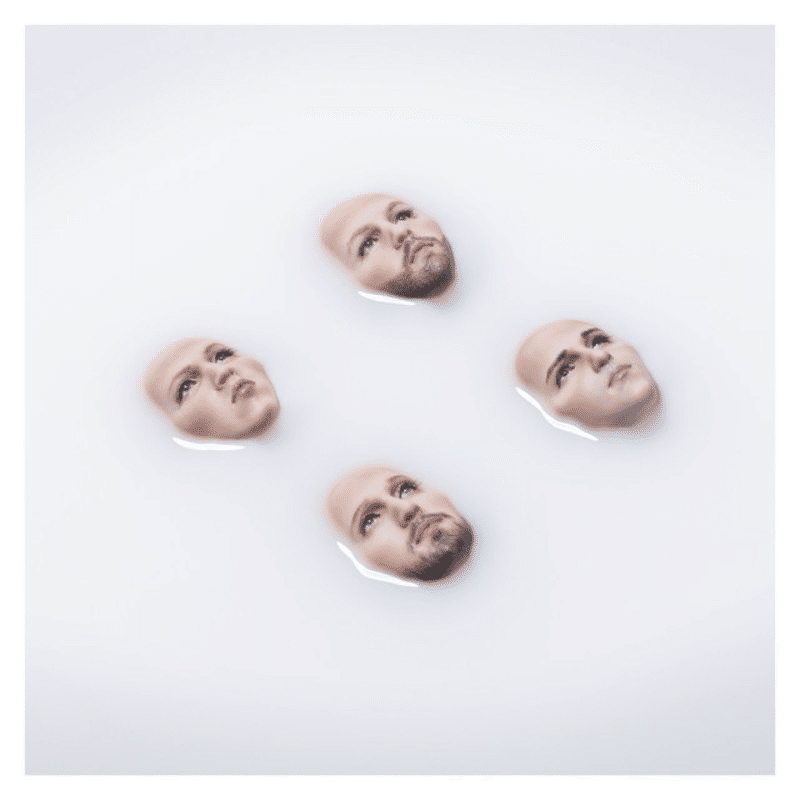
この謎なアートワークは一体何なのか?と言わずにはいられない。…触れたら負けな気もしたが、どうにも抗うことができなかった。肝心のアルバムの内容に、語るべき点があまり見つからなかったせいもある。本作もまた前作と同様に、取り立てて捻りの無い、やたらスケール感の大きい楽曲が並んでいる。ただ、泥臭いサザン・ロック的な要素が消え、生真面目で優等生的な、スタイリッシュな音が鳴らされているのは前作と異なる点だ。サザン・ロックという特徴がしっかりと示されていた分、まだ前作の方が良かったとも言える。ヒリヒリするようなバンドアンサンブルや展開は無く、ただただオーソドックスな曲が整然とコンパクトにまとめられたアルバム。と、ついつい辛辣になってしまうのは言わずもがな、これまでの作品によって期待値が上がりきっているからだ。
8th『When You See Yourself』(2021)

ここまで聴き進める中で、『キングス・オブ・レオンらしさ』とは一体何なのだろうかと考えた時に、"ファストで荒々しいロックンロール"などというキーワードを思い浮かべたりもしたが、本作を聴けばその考えは変わる。ミディアム〜スローテンポな曲が並ぶ本作からも、KOLらしさを確かに感じ取ることができるからだ。キャッチーなメロディや派手なリフなど無くとも、バンドアンサンブルの妙、その一点のみでじっくり聴かせられるのがこのバンドの最大の強みだと、私は本作で確信した。直近3作と比較して、シンセの使い方がまるで違う。印象的なフレーズを鳴らしてはいるが、前に出過ぎることはなく、あくまで脇役に徹している。"Golden Restless Age"〜"Time in Disguise"の味わい深い流れが特に素晴らしい。ロックバンドとして老け込んだだけのように捉えられかねない音楽性であり、私としても後半に関してはやや精彩を欠く部分もあるかとは思うが、それでも全体的には丹念なソングライティングが光っており、またここから新たな傑作を生み出していく上での転換となってくれる作品だと思う。
9th『Can We Please Have Fun』(2024)

冒頭の"Ballerina Radio"と"Rainbow Ball"のソングライティングに今一つキレを感じなかったので一抹の不安を覚えたが、"Nowhere To Run"や"Don't Stop The Bleeding"など、前作の路線を継承する味わい深いミディアムテンポナンバーもあり、中盤は持ち直してくれた。アルバム後半にかけては、"Nothing To Do"や"M Television"など、久々にアッパーかつ重厚なバンドサウンドを連打する流れが見られる。ただ、これがアクセント的な役割であればいいのだが、そのまま最後までキャッチー路線のまま突っ走っているように映る。中盤はソングライティングの良さが光っており非常にいい流れだっただけに、後半の展開には惜しい印象を受けた。方向性としては悪くないアルバムと思うが、個人的には期待していた所に一歩及ばなかった。
◇
最後に、個人的な順位を付ける。
1. 4th "Only By The Night" ('08)
2. 3rd "Because of the Times" ('07)
3. 1st "Youth and Young Manhood" ('03)
4. 8th "When You See Yourself" ('21)
5. 5th "Come Around Sundown" ('10)
6. 9th "Can We Please Have Fun" ('24)
7. 2nd "Aha Shake Heartbreak" ('05)
8. 6th "Mechanical Bull" ('13)
9. 7th "Walls" ('16)
順位を付けるのは悩むことが多いのだが、今回はかなり順当にすんなり決まった。
今まで全く聴いてこなかったキングス・オブ・レオンだったが、良いアルバム、特に上位4枚に出会えて非常に満足している。
願わくば、またキャリアハイを更新するような傑作を聴いてみたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
