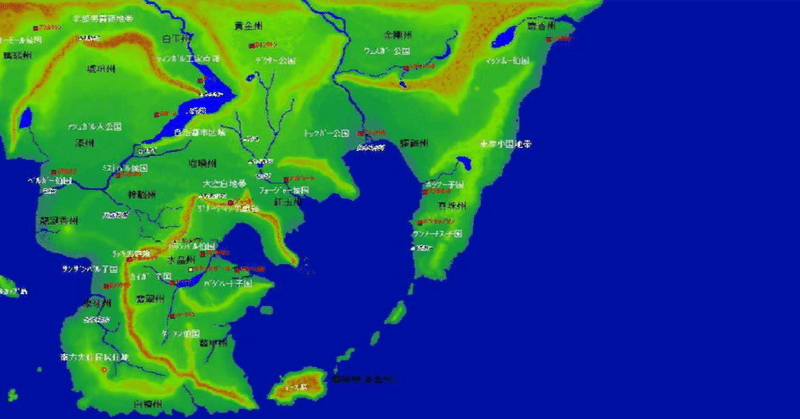
ティルドラス公は本日も多忙⑤ 嵐の年、国滅ぶ時(2)
第一章 ケーシを後に(その2)
帰国の準備を進めつつ、こうした付き合いもこなさねばならないという慌ただしい日々の中、王宮ではティルドラス送別のための宴席が設けられることになった。設けられると言っても費用は全て送られる側、つまりティルドラス持ちで、要するにティルドラスの金で朝廷の人間たちが盛大に飲み食いする席である。本当ならそんな席になど出たくないのだが、辞退することは許されず、わざわざ王宮に呼びつけられて事前の打ち合わせまでさせられる。
「肉料理はどのようなものがお好みでございましょう。」献立を決める大膳官がそう訊ねる。
「実は肉は苦手でして。どちらかと言うと、野菜入りの粥に漬け物あたりの方が好きなのですが……。」とティルドラス。
「肉はお嫌いで!」大膳官は目を輝かせる。「して、御酒はいかほど?」
「酒も苦手です。小さな杯一杯くらいなら何とか。しかし二杯ともなると酔いつぶれて不調法をしでかしかねませんので、できれば飲まずに済ませたいところです。」
「御酒もお上がりにならない!」大膳官はもう、興奮のあまり声を上ずらせていた。「あと、お菓子はどのようなものを?」
「あまり脂が強くないものが好きです。干し果物ですとか、糖蜜をかけたくず餅ですとか……。」
「では、乳脂のたっぷりかかった焼き菓子などはお好みではない! かしこまりました。そのように致します。」そして大膳官は恭しく一礼すると、ティルドラスの気が変わらぬうちに、とでもいった様子で、あたふたと彼の前を退出していく。
「そのように、とは、どのようになのだろう?」何が何やら分からず、呆気に取られるティルドラス。
三日後、王宮の片隅にある格の低い饗応の間で、ティルドラスを送別する宴が開かれる。出席者は主に朝廷の高官や王族たちだが、ケーシ滞在中一度も顔を合わせたこともない顔ぶれも少なからず混じっていた。王が臨席するほど格の高い宴席ではないとのことでゴディーザム王は顔を見せず、ルシルヴィーネの姿も見えない。
「お食事の半分は残されますように。」主賓の席に座ったティルドラスに向かって、付き添いとして傍らに立つフォンニタイが囁く。
「分かっている。」とティルドラス。宮廷のこうした宴席では出されたものを全て食べ尽くすのは失礼に当たる。出された量が足りないという意思表示と取られてしまうのだ。
とはいえ、この日の宴席でティルドラスの前に出された食事の量はあまりにも少なかった。
料理の品数そのものは多く、一度に何品も大きな盆に載せられて運ばれてくるのである。それがティルドラスの前に並べられ、膳部係の役人が「どれにいたしましょう」と重々しく尋ねる。彼が料理を選ぶと、それを役人が給仕に伝え、給仕が皿の傍らに控えた料理人に伝え、料理人が大皿から料理を取り分ける。汁物であれば掌に乗るような小さな碗の底に少しだけ。野菜や果物であれば葉っぱ一枚・実の一かけら。魚や肉であれば、もとの大きな塊から、よくぞここまで薄く切れるものだと感心するほど薄く小さな切れ端が切り分けられ、銀や青磁の大きな皿に丁寧に盛りつけられる。それが料理人から給仕へ、給仕から役人へと渡り、役人がしかつめらしくティルドラスの前に食器を置く間に、並んでいた料理は一つ残らず、まるで風に吹き払われたかのように、彼の前から運び去られて姿を消すのだった。
他の出席者たちは給仕を呼びつけては自分の望む料理を欲しいだけ持ってこさせ、盛んに食べている。ティルドラスだけが、彼らの半分にも満たないような量の食事しか与えられず、さらにその半分は残さねばならないのである。半分どころか、わずかでも彼の箸が止まれば、その瞬間に待ち構えていた給仕たちが彼の目の前から素早く皿を下げ、どこかへ持っていってしまうのだった。
せめてもの救いは、宴席の途中で何度も起立しては出席者たちの健勝と王の千秋万歳を祈念して杯を乾す場面があったにも拘わらず、いつものように酔い潰れることが全くなかったことだった。理由は簡単で、給仕の役人がいかにも親切らしく「伯爵は御酒を嗜まれぬとお聞きしましたので」と囁きながら彼の杯に注いだのが実は酒ではなかったからである。白葡萄酒のように見えたのは水で割ったただの茶で、赤葡萄酒のように見えたのは、猛烈に苦くて酸っぱい上にちょっと異様な渋みと臭気のある、何やら得体の知れない赤紫色の液体だった。後から聞いた話では、それは何かの樹皮を煮出した汁にりんぼくの実(スローベリー)だの葡萄酒の絞り滓だのを漬け込んだもので、タチの悪い酒商人たちが安物のリンゴ酒や水で割った焼酎に混ぜて偽の赤葡萄酒を作るため密かに、しかしおおっぴらに使っているものだったらしい。給仕の役人はどうやらその液体を原液のまま彼に飲ませたらしく、ティルドラスはその後三日ほどの間、胃の不調、そして交互に襲ってくる猛烈な下痢と便秘に悩まされるはめになる。
しかもこうした食事の間、傍らに立ったフォンニタイが自分の一挙一動にまであれこれと口を挟んでくる。――左手は常に膝の上に置き、食卓の上に上げることは厳に慎まれますように。羮を召し上がる時に音を立ててはなりませぬ。魚の切り身は左側から順に食べ進むのが礼儀。果物の種は皿の左上、縁から二寸の場所に集めておくものと決まっております。ああ、覇者・キッツ伯爵の嫡長の孫にしてハッシバル家の当主たるお方がそのようなことでどうなされますか、嘆かわしい――。
「………。」
何かの懲罰でも受けているかのようにティルドラスには感じられる宴席は正午から日没に至るまで延々と続いたが、その席で飲み食いできるのは身分の高い人間だけで、供の者たちは空き腹を抱えたまま宴が終わるのを待つしかない。ティルドラスの付き添いとして王宮にやって来たホーシギンも、饗応の間に入ることすら許されず、所在なげに周囲をぶらついて時間を潰すことになる。
歩き回るうちに裏手の配膳室までやって来ると、そこではティルドラスの前からほとんど手つかずで下げられた残り物を巡って台所の者たちが浅ましい争奪戦を繰り広げていた。
「誰が何と言おうとこの蒸し豚は全て我が輩のものである!」部屋の中央に仁王立ちになった大膳官が、居丈高に周囲の部下たちに向かって叫ぶ。「残った酒もむろん我が輩のものである。そこにある果物も――」
「いやいや大夫、あなたはまだお役に就かれて日が浅いからそんな事を仰られますが、そうやって何もかも独り占めされておられると、いずれ部下の誰かが王にお出しする料理の中に砂だの木の葉だのをこっそり入れて、それを大夫の責任にいたしますよ。長くお役目に就いていたいなら、ここは欲張らずに他の者たちにも気前よく分けておやりなさい。」傍らから、台所の者たちの顔役らしい男が脅すような口調で声をかけた。
「ハッシバル伯爵は良い方じゃ。有徳の君とはあのような方のことを言うのであろうか。」目の前に置かれた酒瓶を嬉しそうにさすりながら、年輩の給仕が言う。「何せ酒を一滴もお飲みにならなんだ。おかげで、伯爵にお出しするはずだった酒が残らず我らの役得となる。ありがたい事じゃ。」
「肉もほとんど召し上がらなんだ。このような方ばかりであれば良いのだが。」別の給仕も頷く。
別の一角では、誰がどの残り物を取るかでの言い争いも起きていた。
「この鍋に残った羮を私にいただきたい。その代わり、伯爵の食べ余した分は残らず貴殿に進呈いたす。」
「何を申されるか。そちらの方が三倍から多いではないか。」
「お願いだからその焼き菓子を半分ちょうだい。うちの子供たちは一度もお菓子なんか食べさせてもらったことがないの。せめて、一度だけでもいいから子供たちにそれを――」
「うるさい、うるさい、うるさい! よってたかって勝手なことばかり申すな! くじ引きだ! くじ引きだ!」
ホーシギンはため息をつく。
彼らを責めるのは酷というものだろう。清廉潔白をもって任じる朝廷の官吏には彼らのこうした行為を居丈高に咎める者も多いが、悪口屋で通っている割に、ホーシギン自身は一度も彼らに対して非難や侮蔑の言葉を投げかけたことはない。それも仕方のないことなのだ。礼制で定められた華やかな衣装や職務上の交際費、それら全てを自腹で賄わねばならず、物入りばかり多い割に薄給で、しかもその僅かな俸禄さえ滞りがちな朝廷の小役人たちにとって、時たま入るこうした役得は文字通り命の綱なのである。
いたたまれない気持ちになって裏口から外に出ると、そこでは残り物にさえありつけない雑色たちが裏口の周りを半円形に囲んで座り込み、配膳室から流れてくるご馳走の匂いをおかず代わりにてんでに餅だの雑穀の握り飯だのを貪り食っていた。
「腐っている。」足早に外へと抜け出し、見た目だけは美しく整えられた御苑の中を歩きながら、ホーシギンは吐き捨てるようにつぶやく。「ここでは何もかもが腐っている。しかも、誰一人としてそれがおかしいとは考えない。そこまで腐りきっている。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
