
THE RED PILL 赤い丸薬
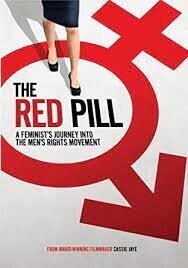
THE RED PILLというドキュメンタリー映画をご存じだろうか。Cassie Jaye(キャシー・ジェイ)というフェミニストが、男性がおかれている現状にMRA(men's right activists 男性権利活動家)へのインタビューを通して探っていくという映画だ。
弱者男性や反フェミニストの話に明るい方はご存じかもしれない。しかし、その映画の内容まで知っている方は少ないと思う。twitterの反応では気になっている方もいるようなので、稚拙ではあるがこのような形で述べさせていただきたいと思う。
出来るだけ映画の内容について細かく語っていきたい。なにぶん英語はあまり得意ではなく、間違っているものがあればコメントで教えていただけるとありがたい。
キャシー・ジェイという人物
この映画を撮ったキャシー・ジェイから述べていきたい。彼女はおとなしい子供だったようで、心配した母親が演劇を始めさせた。演劇を好きになった彼女は、18でハリウッドに行くことを決意するが、そこでは彼女の役はブロンドの髪をしたいつも死んでしまう役しか与えられなかった。そのように何か決めつけをされるのもそうだが、プロデューサーや写真家などからのセクハラがひどいもので、彼女は演じることをやめてしまった。
そこから彼女はフェミニストとなり、カメラを手にし、映画を撮るようになる。LGBTQ+、シングルマザー、出産といったもののドキュメンタリーだ。あるとき、キャシーはニュースでレイプカルチャーなるものの存在を目にする。それは女性自身がレイプを望んでいるといった記事で、A VOICE FOR MENというMRAが運営しているネット上のサイトに掲載されていた。彼女はそのような人物に一度でも話を聞いたことがあるかと問いかけ、少しでも理解できるように、件のサイトの記事を読み漁った。しかし、理解は難しく、行き詰った彼女はMRAのもとへ話を聞きに行く。彼女は”This begins my journey”とMRAへのインタビューが遠く離れた世界の話であったかのように語った。
これより後は、MRAへのインタビューとなるが、カメラが細かく切り替わり、様々な人物が入れ替わり立ち替わりインタビューに答えていく。映画のやり方とは異なり、一人ずつ自分が記憶に残った話を述べていきたいと思う。
Fred Hayward氏
Fred氏は責任を引き受ける家父長主義だった。曰く、何かが起こった際には女性や子供を先に逃がさねばならない、それは私が男であるから。女性は出産や子育てに子育てに追われる人生で選択の余地はないというがそれは男性も同じで、金を稼がねばならず、自分よりも弱い人間を守らねばならないと言う。彼の価値観は伝統主義的でフェミニズムと真っ向から対立していた。
彼が強く訴えかけていたのは子供の親権問題だった。アメリカでは約80%が母親のもとへ親権がいってしまう。彼もまた、親権を奪われた父親の一人だった。彼が ”もし君が女であると理由で会社から就職を断られたとしよう、そうしたら君はまた別の会社に面接に行くだろう。じゃあ、私が男であるという理由で親権を取れなかったとしよう、そうしたら別の子供の親権を取ろうなんてそんなことがあると思うかい?” と冗談交じりに言った言葉がとても記憶に残っている。
彼は14年間息子の親権を取るために法廷で戦ったが、体の衰えから戦うことが難しくなり、親権を諦めざるを得なかった。彼は戦うために裁判費用、子供の養育費などに彼の年収の5年分を使っていた。養育費を払わなければ親権を争うにあたって不利になるためだ。
詳細は省くが、彼は彼の妻と同じだけの育児をしていたにもかかわらず、親権を取ることが出来なかった。彼の妻は息子に対し、お菓子を好きなだけ与え、夜更かしも好きなようにさせていた。子供がある程度の年齢になると親権をめぐった裁判において子供の意見が通りやすくなる。妻の行動は母親と呼べるものではなく、親権を手にするためだけの、子供のことなど考えてはいないひどく醜悪な行動である。(事実、彼の息子は太っていることが原因で学校でいじめにあっていた)これもある種のDVであり、毒親的なものだ。
Fred氏だけでなく、親権を争ってきた男性のほとんどが法廷では、子供の世話は女性の方がいいという偏見は確かに存在するという。

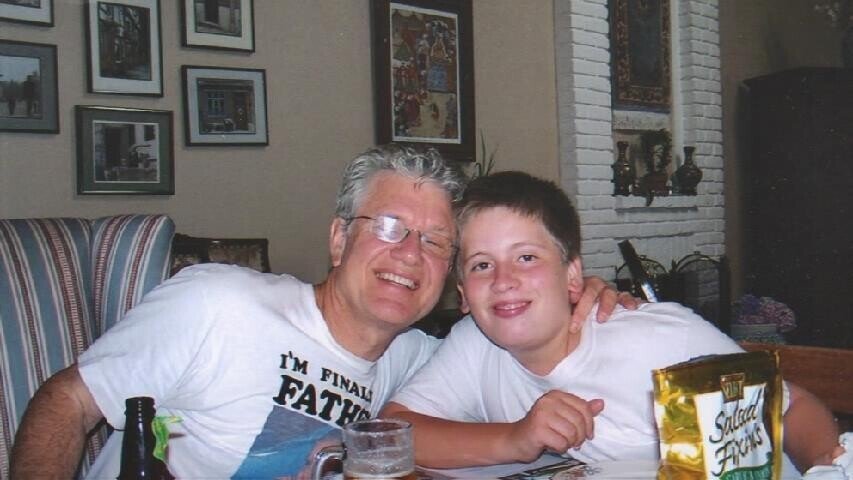
仲のよさそうな親子に見えるが、彼らは法の下では親子ではない。こんなにも悲しいことはそうない。
Harry Crouch氏

彼は声を荒げることはなかったが、どこか静かな怒りを感じるような話し方をした。彼はキャシーに対し、全ての悪は家父長制からきているというがあんたはこれを知っているかと、アメリカにおける男性の戦死者、職場での死亡者、殺人事件での死亡者、自殺者数についてキャシーに言い聞かせる。これらすべて友人や家族のために、あなたのために男は死んでいくのだと。これまでに存在した社会において女性は特権と保護があった、残念ながらそれらは男には無いものだという。
彼の強く訴えかけるものでは父親詐称、いわゆる托卵におけるものが上げられた。彼はテキサス州で起こったことについて語った。ある子供が怪我をし、病院に運ばれた。そこで父親が呼ばれ、輸血が必要だと言われ自分の血を子供に与えようとする、しかし、輸血はできなかった。その子供は自分とは血がつながっていなかったからだ。血のつながりがなくとも父親は子供を愛していた。しかし、この例では親が知っただけでなく、子供も知ってしまっている。どれだけの影響がこの家庭に与えられたのか、想像するだけでも苦しいものがある。Harry氏はなんと恐ろしいことかと”horrific ”と繰り返し口にした。
Paul Eram氏

この映画の主軸となる人物がこのPaul氏になる。彼はA VOICE FOR MENの設立者で、キャシーの目に留まった、レイプカルチャーの記事を書いた人物でもある。彼が一番パンチが強く、彼の書いた記事では ”10月は暴力的なクソビッチどもをぶったたく月だ” などミソジニックな言説が多く取り上げられた。これは理由のない暴力(女性の暴力は愛情表現や、男性のマゾヒズムを満たすプレイに見なされることが多い)における70%が女性によるものであるということを踏まえた記事だったが、その結果としてA VOICE FOR MENはヘイトグループとみなされてしまう。
正直、このような記事がほとんどの中、男性がおかれている状況を知るべく読み漁ったCassie氏には尊敬の念を抱かざるを得ない。現在の日本のジェンダー学(笑)ではできそうもないことだろう。彼ら、彼女らが小山晃弘氏の狂人日記を全て読めるとは思えないし、すべて読み、なおかつその人物にインタビューに行くなんて不可能なことだと思う。
Paul氏の話に戻ろう。彼は女性が責任を果たしていないことへの怒りがあるようだった。現在の女性は教育でも仕事でも何でもしたいことをすることが出来るようになり、女性の働き方は変わってきたという。しかし、男性は変わっていない、女性はトラックを運転することも、炭鉱で働くこともない。そこで女性が働いていないことを文句を言う人間はフェミニストの中で聞いたこともない。もし、船から誰かが下りねばならない時それは男性に期待されるものであると。女性の生活が変わり、さらに男性も変われというのはひどく傲慢ではないかと考える。
”the only answer to that I have ever been able to came up with is that people are not angry because they do not see men as human being” 彼はMRAが怒っている理由が分からない人々は男を人間扱いしていないからだという。男性活動家の活動にはフェミニストの妨害があるが、フェミニストには女性だけでなく男性もそこにはいる。ひどく口汚くののしられることもあるが、フィルムの中では男性活動家は声を荒げることはなかった。
この映画のタイトルであるRED PILLというのは英語圏におけるスラングであり、「THE MATRIX」という映画の中で登場人物が選択に迫られることになることに由来する。登場人物はblue pill(青い丸薬)かred pill(赤い丸薬)のどちらかを飲むように言われる。blue pillは飲むと快適な夢の世界に戻ることができる薬だが、red pillは飲むと今まで見えなかった世界の真実に気付くことができるという薬だ。そこからred pillという言葉は、苦しくとも真実を見ようといった意味を持つ。Paul氏はフェミニストはblue pillを飲んだ世界に生きていると痛烈に批判する。この世のすべての力は男が握っていて、男がDVをし、セクハラをし、女は同一労働でも男と同じ給料をもらうことができない。それらすべては男で解決しろと言う。そのような世界観が作られたのはすべてフェミニストのおかげだろうと、吐き捨てるように口にする。
フェミニストとの対比
この映画の中ではフェミニストがMRAの活動を妨害しようとするシーンが何度も出てくる。
カナダの大学で行われた「男性権力の神話」の著者である、ワレン・ファレル氏の講演を邪魔するシーンなどは象徴的だ。彼は、大学に入る際にフェミニストと思われる女性から口汚く罵られる。

しかし、ワレン氏は声を荒げることはせず、彼女が来ないところはないかと警備員に尋ねる。それでも罵ることをやめない女性に、「私は意見を交わしたいだけでどちらの立場でもない」と告げる。ワレン氏は男性学の主唱者ではあるが、その前にはフェミニズムに傾倒していたこともあり、決して女性のおかれている状況について無知なわけではなかった。
抗議活動は過熱していき、ワレン氏の講演に無理矢理入ろうとするフェミニストがいた。警備員は無理矢理会場の外へ出すが、それに対し、「あんたらは誰を守っているのか分かっているのか?」などと警備員に詰め寄る。

これが男が持つ権力だとフェミニストは叫ぶ。こいつらは何を言っているんだと呆れた顔の警備員の顔が強く印象に残った。
権利もないのに会場に入っては駄目なのは至極当然であるはずなのだが。正直、フェミニストの活動においてはどこの国でも変わらないものなのだろうと思った。
また、別のフェミニストの抗議活動が行われた。大学の構内でMRAの講演が行われていたようだが、廊下では会場に入ることのできないフェミニストが大声を上げ妨害を行っていた。

彼女たちは大声をあげるだけでなく、火災報知機を作動させ、むりやり男性活動家を大学構内から追い出した。そのことで歓喜の声をあげるフェミニストの姿は誰の目から見ても醜悪に映ることだと思う。
後日、大学の教室が使えないので路上でフェミニストと男性活動家が路上で意見を交わした。しかし、フェミニストは感情的でまともな議論ができるような状態ではなかった。

少しばかり悪意のある切り抜きをしたが、この写真だけでは彼女の男への憎悪のすべてが伝わるものではない。お互いに話をしたいと考えている男性活動家と男に話すことなどないと思っているフェミニストでは会話というものが成り立つことはなかった。
余談ではあるが、この赤い髪の女性は、フェミニストになり三年になるという。たった三年でこのようになってしまったようだ。フェミニズムの重病率の高さはすさまじいものがある。ステレオタイプなフェミニストの表現として、赤い髪で髪が短い女性というのが海外でのイメージらしい。そのような人物に目を付けられた際には一刻も早く逃げることをお勧めする。
Cassie氏の変化
キャシーは映画の中でビデオ日記をつけており、彼女の男性に向ける感情が変わっていく様を見ることができる。最初は男性の置かれている状況というものを知りたいだけであった。しかし、男性活動家と話をしていく中で、彼女は女性として生まれたことが不利だと思っていたのに対し、女性に生まれるのは恵まれてすらいると考えるようになる。キャシーは ”私は男性がおかれている責任を負うことは決して耐えられない” と口にした。


彼女はこの映画を撮り始める前はフェミニストとしての価値観が揺らぐことはないと考えていた。しかし、男性がおかれている状況を目の当たりにするたびそれが揺らぎ始め、映画の最後のシーンでは彼女は”私はもうフェミニストを名乗ることはできない”と告白して映画は終わる。おそらくこれは男性のおかれている状況を知ってしまったから出た言葉なのだろうと思う。少なくとも、もう見ないふりはできなくなってしまった。red pillを彼女は飲んだのだろう。
その他記憶に残ったこと
この映画の中で、キャシー氏はフェミニストでありながらもフェミニストに否定的な発言を多く取り上げていた。例えばスウェーデンでは男性税を取り入れようとフェミニストが活動していたこと、またインドではレイプに関する法律の中に男性被害者も含んで欲しいという要望に反対していたことなど映画の中で語られた。
また、父親詐称について抗議をしている男性活動家がラディカルフェミニストに言われた「私たちは出生時にDNA鑑定を行うことを良しとはしません。真実を基準としたくはないのです。フランスではDNA鑑定は配偶者の許可が無ければ違法なので、DNAは尋ねないでという意味を持つでしょう」といった発言には思わず耳を疑った。実際、近年になり托卵の問題は大きくなってきており、フェミニストが出生時のDNA鑑定に反対しているというのは有名な話だ。決して彼女たちは自分が抑圧者であるとは考えず、男性がすべての抑圧者であると考え、女性はその被害者であると考える。ゆえに彼女たちはblue pillの世界で生きていると言われるのだろう。
まとめ
正直に申し上げて、この映画で語られる男性の境遇について既知であるという男性は少なくないと思われる。自殺者、過労死、親権、托卵、DVの偏見、このような男性が抑圧されていることは何度もネット上でも語られてきたことだ。しかし、この作品ではフェミニストへのインタビューもあり、この二者においての大きな溝について明らかにした映画と言える。しかしながら、オーストラリアで上映された際にはフェミニストの手によって上映中止に追い込まれた。この件からもそうだが、もうフェミニストと対話を交わすというフェイズはとっくに過ぎてしまっているのではないかと感じてしまう。
主張
自分の考えを述べさせていただくと、フェミニズムというのは女性のエゴを開放する運動なのだろうと思う。それゆえに女性のなかで幅広く支持されている活動なのだろう。フェミニズムは男女平等主義などと呼ばれることがあるが、これは結局女性というものは抑圧されているという世界観を共有している者達が、女性の持つ権利を拡大することによって平等を目指すという活動でしかなく、女権拡大主義を現代に即したように言い換えたに過ぎない。残念ながら法の下での平等はとうに達成しているので、女性優遇を目指すと言っても差し支えない。フェミニズムは男性も助けるなどと言ってはいるが、そんなことは決してなく、期待をしない方がいいだろう。期待の熱量によっては己の身を焦がすことになる。
フェミニズムというものがどれだけ頓珍漢なことを言っているかは、この記事を読んでいる皆様ならご存じであると思うので、特段述べない。しかしながらフェミニズムが広く世界に伝播し、女性からの指示があるのもまた事実である。

フェミニズムは宗教で、狂っていると強く語る男性活動家がいた。世界の関節はとうに外れてしまったのかもしれない。
フェミニストは男らしさから下りてもいいというが、それは果たしていいことなのだろうかと思わざるを得ない。女らしさから解き放った結果、托卵であり、子供の連れ去りであり、男性を蔑視することになったのだ。私個人としては男らしさから解き放たれた瞬間、どのような悪徳が噴き出すのか見当もつかない。小田急事件はその両方が現れた事件というべきなのかもしれない。現状ではまだ男らしさというものは残っているように感じるが、男らしさから解放したところで社会が良くなる保証なんてどこにもない。
本邦においては男女平等というものはまだ百年もたっていない、まだまだ新しい考え方である。他の国を見回しても男女平等という概念はまだ数百年ほどしかたっていない。それが正しいという保証もない、まだまだひよっこの概念である。男女平等とは何なのかという議論のほかに、男女平等とは正しいものなのかという議論もまた同時にすべきではないだろうか。Twitterでは’91年世代大反省会が行われたが、私は今年21歳になる、生まれた時から世間がうっすらとリベラルに染まっている時代で育ってきた。個人を大切にしましょう、かけがえのない一人の人間なのです、そういった言葉はたくさん耳にしてきたため、リベラルを標榜する方々の差別意識には辟易している。結局私は、リベラルがよく盾にする若者はあんたらのことをクソだって思っていると言いたいだけだ。
最後に
Paul氏はblue pillではなくred pillを飲めという。アメリカではお目覚め文化なるものが流行ったらしいが、それは見たいものしか見ようとしないblue pillでしかない。つらい現実から目をそらすな、それは私たちにも言えることではある。女性を悪魔化するのはすべきではないことは分かっている、しかし、相手と同じ土俵に立ったうえで相手の横っ面を殴りつけてやりたい感情も同様に持っている。私はそのようなことをするつもりはないが、そのような手段を取るものが現れてもおかしくはないと考えている。
その他、red pillに関する質問があればお答えできることがあればしたいと思うのでコメントに書いていただけると嬉しい。
最後まで読んでいただき心から感謝申し上げる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
