
D&D5eに日本オリジナルサプリが出るという可能性
『ダンジョンズ&ドラゴンズ』第5版が日本独自のラインナップを展開するという中で、既存のサプリメントを翻訳するだけでなく、日本オリジナルのサプリメントも視野に入るのではないかと思った。
現状のD&Dそのままでは、平均的な日本人に対するアピールに関して、言語感覚を含むファンタジー観や絵柄が大きなネックとなっており、実際に『スターター・セット』や『デラックス・プレイ・ボックス』のプレイヤーキャラクターに日本人アーティストを招いたアートワークをあてる企画も公式に行われた。オリジナルのサプリメントはこれらの延長線上とも言える。
しかし、現状公式発表もなく、このような事をわざわざ行う価値があると判断される程日本国内でD&Dが成熟しているかと言われればNOであり、まだ突飛な話ではあるが、一つの可能性として聞いてもらいたい。
筆者の見解として、日本独自のサプリメントとして有望な候補を3つ考えた。
1. 設定の補完
公式の世界観に関しては、現状の第5版の日本語環境では十分とは言えないため、そこを補完する余地は存在するとは言える。
フォーゴトン・レルムやエベロンといった物質界メインのものや、九層地獄やメカヌスなど次元界に関するもののほか、ターシャやモルデンカイネンといった多元宇宙に名だたる名士達を紹介するものも捨てがたい。
ただ、これに関しては既存の本の再販や新規翻訳でも十分カバーできるのではないかという懸念もある。
フォーゴトン・レルム(特にソード・コースト)やエベロンに関してはホビージャパン時代の各書籍の再販はあり得るが、収録されているサブクラスや種族のデータの一部がのちのサプリメントで再録されており、データが古いものになってしまっているのがネックか。
一方で、英語版が2024年12月に発売予定の改訂版『Dungeon Master's Guide』では、多元宇宙に名だたるキャラクターたちに関する簡単な紹介がされると説明されているため、この需要は特別に対応せずとも時間をかければ満たされるとも考えられる。
さらに、近年ではD&Dのルールに関わらない、設定やイラストだけの書籍なども発売されており、単に設定を補完するだけならこのような書籍でよいとも考えられる。
『The Practically Complete Guide to Dragons』や「Young Adventurer's Guide」シリーズなどが存在し、主に子供向けに作られているものではあるが、D&Dの世界観を知る一助として、大人からも好評を得ているという情報がある。
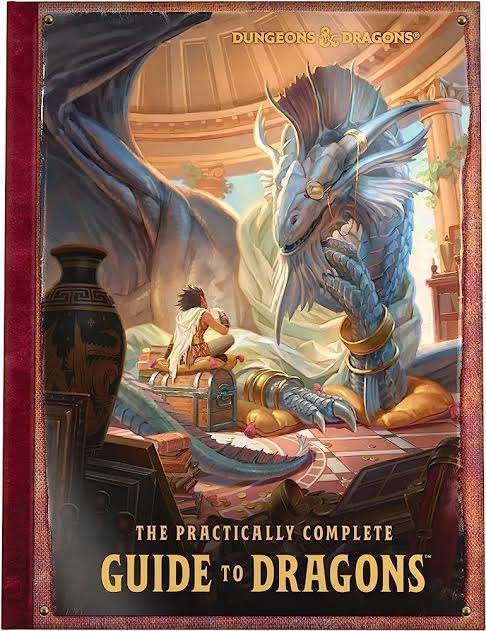
D&Dのルールとは無関係な公式書籍といえば、レシピ本『ヒーローズ・フィースト』は国内でボーンデジタルから発売されており、D&D本体の日本展開がウィザーズ日本支部に移った現在でも、既に第2弾『ヒーローズ・フィースト -美食の多元宇宙』の日本語版の発売が決定している。
ダンジョンズ&ドラゴンズの多元宇宙の料理を、ベストセラー『ヒーローズ・フィースト』の著者による75以上のおいしい新レシピで探検しよう
— ボーンデジタル出版事業部 (@bd_publishing) June 9, 2024
📕ヒーローズ・フィースト - 美食の多元宇宙 - D&D 公式レシピガイド(6月新刊)https://t.co/b9PkNqUZuA pic.twitter.com/vR2VWB0A6Y
こういった設定のみの書籍はゲームそのものには関わらないので、『ヒーローズ・フィースト』同様にウィザーズ日本支部ではなくボーンデジタルのような外部企業が販売権を得られる可能性もある。
2. 和風意識
日本を意識した世界観やシナリオは手っ取り早く共感を呼ぶことができる他、疎外感を呼ぶことなくD&Dの懐の広さをアピールすることができる。
カラ・トゥアのリメイク
『フォーゴトン・レルム』の世界観の一部として存在する、フェイルーン大陸からはるか東方の地「カラ・トゥア」を再登場させるというものである。
これは過去に『Oriental Adventures』として展開されたものだが、一部中国要素も混ざっている上、現在のD&Dに持ち込むには障害が多い。
最後にOriental Adventuresが登場したのは第3版時代、2001年のことであり、当時に比べれば英語圏から国外の情報へのアクセスは格段に向上している上、そのまま復活させるにはデザイン基準が余りにも違いすぎる。
わざわざ復活させるなら、専門家を招いてほぼ1から作り直すレベルの改変が必要になるのではないかと思われる。
しかし、それだけの障害を乗り越えたとしても、Oriental Adventuresのデザインの中心にあるのは忠義によって生き、忠義によって死ぬサムライやニンジャの姿である。日本人からは「外人が考える日本」像止まりになってしまう可能性がある。
そして、その部分をなんとか作り変えたとしても、今度は過去版のOriental Adventuresのファンから改悪、イメージの破壊であるというバッシングを強く受けかねない。
総じて、カラ・トゥアの復活に関して、筆者としては猜疑的である。
レイディアント・シタデルより「海津」の拡張
日本風の世界観といえば、多数の文化的ルーツを持つライターを集めた多国籍なシナリオ&世界観集『レイディアント・シタデル:光の城塞より』に収録された「海津」(うみづ)をさらに広げるという手もある。
本書の世界観はシナリオと地域の情報が両方掲載されているものがほとんどだが、世界観の情報だけが掲載されている地域のひとつとして海津が存在する。
新たにシナリオ本を作るにはお誂え向きと言えるだろう。
この件に関しては再び当時のライターとコンタクトを取れるかどうかにかかってはいるが、レイディアント・シタデルの英語版の発売は2022年と比較的新しいため、既存の資産を活かしやすいという点はメリットだろう。
MtGコラボ 神河
版元を同じくする『マジック:ザ・ギャザリング』の世界観とのコラボはどうだろうか。
2018年から21年にかけて、ラヴニカ、テーロス、ストリクスヘイヴンの3設定の本が英語で発売されたほか、ウィザーズ日本支部による展開開始以降、日本国内のMtGの大きなイベントには頻繁に出典している。
MtGを既に遊んでいるプレイヤーには洋物の絵柄を受け入れる素地があるという点はメリットである。
現状この関係性を利用しようという向きは日本公式からは見受けられないが、既存のラヴニカ、テーロス、ストリクスヘイヴンの世界観本以外にも、日本を意識したサプリメントとしてお誂え向きの世界観がMtGには存在する。
それは「神河」である。
2000年代初頭に登場し、中途半端な和風世界観(これもサムライ&ニンジャが中心にあった)などで人気の最下層にあった世界観だったが、2021年の『神河:輝ける世界』で現代の神河としてサイバーパンク×日本メディアモチーフというド派手なリニューアルを遂げ、人気を博している。
元がカードゲームである以上、流用しやすいアートワークが潤沢にある点はプラスであるほか、日本の伝承ないし国産メディアのお決まりをモチーフにしたオリジナルの呪文やアイテムなども期待できる。
ただ、神河の世界観はSF/サイバーパンク要素が強く、電子機器のインプラントのような肉体改造や、搭乗型のメカも多く登場する。これらは必ずしも魔法が関わるものではないため、魔法のアイテムとは異なる独自のルールが大量に必要になってしまい、世界観的に欲しい情報と合わせると紙面に納まりきらないのではという懸念がある。
日本モチーフのオリジナル世界観
もちろん、オリジナルの世界観を提供する事も考えられるだろう。
日本の伝承の世界において象徴的な妖狐や天狗といった人ならざる種族や、陰陽師や僧兵のようなアーキタイプはD&Dのクラスと種族という構成とも噛み合わせやすく、桃太郎や酒呑童子の討伐といった伝説の数々はD&Dのヒロイック像とも重なる点が数多くある。
信仰に関しても、フォーゴトン・レルムの設定に組み込まれた北欧やエジプト神話の神々のように、アマテラスをはじめとする日本神話や、弁財天などのような国産仏教関連のパンテオンを組み込むことも考えられる。
これは2014年版『Dungeon Master's Guide』に示されてはいるものの、公式な実例が存在しない「アニミズム」―緊密なパンテオンの実例にもなりうる。
3. 日本のファンタジー観
コンピューターのRPGを軸に、日本では独自の西洋風ファンタジー観が育っている。それを理解し利用するのはどうだろうか?
日本人デザイナーを招き、D&D多元宇宙をまたいで描かれるティアマトとバハムートの対立やロルスの暗躍などをつまみ食いしながら、日本人でもとっつきやすい世界観を提供することができる。
例えば精霊=エレメンタルへの強いフォーカスや、秩序性の権化たる神がフィーンドと同様に人々の害となり敵に回るなど、東洋の陰陽五行説や仏教などにルーツを持つ要素の数々は、キリスト教的バックグラウンドを持つ西洋のデザイン感覚ではたどり着けない共感を呼ぶことができる。
こういった日本を中心とした独自の西洋風ファンタジー観は、古今東西のメディアの「お決まり」をまとめたサイト・TV Tropesでも専用の記事が設けられており、欧米圏にとっていかに異質かが伺い知れる。
欧米圏の人が日本風、「Anime風」と言えば結局それは欧米圏好みの雰囲気に、日本のメディアでありがちと認識された要素を足しただけになってしまうことも予想される。特に少年漫画などの要素が顕著で、必ずしも上述の日本のファンタジー観などと噛み合わない可能性があり、国内のデザイナーを呼ぶ事の重要性がここにある。
しかし、ここまでやるなら国産のシステムでいいのではないか?という懸念は捨てきれない。
その上、D&D側の固有名詞などに頼れないという点こそあれど、オープンゲーミングライセンスで日本から独自に本を出して、ウィザーズの手を煩わせなくてもよいのではないかという懸念もある。
事実、国内でのOGLを用いた『フィフスエディション』展開に積極的なホビージャパンは、自社のカードゲーム『ラストクロニクル』の世界観を用いた『ラストクロニクル5E』を展開している。
これを踏まえた上で、現状日本でD&D5eに精通したデザイナーがホビージャパン程度しか見受けられないという点もネックである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
