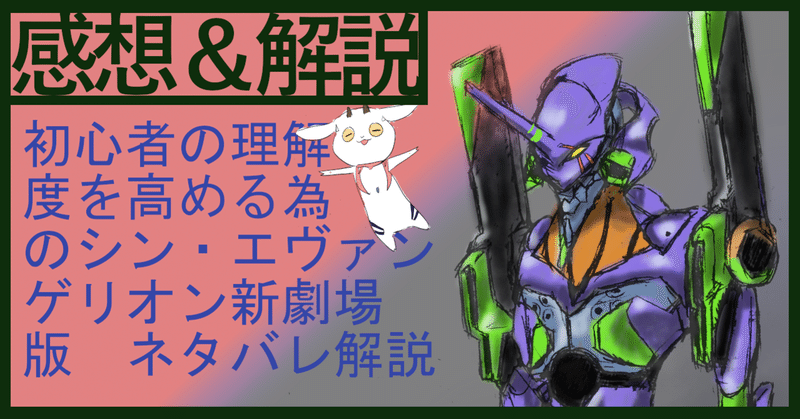
初心者の理解度を高める為のシン・エヴァンゲリオン新劇場版 ネタバレ解説
メ~メ~。
「シン・エヴァンゲリオン劇場版」は、もうご覧になったでしょうか。
ネタバレが自重される傾向が強すぎて、公式から感想をもっと書いて欲しいとほのめかされるほど、厳格なるファンやネタバレについて気にする人が多いことからも、エヴァンゲリオンの人気の深さが推定できるというもの。
さて、エヴァンゲリオンは1996年に開始されたテレビシリーズを発端とし、漫画やゲームといったメディアミックスを行われた作品となっています。
いわゆる、リビルド(再構築)作品として再び世にでた「エヴァンゲリオン新劇場版」シリーズですが、やはり、どこからみるのか、どう見ていくべきなのか、わからない人も多いと思います。
現在上映されている映画も、可能な限り見に行きたいという方もいると思いますのが、まるっきり知識がない中でみても、少し辛いところです。
当記事では、エヴァンゲリオンを見るうえでの最低限の雰囲気と、後半には、理解を深めやすくなるような他作品も含めて紹介しつつ、率直なネタバレ感想を含めてお伝えしていければと思います。
エヴァンゲリオンはどこから始まった
今回の映画のみを楽しむのであれば、「エヴァンゲリオン新劇場版 序」から順番に、「破」「Q」とみていくのが順当です。
ただ、アニメシリーズやゲーム等も多数でておりますので、概要を知っておけば、新劇場版をきっかけに他も追いかけたい、という場合も便利かと思いますので、ざっくりと紹介していきます。
1996年のお茶の間がまだ晩御飯を食べているような時間帯に、「新世紀エヴァンゲリオン」は始まりました。
渋いオジさんである加地良治と、ミサトさんとのベッドシーンが放送されて、夕食を家族と食べながら、気が遠くなったことを今でも覚えています。
アニメ会社GAINAXによってアニメオリジナルとして放送された本作品は、夕方に放送する内容ではなく、14歳の少年少女がロボットに乗って戦うという、よくあるフォーマットなはずなのに、倦怠感あふれるシーンと子供たちの自意識が爆発しており、放送当時はそれほど人気がありませんでした。
ただ、当時にわかに注目を浴びていた、深夜アニメの時間帯に再放送されたことで、一気にブレイク、その後は、世間で騒がれアニメを見ていない層が一気に見たことで、社会現象としてメディアに取り上げられることになります。
当時の深夜アニメといえば、「星方武侠アウトロスター」とかが放送されていたりと、なんか面白いものが放送されそうな時間帯ではありましたね(これは、たんなる思い出話です)。
「シン・エヴァンゲリオン」をより楽しみたい方は、テレビシリーズも見返すとより面白いとは思いますが、アニメから始まり、その後の社会現象の中で漫画はもとより、「鋼鉄のガールフレンド」といったゲーム作品へと広がっていった、というところだけ抑えておけばエヴァンゲリオンの成り立ちについては十分かと思います。
GAINAXとはどういう集団だったか、庵野秀明とはどういう人なのか、という点については、また機会があれば紹介させていただきたいと思います。
長くなりましたが、「シン・エヴァンゲリオン」の見どころを含めつつ、エヴァをあまり知らない方は、どういうスタンスでみていけばいいのか、陥りやすい罠を含めて、ざっくりと語ります。
宗教用語や世界観はデコレーション
「ロンギヌスの槍」
「ガフの扉」
「人類補完計画」
「セカンドインパクト」
「エヴァンゲリオン」シリーズの特徴としては、なんだか格好いい単語がすごく多いということが挙げられます。
それらについては、考察すればするほど沼にはまってしまい、エヴァンゲリオンの世界観に引きずられて、結局、この話はどういう話なんだ、ということを見失ってしまう要因になってしまいます。
ショートケーキにおいてイチゴは大切なものですが、そのイチゴが豪華過ぎて、ショートケーキの生地に手をつけないのは本末転倒というものでしょう。
ざっとエヴァの世界観を説明すると、「セカンドインパクト」と呼ばれる大災害で、人口が半分に減り、一年中夏になってしまったというのが、この世界です。
そこに使途と呼ばれる怪獣(?)がやってきたので、ロボット(エヴァ)で、子供たちが戦う、という大まかなストーリーラインとなります。
新劇場版からエヴァを見る人は、映像として写されていても、いまいち説明されない事柄も多いと思います。
例えば、赤い海。
セカンドインパクトによって、海が赤くなってしまった、というのが新劇場エヴァンゲリオンです。
なんで、セカンドインパクトが起きると海が赤くなるのか。ニアサードインパクトによって大地が赤くなってしまったのはどういうことなのか。
そんなことは考える必要は、ありません。
もちろん、そこが気になった方は、深い考察をされている人がたくさんいますので、そちらを参考にしていただきたいと思いますが、あくまで、初心者の方が作品を楽しむ場合には、それらの言葉は、ケーキの上のデコレーションだと思ってくださって結構です。
様式美も抑えておく
といいながら、話は脱線しますが、ロボットアニメというものは、ある程度の様式美というものが存在します。
主人公はロボットに乗って戦うわけですが、主人公が戦う理由、というものが存在します。
熱血な主人公であれば、俺がみんなを守る、といえばいいですし、自分の親類縁者が作ったロボに乗るとか、そういうのがあればいいのです。
ただ、現代においては、ロボットに乗るからには理由が必要です。命をかけて戦うのに、謎の使命感を頼りに戦うわけにはいきません。
「機動戦士ガンダム」であれば、戦争に巻き込まれる中で、生きるためにロボットに乗り、成長しながら仲間のためにロボットに乗る、という、理由を成長と結びつけたりするといった、主人公の内面描写を含めて描かれるなど、その理由は重要なものになりますし、物語における、主人公のモチベーションとしても大変重要な役割を持っています。
翻って、エヴァンゲリオンはどうでしょうか。
主人公の碇シンジは、親から見捨てられたと思っています。
親である碇ゲンドウに呼ばれるまで、彼は田舎で暮らしており、センセイと呼ばれる人の言いつけを守りながら生活していました。
近年流行った「うっせぇわ」という曲がありますが、いわゆる、大人しくて真面目な子供が主人公です。
碇シンジは、繊細で傷つきやすく、親から捨てられたという意識をもちながら、それでも親に愛されたいという屈折された想いの中で、いい子を演じます。
誰にだって、他人によく思われたい、というものがあるとおもいますが、エヴァにおいて、碇シンジという主人公は、14歳という他者への警戒心が増大する年齢ということも相まって、非常に精神状態が不安定です。
いきなり、親に呼ばれて、エヴァンゲリオンに乗れと言われる。
見知らぬ女の子が、自分の代わりにエヴァに乗るというが忍びないから、わがままをいいつつも、いい子を演じている彼は、エヴァンゲリオンに乗り込みます。
「ガンダム」における主人公アムロ・レイが、ガンダムを通じて仲間との関係を築いていくという点を考えると、エヴァを通じて碇シンジというキャラクターが成長していく話というのが、内面的な動きになります。
誤解を恐れずにざっくりと解説すると、新劇場版の「序」で、主人公はエヴァに乗ることを受入、「破」では、やる気を出そうとしたら世界が壊れかけて、「Q」では、壊れた世界でみんなに無視され、「シン・エヴァンゲリオン」においては、自分が何のためにエヴァに乗るか、ということをはっきり意識します。
ロボットものの様式美というものを意識すると、それはそれでエヴァの見方は変わります。
エヴァをどう見るか。
外側ばかりをなぞっているような記事になっておりますが、感想に入る前に、エヴァンゲリオンは結局、どういう話なのか、ということを誤解を恐れずに書いていきたいと思います。
オタキングこと岡田斗司夫氏が社長となって立ち上げたアニメ制作会社「GAINAX」。
ガイナックスはアニメに対して熱い想いをもち、庵野秀明氏含む、天才的な実力を保有した人が多数所属していた伝説的な会社です。
「王立宇宙軍 オネアミスの翼」を制作する為に作られた会社は、その興行的な失敗を背景に、結果として「トップをねらえ」「不思議の海のナディア」といった名作を生みだしていきます。
そんな「GAINAX」による「王立宇宙軍 オネアミスの翼」は、アニメーターたちの内面をむき出しにした作品でもあります。
我々とは異なる文明の中である異世界を舞台に、ロケットを打ち上げる男たちを描いた物語となっているのですが、そのキャラクター達は、アニメを頑張っているスタッフたちの内面と深くリンクしている、というのが特徴です。
アニメは子供たちに向けながらも、大人も楽しめるものを、といった流れの中で、俺たちの内面を見ろ、と打ち出された作品は、のちの多くの作品に影響を与えています。
作家性と置き換えてもいいですが、作品を通じて、クリエイターの内面を露出させていく、という行為を読みとることができる作品となっています。
作品作りに係わっていた庵野秀明氏もまた、エヴァンゲリオンでもこの手法をつかいながら、作られており、ある意味において、キャラクター達のそれぞれが、庵野秀明監督の、様々な人格としてみることによって、作品は、本来の内容から解き放たれて、見えやすくなっていきます。
庵野秀明の私小説として捉える
さて、話はどんどん横道に逸れていきますが、エヴァンゲリオンを庵野秀明監督の私小説的なものとして捉えてつつ、各キャラクターの内面をみていく、というところに、一つの面白さを見出してしまうところです。
「新世紀エヴァンゲリオン」の社会的なブームと名声とは裏腹に、庵野秀明監督は、苦境に立たされます。
アニメというのは、あたるか当たらないかは、博打と同じです。
良いアニメを作ればあたるというものではなく、クリエイターである以上悪いものは作りたくはない。
極大のヒットを飛ばしてしまった庵野監督が、いつまでも、エヴァンゲリオンにとらわれてしまうというのは無理らしからぬことです。
本人が、というよりは、世間がとらわれてしまうところですね。
ガンダムをつくった富野由悠季監督が、いつまでもガンダムを求められてしまうように、庵野秀明監督もまたエヴァを求められてしまう。
そんな苦悩の中で創作や現実から逃げてしまう男を描いた、庵野秀明実写映画「式日」では、庵野秀明自身のことだろう、とツッコミたくなるような内容となっていますので、気になった方はぜひご覧いただきたいと思います。
さて、ここから、ようやくネタバレを含めた感想を述べていきたいと思います。
ネタバレ感想。
「シン・エヴァンゲリオン」においては、様々な言葉や設定があり、ついついそちらに気持ちを奪われそうになりますが、上記の事柄を意識してもらいつつみてみると、庵野秀明監督自身の気持ちの移り変わりがよくわかります。
また、安野モヨコ夫人による「大きなカブ」の漫画をみてもらうと、庵野秀明氏か立ち上げた「スタジオカラー」がよくわかるところです。
さて、シン・エヴァンゲリオンを見て、驚くのは、その生というものの描き方です。
アニメシリーズにしても、映画作品にしても、死が意識された作品として描かれています。
悪の親玉に見える、ゼーレと呼ばれる人たちも、人間の争いや死への恐怖など、よかれと思って人類補完計画を行っていますが、その方向性は、現実の肯定にはなっていません。
どことなく非現実的な世界の中で、無機質な生と死が積み上げられているのがエヴァンゲリオンの雰囲気だったはずが、「シン・エヴァンゲリオン」はまったくの逆です。
物語の冒頭では、コア化した(また、こんな感じの用語がでていますが、汚染された場所みたいなイメージで読み解いてください)パリを、ヴィレ(そういう組織名です)が解放しようとするところから始まります。
そう、今回の作品は、既に冒頭から、無機質な世界から、現実を取り戻す物語なのです。
「Q」でショックを受けすぎた碇シンジ(ちなみに、庵野秀明監督もまた、Qの完成後、鬱病状態となり長く休んでいるような状態でした)は、赤い町をさまよいながら、第三村と呼ばれる場所で生活することになります。
そこには、自分よりも14歳年を取った、同級生たちが暮らしています。
ここで驚くべきは、みんながとにかく優しいことです。
人類がとことん崩壊して、食料なども乏しい中、シンジが無気力になっているのに、はっきりと怒る人は、委員長のお父さんぐらいです。
「出されたものを食べないのは、失礼だぞ。シンジくん」
同級生である、鈴原トウジは、まぁまぁ、と義父をなだめますが、かつて、物語の前半で、躊躇なく主人公を殴っていたやつとはとても思えません。
「生きるためには、人にはいえんようなこともやった」
第三村で気づくのは、死ではなく、生です。
猫はおなかを大きくさせて子猫をつくり、鈴原トウジもまた委員長と子供をつくっている。
第三村は、かつての都市生活と比べると散々たる状態であるにも関わらず、生があふれているのです。
生をまったく感じさせない、綾波レイというキャラクター(劇中では、そっくりさんと呼ばれている)が、黒いプラグスーツを着た上から麦わら帽子をかぶり、おばさんたちと一緒に、田植えをします。
この違和感のある光景。
第三村では、それぞれの人間が助け合い、自分たちができることを必死に行っていますが、どこか朗らかです。
ニアサードインパクトと呼ばれる現象によって、人類はほとんどがいなくなってしまった世界とはいえ、その中で彼らは懸命に生きており、驚くことに、その災害について、誰一人として文句を言っていないのです。
勿論、苦労や辛いこともあったでしょうが、それを踏まえて、主人公であるシンジ以外のキャラクターは、みんな大人になっていたのです。
「シン・エヴァンゲリオン」は、まさに、主人公たちが大人になる、という話であることに尽きます。
映画を一度みただけだと気づきずらいかもしれませんが、式波アスカというキャラクターは、とにかくキツイことを言ってきます。
ですが、アスカなりのやさしさであることに気づきます。
優しい言葉をかけるだけがやさしさではないのです。
えてして、若いころ、特に14歳のころなんかは、他人の親切を煩わしく思ったりしますし、言葉の意図を読み違えたりするものです。
無理やりレーション(いわゆる戦闘食料と呼ばれるもので、非常に美味しくない)を食べさせて栄養をつけさせたりします。
食べること(生)を拒絶していたシンジくんが、やっぱり、お腹が減ってしまって、結局レーションを食べてしまう、というシーンは、食べなきゃ人間腹は減る、という当たり前でありながら、自分が一人では生きられないことが一番よくわかるエピソードです。
そうやって、いろいろな人のおかげで世の中ができていることがわかったり、自分のことを考えてくれる人がいると思うと、大人にならざるえない、というか、大人になってしまうもの、だったりします。
拗ねていたシンジくんも、そっくりさんという犠牲を経て、ようやく、エヴァンゲリオン(ヴンダー)に乗る決意を固めるのです。
そのため、物語の前半ではとにかく、子供的な反抗や、隷属が多かったシンジ君は、物語の後半において、きわめて大人になっています。
大人になることで、初めて、父親という存在と対等に話ができる。
「子供が親にできることは、親を殺すか。親の肩をたたいてやることぐらい」
と劇中で言われてますが、まさに、シンジ君は、実は、一番の子供であった父親の話をきいてあげて、願いを叶えてあげるのです。
全てのエヴァンゲリオンにとらわれた人へ
細かい内容に関する解説や感想については、他の有識者に譲らせていただきたいと思いますが、今回のエヴァンゲリオンの終わらせ方が、非常に見事だった、という点においては、異論が少ないのではないかと思います。
物語は始めるよりも、終わらせるほうが難しいのが常です。
どんだけ物語の序盤が面白くても、広げた風呂敷がきれいにたたまれていないと人は不満に思うものです。
そして、物語の性質上どんな、終わらせて方をしても、次回作があるように思ってしまう作品になりかねないのも、エヴァンゲリオンの恐ろしいところです。
「さようなら、すべてのエヴァンゲリオン」
初見の人が理解しずらい点としては、本作品が、非常にメタ作品であることが挙げられるでしょう。
メタであるということはどういうことかといいますと、物語というのは、常に物語の中でルールが完結しているものですが、それを超越(メタ)してしまっている作品が、エヴァンゲリオンとなります。
旧劇場版においても、映画館で映画をみている観客が映されるシーンがあったりして、アニメの出来事と現実世界とが地続きであることを暗に示してきていました。
新劇場版では、ゴルゴダオブジェクトと呼ばれる、世界そのものを書き換えてしまう装置がでてきて、それを物語のキャラクターたちが書き換えてしまう、というやり方を行っています。
意味がわかりづらいかと思いますが、ミステリーの世界でも時々やられていた手法で、本当の犯人は、編集者だったとか、作者本人こそが、本当の犯人だったのだ、といった具合に、本の外側に犯人を求めたりするアクロバティックな手法もあったりしたわけです。
それをやりすぎると、物語が破綻してしまうので加減が難しいところですが、「シン・エヴァンゲリオン」では、それを、おまじない、という形で行っています。
綾波レイこと、そっくりさんは、何も知らない子供のような存在として第三村で生活します。
「おはよう、って何?」「おやすみ、って何?」
委員長は、そんな当たり前すぎて疑問にも思わないことを、そっくりさんに説明するのですが、そのときに必ず、「おまじない」というのです。
挨拶はおまじないではないはずですが、今作品においては、おまじないなのです。
呪術的なるおまじない
さて、このおまじない、という点からの考察については、ガイナックス元社長であり、評論家、大学で講師も務めたりしたことのある岡田斗司夫氏の解説がもっともわかりやすいので、ぜひそちらをみていただきたいと思いますので、気になった方はyoutubeで探して頂きたいと思います。
庵野秀明監督が、「シン・エヴァンゲリオン」をおまじないというものを意識して作っているのは、明らかです。
儀式と言い換えてもいいですが、何かに呪われたとき、人は、儀式を必要とします。
学校の卒業式、20歳になった際の成人式、入社式といった時々発生する、式とよばれるもの。
庵野監督の実写映画「式日」が、そのまんまだったりするのも面白い点です。
人というのは、式があることによって変わる。
エヴァンゲリオンは、我々の多くの人の心に良くも悪くも呪いを残しました。
大人になれない、という呪縛。
「シン・エヴァンゲリオン」を見終えて思うのは、ああ、終わったな、という感覚でしょう。
主人公たちはみんな大人になり、いつまでも、子供のままではいられないということを教えてくれる。
最後に、様々な犠牲のもと、世界を書き換えた主人公は、庵野秀明監督の故郷である山口県、宇部新川駅へと舞台が移ります。
大人になった主人公と、安野モヨコ夫人の象徴であるマリという女性は、駅を駆け上がっていきます。
線路の反対側には、その場に残るといっていた綾波レイと渚カヲルに似た男女。
呪術的には、河であるとか、線路とかそういう何かを隔てるようなものの向こう側というのは、異界であるという呪術的な考えがあります。
そのあたりの設定がお好きであれば、「呪術廻戦」を参考にみてもらえればと思いますが、漫画を紐解くまでもなく、人間というのは、おまじないの影響を受けるものです。
こうしていきる我々の世界は、すべてのエヴァンゲリオンを犠牲にして作り上げた、エヴァのいない世界かもしれませんが、向こう側の世界にはまだキャラクター達はいます。
そして、我々の世界には、エヴァがいたかもしれないわけです。
エヴァンゲリオンは、たしかに終わった。
そんな式日を迎える為にも、エヴァンゲリオンにはまったすべての人たちに、見逃さず見て頂きたいのが、「シン・エヴァンゲリオン」となっております。
様々な苦悩を経て、庵野秀明監督自身が、大人になった。おそらく、10年前ではとうてい作れなかったであろう作品です。
「もしも、願い一つだけ、叶うなら」
宇多田ヒカルの曲が流れて、「終劇」とでたときの、終わった感じは、格別です。
あと、2時間以上の長い作品なので、体調管理は大事ですので、お気をつけください。
補足的作品
さて、ここからは、作品への理解を深めるために、見ておくとわかりやすくなる作品について紹介していきます。
庵野秀明監督は、特撮もの(仮面ライダーやウルトラマン等)の影響が大きいことは知られており、シン・エヴァンゲリオンにおいても、その影響が大きいことは知られています。
ただ、もともと、特撮が好きな人であれば抵抗はないと思いますが、なかなか映像のジャンルが異なるものに手を出すのは大変だと面ますので、アニメ作品で、関係はないのですが、理解の一助になる作品を紹介してみたいと思います。
シン・エヴァンゲリオンをみて、前半はわかるけれど、後半はまったく意味がわからない、という人がいるのではないでしょうか。
最後の最後に、現実世界に戻ってきて、「君の名は」的に、二人は出会うっていうのはわかっていても、マイナス宇宙で戦うという時点で、置いていかれてしまう人もいるはずです。
マイナス宇宙は、いわゆる、精神世界と考えてもらえればいいかと思います。
物理的な世界と異なり、魂といっていいのかわかりませんが、精神的なもののほうが重要な世界です。
「人間では知覚することができない」
と劇中でもされておりますが、東映のセットで戦ってみたり、ミサトさんの部屋で戦ってみたりというのは、あらゆるイメージと世界が直接結びついた世界だからです。
「量子テレポート」
といった単語もでてきますが、物理的な移動ではなく、精神的な移動を行うという点で、碇ゲンドウは、マイナス宇宙の利にかなった行動をして、それに適応しているという点で驚嘆していた、ということです。
頭でわかっていても、法則の異なる場所というのは、そもそもイメージがつかないものです。
さて、この手の戦いでは、「天元突破グレンラガン」の最終話付近は、まさにこんな感じです。
銀河を巻き込む戦いに発展し、精神世界がでてきたり、ありとあらゆる力のインフレが多発して、最後には、次世代に想いが託されて終わるアニメです。
こりゃわからないと思ったら、この勢いで終わらせてしまう本作品をみることで、一気にマイナス宇宙であるとか、そういった話がわかります。
ようするに、根性があるやつが一番強い、といったところでしょうか。
エヴァンゲリオンでは、そこまで単純ではないですが、おまじないによって作り上げられた世界や行動の中で、犠牲を払いながら、世界を書き換えることで、世界(庵野秀明監督や、とらわれた人たちの心)を救う物語が、「シン・エヴァンゲリオン」となっております。
細かい用語や設定は、あとのせサクサクのトッピングだと思って、そんなものだと思いながら、なかなか大人になれなかった庵野秀明監督が、いろいろな犠牲や、いろいろな人たちの力を借りて、大人になるための大きなカブを引き抜いた物語としてみると、複雑に見えるエヴァンゲリオンを素直に楽しめるようになるかと思います。
以上、初心者の理解度を高めるシン・エヴァンゲリオン新劇場版 ネタバレ解説でした。
次回も、メーメー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
