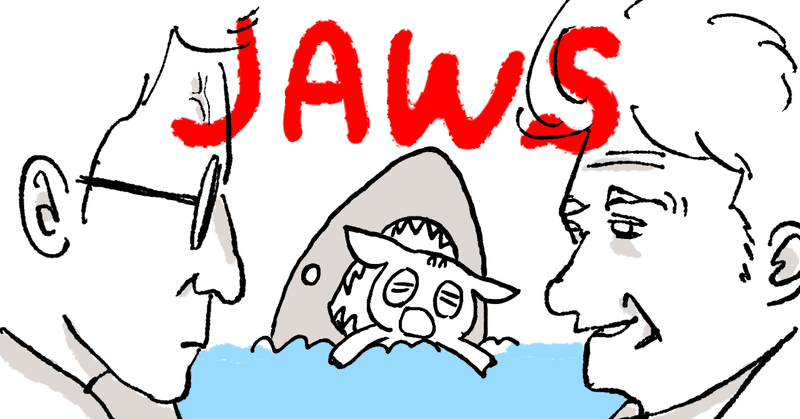
サメは意外と出てこない。映画「ジョーズ」
公 開:1975年
監 督:スティーブン・スピルバーグ
上映時間:124分
ジャンル:アクション/スリラー
見どころ:サメ

特徴的な音楽、現れる巨大な、サメ。
サメ映画といえば、スティーブン・スピルバーグ監督の代表作の一つ「ジョーズ」でしょう。
「ジョーズ」そのものは、監督を変えながら4作品ほどつくられていますが、何よりも大きいのは、サメという生物が、後のB級映画におけるモンスターとして大きすぎる影響を与えたことでしょう。
「MEGザ・モンスター」や、サメの恐怖とストーカーの恐怖を合わせた「サメストーカー」まであったりしまして、映画界におけるサメの知名度を爆上げした作品でもあります。
また、映画の歴史においても、その興行収益の凄まじさ、スティーブン・スピルバーグの2作目でありながら、その名声を高めるきっかけともなった作品でもあることから、映画をよく見る人にとっては、避けて通れない作品ともいえるでしょう。
とはいえ、本作品は1975年公開の作品となっていますので、改めて、見るにあたって考えておくと頭に入りやすい内容を踏まえつつ、本作について解説してみたいと思います。
前半と後半でジャンルが違う。
当たり前ですが、「ジョーズ」といえばサメがでてくる映画です。
その後に続々と誕生するサメ映画においては、ビーチで遊んでいる男女が次々と喰われる展開なんていうのはザラなので、サメ映画の金字塔である「ジョーズ」もついつい、そんな映画かと思ってしまいがちかもしれません。
「ジョーズ」は、アメリカの東岸部に位置するアミティ島で警察署長をしているブロディが主人公となっています。
海水浴シーズンを前に、サメに食い殺された遺体がでてきたことで、ビーチの閉鎖をしようとするブロディですが、観光業の収入低下を恐れる市長は、その事件をなかったことにしてしまいます。
前半の作品は、サメがいるにも関わらず対策ができないブロディ署長の気持ちに寄り添いつつ、実際に少年が被害に会うことで、サメの脅威があることを知りながら市民に被害をだしてしまった葛藤が描かれます。
単純にサメと人間という構図ではなく、人間の立場によって描かれる対立や、それでも、実際にサメがビーチに侵入してくる可能性があるにも関わらず、一般市民が気にせず遊んでいることへの恐怖感が見事です。
いつ事件が始まるのか、そのサスペンスの演出と、見たいものしか見ようとしない周りの人間のもどかしさも含めて、普遍的な作品としてみることができます。
印象付けのうまさ
「ジョーズ」の面白さは、やはり、その演出の絶妙さにあります。
巨大なサメは、だいたいにおいて、被害者の足に喰らいつきます。
足を引っ張られ、海中へと引き込まれる姿をみせつけられると、足の有無が重要であることがなんとなく刷り込まれていきます。
ブロディ署長の息子が意識を失い、海中から引き出されるときにその演出は際立ちます。
本作品において、上半身が無事であることは必ずしも、被害にあっていないことを意味するわけではないためです。
海から上半身だけで運ばれるだけでは観客である我々は安心できず、やや長めに映し出される足をみたときに、この子は生きているな、と安心できるのです。
恐怖の部分だけではなく、小道具の印象付けもうまく、高圧圧縮酸素ボンベは重要アイテムとして繰り返しでてきます。
これがちゃんと固定されておらず、ゴロゴロと動きそうになったり、実際に動いたりすることで、不安定なものの印象を与えます。
これが、登場人物の命を奪うきっかけになると同時に、サメを倒す最大の武器にもなるという点も絶妙です。
後半は、白鯨
物語の後半は、サメ退治のスペシャリストであるクイントが、1万ドルの依頼のもと、ブロディ署長と、海洋学者であるフーパーの3人で対決する話になります。
途中、ブロディ署長とフーパーにより、市長に対してどのようにしてサメ退治を決断させるのか、という部分もでてきますが、本作品の見どころは何よりも、戦いのあるでしょう。
「白鯨」といえば、ハーマン・メイヴィルの有名な小説となっており、巨大なクジラとの戦いを描いた作品となっています。
アーネスト・ヘミングウェイの「老人と海」を思い出す人もいるかと思いますが、海で、老人または、信念をもった人物が、海の生物と戦うという点において、思い出さずにはいられない作品でしょう。
「ジョーズ」にでてくるクイントは、クジラではなく、サメに対して執着している人物であり、無線機を破壊してでも、対決を望む姿は、「白鯨」にでてくるキャラクターと同じ発想だと考えても問題ないでしょう。
蛇足ですが、異世界ものの作品「Re:ゼロから始める異世界生活」においても、白鯨という魔物がでてきたりしますね。
男の友情は傷を見せ合う
海洋学者であるフーパーは、最新の道具を使うハイテクな人間である一方、クイントは、最低限の道具でサメと渡り歩くローテク人間です。
お互いがお互いをバカにした風でありながら、船の上で、お互いのケガした部分を自慢し合ううちに、すっかり仲良くなるあたりは、ほほえましかったりします。
灯台守の話である「ライトハウス」も、気難しい老人と、中年の大喧嘩の話でしたが、強い酒を飲んでいくうちに打ち解けていくあたり、海の男には、お酒が必要なようです。
キャラクターの面白さ
床にオイルが流れ、そこに火がつく。
船内に燃え広がりそうになっているのに、クイントは冷静に言います。
「署長、火を消せ」
トラブルが発生したときに何より大切なのは、冷静な判断力です。
クイントという人物は、サメ退治を長年やってきたこともあり、緊急時ほど冷静です。
海が苦手なブロディ署長というキャラクターもまた、市民を守る為なのか、家族を守るためなのか、揺れる船内へと乗り込みます。
若き海洋学者であるフーパーもまた、生意気そうでありながら、サメの事件に真摯に向き合います。
異なる3人のキャラクターが、船内で一つになっていく姿もまた面白いところです。
サメは意外にでてこない。
製作の裏話を知っている人であれば、有名な話ではありますが、「ジョーズ」は、思った以上にサメがでてきません。
黄色いタルが迫って来たり、壊れた桟橋が近づいてきたりと、サメが見えないことでサメの恐怖が倍増する演出が見事といわれ、実際に、それは効果を上げています。
しかし、当初は、作り物のサメ(通称、ブルース)が頻繁に壊れたことにより、思ったより使えなかったということが背景にあるようです。
結果として、ここぞという場面以外には、ヒレがでるだけであったり、音楽で匂わせたりで、演出による恐怖が増したということになっています。
また、ジョン・ウィリアムズの音楽もまた、誰しも聞いたことがあるのではないでしょうか。
でーでんでんでんでん、と迫ってくるような音とリズムは、映画史においても特徴的です。
音楽と絶妙な演出によって、サメ映画の原型であると同時に最高傑作が作られており、他の作品でもありがちですが、そのジャンルの最初の作品が圧倒的に面白い、という典型的な事例の一つともなっています。
「ジョーズ」だとカラー作品だからまだいいですが、いわゆる古典作品と呼ばれるものは白黒であったり、歴史的に重要であったとしても、様々な模倣が繰り返されていて、現代の作品に大量に触れた人間からすれば退屈にみえる作品も多くあったりします。
そんな中でありながら、「ジョーズ」は、オマージュされている原型をみることもできますが、その演出やテンポの良さ、人間ドラマも含めて、見劣りするものがない作品となっています。
また、アニマトロニクスで作られたサメは、CGが発達した現代においても、決して見劣りするものではありません。
むしろ、妙な生々しさがあったりして、逆に驚いたりします。
もし機会がありましたら、いわゆる名作を見返してみると、新たな発見があったりするかもしれません。
以上、「サメの出番が少ない大ヒット映画「ジョーズ」でした!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
