
上司がわからず屋なら「退職ブログ」を書いて辞めるしかないのか
経営学者・宇田川元一さんと劇作家・平田オリザさんの対談第2回。組織を強化し、前進させる「対話」の力。一方で、その足かせとなる世代間のギャップや教育の課題。そんな時に撤退するかもう一歩踏み込むか。今回はそんな「対話の難しさ」について話し合います。
※本記事は、2019年10月にcakes上に公開された記事を転載したものです。
対話を遮断する「身体的文化資本」の問題
宇田川 私が企業の中で、対話を促す仕組みの開発を行うにあたって、しばしば直面する問題がありまして。
外から見ると、問題だらけで困ってそうに見える組織の現場の人から、なぜか「私たちは特に困ってない」という言葉がよく出てくるんです。それでこれに対して、余計なお節介になってしまっては元も子もない。どうアプローチすればいいものか、と。

平田 いくつかの段階があると思うんですが、1つは問題を意識化できていないということですよね。なかったことにしてしまったり、見て見ぬふりをしてしまったり。その場合は、前回でも出てきましたが、意見を言いやすい環境をどう作るかということです。
もう1つの問題は、教育構造の問題だと思います。あまり世代論は良くないと思いますが、一方でやはり……。
宇田川 ありますよね。
平田 40代から50代の「上の言うことは絶対」つまりトップダウンの上意下達型の組織の名残りがある人たちですね。
宇田川 私の世代です(笑)。
平田 講演をするとその世代の方々からもよく質問を受けます。「自分たちはどうすればいいんですか」と。上は上意下達型の組織人だし、下はアクティブ・ラーニング※とかを経験している。2つの大きな世代に挟まれて、かつ就職氷河期とも重なっている、非常にかわいそうな世代なんです。
※アクティブラーニング:学習者である生徒が受動的となってしまう授業を行うのではなく、能動的に学ぶことができるような授業を行う学習方法
組織論的な視点で言えば、今後数十年に渡って、日本を悩ませる問題になるでしょうね。ただ、そういった問題があるんだということを意識化するだけでもずいぶん違うと思うんです。
一方で深刻なのは、若手の、特に女性の社員が「うちの上司はもう無理。変われないと思う」と言う人が多いということです。身体的な文化資本というのは大体20歳から25歳くらいで決定されてしまうんですね。特にジェンダーの問題や、女性に対する偏見がなかなかなくならないのはそのせいでもあります。
変われなくても上手く社交性で補える人はまだ良くて、たいていの上司は変わらず、自分のやり方を押し通してしまう。その場合はもう辞めるしかないですよね。対話は、相手にも参加の意思がないと成立しない性格のものですから……。
肉を切らせて骨を断つ
宇田川 ただ一方で、私としては、撤退という選択肢を持ちながらも、「もうひと勝負」することもあり得ると考えたい。

つまり、そいつ(上司)は変わらなくていいから、自分がやりたいことができるように、肉を切らせて骨を断つというか。実を確実に取りに行く、そういう意味での対話もあるのではないかと思います。相手にとってのトリガーは何なのかを見極めるといいますか。
最近、「退職ブログ」っていうのが流行ってるらしいんですけど、ご存知ですか。「私はこういう理由で、この大企業を辞めた」という。
平田 そんなのあるんですね(笑)
宇田川 あるんですよ。例えば「某大手メーカーは、全然自社の独自技術なんて持っていなくて全部外注してる。バカバカしいから俺はもう辞めた」みたいな。
平田 なるほど。
宇田川 こないだ、先輩がFacebookでシェアしていた「退職ブログ」にはこんなことが書かれていました。
「上司は数字のことしか言わない。使っているツールは古臭い。学ぼうとしない。こんなところで働いていても意味がないから転職した。転職先では、給料も上がって、今のところは幸せだ」という。
平田 なるほど(笑)。
宇田川 そのブログを読んで私が思ったのは、「なぜ、この人は会社というよくわからないものを変えようとしたんだろう」ということでした。つまり、会社が変わらないと、自分は何もできないと思い込んでいるところがあるのではないかと。
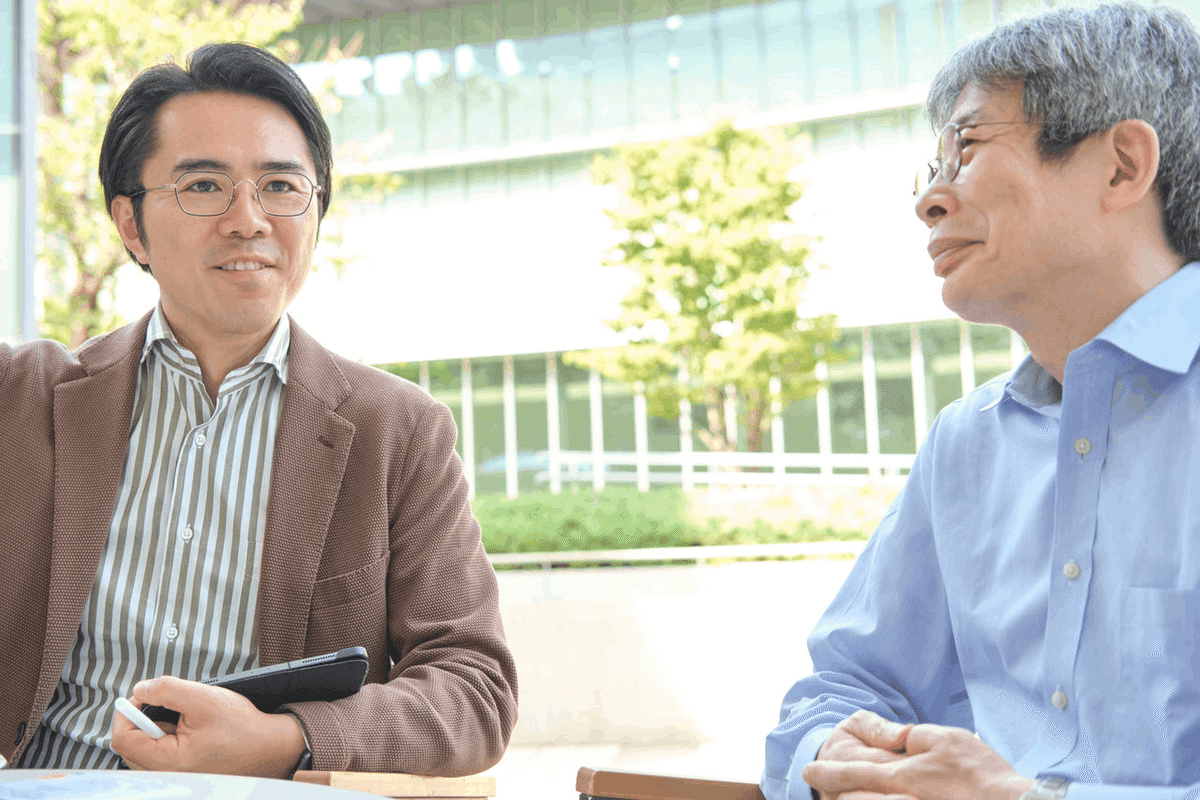
平田 そうですね。半径5メートルから変えていくしかないと思います。ただ、本当に酷い時は逃げるしかないんですけど。でも他者との関係をきちっと作っていけば、ちょっとずつ物事は変わっていくんだということが信じられるかは大切な要素ですね。僕は、それをよく小学生に言います。
宇田川 小学生ですか。
平田 小学5、6年生に演劇の授業をやったあとにこう言います。「今日の授業、みんな楽しくやったけど、ちょっとむずかしいところもあったよね。相手を論理的に説得できるとは限らないんだよ」と。
例えばメロンとイチゴの話です。メロンが好きな子をイチゴが好きな子にはできないし、逆もまた然り。でも、何らかの結論を出してお母さんに伝えないとどちらも食べられない。そこで「じゃあ、どうする?」っていうと全員が「話し合う」と言うんです。どちらかが妥協する。今日はイチゴで良いけど明日はメロンにしてほしい。両方出してほしい……。選択肢はいろいろありますよね。
要するに、自分の意見が全面的に通るなんてことは人生ではまれ。けれど、相手が何を望んでいるかを受け入れると自分の意見も通りやすくなる。ただ、このことって、教えないとなかなかできないんです。
宇田川 そうなんですよね。特にビジネスだとこじらせることが多い。短期的に結果を出さないといけないというプレッシャーがあると、視野が狭くなって、余計に互いの関心が焦点化しやすくなってしまう。
心のブレーキをはぐくむ
──そんな時に、引き続き対話を試みるのか、諦めて辞めるのか、その分水嶺はどこにあるんでしょうか。
宇田川 そうですね。私の経験に即して言うと、私自身も勤務していた大学を辞めた経験があるんですね。その時に感じるのは、1度離れると、辞めなくても良かったとか、まだできることがあったかな、ということに気づく場合もある。
1度撤退してみることで、自分自身を客観視できるというメリットはあると思いますね。さっき退職ブログのことを話しましたが、あれは私自身、過去にこの組織を変えなければいけないのだと思いこんでいたところがあり、その自分と重なって見えていたのです。そう考えられたのは撤退をしたことがあるから。
だから、1度撤退してみることも、そうやって考えるためには必要なことなのではないかと、敢えて思います。
平田 演劇のフィールドで例えると、俳優たちが、初めての演出家と組んだ時に、たいていは上手くいくんですよ。でもまれにどうしようもなく上手くいかない時がある。そんな時は、精神を病んでまで続ける必要はないということはハッキリ伝えます。
アートの世界の特殊な部分としては、人間の暗部を描くから、当然心が傷を負うわけです。例えば殺人犯も演じないといけない。“人を殺す”という心境について考えないといけない。それは非常に辛いことなんです。
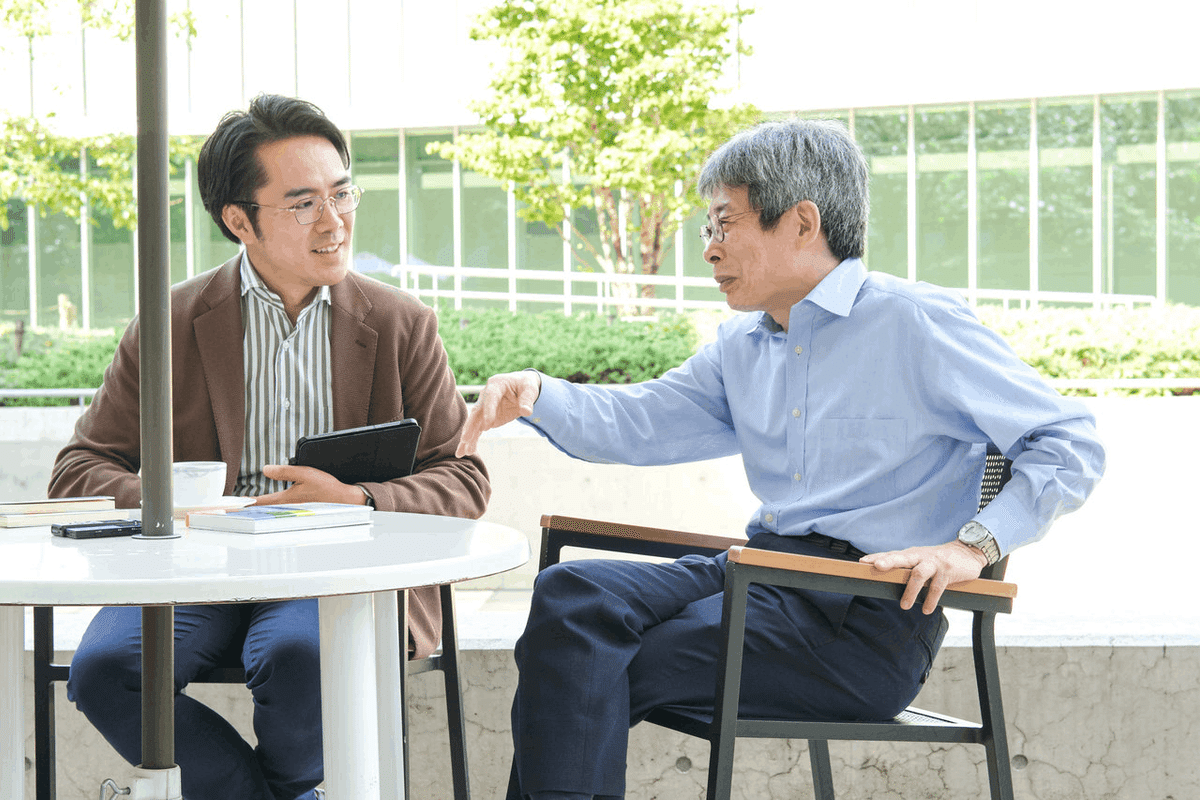
僕はよくアートの世界をチキンレースに例えるんです。つまり崖まで最高速度で走って、淵で止まって崖下を覗き込んで戻ってきた奴がアーティストになれる、と。しかし、崖から落ちたら精神を壊してしまうし、ゆっくり進むのは一般人と一緒。ただ、アクセルは教えられても、ブレーキはたいていの場合教えられないんです。
そんな時に心のブレーキになるのは友人だったり家族だったりする。要するに、相談できるネットワークを持てるか、ということも大切だと思います。
(編集:中島洋一 構成:吉田直人 撮影:小林由喜伸)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
