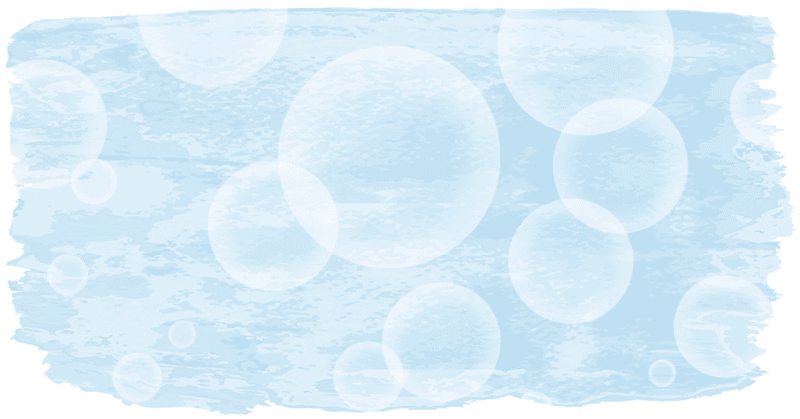
私の中の、多声を拾う。
先月から、日記を書き始めた。
あまりにも些細すぎて人には言いにくい出来事、他人のプライベートな話で感銘を受けたこと(を勝手に詳細を発信するわけにはいかない)、そして恨みや憎しみ、恥、寂しさや死にたさなどをこれでもかというほどぶつけている。私しか見ないから。誰が受け止めるでもない言葉だから。無責任に、読めないくらいに酷い字で、書き殴っている。
思うがままに感じたことやその日あったことを書き殴っているうちに、私の中で、人との会話で発する言葉、実際の行動、日記に書いている内容は、それぞれの場面、またはそれぞれの日付で、いとも簡単に裏返り、引き攣れ、矛盾してしまうことが見えてきてしまった。
たとえば一人になりたいと書いた次の日に、意気揚々と人に会いに行く。たとえばもう憎んでないと宣言しながら、恨みつらみを書き続ける。たとえば楽しかったとツイートしたその日の夜、ふと、死んじゃいたいな、と零れてしまう。
あの時、私は主体的だった。あの時、私は受動的だった。ああするしかなかった。自分がそうしたかった。相手がそう望んでいたから。相手がそう望んでいないとわかっていて。
出来事を振り返る私の言葉も、日によってまちまちだ。「本当」にそうだったのだろうか?「本当」は違ったんじゃないか?「本当」はああしたら良かったんじゃないか?
内省すら、浮かんでは消えていくその頼りなさ。をどう掴んだら良いのだろう。どうすれば「一つ」に練り上げられるのだろう。私の中の「正解」を探して、発見しなければならないのに。あてもなく書き始めた日記の前で、自身のばらばらさに腰が引けてしまっていた。
そんな折に、生活の批評誌No.4「【特集】わたしたちがもちうる"まじめさ"について」を手に取った。(https://seikatsuhihyou.hatenablog.com/entry/2020/08/12/192552)
自分の文章が載っている気恥ずかしさもありつつ、なんとなく何か縋るような、緊張した気持ちで読み進めた。「まじめさ」に「まじめ」に向かい合った文章たちの堂々たる存在感に、ほっとするような気持ちになりながら、インタビュー「いまここにある言葉を、書き記す――語りをめぐる”まじめさ”の話――」の一節が目に留まった。
「いわゆる近代的な作法ではないような書き方を作って、言葉をどうやって、多声のまま残していくかっていうのを考えています。」(p.45)
ここでは、瀬尾夏美氏がインタビューを行う際において、聞き手と語り手の言葉が「混ざってる」と語っている。自分の中に「解釈」がある聞き手と、「相手が聞きたがっていること」を想定しながら自分の主張を混ぜ込む語り手があって、その言葉は「両方”あいだ”」なのだと。
それは「人の言葉をどう取り扱うか」という「まじめさ」に触れた文章だったが、何故か私のばらばらな日記までも肯定されたような気分になった。
楽しかったし、疲れた。憎んでいないし、恨んでいる。やりたいようにやったし、ああするしかなかった。
たしかに、一つ一つがすべて実在する私の「声」なのだろう。その「声」に大小はあれど、常に存在し続けているのだろう。そして私以外の人にも。複数の出来事、複数の場面、複数の関係性において、さまざまな思いが、矛盾しながら、引き攣れながら、重なりながら、多声的に流れている。
「矛盾しないこと」が高潔な大人なのだと、何となく考えていた。けれど、その潔癖さから距離を置いてみて、もう少し、矛盾し続ける―多声的な私の―日記を書き続けても、良いのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
