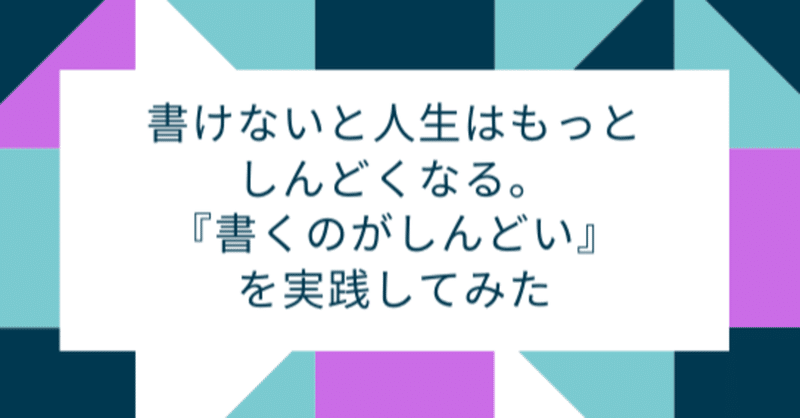
書けないと人生はもっとしんどくなる。 『書くのがしんどい』を実践してみた
「この本、役に立つの?」
そんな思いを持った方の少しでも力になれればと思い、始めた文章ノウハウ本実践シリーズ。9回目の今回は『書くのがしんどい』を実践してみました。『メモの魔力』や『実験思考』など数々のヒット本の編集を担当してきた竹村俊助さんが、なんと著者として素敵な文章本を書いてくれました。
最近は新型コロナウイルスの影響でリモートワークする方も増えてきました。そんなときコミュニケーションの基本となるのが、文章です。ただ、文章書くのが苦ではない、なんて人は少数派です。でも仕事では文章でコミュニケーションを取らなければなりません。『書くのがしんどい』なんて思うことも多々あるでしょう。そんな方々に本書はとってもおすすめです。書くことに苦手意識がある人は必読といっても過言ではありません。それぞれの章で例文を用いながら説明してくれたので、他の文章の本よりも理解できるスピードがはやかったです。
本著で紹介されているコツをかいつまんで実践しながら
・好かれる質問、嫌われる質問
について書いていきます!リモートワークでどう質問すればいいか悩んでいる人は例文も読んでみてください!では今回実践するにあたって参考にした章をご紹介します!
「文章のデザイン」を考える
文章のデザイン?なんだそれ?となってしまいました。だって、デザインは絵とか建築とかに必要であって、文章にデザインなんて必要ではないと思っていましたから。ただ、言われてみれば確かに文章のデザインも必要じゃん!となりました。
例えば改行が全くない文章だと、どれだけ内容が良くても内容にたどり着く前に読む気が減ってしまいます。世界で一番綺麗な夕陽が見れるとしても大の夕陽好きでない限り、そこにたどり着くまでに崖を登ったり幅50メートルの川を泳いで渡らなければならなかったら、見る気が失せてしまいますよね。それと同じように読み手の障壁はなるべく減らさなければいけません。読み手はそもそも興味がないことがほとんどですからね。
その障壁を減らす方法として、4~5行を目安に改行するが紹介されています。試したらすぐに効果がわかります。これから書く文章もこの「文章のデザイン」を意識します。
おもしろい文章は「共感8割、発見2割」
「共感」は文章においてもものすごく大事です。お笑いであるあるネタがウケるのと同じです。ではどのように「共感」を文章に組み込んでいけばいいのか。
「共感→発見→感動」の順で書くと、読まれるかつ面白い文章になると著者の竹村さんは言っています。少し難しそうですが、これも意識していきたいと思います。
ちなみに怪しいセミナーの宣伝は「共感」に加え、「夢」も混ぜ込んでくるそうです。怪しいセミナーでなければマーケティングにこの考え方は採用できそうです。怪しいセミナーでなければ。
「読み手のメリット」をいち早く示す
この文章は読むメリットは何か、をなるべく早く読み手に知ってもらわないと離脱してしまいます。文頭に持ってくる、もしくはタイトルに持ってくるといいでしょう。僕はタイトルに持ってこようと思います。
「たとえ」の達人になる
たとえは文章を魅力的にします。特に、半径3メートル以内のことでたとえることを、本書では紹介されています。
一冊の本から自分の好きな言葉を見つけると、宝探しに成功した気分だよね
少しわかりづらい表現になってしまい申し訳ないですが、上記の例文みたいな感じです。宝探しという誰にとっても半径3メートル以内の事柄に例えると、読み手にとって半径3メートルより外の出来事(一冊の本から自分の好きな言葉を見つけた時の気分)を伝えることができます。難しいですが、これは特訓あるのみです。
では、実際に例文を書いてみましたのでご覧ください。(結構良い文章書けた気がするので、別途投稿します)
タイトル:好かれる質問、嫌われる質問
面倒くさいと思われたくない。少なくとも仕事ではこう思っている。
ただ新人時代、この思いと裏腹にある行動を取らなければ仕事を進めることができない。「質問」だ。
相手の時間を奪い、自分のために使わせる。ジャイアンのようななんとも罪深い行為。仕事ができないジャイアンとか絶対面倒くさいと思われてしまう。でも質問しなければ仕事ができない。このもどかしさ、わかってくれる人はいるだろうか。
同時に質問するのが新人の仕事だとも思っている。だから質問をやめるわけにはいかない。
どうしようか。一旦自分が質問受けた時のことを考えてみた。自分が受けて一番億劫になる質問はなにか。瞬時に思い浮かんだ。
「これってどうすればいいですか?」
こう質問されると答える気が失せる。いやまあ自分の器の小ささの問題なんだけど。
まず「これ」を会話の中や文脈から読み取らなければいけない。つまり相手に余計な考える時間を費やさせてしまう。
また、質問者がどこまで理解できているのかがわからない。それはつまり、質問を受けた者がどういう説明をするのが適切かを見極めなければならない。掛け算までしか学んでいない人に微分積分なんて教えられないのと同じだ。何を理解しているかによって説明する内容は変わってくる。よって、どこまで理解しているかを掘り下げる時間が追加で生まれる。
そしてもう一つ、どうしたらいい?は答えにくい。つまりオープンクエスチョンであることだ。イエスかノーかで答えられる質問とは、回答にかかる時間が天と地ほどの差。また、イエスかノーかで答えてもらったら補足の説明も引き出しやすいという利点もある。それにオープンクエスチョンにはデメリットだってある。回答には時間かかるし、欲しかった答えが返ってこない可能性もある。だって相手も人間だもの。もう本当にまじで考えたけど全然わからない!ときは仕方がない。そんなときは
「ここまでは理解できたのですが、ここから先が30分考えたけどさっぱりわからないので申し訳ないですけどどうすればいいか教えてください!」
と開き直る。僕は開き直りの天才だから。ただ、これは最終手段。出来るだけ自分の中で噛み砕いてイエスかノーで答えられる質問まで落とし込む。
まとめると、指示語は使わない・自分の意見を混ぜる・出来るだけオープンクエスチョンはしないの3つが必要だ。これができればたとえ質問者が自分みたいな器の小さな人間だったとしても、面倒くさがられることはない。
色々と偉そうに書いてきたが、文章の締め方がわからない。
これってどう終わればいいんですか?
文章のデザインを意識して4~5行で改行しました。
また、タイトルには読むメリットをいかにインパクト大きく伝えられるかを意識しました。その結果最初は「いい質問、悪い質問」でしたが、「好かれる質問、嫌われる質問」に変わったのです。みんな好かれたいという欲求が少なからずあると思いまして。
「共感」も意識しました。読み手をリモートワークが盛んな時代の新入社員と捉え、質問しすぎて嫌われないか不安になっている感情を想定しました。
「たとえ」も複数の箇所で使っていますね。
相手の時間を奪い、自分のために使わせる。ジャイアンのようななんとも罪深い行為。
質問を受けた者がどういう説明をするのが適切かを見極めなければならない。掛け算までしか学んでいない人に微分積分なんて教えられないのと同じだ。
共感→発見→感動の順では少し難しい文章の内容になった(単純に感動で締める素材がなかった)ので、読後感を意識しました。途中で自分が一番して欲しくない質問を、最後に読者に投げかけることで、反面教師として印象づけようと思った次第です。少しアレンジしてしまいました。
文章を書く力が今の時代には必要不可欠
コミュニケーションの手段として文章が多くなってきたから必要ってだけでなく、人の気持ちを動かすにも文章の力は必要です。モノを売るにしろ、人を集客するにしろ、人を喜ばせるにしろ、文章はいろんな力を持っています。しかも今は目の前の人だけでなく、自分が知らない人にも届けられる時代。文章という飛び道具を使って、あなたの人生を変えてみてください。人生を変えるために、文章力という武器を『書くのがしんどい』を使って磨いてみてくださいね。
サポートありがとうございます!頂いたサポートは自己啓発のための書籍代に使わせていただきます!!
