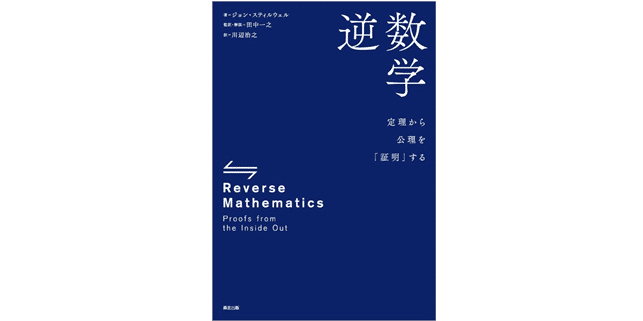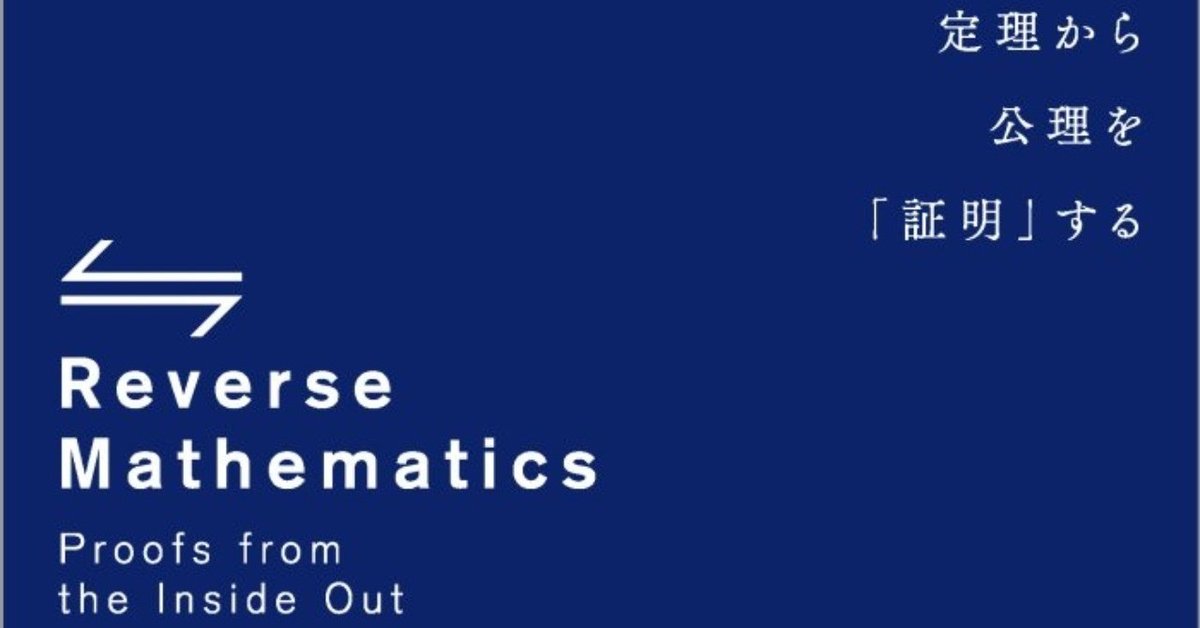
『逆数学』(ジョン・スティルウェル著、田中一之 監訳、川辺治之 訳)【監訳者解説公開】
「定理の証明には、いったいどれくらいの公理が必要なのだろう?」
この疑問にある種の回答を与えるのが、「逆数学」とよばれる数学基礎論の分野です。2019年2月に、その入門書『逆数学:定理から公理を「証明」する』が刊行されました。
この分野の第一人者である田中一之先生による「監訳者解説」を一部公開します。なお、田中先生は『数学基礎論序説 -数の体系への論理的アプローチ-』を2019年6月に刊行されており、こちらはさらに本格的な数学基礎論・逆数学への入門書となっています。
また、田中先生の「ヒルベルトのプログラムから逆数学へ」という記事が、雑誌『数理科学』2019年9月号に掲載されています。本書とも関連が深いので、こちらも読んでみてはいかがでしょうか?
『逆数学』監訳者解説(一部抜粋)
著:田中一之
本書は、数学についての精力的な執筆活動を長年続けているジョン・スティルウェル教授による待望の新刊Reverse Mathematics: Proofs from the InsideOut (Princeton University Press, 2018)の全訳である。
「逆数学(reverse mathematics)」は、数学の証明において明示的あるいは暗黙に用いられている集合存在公理や論理的諸原理を探査し、その必要性を検証することを目的とした現代数学基礎論の研究プログラムである。定理に対して公理の必要性を示すためには、定理から公理を導出することになるので「逆数学」とよばれている。そして、必要な公理の強さによって数学の定理を分類してみると、数学史の流れや、異なる理論間の感覚的な類似性がとらえられるというのがこのプログラムの特長である。
“Proofs from the Inside Out”という副題は秀逸なネーミングだと思う。日本語に訳しにくいので、本書の副題は意訳になっている。数学は、学ぶ立場で眺めると、公理から定理を導く証明の集積である。では、数学者は、材料の公理を加工して、定理という製品をつくり出す機械みたいなものか、といえば決してそうではないだろう。むしろ、ある定理を生み出すためにはどんな概念や仮説が必要か、あるいは、どうすればもっと少ない仮定で同じ定理が導けるかと考えていることが多いはずである。そのような数学の創造的思考は、完成した数学からは多くの場合読み取れない。では、数学の内側(inside)を探る方法はないだろうか。この素朴な疑問に対して、内視鏡のような強力な道具を与えるのが逆数学なのである。
その誕生からすでに半世紀近い年月が経ち、逆数学は数学基礎論の大きな分野に育っている。だが、本書のような入門レベルの解説はこれまでなかった。その理由は簡単で、現代の公理論的な数学について高校以前ではほとんど習うことがないため、逆数学を説明する以前に普通の現代数学を説明しなくてはならないからである。本書は、扱う数学を実数論と解析学の基礎に絞ることによって、高校程度の数学の素養があれば理解できるようなさまざまな工夫やわかりやすい説明がなされている。その代償として厳密さが多少犠牲になり、また逆数学の研究のダイナミックさが伝わりにくくなっているかもしれない。その辺は、あとで述べる参考文献等で補っていただければ幸いである。
ここで、数学基礎論の歴史について簡単に述べておきたい。数学基礎論は、19世紀の終わりに数学の基礎づけを目的に始まったが、20世紀前半のゲーデルの不完全性定理により、その目標は原理的に閉ざされた。しかし、ゲーデルの証明とそれに続く発見は多くの新しい技術を生み出し、数学基礎論は、集合論、モデル論、証明論、計算理論などの技術論に分かれていった。そして、それらを総称して「数理論理学」あるいは「ロジック」とよばれることが多くなった。だが、20世紀の終わりが近づくと、技術を追求するだけのロジック研究に分野内外から批判の声が上がった。とくに、アメリカ数学協会やアメリカ数学会の会長を歴任したマックレーン氏の随筆(『数学の健康』(1983)に始まる一連の論争に所収)に刺激されて、この分野の研究者たちは数学基礎論がどうあるべきかの再考を迫られた。そんな時代の風の中で、基礎論再興の先鋒に立ったのが、MITのサックス教授の門弟である、フリードマン、シンプソン、ハーリントンらであった。彼らの活動は逆数学のみにとどまるものではないが、新時代の基礎論の象徴である逆数学の発展への貢献はとくに著しい。
著者スティルウェルと逆数学の人たち
1942年にオーストラリアで生まれたスティルウェル氏は、大学院で渡米し、1970年にMITのロジャース教授(再帰的関数論の有名な教科書の著者)のもとで博士号を取得した。その後母国のモナシュ大学で長らく教えていたが、2002年に再び太平洋を渡り、サンフランシスコ大学の教授になった。モナシュ大学時代にはシュプリンガー社から10冊ほど純粋数学の教科書を出版しているが、再渡米後は専門だった数学基礎論の知識を活かして、より広い読者層に向けた啓蒙書を書いている。本書も後者の趣旨の一冊といえるだろう。
日本語に訳されたスティルウェル氏の著書には、オーストラリア時代の『数学のあゆみ〈上〉〈下〉』(朝倉書店、2005、2008)と、アメリカ時代の『不可能へのあこがれ:数学の驚くべき真実』(共立出版、2014)、『初等数学論考』(共立出版、2018)がある。これらを並べてみると、どれも広い範囲の数学を射程におきながら、その視座が段々と明確になってきているように思う。そう見ると、今回スティルウェル氏が逆数学について筆を執ったのも自然な流れに感じる。逆数学は、1970年代半ばにフリードマンが創始し、1980年代にシンプンソンと弟子たちが大きく発展させた。フリードマンもシンプソンも、スティルウェル氏とほぼ同時代(1960年代後半~70年代前半)にMITで学んでいるが、彼らの指導教員はロジャース教授ではなく、同じ分野のサックス教授である。とくにサックスの弟子たちが逆数学を推進したのは、再帰理論の一般化に関してサックスと交流をもっていた、証明論の権威クライゼルの影響が大きいと思う。クライゼルは謎の多い人で、ケンブリッジではヴィトゲンシュタインに師事し、アメリカに渡ってからはゲーデルと親しかった。彼は、博士号を取ったばかりの19歳のフリードマンを自分のいるスタンフォード大学の助教授に招いたのだが、その後仲違いし、公私に対立するようになった。余談だが、私の研究は逆数学をやや批判的に分析するものが多いので、クライゼルからは評価されて手紙のやり取りなどもあったが、実はフリードマンとはあまり交流がない。私の師匠はハーリントンだが、彼からシンプソンを紹介してもらい、学生時代から彼と交流できたお陰で、彼の本Subsystems of Second Order Arithmeticには、私の結果がたくさん紹介されている。
前世紀の終わりごろからは、私自身が東北大学で逆数学関係の博士論文を指導するようになった。本書に登場する坂本伸幸、横山啓太、堀畑佳宏の仕事は、彼らの博士論文にもとづく結果である。さらに付言すると、彼ら以外にも優れた博士論文を書いた学生たちはたくさんおり、新しい基礎論における私たちの研究は、世界的にもかなり注目されているだろう。
本書の概要と読み方
本書は8章で構成されているが、大観すれば、第1章~第3章は大学初年級で習う解析学の基礎について概説、第4章と第5章は逆数学の道具となる計算理論などロジックの説明、第6章~第8章は逆数学入門といったように、三つの部に分けられるだろう。(監訳者の便宜的な分け方に過ぎないが)各部ごとに概要と、読むうえのアドバイスを述べよう。
第I部 解析学の基礎
第1章「逆数学に至る歴史」は、現代数学においてはもはや常識となっている公理論的な議論の仕方や考え方について、さまざまな幾何を例に用いて説明してくれる。第2章「古典的算術化」は、かつては大学初年級の解析学の教科書には必ず書かれていた、自然数をベースにした解析学の基本概念の組み立てについて述べている。つまり、自然数のペアである分数として有理数を定義し、有理数の無限列や無限集合として実数を定義し、そして連続関数を定義していくような議論展開である。この議論を公理的に扱うために、ここではまず、自然数の公理系であるペアノ算術PAを導入する。実数や連続関数を扱うにはPAを拡大した2階算術が必要になるが、それについては第6章以降で述べる。第3章「古典的解析学」は、2階算術の公理系は持ち出さないが、あとでその上で議論することを意識して、実数や連続関数についての古典的な定理を解説している。
第II部 ロジック
第4章の「計算可能性」は、再帰理論あるいは計算可能性理論についての基本を説明している。逆数学は、再帰理論研究者による再帰理論を道具とした数学基礎論であるから、この辺の知識は必須である。ちなみに最近は、再帰的関数は計算可能関数とよばれることが多いものの、両者に若干ニュアンスの違いもある。計算可能性は標準的自然数に対するメタ数学概念であるのに対して、再帰的関数は形式的概念として扱うことが多い。たとえば、算術の超準モデル上でも再帰的関数は自然に考えられるが、その上で計算可能性は何を指すのかわかりにくい。第5章「計算の算術化」では、計算可能性あるいは再帰性を算術の論理式で表現している。とくに、再帰的集合はΣ_01でもΠ_01でも表せる(Δ_01という)ことに注意する。
第III部 逆数学入門
第6章「算術的内包公理」では、2階算術の公理系として、算術的内包公理の体系ACA_0が導入される。この体系はペアノ算術PAの自然な拡張(保存的拡大)になっており、最初に扱う形式体系としてはなじみやすい。その反面、逆数学的な議論の筋道は見えにくくなっているかもしれない。たとえば、6.3節で実数の完備性について議論しているが、実数の定義は次章に後回しにされている。第7章「再帰的内包公理」で、実数を縮小閉区間列で定義しているが、これは通常の逆数学の定義(収束率を伴う基本列)よりもわかりやすくてよいと思う。第8章「全体像」では、数理論理学の知識を補足し、逆数学が定理の「深さ」に対する一つの尺度を与えているという話で大団円を迎える。
*
逆数学に関してこのような一般向けの本が出るようになるとは、前世紀には考えられなかったことである。本書を通じて一層多くの方々と新しい数学基礎論の意義と面白さを分かち合うことできれば、監訳者としてこれほど幸せなことはない。
出典:『逆数学』監訳者解説
田中一之(たなか・かずゆき)
東北大学大学院理学研究科数学専攻教授。カリフォルニア大学バークレー校博士課程修了(Ph.D.)。専門は数学基礎論。とくに、逆数学や不完全性定理の研究。著書に『ゲーデルと20世紀の論理学』(全4巻、東京大学出版会、2006-2007)、『数学基礎論序説:数の体系への論理的アプローチ』(裳華房、2019)、訳書に『ゲーデルの定理:利用と誤用の不完全ガイド』(みすず書房、2011)など多数。
***
『逆数学:定理から公理を「証明」する』
【目次】
第1章 逆数学に至る歴史
第2章 古典的算術化
第3章 古典的解析学
第4章 計算可能性
第5章 計算の算術化
第6章 算術的内包公理
第7章 再帰的内包公理
第8章 全体像
監訳者解説
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?