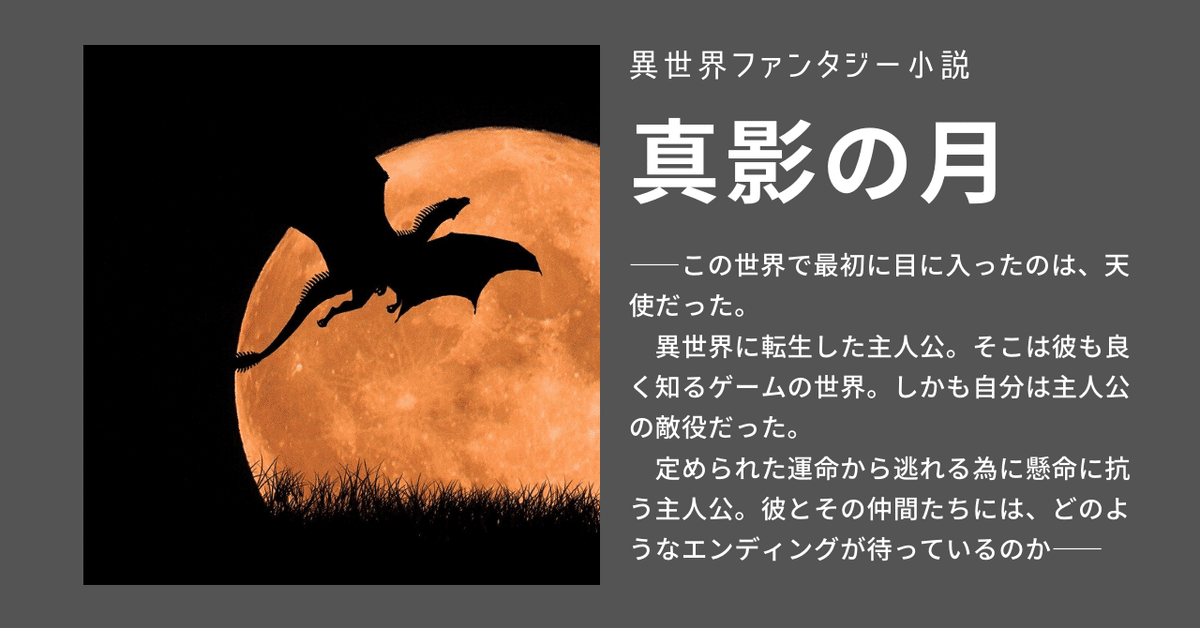
真影の月 真影の刻:第169話 潔さと往生際の悪さ。終わりの形は人それぞれ
ボルトン丘陵の戦いの結果はハートランド侯爵領にも届いた。これほど短期間で決着がつくとは考えていなかったシャロン女王。しかも三倍の兵力差がありながら完敗という、まさかの結果に呆然としている。
驚いたのはハートランド侯爵も同じ。戦況について報告を受けたあとは、厳しい表情のまま、じっと何かを考え込んでいる。
「周辺貴族家が攻め込んでくる可能性がありますが?」
ボルトン丘陵の戦いの結果を受けて、他の多くの貴族家はレイモンド支持に回るに違いない。中には点数稼ぎの為にハートランド侯爵の命を狙う貴族家もいるはず。それを家宰は忠告した。
「……分かっている。だからといってどうする? 領地を守る軍勢はわずか。戦っても勝てるはずがない」
ほとんどをボルトン丘陵の戦いに参加させたせいで、領地に残っている軍勢の数はわずか。守り切れる数ではないとハートランド侯爵は判断している。
「お逃げにならないのですか?」
負ける戦いを行う必要はない。勝てないのであれば逃げればいい。家宰はこう考えている。
「どこに逃げるというのだ? 私も考えてはみたが、逃げる先が思い付かない」
ハートランド侯爵が考えていたのは、この先どうするか。その中には当然、逃亡という選択肢もある。
「スコット王国は駄目ですか?」
「スコット王国に戦い続ける意思があるのであればいい。だがそうはならん」
「降伏するとお考えですか?」
「レイモンドがすぐに戦いを挑むとは思えない。おそらくは休戦を申し出て、スコット王国もそれは受けることになる」
ブリトニア王国は戦い続きで疲弊している。レイモンドが愚かでなければ、戦いを止めて、国力回復に専念するはずだとハートランド侯爵は考えている。
「……では侯爵様も降伏を申し入れてはいかがですか?」
「首謀者である私は許されん……いや、お前たちの為にはそれもなくないか」
ハートランド侯爵は簒奪の首謀者。それを許すことは、万が一レイモンドにその気があっても、出来ることではない。だがハートランド侯爵家全体のことを考えれば、ハートランド侯爵の命で済ませることに意味はある。
「いえ、我々のことはお気になさらずに」
「気にしないわけにはいかない。そうでなければ私は愚者として名を残すことになる」
悪あがきに家臣を引きずり込んだ愚かな貴族。そんな風に言われることはハートランド侯爵には我慢が出来ない。
「……承知いたしました。それでは早急に使者を送ることにします」
「私はどうなるの?」
ハートランド侯爵は降伏を決めた。死を覚悟した降伏だ。それを聞いて、シャロン女王は自分がどうなるのか不安になった。ようやくそう思えるくらいに気持ちが落ち着いたともいえる。
「……それは私には分かりませんな。レイモンドの気持ち一つ。そういうことだと思います」
シャロン女王の処遇をどうするか。ハートランド侯爵にはレイモンドの考えが読めない。一つだけ分かるのは自害してもらえれば助かるだろうというくらいだ。だがシャロン女王にその気がないのは分かっている。
「レイモンドに私が会いたがっていると伝えて」
自分が助かる為にはレイモンドと直接話すしかない。そう考えたシャロン女王は同行している諜報組織の人間にレイモンドのところに向かうように命じた。
「承知しました。ただ……」
「ただ何?」
「これが最後のご奉公になるかもしれません」
「えっ? どうしてそうなるの?」
「ブリトニア王国の王に仕えるのが我々の使命ですので」
「そう……そういうことね」
諜報組織はすでに自分を王として認めていない。そういうことなのだとシャロンは思い知らされた。
「正式な王が決まるまで我々は中立の立場で行動いたします。これをレイモンド様にお伝えする必要がありますので、シャロン様の伝言も間違いなくお届けします」
「レイモンドにわざわざそれを言うの?」
順当に行けばレイモンドに仕えることになる。そうであるのに、それまでは味方しないなどと伝える必要性をシャロンは感じない。
「そうしなければ組織が潰されてしまいます」
「えっ?」
「レイモンド様は敵に対しては非情な御方。そして今回は、それを隠すつもりはないと思います」
もともとのレイモンドがそうであるが、とくに今回は甘いところは見せられない。混乱を早期に終息させるために、レイモンドは力での支配を行うはずだ。力を持っている相手に対してだけだが。
ロンメルスでのレイモンドのやり方を諜報組織はちゃんと調べているのだ。
「……私は敵なのかしら?」
話を聞いたシャロンは顔を青ざめさせている。自分はレイモンドにとってどういう立場なのか。それ次第で運命が決まってしまうのだ。
「それは私が決めることではございません」
「……レイモンドの気持ち次第ね」
これを口にするシャロンはやはり甘い。自分の立場というものを分かっていない。
「いえ、決めるのはレイモンド様ですが、どう思われるかはシャロン様次第ではありませんか?」
「私?」
「はい。私はそう思います」
レイモンドに敵と認定されたくなければ、そう思わせるような行動を取るべき。レイモンドに生かしておいて役に立つと思わせるようなことを伝えるべきなのだ。
それを考えるヒントを諜報組織の人間は与えている。シャロンの為ではない。レイモンドの為だけでもない。諜報組織としてはブリトニア王国の国王を早く定めて欲しいのだ。そうでなくては自分たちが仕える相手が決まらない。
それに恐らくは仕えることになるだろうレイモンドには、諜報組織にとっての強力なライバルが存在する。元特務部隊にバジリスク。この二つの組織を超える、すぐには無理でも並ぶくらいの信頼を得る為に彼らは働かなければならない。
「……急いでレイモンドの、いえ、レイモンド殿の下に向かうわ。だから釈明する機会を作って欲しいとお願いしてもらえるかしら?」
シャロンはヒントを生かすことが出来た。少なくとも下手に出なければならないことには気が付いた。あとは得られた機会をどう生かすか。
「その場で、いや、会う前に支持を表明するのですな」
「えっ?」
さらに得られた機会を生かす為のヒントが、これはハートランド侯爵が与えてくれた。
「女性とはいえ、もっとも前王の血が濃い貴女がレイモンドの国王就任を支持する。願い出るが良いかもしれない。そうなると意を唱える者はいないでしょう」
「それをしなければどうなるのかしら?」
「また別の誰かが貴女を担ぎ出そうとするでしょう。すぐに行動を起こすわけではありません。レイモンドが何か失政を犯したり、そうでなくても貴族家の不満が溜まるような事態を待ってとなるでしょう」
レイモンドに厚遇されることにならなければ、そんな野心を持つ者も現れる。いつの時代もそうであり、ハートランド侯爵もそんな一人なのだ。
「…………」
そんな時が来る可能性があるのであれば。シャロンの気持ちに迷いが生まれた。
「レイモンドは馬鹿ではありません。それは分かっている」
「そ、そうね。助言ありがとう。私はレイモンド殿が国王になるべきだと思うわ。他に相応しい人はいないもの」
最後のヒントもシャロンは役立てた。これが分からないほどの馬鹿であれば、レイモンドに殺されるべきだろう。ブリトニア王国を乱す害にしかならないのだから。
「……感謝の気持ちがあるのであれば、我が家のことを頼みます」
「えっ?」
「私は罪を認めて自害します。その代わりに家臣に対しては温情を、と伝えて頂けますかな?」
シャロンに対する好意でハートランド侯爵は助言をしたわけではない。ブリトニア王国の為、そして何よりも家臣の命を助ける為だ。
「……分かったわ。必ず伝えるから」
ハートランド侯爵が死に、シャロンが恭順の意思を示すとなれば、それでブリトニア王国の王位を巡る争いは終息することになる、はずだ。
◇◇◇
城内にある大広間。今そこにブリトニア王国の各地からやってきた貴族が集まっている。これだけの貴族が一堂に会することなど誰が国王であった時以来だろう、などと思うほどの大人数。その全てがレイモンドと誼を通じようと考えて集まってきた人々だ。
だが彼らはこの日までレイモンドと会うことさえ出来ていない。レイモンドが拒んだのだ。
レイモンドの立場はあくまでも、正統な王を取り戻す為に一時的に王家を代表した、というもの。国王どころかその候補者にも、正式にはなっていない。そんな立場で多くの貴族と個別に会っていては野心を疑われる。これがレイモンドが面談を断っていた口実だ。
何を今更と思っていても、理由としては文句は言いづらい。会えないことに苛立ちを覚えながらも、貴族たちは面談が許される日を待ち続けていた。
それがようやく今日、招集がかかったのだ。全員が一堂に会するという望んだ形ではなくても、とにかくレイモンドに会って、名前と顔を覚えてもらう機会ではある。それなりに期待して貴族たちは集まったのだが。
大広間の玉座には何故かシャロンが座っていた。
「王女殿下。よくぞご無事で。皆さん、王女殿下がお元気であることを知って、喜んでおります」
そのシャロンの前で、無事の帰還を喜ぶ言葉を述べているのはレイモンド。何故、こんなことになるのかシャロンには分からない。そして分からないのは貴族たちも同じだ。皆がレイモンドの行動に戸惑っている。
「今回、ブリトニア王国を騒がせたこと。まずはお詫び申し上げます。申し訳ございません」
今回の騒動について謝罪するレイモンド。ますますシャロンは訳が分からなくなった。
「ただこれはブリトニア王国を正しい形に戻そうという気持ちからの行動。決して悪意があってのことではないことを信じて頂きたい。王女殿下、信じて頂けますか?」
「……ええ、信じるわ」
どうしてレイモンドがこんなことを言うのか、まったく分からないのだが、とりあえず逆らうことは止めておいた。恭しい態度を見せているが、レイモンドはシャロンを王女と呼んでいる。即位を否定しているのだ。
「さて簒奪者の始末は無事終わりました。これで私が望んでいた通り、ブリトニア王国を統べる方を正しい手続きを経て、決めることが出来ます」
「ええ、そうね。それなのですけど」
「ただ王位を望まれる方が誰もおらず、候補者は王女殿下だけとなっております」
「えっ?」
自分の話を遮ってレイモンドが告げてきた言葉。まさかの内容にシャロンは驚いた。当然、貴族たちも。大広間にはその貴族たちのどよめきが広がっている。
「ブリトニア王家の血を引く方々にお聞きしました。その結果は」
「それについては私からご説明します」
貴族の中から声があがった。前に進み出てきたのは黒髪の男性。それが誰か知っている人たちからは、また小さなどよめき声が聞こえてくる。
「王女殿下とお会いするのは初めてですか。私はノーザンランド公爵家のルイスと申します」
前に出てきたのはレイモンドの母、キャサリンの兄だ。
「ノーザンランド公爵家って」
「はい。そこにいるレイモンドの母は私の妹です。ただこれからお話するのは、それとは関係なく公家を代表しての発言となります。当家を含め、どの公爵家からも王位を望む者はおりません。これは各家にきちんと確かめた結果です」
ルイスは王位候補者をどの公爵家も出すつもりはないということを告げてきた。この発言については疑問に思うことはない。そんな人物がいないことは誰もが分かっている。
「分かったわ。そうなると国王候補者は」
レイモンドだけ。こう言おうとシャロンはしたのだが。
「王女殿下だけとなります」
「えっ?」
先にレイモンドがまさかの発言をしてきた。
「他に候補者がいないのであれば、王女殿下が次の国王となります」
「ち、ちょっと待って。それで貴方はいいの?」
いいはずがない。レイモンドは王位を狙っているはず。そうシャロンは思っている。
「何がいいのか分かりませんが、今回の働きを認めてくださるのであれば、それに見合った報酬は頂きたいと思います」
「報酬?」
「具体的に希望を述べてもよろしいですか?」
「……ええ。言ってみて」
これでレイモンドの本心が見える。そうシャロンは考えたのだが。
「ブリトニア王国の東部。アイル王国の国境からレインウォーター伯爵領までの領土を頂きたい」
「……それだけ?」
希望を聞いてもシャロンにはレイモンドの本心が分からなかった。
「それだけと言いますが、今申し上げた領土は結構な広さだと思います」
東の国境防衛帯とレインウォーター伯爵領。レイモンドの言うとおり、広さはかなりのものだ。
「広さはそうだけど……」
国境防衛帯は耕作地の少ない、領地とするには旨味のない場所。それを求めるレイモンドの意図が分からない。
「王女殿下のその反応ですと望み通りの報酬を得られると思って良いでしょうか?」
「そうね。それだけであれば問題ないと思うわ」
国境防衛帯は貴族家の領地ではなく直轄地。何の調整も必要ない。レインウォーター伯爵領はそうではないが、それも問題になるはずがない。
「では私への報酬については王女殿下が王位についた後で、正式にお約束を頂くことになります。さて王女殿下。ブリトニア王国の玉座をお求めになりますか?」
「……ええ」
レイモンドの問いに諾を返そうとするシャロン。シャロンは、問いを発したレイモンドの口元に冷笑が浮かんでいることに、気が付いていないのだ。
「恐れながら!」
そのシャロンを邪魔する声。声の主はクレアだった。それを知って戸惑うシャロンと、苦い顔を見せるレイモンド。
「恐れながら王女殿下には、ブリトニア王国にとって何が最善かをお考え頂きたく思います」
「……最善って」
自分の器量を否定する言葉。クレアの話をそう受け取って、シャロンは不満そうな顔を見せる。
「度重なる戦いで、ブリトニア王国の民は疲弊しております。その民の苦しみを一日でも早く取り除き、さらに暮らしを良くする為に王国の政治はどうあるべきか。それをお考えください」
ブリトニア王国の民を見捨てるわけにはいかない。レイモンドにそれをさせるわけにはいかないのだ。
「……私だけでは無理。それは分かっているわ。王国の復興には皆の力が必要。レイモンドには存分にその力を発揮して欲しいと思っているわ」
「レイは、いえ、レイモンドはブリトニア王国の臣下ではございません」
シャロンが気が付いていない事実。それをクレアは教えた。それを聞いたレイモンドの表情には苦笑いが浮かんでいる。
「えっ? でも彼は報酬を……えっ、どういうこと? レイモンド?」
「……私はブリトニア王国を除名になっております。それを正式に許された記憶はございません」
「じゃあ、報酬って? どうして臣下でもない貴方に報酬を渡さなければならないの?」
「報酬ですから。私は領地ではなく領土を頂くと言いました。王女殿下はそれを許したはずですが、いきなり約束を反故にするおつもりですか?」
「領地ではなく領土……アイル王国に割譲するってこと?」
臣下に領地を貸し与えるということではない。それはシャロンも分かった。だが、それだけではまだ足りない。
「いえ。アイル王国ではなく私の国です」
「何ですって!?」
「新たに国を興します。それを望む人たちがいますので」
ブリトニア王国の玉座などレイモンドは必要としていない。レイモンドは守りたい人たちの為の王になるのだ。ブリトニア王国の為に王になるつもりなどない。
「……それを望む人たちというのはどれだけいるのかしら?」
ようやくシャロンにも話が見えてきた。そして自分が大きな過ちを犯したことも。
「今、分かっているのはロンメルスとレインウォーター伯爵領の人たちだけ。あとは聞いてみないと分かりません」
周囲にいる貴族たちからうめき声が漏れる。考えていなかった難しい判断を求められる。それが彼らにも分かった。そしてレイモンドが事前に会おうとしなかった本当の理由も。
「……お願いがあるのだけど」
「何でしょうか?」
「私にはブリトニア王国を治める自信がないわ。だから、それが出来る貴方にブリトニア王国を任せたい。私の願いを受け入れてもらえないかしら?」
もっと早く言うべきだった言葉。それをシャロンは口にした。レイモンドの試しに気付くことなく、自分の欲を晒してしまった後では手遅れからもしれないが。
「私はブリトニア国民ではありません。ブリトニア国王になる資格はありません」
「じゃあ、ブリトニア王国を併合して! 貴方の国に! これでどう!?」
ブリトニア国王になってもすぐにレイモンドに滅ぼされることになる。それどころか戦うこともなく多くの臣下が背き、名ばかりの国王になってしまう可能性だってある。
それを回避しようとすれば初めから全てを差し出すしかない。もともとそうするつもりだったはずのことだ。
「……国王となる貴女がそれを望んでも、それに従う人はどれだけいるのでしょうか?」
シャロンが全てを諦めようとしても、レイモンドはまだ許そうとしない。ただこれは許しでもある。生かしておく可能性をまだ残しているのだから。レイモンドがまだ試そうとしているのは、周りにいる貴族たちだ。
「もう良いのではないか?」
シャロンの言葉に疑問をなげたレイモンドに声を掛けてきたのはウエストモーランド伯爵。シャロンにとっては救いだ。
「シャロン王女を担ぎ上げようと考える者などいない。それに値する人物ではないと皆、分かったはずだ。本人も自分にそんな器量がないことを思い知っただろう。野心など二度と生まれないはずだ」
こんな言い方をしているが、ウエストモーランド伯爵はシャロンを庇っているつもりだ。シャロンが助かるには自分が無価値であることを証明しなければならない。それを助けているのだ。
「良いのですか? 自国の王女に対して、そんなことを言って」
ウエストモーランド伯爵の思惑が分かっているレイモンドは苦笑いだ。
「かまわない。私はレイモンド殿。貴方に仕えることに決めている。それがブリトニア王国であっても、新しい国であっても」
シャロンが考えた通り、ブリトニア王国を離れてでもレイモンドに仕えるという人物が出てきた。そしてそれはウエストモーランド伯爵だけでは終わらない。
ウエストモーランド伯爵に抜け駆けされたと思った他の貴族たちが、次々とレイモンドに向かって臣従を誓い始める。シャロンの存在などもう誰も気にしていない。
どこの国王になるか決まる前に、レイモンドに多くの臣下が出来ることになった。大広間にいる全ての貴族が臣従を誓ったのだ。それはブリトニア王国全土が臣従を誓ったとほぼ同じ。レイモンドの本心としてはもっとふるいにかけたかったのだが、こうなっては仕方がない。
結果、レイモンドはブリトニア王国の国王となる。すぐにアイル王国が臣従を誓うことになるので、ブリトニア帝国と名を変えることになるが。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
