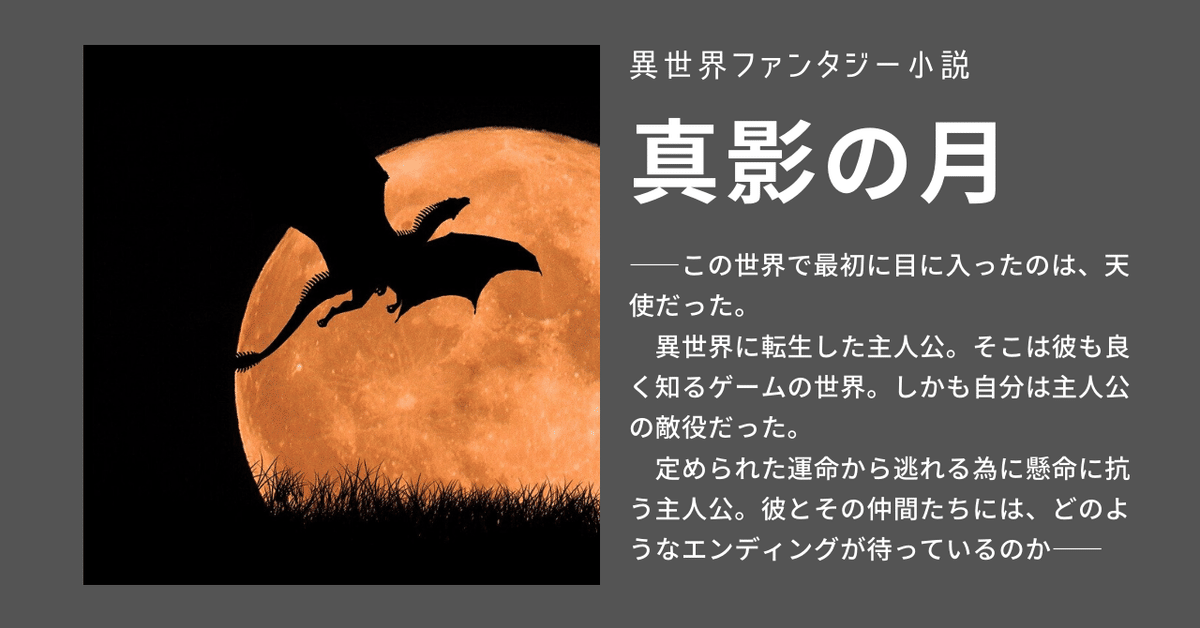
真影の月 真影の刻:第167話 敵の敵は味方。味方でなければ敵。どっち?
アーサー自称国王軍とシャロン女王軍の戦いは続いている。といっても開戦当初の勢いは双方共に失っており、戦いの頻度はかなり少なくなった。決着の見えない消耗戦に両軍の士気が多いに低下していること、さらに物資の不足がそれに拍車をかけている。
それでも停戦という選択肢はない。アーサーとシャロン女王のどちらか勝った方がブリトニア王国の王、そして将来のハイランドの覇者になる、と双方共に思っているのだ。ここで決着を先延ばしにするわけにはいかない。
だがそんな両軍の意思に変化をもたらす事件が起きる。王都陥落。まさかの情報が届いたのだ。
「……もう一度説明してもらえるかしら?」
信じられない情報に接して、シャロン女王は伝令に再度の説明を求めた。
「王都がレイモンドの手に落ちました」
「……レイモンドって、あのレイモンドよね?」
「はい。アイル王国亡命前はレイモンド・ザトクリフ。亡命後はレイモンド・ワイバーを名乗っていた、あのレイモンドです」
「……やっぱり生きていたのね」
レイモンド生存の可能性があることはシャロン女王も分かっていた。それはハートランド侯爵も同じ。
「生きていたのはいい。どうしてレイモンドが王都を攻めるような真似をしたのだ?」
レイモンドが生きていた事実はハートランド侯爵にとって驚くことではない。分からないのは何故、王都を攻めたのか。それを尋ねるハートランド侯爵の心にはわずかな期待が生まれている。
「ブリトニア王国に正統な王を取り戻す為の戦い。そう訴えております」
「それは王を僭称するアーサーを討つ目的と考えて良いのか?」
そうであって欲しい。ハートランド侯爵は、話を聞いているシャロン女王もそう思っている。だが、その願いが叶うことはない。
「……レイモンドの名で国中にばらまかれている檄文がございます」
「檄文? どういった内容だ」
「それは……これが写しでございます」
伝令役の騎士は自らの口で説明することを避けた。口にしづらい内容なのだ。
「どれ……これは……」
受け取った写しを読み進めるハートランド侯爵。その表情が徐々に厳しいものに変わっていく。
「何が書いてあるのかしら?」
その反応を見てシャロン女王は自分たちにとって良くない内容だと分かった。そうであったとしても中身を知らないままではいられない。
「……まずアーサーを簒奪者として糾弾しております。ブリトニア王家とは一切関係のない臣下の身でありながらブリトニア国王を名乗るのは恥知らずの行為だと」
「それはその通りね。それで?」
「女王陛下の……その……即位の正統性に対しても疑義を述べておりますな」
「私の即位に正統性がないというの!?」
シャロン女王自身はそのようなことを全く疑問に思ったことはない。兄が亡くなったからには唯一の肉親である自分が後を継ぐしかないと考えたのだ。
「……女性が王位に就くのは初めてですので」
だがハートランド侯爵は違う。シャロン女王以外にも選択肢があると、本来はその別の選択肢のほうが正しいと知っていながら、自家の都合でシャロンを女王に祭り上げたのだ。
「でもそれは他に……そういうことね?」
シャロン女王も気が付いた。ブリトニア王家の血を引いている男子となれば他にもいることを。
「はい。王位継承の優先順位は女王陛下が第一位ではなかったはず。それを明らかにし、改めて誰が王位に相応しいかを正式な手続きをもって決めるべきだという主張です」
「……もしそれに同意したらどうなるかしら?」
結果、自分が国王に相応しいとなる可能性もある。シャロン女王はそう考えた。シャロン女王はまだレイモンドの意図が分かっていないのだ。
「女王陛下が選ばれるにはまずは身の潔白を証明しなくてはなりません」
「身の潔白? 私が何をしたと言うの?」
「当家と組んで王位を簒奪した」
「な、何ですって!?」
そのようなことをした覚えはシャロン女王にはない。自分は仕方なく王位に就いたと考えている。実際にそうではあったのだが。
「これにはこう書いてあります。エバートの出自についてはかなり疑問な点はあるが、その調査は十分に行われたとは言いがたい。確たる証拠もないままに疑いだけで国王の地位にあったものを処刑したと」
「じ、冗談じゃないわ! もともとはレイモンドがもたらした情報でしょ?」
「はい。ですが確たる証拠がないのは事実ですな」
レイモンドの情報はアルフレッド管理官と当時の王妃、シャロン女王の母親の親密さを示していたのみ。エバートの出自が実際にどうであるかなどは何も記されていない。それをハートランド侯爵は良く知っている。分かっていてエバートは不義の子と決めつけ、強引に証拠を作ったのだから。
「……彼の証言は? 不義を働いた男の証言があったはずよ」
アルフレッド管理官の自白調書。それを見せられてシャロン女王はエバートの拘束を許可したのだ。
「拷問により無理矢理自白させたもの、と主張するかもしれません。それも女王陛下に頼まれて」
「私はそんなことはしていないわ!」
「事実などどうでも良いのです! レイモンドは意地でも我々を簒奪者にしようとしている! そういうことなのです!」
ハートランド侯爵の言うとおり、事実がどうであるかなど関係ない。アーサーとハートランド侯爵家は王位を簒奪した大罪人。レイモンドはそういう形に持って行きたいのだ。ハートランド侯爵がエバートをそうしたように。
その中でシャロン女王の立場はどうなるか。ハートランド侯爵としてはシャロン女王は関係ないなんてことにするつもりはない。それでは自分たちの正統性を失うことになる。
「……でも私は簒奪なんて」
「一つ方法はあります」
「それは何!?」
「お母上に証言してもらうのです。エバートは確かにアルフレッドとの間に出来た子供であると」
「そんなこと……」
母親が認めるはずがない。自分の為に認めてくれるかもしれない。だがそうした場合に母親はどうなるのかという不安もシャロン女王にはある。
「お母上の御身を心配なさる気持ちは分かります。しかし、それをして頂かないと女王陛下は候補者として残れません」
「母はどうなるの?」
「それは……罪には問われるでしょう。しかし、それを受け入れないと女王陛下が代わりに罪を問われることになります」
王妃の身でありながら不義を働いた。王位を簒奪した。どちらも大罪だ。普通は死を求められることになる。
「……私は王のままでいられるのかしら?」
死から免れるのであれば母親に証言してもらうしかない。その上で王として恩赦を与える。こうシャロン女王は考えた。
「可能性はあります」
「……そもそも他の候補者って誰なの?」
自分の競争相手となる人物をシャロン女王は尋ねる。それで勝ち目を判断しようと考えたのだが。
「現時点で分かっているのは一人だけです」
「誰?」
「レイモンド」
「えっ?」
「ご存じなかったのですか? レイモンドはノーザンランド公爵家の血を引いております。つまりブリトニア王家の血を引いているということです」
「……血を引いているといっても」
王位継承者になるには血が薄すぎる。シャロン女王のこの考えは正しい。他にもっと相応しい人物はいる。あくまでも血の濃さだけでいえば。
「彼には力があります。ブリトニア王家に連なる人物としてはただ一人、我々に対抗出来る力を持っております」
「……彼よりももっと血の濃い人を担げばいいのではないの?」
それによって逆にレイモンドの行動に対して正統性を問う。間違ってはいないのだが、シャロン女王は重要なことを忘れている。
「その場合、女王陛下のお立場はどう考えればよろしいのですか?」
「それは……今は何も案はないわ」
これは嘘だ。その担ぐ人物と結婚することで一定の権力を残すという方法がなくはない。だがそれではハートランド侯爵家には何のメリットもない。シャロン女王本人にとってもそれが本当にいいことなのかは分からない。
「……女王陛下のお許しを得られたのであれば当たってみますが、見つかる保証はございません」
「どうしてそう思うのかしら?」
「当家は簒奪者として糾弾されております。それに味方すればその方もまた簒奪者に加担したとして罪を問われるでしょう」
シャロン女王がどうしようとハートランド侯爵家は罪を逃れることは出来ない。レイモンドがそれを許さないだろうとハートランド侯爵は考えている。そしてそれは、そのハートランド侯爵家と手を組んだ相手も同じ。
「……もしかして戦っても勝てないと思っているの?」
「間違いなく勝てると思っているのでしたら、このような議論はしておりません」
戦争に勝ってレイモンドを黙らせる自信があるのであればこのような打ち合わせは必要ない。それが出来ないから、何か方法はないかと話し合っているのだ。
「レイモンドはどれだけの軍勢を率いているの?」
「正確なところはまだ。しかし王都は千や二千の軍勢では落ちません……いえ、あの男であれば落としてしまうかもしれませんが、こちらをここまで追い込むことはしないでしょう」
「どういうこと?」
「レイモンドは話し合いでの解決など考えておりません。逆にどうにかして戦いに持ち込もうとしております。それをしても勝てると思えるだけの軍勢がいるのです」
檄文を読めばそれは明らか。アーサーとハートランド侯爵を簒奪者であると決めつけ、反論を許さない状況証拠が記されている。そしてそれはシャロン女王も同じ。簒奪者までいかなくても王位には相応しくない人物と思わせようとしている。
「……戦って勝つしかない。でも勝てる見込みは少ない。そういうことかしら?」
「今のままでは」
「打開策があるというの?」
「成功するかは分かりませんが、方策はあります」
「それはどのようなものなの?」
「アーサーと手を結びます」
「な、なんですって?」
まさかの方策。今戦っている真っ最中の相手と手を結ぶ。そんなことが可能とはシャロン女王には思えない。
「三つ巴の戦いになんてなればレイモンドの思うつぼ。逆にアーサーと組めば両軍併せておよそ六万。さらに援軍を加えると七万か八万か。レイモンドの軍勢がどれほどのものかは分かっておりませんが、これ以上の数を揃えることは出来ないはずです」
「どうしてそれが分かるの?」
「レイモンドが率いているのは恐らくアイル王国侵攻軍の一部。最大でも三万です。さらに王都にいた軍勢が全て投降したとしても五万は超えません」
「逆に言えば合流しないと同数、下手をすれば少ない数で戦うことになるのね?」
「はい。勝つ為にはアーサーとの共闘しかありません」
「……アーサーは受け入れるかしら?」
これを聞くシャロン女王の気持ちは決まっている。勝てる可能性のある方法を採るしかないのだ。
「交渉してみなければ分かりませんが……レイモンドが敵となれば可能性は十分にあると思います」
レイモンドがブリトニア王国の王になる。これを告げるだけでアーサーは共闘に合意する。アーサーのレイモンドに対する嫉妬心は、楽観視は出来ないが、成功の可能性を感じさせる。そもそも可能性がどれだけ低くても、交渉を行わないという選択肢はないのだ。
◇◇◇
王都陥落の情報はアーサーにも届いた。援軍二万の情報に少し遅れる形で。
「どうして王都が簡単に落とされるんだ!? あり得ないだろ!? マーリンは何をしていた!?」
会議用の大きな天幕の中。アーサーは情報を伝えてきた騎士に向かって次々と問いを投げかけている。援軍の二万が間もなく到着すると聞いた時には、そのマーリンの判断を多いに褒め称えていたアーサー。もうそんなことは忘れているようだ。
「詳しい情報は届いておりません」
「マーリンは戦況も伝えてこないのか!?」
「王都が敵の手に落ちたことを考えれば、マーリン殿が無事でいるとは思えません」
無事でいれば、マーリンも二万の軍勢と同行しているか、そうでなくても何らかの情報を伝えてきているはず。騎士はそう考えている。
「……そんなの自業自得だ。マーリンが王都の守りをしっかりと固めていれば、こんなことにはならなかった」
「それはそうかもしれませんが……」
ハートランド侯爵家との戦いに主力といえる軍勢、兵というより指揮官であるが、は投入されている。王都の守備が果たして万全であったかといえばそうではない。
実際にはそんなことは関係なくレイモンドの奸計によって王都は奪われたのだが、それを知らない騎士にはマーリンを責めるのは酷だと思われた。
「それでこの先どうする?」
「……目の前の戦いに集中するべきだと思います」
この先の戦略など進言する立場にない騎士だが、聞かれればこう答えるしかない。今はシャロン女王軍との戦いの真っ最中なのだ。
「王都が落とされたのに放っておくのか!?」
「落とされたものは取り返せばいいのです! それにはまず今の戦いに勝つことではありませんか!?」
シャロン女王軍と戦いながら王都奪回に動くことなど出来るはずがない。目の前の戦いにおいてもまだ勝敗はどちらに転ぶか分からない状況なのだ。
「……それはそうだ」
「増援の二万が到着すれば敵兵力を大きく上回ることになります。そうなれば――」
「それはどうかな?」
騎士の言葉を遮る声が天幕の入り口の方から聞こえてきた。アーサーには聞き覚えのある声だ。
「ランスロット!?」
天幕の入り口に立っていたのはランスロット。その周囲を剣を構えたアーサー軍の騎士が囲んでいる。
「話があって来た。まずは彼らを下がらせてもらえるかな?」
「……剣を収めろ」
ランスロットの言うとおり、騎士たちに警戒を解くようにいうアーサー。ランスロットの考えていた通りの行動だ。堂々と現れた敵を討つような卑怯、アーサーの基準では、な真似は出来ないとランスロットは知っているのだ。
「話は聞こえていたよ。王都がレイモンドに奪われた件はもう伝わっているようだね?」
「ああ」
「それを知った上で、我々との決着をつけるのが先だと考えているようだけど、それは間違っているね」
「……何故そう思う?」
「レイモンドが王都だけで満足すると思うかい?」
「あいつは何を狙っている?」
アーサーが知っているのは王都がレイモンドによって落とされたということだけ。この問いでそれが分かる。ランスロットにとっては好都合だ。知られていても説得する自信はあるが。
「ブリトニア王国の玉座」
「……やはりな」
王都を落とすということはブリトニア王国を手に入れるという意味。間違いではない。
「私たちが潰し合いを続けることは彼を利するだけだ。我々が戦っている間に彼はブリトニア王国内で勢力を広げ、一方で我々は消耗し、彼と戦う力を失ってしまう」
「そうだな」
漁夫の利、なんて言葉はこの世界にはないが、ランスロットの説明にはアーサーも納得だ。
「優先すべきはレイモンドを排除すること。そう思わないかい?」
「でもどうする?」
レイモンドを討つことを優先することにはアーサーも同意だ。だが具体的にどうするかが思い付かない。
「手を組もう」
「何?」
「レイモンドは我々にとって共通の敵。それを討つためであれば協力出来るはずだ」
「……俺たちの決着は?」
協力が永遠のものであるはずがない。そんなことは誰にでも分かる。
「それはレイモンドを討った後に、改めて行えばいい。一応、伝えておくけど、こちらが不利だからこんなことを言っているわけではないからね」
「俺たちには二万の増援がある」
「こちらにも増援はある。正直、正確な数は分からないけど一万は下らないはずだね」
シャロン女王というよりハートランド侯爵家への増援はスコット王国軍。切り札とするつもりだった援軍の存在をランスロットは明かした。アーサーに、このまま自分たちと戦い続けても簡単に勝てるなんて思わせるわけにはいかないのだ。
「……九万か」
「実際にはもっと少ない。そちらの損害は知らないけどね」
ずっと消耗戦のような戦いを続けてきている。死傷者の数はかなりのものだ。
「あいつの軍は?」
「王都にいた二万を吸収出来なかったみたいだから……多くて三万かな?」
「三万?」
三万なんて軍勢をレイモンドがどこから連れてきたのか、アーサーは疑問に思った。まだ重要な事実に気付いていないのだ。
「我々はアイル王国に侵攻していた軍だと考えている。他にまとまった軍はいないはずだからね」
「ガウェインは負けたのか……」
アイル王国を制圧した後は、シャロン女王軍との戦いに参加するはずだった軍。その軍を、そして指揮官であるガウェインを失ったであろうことにアーサーはショックを受けている。
「アーサー。君に選択肢はないよ。二正面作戦なんて出来ない。それが出来る軍勢はいないからね。我々とだけ戦うことの愚かさも分かっているはずだ」
「ああ、そうだな」
「協力すれば敵の三倍の軍勢になる。王都に籠もられても十分に戦える数だ」
協力し合えばレイモンドには必ず勝てる。ランスロットはそう思っている。なんといっても少なくても三倍の兵力で戦うのだ。まず負けることはない。
「分かった。一時休戦だ。まずは邪魔者を排除する。その上で決着をつけよう」
アーサーも勝つことを微塵も疑っていない。もともと自信家のアーサーが三倍の兵力で負けるなんて思うはずがないのだ。
結論は出た。三倍の軍勢で邪魔者であるレイモンドをさっさと討ち取り、その上でブリトニア王国の玉座をランスロットと争う。アーサーとランスロットは協力して、レイモンドと戦うことになった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
