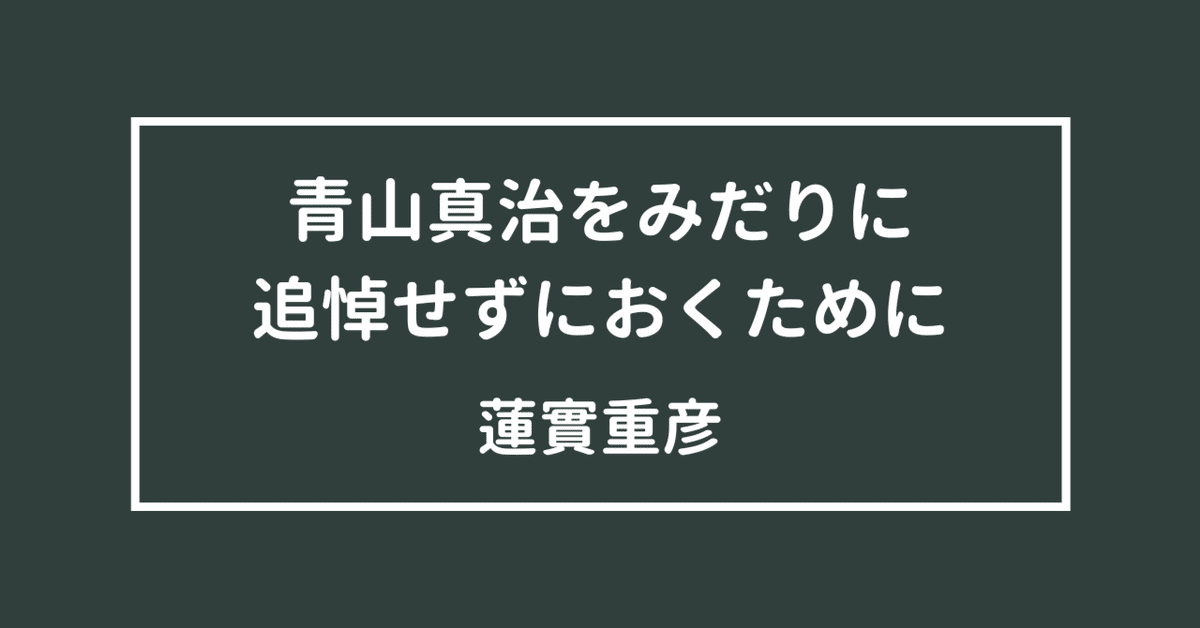
青山真治をみだりに追悼せずにおくために/蓮實重彦
まだまだ元気だった頃のその人影や声の抑揚などをせめて記憶にとどめておきたいという思いから、死化粧を施されて口もきくこともない青山真治――それは、途方もなく美しい表情だったとあとで聞かされたのだが――の遺体に接することなどこの哀れな老人にはとても耐えられそうもなかったので、その旨を伴侶のとよた真帆に電話で告げることしかできなかった。そのとき、受話器の向こうで気丈に振る舞う真帆の凜々しさには、ひたすら涙があふれた。こうして青山真治の葬儀への参列をみずからに禁じるしかなかった老齢のわたくしは、その時刻、式が行われているだろう空間へと思いをはせながら、さる日刊紙のため、映画作家としての彼の特異な魅力と思いもかけぬ素晴らしさをあれこれ書き続けていたのだが、つもる思いとそれを伝えようとする言葉とが、新聞特有の行数と字数の制限に阻まれてひたすら空転するしかなく、思うように筆が進むはずもない。だから、その日も終わる頃にはさすがに疲れはて、ぐったりとして仕事机を離れてソファーへと逃れ、さて煙草を咥えるべきか、それともテレビの受像機に向けてリモコンのボタンを押すべきかとしばし悩んだ末に、結局のところ、おそらくは生来の怠惰さからだろうか、これという確かな理由もないまま、深夜の喫煙と深夜のテレビ画面の点灯とをほぼ同時に始めてしまう。
すると、小さな画面には、何やら石段めいた傾斜した空間に立ったり座っていたりする男女が映し出されることになったのだが、どうやら連続ドラマの最終回らしいその画面の構図がことごとくみごとに決まっていたので、深夜のこの種の番組にしてはごく稀なことだが、これはショットの撮れる監督の作品だぞと奇妙な興奮を覚え、話の筋も、作中人物たちの関係も皆目わからぬまま、思わず最後まで見続けてしまう。
その画面の連鎖にはどこかしら青山真治的なところもあり、いったい誰がこんなドラマを撮ったのかが知りたくてならなくなり、最後に流れるキャストとスタッフの名前の連鎖に目を凝らせていると、『シジュウカラ』という題名らしいそのドラマの演出家の名前は、どう読めばよいのか皆目見当もつきかねる大九明子というものであることをつきとめる。ところが、その名前は、その日の午後に送られてきた『レオス・カラックス――映画を彷徨うひと』(2022 フィルムアート社)の目次にも読めるものだったのでそのことに改めて驚き、発行元の編集者である田中竜輔氏にメールで問い合わせると、それは『勝手にふるえてろ』(2017)などで見るものを魅了しつくした女性監督だと知らされ、みずからの無知――それを年齢のせいだとはいうまい――を深く恥じながら、早速、その翌朝から、大九明子監督とのメールの交換を始めることになったのである。
その電子的な文通を通じて感動とともに知ることになったのは、『シジュウカラ』の演出家が、映画美学校の第一期の修了生で、青山真治を師と仰いでいたという事実にほかならなかった。だが、それにしても、青山真治の葬儀の日の深夜に、まったくの偶然から、青山ゼミの出身者が演出した良質という言葉には到底おさまりがつかぬ極上のテレビ・ドラマに触れて深く心を動かされてしまったのだから、それはあたかも、青山自身が、その名刺――そんなものを持っていたかどうかは知る由もなかったが――をそえて、この女性監督をわたくし自身に紹介してくれたのだとしか思えなかった。彼女の作品のDVDをたちどころにその場で購入したのはいうまでもない。
前記の『レオス・カラックス』には、青山真治もまた町山広美との対談「映画の箍はすでに外れている」を載せているので、大九明子監督は、自分の書いた「レオス・カラックス監督特別講義」が師の青山真治に読まれることになるやも知れず、こそばゆい思いをいだいたものだと述べておられた。だが、彼女の師である青山真治の逝去によって、その機会は永遠に失われてしまうほかなかったのである。とはいえ、ほとんど理不尽にわたくしどものもとから去って行った青山真治は、そうと口にすることなく、大九明子による卓抜なショットの連鎖を、まるで意図せぬ遺言のように、わたくしに知らしめてくれることになったのだから、青山真治、ありがとうと深夜に孤独に口にするしかなかった。実際、これは、この後期高齢者には過ぎたあまりにも贅沢な贈り物だった。
青山真治は、立教大学でのわたくしの教え子ということになっている。それは確かに間違いのない事実なのだが、彼の兄貴分にあたる黒沢清や万田邦敏らの世代と異なり、彼らの8㎜フィルムによる作品を授業中に上映したり、喫茶店へ場所を移して感想を述べ続け、その後に親しく語りあうといった打ち解けた仲ではなかった。それは、そのときわたくし自身が立教大学の教師であることをすでにやめており、週に一度だけ非常勤講師として講義を持っていたという制度的な問題とも無縁ではなかったのかも知れない。だから、青山真治という名前には強く意識的だったにもかかわらず、その顔を認識したのははるか後のことに過ぎない。たしか、アテネ・フランセで行われたダニエル・シュミット作品の上映会の折、彼の助監督だった青山真治から静かに挨拶されたことがある。それが、まだまだ豊かな長髪を肩になびかせていた彼の顔を認識した最初の機会だったと思う。
その名を特別に意識していたというのは、彼が文学部の一年だったときに書いた学期末のレポートが、途方もなく優れたものだったからである。それはイタリア映画についての小論だったが、「今まで自分が最も恐怖した映画における『眼』は、小津安二郎のそれだった」と書き始め、「その温かみが恐く、その優しさがまた恐怖を増幅させるのである」と結んでいるように、その「温かみ」と「恐」さ、またその「優しさ」と「恐怖」との弁証法的な記述ともいうべきものを、大学一年の後期のレポートだからまだ二十歳になったばかりの若者がごく自然にやってのけているところに、教師としての余裕を超えたすえ怖ろしさを覚えたものだ。ほとんどのレポートはあらかた処分してしまったのに、〈a〉よりもはるかに優れた〈A〉の評価が記されているその短文がいまだに手元に残されているのは、この「青山真治」という名前を忘れてはならないという強い意志があってのことにほかなるまい。
実際、彼は優れた書き手でもあった。それは、あの傑作というほかはない『EUREKA ユリイカ』(2000)のノベライゼーション版で、誰かさんの書いた『伯爵夫人』などより十五年ほど前に、すでに三島由紀夫賞を受賞していたことからも窺えることにほかならぬ。また、それとは別に、例えば近著『宝ヶ池の沈まぬ亀――ある映画作家の日記2016―2020』(2022 boid)のどこでもよいほんの一頁に眼を通してみるだけで、青山の文才のほどは誰の目にも明らかになろうというものだ。また、彼は優れた批評家であり、その批評眼の鮮烈さは、この書物のいたるところに感じとることができる。映画作家である青山真治の死、そして小説家としての青山真治の死は、現代日本のもっとも優れた映画評論家の死そのものをも意味しているといわねばなるまい。
彼の批評家としての側面は、黒沢清とわたくしとの共著『映画長話』(2011 リトルモア)での長い時間をかけた討議を通してそのつど感じとっていたものにほかならず、その否定しがたい現実は、すでに『青山真治と阿部和重と中原昌也のシネコン!』(2004 リトルモア)などを通しても充分すぎるほど察知できたことだった。彼は、ただたんに優れた映画の撮れる監督にとどまらず、優れた言葉で映画を語ることのできる日本でもごく稀な批評家だったのである。それは、すでに触れておいた『レオス・カラックス』における町山広美との対談で、彼女が口にしたカール・ドライヤーの『ゲアトルーズ』(1964)をめぐって、「現代映画の先鞭をつけた『ゲアトルーズ』は誰にとっても超えるべき霊峰には違いない」にしても、より現代性の強い『アネット』などは、「『ゲアトルーズ』の厳格な価値基準から言えば、むしろその境地からの逡巡を描く映画だという気がしないでもない」と述べていたことを想起しながら、こうした正確きわまりない価値判断を口にしうる批評家がいま何人いるかと、いささか心もとない気がしないでもない。
青山真治とは、この二月の下旬まで、Eメールであれこれ言葉を交わす仲だった。わざわざ送ってくれたあの傑作と呼ぶしかない『空に住む』(2020)を妻と並んで見ていたとき、ソファーに身を委ねる多部未華子の身のこなしが途方もなく美しいと嘆息していた彼女の反応を伝えると、青山真治は素直に喜んでくれた。いうまでもなかろうが、この追悼文を書くにあたって、青山真治の撮った何本かの作品をDVDで見直さなかったわけではない。だが、そのほんの一部を目にしただけでどっと涙にくれてしまうので、いずれも途中で見るのをやめてしまった。例えば、『Helpless』(1996)にいく度か挿入される北九州市の何らかの工場の無人のショット。それを見て思わず涙してしまうのは、それが美しいからではいささかもない。また、物語にふさわしいそのショットの的確な挿入ぶりが涙を誘うわけでもない。その被写体に向けるべきいくつものアングルの中から、これ一つしかないという的確きわまりないキャメラの位置を青山真治が選択しているというその絶対的な正しさが、涙を誘うのである。
そうした点から、わたくしが青山真治の「眼」を深く信頼することになったきっかけである『セレブレート シネマ 101』(1996)の一篇を見直そうとしたのだが、それはVHSのテープでしか存在していなかったので、久方ぶりにおそるおそるその古めかしい装置に古びたテープを挿入したところ、いきなり不自然なほど奇妙な音が機械から漏れ、どのボタンを押そうと、ピクリとも動かなくなってしまった。それを取りだそうとしても、金属製の蓋が閉まったまま微動だにしない。かくして、それまではかろうじて機能していた――じつは、『ジョン・フォード論』の執筆のために、彼のテレビ作品を見るために何度も使用していた――この時代遅れの機材は、青山真治のせいで機能不全に陥ってしまったのだから、ぜひとも責任をとってほしいといいたいところだ。
幸いなことに、いまとなってはVHSで見るべき作品など一本も存在しない。だが、それにしても、青山真治よ、と呼びかけずにはいられない。貴兄は、拙宅の古びたVHS再生装置を、徹底的に破壊してしまったのである。なんと小癪な男なのだろうか。
もっとも、『宝ヶ池の沈まぬ亀』のページをくっていると、青山真治の批評的な鮮烈さが多少とも鈍る瞬間がないわけではない。それは、いつでもそうと名指されているわけではないが、このわたくし自身が問題となっている瞬間である。
2018年のサッカー・ワールドカップの折、彼とのメールの交換で、モドリッチを南軍将校に譬えたのは、まぎれもなくこのわたくしである。実際、青山真治はこう書いている。その譬えを目にして、「寝不足の日々が報われた、というか自分が見ていたものが何であったかはっきり教えられて気分爽快となった。そう、私はモドリッチのおかげで無意識にThe Civil Warを描くフォードとペキンパーの西部劇をワールドカップに重ね合わせながら見ていたのだった。非常に合点の行く解説」(p.189)だと反応してくれている。
誓っていうが、そう書いてわたくしの意図を理解してくれるのは、この狭くはない世界でも青山真治ひとりしかいまいと確信している。それは、いわば、彼へのひそかな恋文のようなものだったといってもよい。だが、そのことを誇るよりも、むしろ恥じらいを覚えていたというのが正しい。
ところが、わたくしは、どうやら彼を泣かせてしまったこともあるらしい。「某日、昼に届いた『文學界』掲載の『ジョン・フォード論 樹木』を一気に読む。最初のページから涙腺が緩み始め、予想通り『静かなる男』を経て『荒野の女たち』のくだりに差し掛かって以降、事情を知らぬまま隣にいた女優に『なんで嗚咽?』と驚かれた。これは自分でもなんだかわからないのだが、おそらく重臣くんのことが深く関係している気がする。ひとり息子を失った方にしか書けない文章だと思われたのだ」(p.422)と書かれているのである。嗚咽とともにこんなことを書いてくれるのは、青山真治しかこの世界には存在していない。そう確信して、わたくしもまた嗚咽するしかなかった。
あれは、三浦春馬を『静かなる男』のモーリン・オハラのように木から遠ざけることで途方もなく感動的な『東京公園』(2011)を撮ってからしばらくたってからだったと思うが、重臣が鈴木卓爾監督の『私は猫ストーカー』(2009)や菅沼栄治監督の『ささめきこと』(2009)に楽曲を提供して以降、やや体調を崩して最初の入院生活を送っていたとき、見舞いに行ってその病室に近づいて行くと、中から朗らかな笑い声が響いてくる。そこで入室をためらい、後戻りしようとすると、その声の主が青山真治であることにすぐさま気付いた。であるなら、しばらくは若者たちに会話を楽しませようと思い、待合室に戻ってしばらく待つことにした。新進作曲家の重臣と、その小学校のクラスメイトを妻とした映画作家との間には、とよた真帆をめぐるあまたの話題があって当然だと思ったからである。
だが、十五分たっても、半時間たっても、やがては一時間すぎても、遥かな病室から漏れてくる笑い声はたえようとしない。結局、一時間半ほどしてから、野球帽をかぶった青山真治が廊下を通りかかり、ああ、いらしてらしたのですかと驚きの声をあげる。いや、いま着いたばかりですと曖昧に応じると、ああ、重臣くん、とてもお元気そうでしたとはにかむように口にして去っていった。病室で迎えてくれた重臣は重臣で、元気になったら一緒に映画を作ろうねといわれたと、心からの笑みを浮かべ、青山真治から次回作の作曲を依頼されたと得意げに報告した。
しかし、その機会は訪れることなく、青山真治のはにかんだような表情も、その弾んだような笑い声も、彼との長い対話を心から楽しんでいた重臣の晴れがましい笑顔も、いまは永遠に失われてしまった。その現実をいったいどう受けとめればよいのか。いうまでもなく、やがて八十六歳になろうとしているこの後期高齢者は、そのためのいかなる方法も持ちあわせてはいない。唯一可能なのは、青山真治をみだりに追悼せずにおくことでしかあるまい。
(初出:「新潮」2022年6月号)
