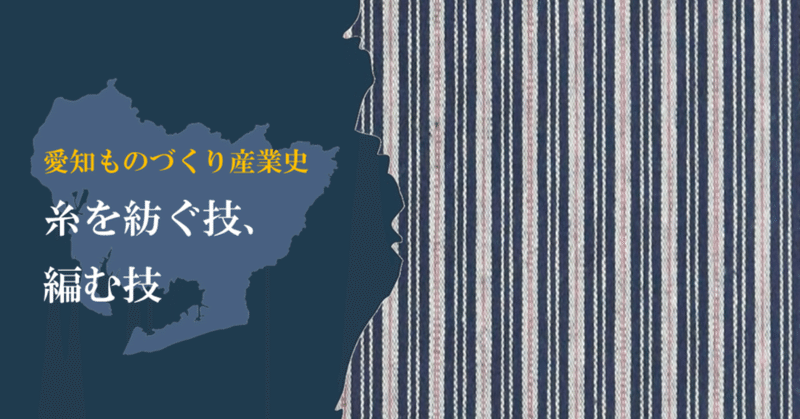
糸を紡ぐ技、編む技⑨ 戦後復興と新繊維の取り込み
昭和12年に日中戦争が勃発し、翌年、国家総動員法が公布されたことで、愛知県下の繊維各社も企業統合や織機などの設備供出を求められた。さらに同16年にはアジア・太平洋戦争も始まって、日用衣料など本来の生産活動は休止状態におちいってしまう。こうした中、存続した繊維会社は軍の指定工場として軍需品生産を余儀なくされたため、戦争末期には米軍による本土空襲の標的となって壊滅的な被害を被った。
しかし、終戦からほどなくして各社は活動を再開する。戦後の衣料不足の中、「つくれば(糸を編めば)売れる」といったおう盛な需要がおこり、アメリカから輸入された余剰綿花と、空襲で焼け残った機械を使った木綿衣料の生産が精力的に行われた。やがて、「民間貿易の再開(昭和22年)」「織物の統制解除(配給制度の廃止。同24年より順次)」「朝鮮戦争(同25~28年)勃発にともなう特需(ガチャマン景気)」といった追い風が吹き、天然繊維(木綿や毛織)の衣料や軍用品の大量生産を行うまでに回復をとげていった。
このように戦後の混乱期をくぐり抜けた愛知の繊維産業は、その後高度経済成長期(同30年代)になると、県の基幹産業として、あるいは陶磁器とならぶ輸出産業の花形として、地域経済、さらには日本経済発展のけん引役を担うこととなる。
また昭和20年代は、戦前より研究の始まっていた化学繊維の実用化が進んだ時期でもあった。その中で愛知と関わり深い素材がナイロン繊維である。東洋レーヨン(現東レ)は同26年、名古屋市内に二つの工場(重合工場と製糸工場)を建設し、ここで国産初のナイロン繊維の生産を開始した。ナイロンとは軽量で耐久性に優れ、形状の自由度が高く応用範囲も広い。「絹よりも細く鋼鉄よりも強い」というキャッチフレーズで売り出された愛知発のこの素材は、「洋服や西洋風住宅の普及」「女性の社会進出」といった社会環境の変化を受け、日用衣料(肌着、ワイシャツ、スーツ、スポーツウェア)、室内装飾品(カーペット、マット、カーテン)、産業用資材(工業用縫糸、合成皮革、人工芝)など、幅広い分野に展開されていった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
