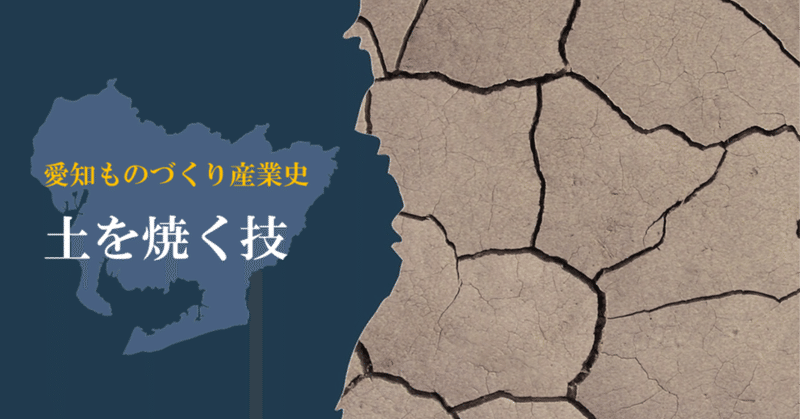
土を焼く技⑤ 新製品の誕生
江戸時代の間、瀬戸製品や常滑製品以外にも特長的な製品が誕生(成長)している。以下その代表的なものである。
一つ目は三州瓦。瓦に適した土に恵まれ、矢作川水運の利がある西三河南部の高浜では、江戸中期頃には専門職人による瓦づくりが成立していた(最古の事例として「享保8年、三州高浜村瓦屋甚六」と刻まれた瓦焼狛犬が高浜市内で確認されている)。三州瓦と呼ばれた高浜の瓦は、水運を利用して、防火対策として町屋の瓦ぶきが進み始めていた江戸へと送られた。現在、三州瓦は全国の粘土瓦のシェアトップを誇り、石州瓦(島根県)、淡路瓦(兵庫県)とならぶ日本三大瓦の一つに数えられている。

(大正時代。大府市歴史民俗資料館)
二つ目は尾張七宝。服部(名古屋市中川区)で鍍金業を営んでいた梶常吉は、オランダから輸入された有線七宝の皿を手がかりにその製法を研究し、天保年間(江戸後期)に七宝焼の小鉢を完成させた。その後常吉は、尾張藩の命により七宝焼の製作に従事、嘉永3年(江戸後期)には第14代藩主・徳川慶勝や徳川将軍家にも献上している。また常吉の技は、遠島(あま市七宝町)の林庄五郎や塚本貝助にも伝えられ、この村の主要産業として成長をとげていった。そして慶応3年(江戸末期)、尾張七宝はパリ万国博覧会(フランス)に出品され、日本を代表する工芸品の一つとして海外でも広く知られるようになる。
三つ目は陶磁器そのもの(土を焼く技)ではないが、岡崎石工品もあげておきたい。天正18年(織豊時代)、徳川家康に代わって岡崎城主となった田中吉政は、城の石垣普請のため、河内・和泉(大阪府)の石工を岡崎に招いた。その石工たちが岡崎に定住し、ここでとれる良質な花崗岩を使って石製品を手がけるようになったといわれている。その後江戸時代になると、燈籠をはじめとする製品が矢作川から三河湾を経由した水運によって江戸や大坂へと送られていった。こうした岡崎の石工の活動は明治時代以降も続き、昭和初期頃に最盛期を迎えている。

なお、三州鬼瓦工芸品(三州瓦のうち、鬼の顔を模して焼かれた装飾瓦)、尾張七宝、岡崎石工品は、現在「経済産業大臣指定伝統的工芸品」に認定されている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
