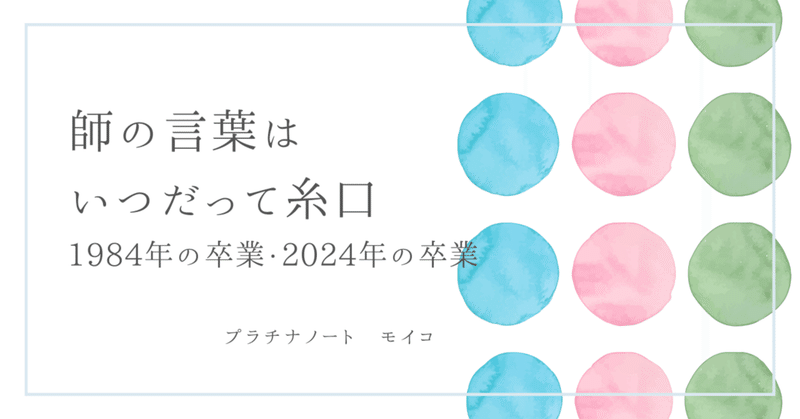
師の言葉はいつだって糸口だという話
1984年に短期大学を卒業した。
当時は短大の方が就職できる(ような)漠然とした周りの声が多かった。
一般職・総合職あやふやな考えであった。
四年制大学も合格していたが「就職しやすい」という思い込みで
あまり興味のない学科の短大へ進んだ。
当時の研究ゼミの教授はとても厳しく、しかしわたしは傾倒した。
どっぷりと最終学年の2年目は真剣に卒論に取り組んだ。
卒業式の日、配布された学園からの冊子に各先生方の餞の言葉があった。
大好きな教授の言葉を見て、帰りの電車の中で泣いた。
学生生活で「何を学んだかではなく、何を得たか」がこれからの社会生活に
必要である、という内容だった。
当時のわたしの研究は、全く会社生活や社会生活には必要ではないもので
時折、これをやってなんになるんだろう?とも感じていたことは事実だ。
でも楽しかった。
ああ、楽しくて苦しいという感覚を得たのだ。
実用的なことを突き詰めようとしても無駄ではないのだ。
腑に落ち、自分はこれで論文を作って無駄ではなかったのだと泣いた。
調査の時に、たくさん得るものがあった。それでいいのだ。
実用的じゃなくてもいいのだ。
それから40年たち、別の分野で卒業をした。
参考↓
先日の卒業式を配信でみたが、どの先生の言葉も本当に素敵だった。
この大学を選んでよかったと心から感じた。
わたしは通信の3年からの編入だが、通学生の入学式は2020年
入学式は執り行われなかった無念が随所にあった。
あの年の入学生はオンラインから授業が始まったのだ。
そのときに言いたかったことを卒業式で伝えます。と学長が述べる。
心からの言葉だ。そして幾度も「みんな幸せになれ!」言葉を投げる。
20代の方々はどう受け止めたかわからないが
祖父母に近い年齢の自分、学長に近い年齢の自分には太くまっすぐ刺さった。
みんな、と呼びかける包容力。ごく普通な言葉なのに
とてつもない愛の言葉だ。シンプルは強い。
「しあわせ」を考える。「しあわせ」という言葉について考える。
受け取る自分について考える。何を以て「自分はしあわせです」と言えるのか。
何を以て、それを言えないのか。
「なれ」の「なる」ために、どう動くのか。何を見るのか。
学びが多い。まだ学びたい。
SNSでは著名人の名言が注目され、それを支えや燈として心に留める人が多いという。
botも少なくはない。短い言葉で芯のある想い、すぐに思い出せることも大事だ。
40年前の「何を得たか」と40年後の「みんな幸せになれ」は、大切な言葉だ。
そうだ。「何を得たか」があって、今ここでこんなことをしている。
この2年間の学業生活を想う。
モイコ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
