
ストーリー・オブ・マイ・ライフ わたしの若草物語 Little Women/グレタ・ガーウィグ ※6/24追記
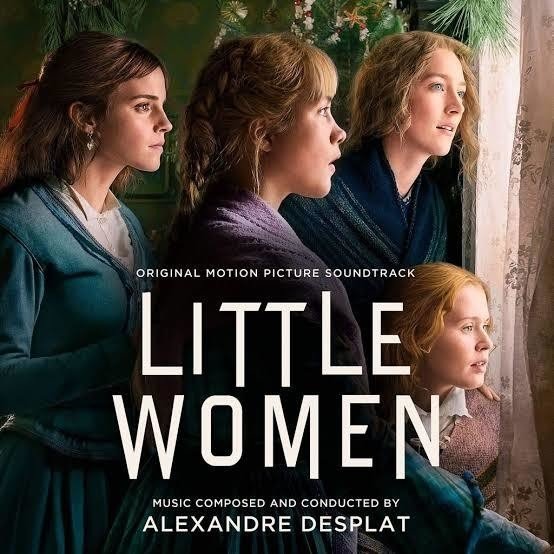
タイトル:ストーリー・オブ・マイ・ライフ わたしの若草物語 Little Women 2019年
監督:グレタ・ガーウィグ
誰しも「若草物語」という物語にふれた人はジョーや姉妹の誰かに自分を投影したと思う。今の世の中、中々四姉妹という家族関係を持つ人はいないと思うけれどそれぞれ異なるキャラクターを持つ姉妹のいずれかに自分を投影できるのかもしれない。
とにかく丁寧に作り上げられた映画だなと感じた。ジョーというキャラクターと、グレタ・ガーウィグの視点が重なる事でシアーシャ・ローナンのポテンシャルが最大限に発揮されていた。グレタ・ガーウィグにとって前作「レディ・バード」の内容をグレードアップした本作は、パートナーであるノア・バームバックと共同で脚本を書き上げた「フランシス・ハ」にも通じている。ジョーとローリーの関係は「フランシス・ハ」でのフランシスとソフィのふざけ合う所に近いものを感じる。グレタ・ガーウィグの根底にあるものが、全て吹き出した集大成が本作であると思う。
地方からニューヨークへ上京するスタイルは、「レディ・バード」、「フランシス・ハ」、「20センチュリー・ウーマン」でも描かれていたけれど、それぞれ時代は異なりながらも都会に憧れ自分の立ち位置を探す物語でもあった。

本作も同様に作家を目指し都会で暮らしながらも半ば夢を諦めて帰郷するという流れは、この三作に通じるテーマではある。しかし、それまでのグレタ・ガーウィグが関わった作品と異なるのは、主人公の独立が主だった話から家族の話へと変わっていて、単純にジョーだけの話ではなくメグ、エイミー、ベスの姉妹と、母マーミー、叔母、ローリーそれぞれの人々が偏りなく描かれている。全てが渾然一体となりながらもそれぞれが丁寧に描かれる事で、各キャラクターが持つポテンシャルも引き出している。この時点でグレタ・ガーウィグという人が「レディ・バード」とは別次元にある事がまざまざと分かる。物語はジョーだけでなく、それぞれに持っている事が分かりやすく、しかも詩的に描かれているのは驚異的なほど。
時系列に話が並んでいた原作を元に再構成された本作は、姉妹が独立した後から始まり過去の幸せだった時代を思い起こしながら、現在に起きている事と過去に起きた出来事を結びつけながら話が進む。冒頭のニューヨークの街並みを駆け抜けるシーンは、「フランシス・ハ」でレオス・カラックスの「汚れた血」を模倣していたシーンを想起させるものの、すでにグレタ・ガーウィグは自分の表現として血肉化している。彼女は憧れや真似事から開放されているのがよくわかる。模倣の時代は終わったのだと。この点でもグレタ・ガーウィグがヨーロッパへの文化的コンプレックスを抱えながらも、自立した作家へと変貌した記録でもある。
家族の成長を、過去への郷愁への想いから現在抱えている問題と交互に映し出す事で、今抱えている悩みがくっきりと表面化されている。時系列を前後させる事でキャラクターが抱える問題がよくわかる構造になっていて、より深い人物像へと昇華しているのは見事としか言いようがない。メグが抱えた経済的な問題、時代に名を残そうと躍起するエイミー(隣の絵を覗き込むシーンは後のキュビズムに差し掛かろうとした時代に旧態然とした自身の視点に才能の格差を感じている)、ピアノの才能がありながらも病気に苦しむベスなど姉妹の有様は観賞後もそれぞれ印象が残る。利他的に奉仕する母マーミーの姿や、ローリーがジョーへの想いを告げるシーンや、ローレンスがベスの演奏を聴いて亡き娘を投影しながらもピアノの調べに心を打たれるシーンなど細かい所も漏れなく描いている。
過去と現在が織りなす場面のコントラストに、過去の家族の幸せが描かれるシーンでは温かみのある暖色の色合いで描かれ、現在のシーンはヒヤリとした寒色で使い分けされている。家の中しか知らない過去の場面は家族の温かみを感じさせながらも、外の世界で生きる姉妹それぞれの心情のコントラストは見事に映し出されている。ラストで再び暖色に戻るのはそういった事ではないだろうか?
この物語が普遍性を帯びているのは、最大のマイノリティである女性の生き様をそれぞれの視点で描いていることではないかと思う。女性として生きることが、姉妹だけでなく、母や叔母の視点ももれなく描かれていて、南北戦争前後の封建的な社会の色濃い時代に個人の自由を勝ち取ろうとする様は、国や人種を超えた普遍的な悩みや問題であるからこそ、この物語に共鳴すること人々が絶えないのではないか。結婚というものも、経済的なものが主軸でありながらも、子供や資産の所有権は認められない事など、さりげなく盛り込まれている。この辺りは母を演じたローラ・ダーンが本作とノア・バームバックの「マリッジ・ストーリー」で演じた弁護士と比較すると面白い。
グレタ・ガーウィグが描きたかったのは単純なフェミニズムではなかったと思う。フェミニズム活動家であるエマ・ワトソンを起用しているように、問題は簡単な事ではない事が劇中で描かれている。結婚=経済的な問題というのは、経済的な家庭事情に厳しい叔母(メリル・ストリープの演技が素晴らしい)が語ったように、男性の資産に依存するか己の資産に頼るかしか選択肢がないと思わされている。ジョーが自ら勝ち取った個人や経済的な自由の影に、結婚がもたらす経済的な依存関係は本作を見る上で見過ごしてはいけない。
四人姉妹が歩んだ道を辿る事で、答えはひとつではなく、幸せのかたちは人それぞれあるという事を描いた傑作なのは間違いない。経済的な理由を持って結婚する事も、結婚しながらも貧困に喘ぐ様も、結婚を否定して個を貫くのも、不自由な世の中と女性の自立の難しさの中でそれぞれが目指す幸せの形がある。
※追加 6/24 原作に触れて
映画を観る前に古い訳で原作を読み進めていたものの、日本の時代劇のような口調に辟易して途中でやめてしまった。丁度同じタイミングで新訳が出ていたので、改めて買いなおしてこちらで読み終える事が出来た。装丁の絵は洋菓子「フランセ」でお馴染みの北澤平祐氏によるもの。
姉妹の十代を描いたⅠと、姉妹の結婚までの道のりを描いたⅡが合本になっていて、映画に合わせて読むのに丁度良い内容となっている。
映画に含まれていない内容も多数あるものの、グレタ・ガーウィグが原作の内容を余す事なく映画にサルベージしたのがよく分かった。映画はⅡを中心に、Ⅰで描かれたかつてのマーチ家を振り返る内容に編集されているものの、映画冒頭のジョーが暖炉の脇に立っていたせいでスカートが焦げるシーンなど、Ⅰで描かれた場面が大人になっても変わらぬ仕草というのを原作の台詞を実際に見せる事で置き換え、過去と現在の繋がりを強調していた。
グレタ・ガーウィグは時系列に進む原作を解体して、成人した姉妹が過去の出来事を振り返りながらも合間合間に細かいストーリーを落とし込んでいる。その全てが現代的に翻訳されてはいるものの、例えばソフィア・コッポラの「マリー・アントワネット」のような強引に現代と結びつけるような事はせず、あくまでも個々のキャラクター(主にジョー)の奔放さを描くために無理のない程度に現代的な「やんちゃさ」を盛り込んでいる(前半のジョーとローリーのダンスシーンなど)。
南北戦争以降の女性のあり方は原作でも細かに描写されていて、貧しい生活を選択したメグが直面した貧困や、芸術に埋没しながら上流階級の生活に陶酔するお洒落なエイミー、病気に苛まれ自身では何者にもなれなかったベス、作家の夢を持ちながら家庭と学校に夢を開くジョーなど、四者が進む道のりは当時の現実を現しながらも「女性が女性らしく生きるには?」という問いに、作者のオルコットはあらゆる形を示していたように思う。金銭的に裕福でも貧困でも「そこに愛があるのか?」と問い、さらに愛の先には自分たちだけではない愛の形を示している。
原作のベースにはキリスト教の教えが根強く描写されている。聖書や「遍路歴程」といった信心深さが随所に登場している。映画の姉妹のカラーの元になった服装の色合いは、原作でクリスマスに母から送られた聖書の色がもとになっている。とはいえ、グレタ・ガーウィグによる映画版ではキリスト教、聖書についての内容はほぼオミットされている。その点はリベラルなニューヨーカーらしいスタンスに切り替えられているように思う。
原作と映画で大きく異なるのは、ジョー=オルコットという視点を入れ込んだ点にあると思う。「Little Women」という自伝に近い物語を出版までこぎつけるシーンは原作には無く、編集者からの申し出で結婚のシーンを付け加えるくだりはジョーではなく作者オルコット自身を盛り込んだメタな内容となっている。出版社が求めたハッピーエンドと独身を貫いたオルコットを同時に描いていて、「若草物語」という物語を飛び越えてオルコット自身の話へと昇華させている。
女性の自立というテーマは現代も変わりなく存在している。オルコットが描いたジョーの時代は、女性が自立するための選択肢は少ないことと、結婚することで夫の経済事情によりそうしかなかった現実(叔母のように例外も取り上げている)は、今現在も変わりない。その時代に比べれば女性が自立しやすい環境にあるとはいえるものの、ドラマや映画を観ていても結婚への強迫観念は薄れてはいないようにも思える。グレタ・ガーウィグはその点にもクローズアップし、150年という年月が過ぎた中でも変わらぬ在り方を否定も肯定も織り交ぜながら描ききったように思う。こうあるべきだという一つの結論ではなく、相手を思いやるマーチ家の愛の形を掬い取った映画であったように感じられた。愛の元に集う家族の物語として感じとる事が、グレタ・ガーウィグの眼を通してみたオルコットのメッセージだったのではないだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
