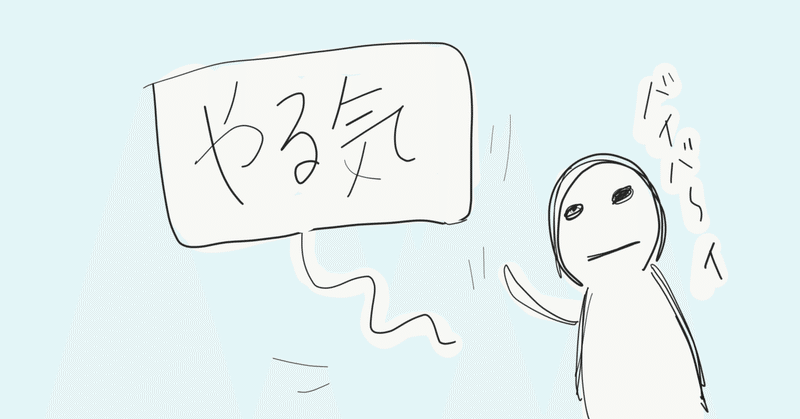
やる気を起こさせる方法
◉やる気が起きないので、行動できない。自分も年がら年中そういう状況ではあるのですが。サラリーマン生活を10年やって、結局辞めてしまったのもモチベーションの問題の方が大きかったですね。中堅出版社でしたが、給料はそこそこ以上に良かったです。編集者の場合出世欲はあまりなくて、それよりも現場にずっといたいという思いが強い人間の方が、多数派ではないでしょうかね。金銭や地位より、やる気を起こさせるものが他にあるわけで。
【「ホワイトなのに若手が辞める」企業の残念な盲点 向上心が高い若者たちを育てる技術の本質】東洋経済オンライン
「職場がゆるすぎて辞めたい」と考える若手社員が増えています。背景には「このまま会社にいても成長できないのではないか」という危機感があります。では、どうすれば上司や会社と若手社員の意識のギャップを埋めることができるのでしょうか。
著書に『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』などがある漫画家・イラストレーター・グラフィックデザイナーのJamさんが、自身の経験を基に解説します。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、〝やる気〟で検索したら、ピッタリの画像が出てきました。
◉…▲▼▲▽△▽▲▼▲▽△▽▲▼▲…◉
■仕事も教育も似ている■
居心地がいい環境、ストレスがない環境って、それに越したことはないんですが。でも、自宅ならともかく、仕事場だとそれは違いますね。例えば、筋肉痛とか、減量での空腹感って辛いですよね? でも、ウェイトトレーニングで筋肉が大きくなっている実感があれば、筋肉痛は気にならない。腹筋が割れていく姿を見れば、空腹も我慢できる。けっきょく、目的や目標、その達成感って大事なんですよね。で、金銭って大して達成感になり得ないんですよね。
人を育てるというのは、方向性をハッキリ指し示す指導者って部分が大きいですね。研究者の人に聞くと、良き指導教官に出会い、研究テーマを与えられ、研究者として引き上げてもらった結果、一廉の研究者になっていたという人は多いですね。企業なら、本人のやるべきことの方向性を示し、それに適性がある人間は抜擢して、責任のある仕事に就ける。そこが上手く回っていない会社は、金銭面的に良い環境でも、やめちゃう人が多いですね。
弱小の出版社では、金銭面で不満をもって辞める人間も多いのですが。そういう人間を片手の数以上、知っていますが。それで中堅出版社や大手出版社に再就職できても、今度は権限のなさに愕然とするわけです。小さな出版社のの自分の裁量でバンバン決められたことが、編集長どころか役員の口出しは多く、自分の裁量で決められないことがあまりにも多い。報酬は間違いなく大事なのですが、失って初めて気づくモチベーションも存在するわけです。
■金銭報酬と感情報酬■
「薩摩に馬鹿殿なし」と言われる島津家中にあって、ひときわ名君の誉れが高い島津斉彬公も、個々人の才能を見出し、活躍の場を与え、本人のやる気とやりがいを引き出したわけで。西郷南洲翁も、その一人。あまりに心酔していたので、斉彬公急死の報に、殉死しようとしたほど。その斉彬公、誰もが褒める人間は八方美人で重大な決断ができないから要職に就けるなとか、主君は愛憎で人を判断するなとか、今読んでも通用する考えが残っています。
実際、お由羅騒動で揉めた腹違いの弟の久光公を重用し、片腕に育て上げてもいます。斉彬公が凄すぎて評価が低いですが、久光公だって島津家史上五指に入る名君なんですよね。西郷隆盛と言うと、部下の言うことを何でも受け止めてくれるような器の大きな人物というイメージがありますが。実際はかなり人の好き嫌いが激しい人物だったそうです。そういう人物は意外と、周囲と対立してしまいます。でもそういう悪い面ではなく良い面を評価する上司が絶対に必要。その評価がモチベーションの源泉。
金銭報酬と感情報酬という言葉がありますが。小説家になった人に、何故なったかを深掘りしてもらったら、小学校の時の読書感想文を教師から褒められて、それでもっと本を読むようになって、書くことが苦痛でなくなって、気がついたらプロになってた、なんて話はいくらもありますしね。自分もそうです。嫌々ながら、仕方なく書いた読書感想文が妙に評価され、市のコンクールに出したら賞をもらって、県の方に回されて、コッチでも賞状を貰って。そんだけです。まぁ、家系的に文系の能力が高く、適性はあったと思いますが。
■動いて出るやる気■
でもそんなものだったりしますね。韓国の朴正煕大統領が進学をすすめてくれた日本人恩師の思い出を語り、金泳三大統領が就任式に日本人の恩師を呼び、金大中大統領が日本人のおいしいに日本語で「先生、豊田です」と話しかけたように。彼らはみんな恩師たちによって、自分の可能性を見出されたわけで。特に朴正煕は、貧農の小倅で、そのままだったら字も読めずに一生を終わったはずでした。日韓併合で学制が導入され、その才能が認められたわけで。
そもそも、やる気は放っといても生まれるものではないですからね。人間はやる気があるから動くのではなく、動いているうちにやる気が出る。これは非常に重要な視点だと思うんですよね。逆に言えば、動くことを習慣化することによって、やる気をある程度一定レベルに保つことはできるわけです。ある映画脚本家の方が、書くアイデアがなくても机の前に座ると言ったことも、これに繋がるのでしょうね。
【人は “こう” 言われれば意欲的になる。「やる気を出して」と言うより簡単に相手を動かせる方法。】スタディハッカー
自分のやる気を出すことでさえ難しいのですから、他者のやる気を自由にコントロールするなどきわめて困難です。しかも、やる気はかなりの “レアもの” なのだとか。
ただ、仕事においては部下や後輩、同僚などに、なんとかやる気を出してほしいときがあるでしょう。そこで今回は、相手のやる気に頼らなくても、相手が自発的に動くようになる、3つの方法を紹介します。
スポーツと習慣づけ。これって重要ですね。知り合いの漫画家で、朝の散歩で健康維持を兼ねて、作品の構想を一緒に寝るという人もいます。歩くことは健康の基本ですし、そうやって毎日の習慣づけの中で、運動が仕事と密接に関係していく。犬を飼っている漫画家さんだと、毎日犬の食事は散歩と付き合うため生活が規則正しくなり、仕事がきっちりこなせるという人もいますね。そういう視点って、かなり重要ではないでしょうか。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ
売文業者に投げ銭をしてみたい方は、ぜひどうぞ( ´ ▽ ` )ノ
