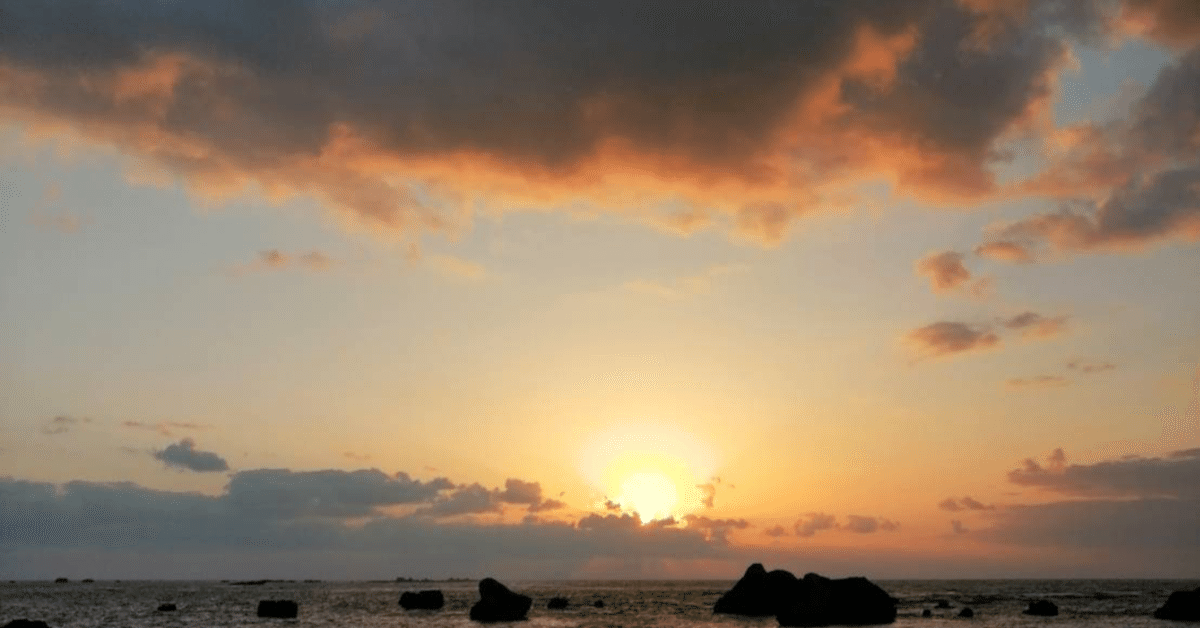
曽野綾子『心に迫るパウロの言葉』の「その人を得るために」自由を、愛をもって互いに仕える
信仰を持つことは
禁欲と束縛ではなく
快楽と自由の味を持つことであるという。
・・・
日曜日に教会に行かないことは大罪ではなく
祈りというものは
教会に行かなくともできる。
そう考えると
いつでもどこでも祈ることはできる。
いつでもどこでも祈ることができるということは
教会に行かなければ祈ることはできないという事よりも
信仰の深さとしては
より深いのではないかと考えたこともある。
・・・
キリスト教の信者が家の仏壇の掃除について神父に尋ねたところ
掃除をしてはいけないと言われたという。
また
葬式の際に黒い喪服を着てはいけないなどどいう
訳の分からないことを主張するものもある。
・・・
それに対してパウロは
「わたしは、すべての人に対して自由であるにもかかわらず、
自ら進んですべての人に仕える奴隷となりました。
いっそう多くの人を得るためです。
ユダヤ人に対しては、ユダヤ人のようになりました。
ユダヤ人を得るためです。
律法の下にある人に対しては、
わたし自身は律法の支配の下にないにもかかわらず、
律法の下にある者のようになりました。
律法の下にある人を得るためです。
わたしは神の律法と無関係な者ではなく、
かえって、
キリストの律法に服しているにもかかわらず、
律法と無関係な人々に対しては、
律法に無関係な者のようになりました。
律法とは無関係な人を得るためです。
良心の病んでいる人々に対しては、
わたしも良心を病んでいる者のようになりました。
良心を病んでいる人を得るためです。
わたしは、すべての人に対してすべてとなったのです。」
コリント(9・19~22)
・・・
その人と同じようになることが
その人への愛であることから
仏壇の掃除などしてはいけないことには
ならないのである。
そこには愛ある自由があるはずなのだ。
・・・
いかなる国家権力、人間関係においても
神の存在があることで
常にその人のようになるという原則があるのであれば
多くの事柄が
解決できるということだ。
・・・
そこに必要となるのが
愛。
愛があるならば
その人のようになり
その人とともに
自らの自由意志で
同じことをするということだろう。
・・・
しかしながら
社会の法律や規則に反することは
難しい。
その時の本当の愛は
その人を守るためにも
法律や規則に反することのないようにいう
納得のいく説明をすることが必要となる。
・・・
すべての事において
重要であり必要となることは
そこに
愛があるかということだ。
愛があるならば
何事においても
十分に
理解される。
愛は必ず伝わる。
よろしければサポートをお願いします。
