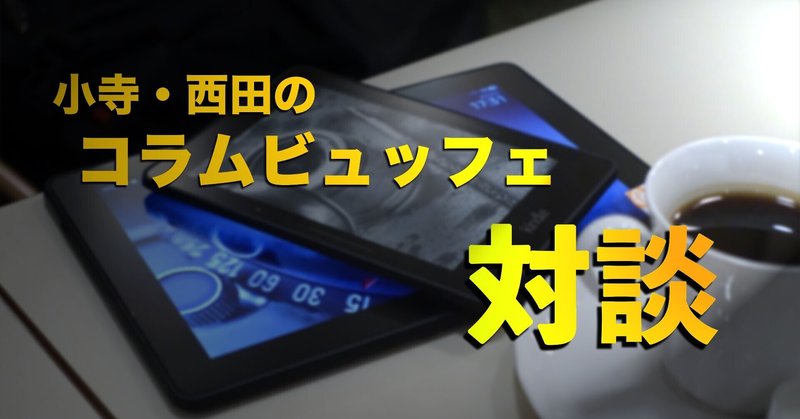
石橋啓一郎氏に聞く「プロ翻訳家」のお仕事(1)
毎月専門家のゲストをお招きして、旬なネタ、トレンドのお話を伺います。
![]()
今回から、西田が担当する対談の新シリーズがスタートする。
対談相手の石橋啓一郎氏はプロの翻訳家である。実は西田とは、中学以来続く長年の友人だ。
ただ、彼はいわゆる「有名人」ではない。名前が出ない形での仕事を中心に活躍している、本人曰く「翻訳職人」だからだ。
翻訳家というと、多くの人は小説や映画の字幕・吹替などを担当している人を思い浮かべるかもしれない。場合によっては、通訳と仕事がごっちゃになっている可能性もある。だが、そうした存在はむしろ翻訳家としては「少数派」だし、そもそも通訳は仕事の質が違う。
英語から日本語に翻訳された文章は日常に溢れている。その中で、名前は出ていなくても、彼が英語から日本語に翻訳した文章を読んでいる……というシーンは意外とあるものだ。だが、そうした翻訳がどのように作られて世に出ていくかを、我々は知らない。そんな「翻訳の職人」がどのようなプロセスで仕事をしているのか、じっくりと聞いてみた。
なお、友人同士の間柄なので、ちょっといつもの対談よりくだけた話し方になっている点は、ご容赦を。
今回は初回につき、全文無料で読める形で公開。次回からは、ぜひマガジンの購読、もしくは単品でのご購入を。(全5回予定)
![]()
■原書が読みたくて英語力がついた
西田:やっぱり普通の人って翻訳家の仕事を知らないと思うんですよ、ぶっちゃけた話。
翻訳家というと、いわゆる翻訳小説とかの翻訳家しか知らない。もっと言うと、通訳との差も分からないと思うんですね。
石橋:そうですね。
西田:全然違う仕事じゃないですか。実際は。僕だって全部を知ってるわけじゃないわけですよ。翻訳家の仕事って。
ただ、今の翻訳家の仕事っていろいろ広がってるんだ、というのは分かってます。それがどんなものなのか、というのをいちばん手軽に聞ける人は石橋さんですね……ということがあるので、お願いしようと思った経緯です。
……まず、私との関係を解説するところからいきましょうか。読む人のために。
石橋:はい、そうしましょう。
西田:あれだよね、いちばん最初って、中学……。
石橋:1年が同じクラスだったんだと思うんですよ。
西田:あ、1年が同じクラスで、2年から違うんだっけ。
石橋:その時にいろいろ趣味が合うということが分かり。
西田:そうそう。我々が通ってた中学って、あの当時としてはたぶん変わった中学というか。
石橋:出身の福井県ではいちばん変わった中学校だったよね。
西田:明らかにね。
石橋:唯一受験のあった中学校だったしね。
西田:私立でもないのに受験があったという中学校だったので。
で、お互い部活も違うんだけど、趣味は非常に近かったということがあって。
高校も同じで、でもクラスは……2年からか、一応一緒だったのは。
石橋:でもさ、高校で僕、留学したので。
西田:留学してたよね。その留学した関係があって、大学の年度は一年ずれてる。
石橋:そう。確か、僕、大学受験に行った時に泊めてもらわなかったっけ、家に。
西田:泊めたよ(笑)
大学はSFC(慶應大学湘南藤沢キャンパス)だよね? SFCは当時からかなり英語をしっかり使う大学だった。今は英語を重視した大学って珍しくはなくなったけど、当時はSFCはそこがちょっと違ってた。コンピュータの使い方も違ってたじゃないですか。
石橋:そう。あそこはたぶん、大学でいちばん最初に入学生全員がメールアドレスを持った大学だと思う。
西田:そうですね。
石橋:それまでも計算機科学の専門の学科に行けばもちろん研究室でアカウントがあって。昔、SINET(サイネット)という大学のインターネットのネットワークがあって。それが大学を繋いでいた。
昔は日本のインターネットって2種類しかなくて、WIDEプロジェクトという研究組織が運営していたネットワークと、それからSINETという大学や研究機関を繋ぐネットワークと、あとはもう社内のイントラしかなくて。
そのWIDEプロジェクト――SINETは国立大学や一部の私大を結んでいるネットワークで、そこからあぶれた私立大学とか、一部の企業とかは、WIDEプロジェクトというところに繋がってた。で、そこの親玉が、当時SFCにいた、恩師の村井純先生。今も「インターネットの父」と呼ばれて取材に応じてたりしますけど、そのインターネットの父が、当時まだ34歳か35歳で。
西田:そっか、村井先生まだそんな歳だったんだ。
石橋:そうなんだよね。その頃にSFCに入った。
その国内有数のインターネットの海外ケーブルからの接続がつながっていたところが、その当時はSFC、僕が通っていた湘南藤沢キャンパスで。それはなぜかというと、うちの親玉(村井先生)の研究室がそのネットワークの運用をしていたから。
西田:(笑)。
石橋:だから学生にも、全員に「もうこれからはインターネットの時代だから、配らなきゃいけないでしょ」とか言って、一期生の時から、入学するといきなりメールアドレスが配られた。
当時、もう30年前だけど、「これを使うのが当たり前だ」と思ってたんだよね。サークルの連絡はいきなり電子メールでやる、という、当時としてはとても進んだ形で。
まだ携帯電話も普及してないからね。ポケベル時代?
西田:そうそう。
僕は東京理科大だから当然理系なんだけど、アドレスはもらえなくて。1年の間はね。
石橋:そうそう(笑)。
西田:あとでもらったけど。うちはサークルとのやり取りとかも電話網だったもんね。固定の。
石橋:ツリー状に電話番号が並んでるという。そういう時代だったよね。
西田:まあまあ、大昔ですよ。
……まあそういう背景があって、結局翻訳家として仕事をし始めたのって何年前から? 十数年前ぐらい?
石橋:プロとして働き始めたたのはそのぐらい。もともと留学していた関係で英語は多少できたので、前からやってはいたけれど。
僕ちょっと、留学とかしててもさ、英語が好きじゃないというか、喋るのが苦手で。喋ったはしから今喋った英語の文法の間違いが気になるタイプなんですよ。
西田:ああー。
石橋:そして喋れなくなる、みたいな(苦笑)。文法の間違いとかが気になるタイプで、話せるようになるまでに時間がかかった。そういうので、かえってよく文法なんかは調べるようになった。
あと、SFが好きで、特にアイザック・アシモフという作家のファンで。今読み返してみても、最近のAIに関する議論が全部「これ30年前にアシモフの本で読んだぞ、この話」と思うという、伝説の作家のファンだったんだけど。
西田:そうだったねえ。『ファウンデーション』のドラマ、今月からだよ。非常に楽しみですね。それはともかく。
石橋:そう。
当時はアシモフ先生がご存命で、まだ新刊が出てたんだよ。
新刊が出るんだけど、日本に来るまでに3年か4年かかる。それで「最新刊を読みたいなあ」と思って原書を読み始めて。最初の1冊は半年ぐらいかかったかな。そうやってSFを趣味で読んでたら、日本の受験の英語は余裕になっていて。SFのおかげで英語ができるようになった。
西田:ああ。それはね、私も影響を受けてますね。あなたに。私はたしか『ドラゴンランス』だったと思うんだけど。
石橋:ああー、『ドラゴンランス』、懐かしい。
西田:『ドラゴンランス』の最初の三部作(『ドラゴンランス戦記』)の次、『ドラゴンランス伝説』か。『ドラゴンランス伝説』がまだ日本で出てなくて、あなたが留学してる時に手紙で「送って」と頼んだ。
石橋:そうだったっけ。
西田:そうそう。私もそれを原書で読んで。
でも僕も、それは読み終わるのに8カ月ぐらいかかった。結果、僕も英語を読むのは受験の時にはだいぶ楽になってた記憶があって。
石橋:じゃあ、根っこは共通なんだね。
西田:そうそう。で、その結果として、そのあと映画を字幕なしで観たりとかするようになって……という感じなんですよね。
石橋:そんなところにルーツがあったとは。
■翻訳家はあまり英語で「話さない」?!
西田:今でもそんなに英語が得意ではないけれど、聞くのと読むのは大丈夫。喋るのは単語力が足りないのですごくブロークンではある。で、文法もめちゃめちゃ、というパターンです。
英語でインタビューもするけど、本当に辛くて。本当に辛くて!
石橋:(笑)。いや、分かるよ。僕、仕事としては翻訳という英語の専門家だけど、たぶん英語を喋ってる機会は宗千佳よりもずっと少ないので。
西田:そうかもしれないね。
石橋:ビジネスメールは書くようになった。
だから、ビジネス英語は書けるようになったけど、言葉で喋る機会ってないんだよね、翻訳者って。
西田:あ、そうか。読み書きはするけど。
石橋:英語ベースでやり取りして仕事ももらうけど、仕事先と音声でやり取りしたのって、15年間で一回しかない。
西田:疑問だったんだけど、翻訳に関するミーティングとかって、別にオンラインミーティングがあるわけじゃないの? だいたい基本はメールとかメッセージとか。
石橋:メールとか、会社によってはメッセンジャーとか。
会社によって使うものは違ってて、今の取引先は、ひとつはGoogleハングアウト。もうひとつはSkypeかな。
翻訳会社は体制を組んだのが早いところが多いから、その頃にいちばん有力だったツールが多くて。だからSkypeを、そのままずっと惰性で使っていて。最近だったらSlackとか Discordとかなのかもしれないけど、今の取引先は未だにSkypeを使ってる。
西田:なるほど。私は今だと、月イチとか月2ぐらいでは英語のインタビューがあったりする。喋ってはいるけど、毎回吐きそう。
石橋:喋るのは、ひょっとすると今は宗千佳のほうが上かもしれない。
西田:そこのところはなんとも言えないところですが。
石橋:分かんないけどね(苦笑)。
■「オンライン化」が進んでいた翻訳業界
石橋:翻訳業界は、いろいろオンラインで仕事をみんなで分担してやるようになったりとか、在宅の人に仕事を頼むとか、国際的にいろんな国の人とやり取りしながら仕事をする、という、今で言うとDX的な働き方の浸透が最も早かった業界のひとつで。
なんでかというと、翻訳者って、やっぱり「英語から日本語」とか、「ドイツ語から日本語」にするのは、日本人に頼むのがいちばん良いわけですよ。
例えば、英語にするなら英語ネイティブに頼むのがよくて。アメリカの英語にするんだったらアメリカ人に頼むのがいいし、イギリス英語だったらイギリス人に頼むのがいちばん無難なんですよね。
西田:まあそうでしょうね。
石橋:でもそうすると、自分の国の――例えばアメリカの人が日本人に頼もうと思うと、日本に住んでる日本人に頼めたほうが、プール(人員)が大きくなるじゃない?
西田:当然そうですね。
石橋:業態的にフリーランスが多い業界だということもあって、やっぱり直で日本人に発注したいとか、そういうケースが結構あったらしいのね。
人材も国際的に調達して、英語でテキストだけを送って、質問とかは別途そのための仕組みを作ればいい……という。
だから、音声でのやり取りってあんまりしなくて。音声だと記録に残らないから、という理由もあるかもしれないけど。
西田:ああ、なるほど。
石橋:英語の質問なんかも、口頭で受けた質問をその人が返せるわけじゃなかったりするしね。翻訳会社が間に挟まってて……
ああ、まず翻訳の業態の話をしたほうがいいのか。
西田:そうだね。
石橋:いろんな働き方のパターンがあって。
翻訳者は別に資格って要らないんですよ。「翻訳してほしい」という人と「翻訳してあげる」という人がいて、仕事のやり取りができればいい。
あと、社内翻訳者というのもいて、たくさん翻訳することが分かっている会社なんかは社内に翻訳者を抱えている。IBMとか、Microsoftとか、そういうところには一定の数の社内翻訳者がいて、その人がある程度の業務をやっているんだけど。
西田:いわゆるビジネスドキュメントが大量に――例えばマニュアルだとか、リリースノートとかが出てくるようなところは社内翻訳者がいて、機械翻訳じゃちょっとダメ、というところは社内翻訳者がやって、というパターン?
石橋:そうそう。
それ以外のもの、専門性が高かったりとか、社内に翻訳者を持っておくほどのリソースを持っておくほどでもない、という場合は、誰か外の人に頼むんです。多くの会社は翻訳会社というところに頼む。
翻訳会社にも、会社内にある程度プールを持ってるところもあるんだけど、わりと多くの会社は社外にたくさんのフリーランスのプールを持っていて。
ひとつの理由は、翻訳ってけっこう、ピークロードがかなりピーキーというか。大きい依頼が来ると、その時だけニーズが増える。そういう案件が取れない時にはそうでもない……みたいなところがあって。社内に一定のリソースをずーっとキープしておいても、いつも食わせられるかどうか分からない。だから、大きい仕事が来たらかき集めるようにしている。
もうひとつの理由は、専門性がけっこう高いから。
例えば、科学にしてもゲームにしても、スポーツや経済にしても、ひとつひとつ分野に専門がある。どれかしらができる人を全部社内に揃えるのも大変だし、その人たちを全部揃えたとしても、そしたら広く薄くなっちゃうから。
突然ITのマニュアルのドキュメントが1万ページ来ました、という時には社内プールじゃ全然間に合わないので、外に頼むと。
西田:なるほど。
石橋:例えば、ITだってプログラミング言語に詳しい人もいれば、ネットワークに詳しい人、セキュリティに詳しい人もいる。ゲームだって、スポーツゲーム、レースゲーム、FPS、RPGでは、使う語彙も違えば精通してなきゃいけない分野も違うので。
西田:その通りですね。
石橋:で、この分野が得意、という人を、いろいろ取り揃えておいて、「じゃ、この仕事はこの人に振ろう」ということをしないと回らないので、翻訳会社が仲介をしてそういう人に回す、という風になってるんです。
……ということは、僕らが受けた質問で分からないことがあったとしても、間には翻訳を依頼するプロジェクトマネージャーが挟まるので、そこに質問するわけですよ。
西田:はいはい。
石橋:その人が、大元へと中継して質問をして、返してもらわなきゃいけない。だから口頭で質問をする、というわけにいかないのね。
西田:うん。
石橋:たぶん書籍翻訳とかだと、エージェントがひとりいて、こっちに出版社と翻訳者がいて、分からないことがあったら原作者に直接聞く……みたいなやり方が成立するんだと思う。
でも、それは特殊なジャンルなんだよね。一般の人が翻訳の仕事って聞いたら、そういうのを想像するかもしれないんだけど、実はそういう仕事はかなり少ない。
一般には、翻訳する人にも、誰が元の文章を書いたかという顔は見えてないし、翻訳してもらってる人にも、誰が翻訳してるかという顔は見えていない。間にエージェントが入って、システマチックにプロジェクトマネジメントしてる、という。
西田:たとえば本だったら、一冊まとまった塊で翻訳していくし、そもそもそんなに仕事の量があるわけじゃないから、1to1で、ある程度チェーンが繋がった形でいく。でも、商業的に大量にフローで翻訳が必要な業態では、属人的にやっていると回らないから、ブロックごとに分けてる。しかも、人の集め方もそのタイミングに合わせて変えながらやっているから、説明してくれたような形になってるということだね。
石橋:そういうこと。
ただもちろん翻訳者も、ゲームのアップデートの仕事とかだと、「過去にこのタイトルの翻訳を担当した」という人の方が、やっぱり文脈も分かってる。「このキャラクターはどういう口調で喋る」とか、けっこう調べるのが大変なんですよ。だから、一度同じタイトルをやったことがある人にもう一度頼むほうが、良いものが上がってくる可能性が高くて、「なるべくならその人に振りたい」というキープの仕方はしている。ITのマニュアルの翻訳とかだとそうでもないけど。
ただ、その人が病気になったりとか、他の仕事で忙しくて受けられない、という事情があったとしても、結局締切は来るので。そういう時は、プロジェクトマネージャーが次善の策で、それに近いタイトルを過去にやったことがある人なんかを見繕って、「今回だけお願いしたいんだけど」と言って頼んだりする。
西田:そこのコントロールはエージェントの人がやってる、という感じ。
石橋:そう。で、僕は末端の職人、という感じ。
ここから先は
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
