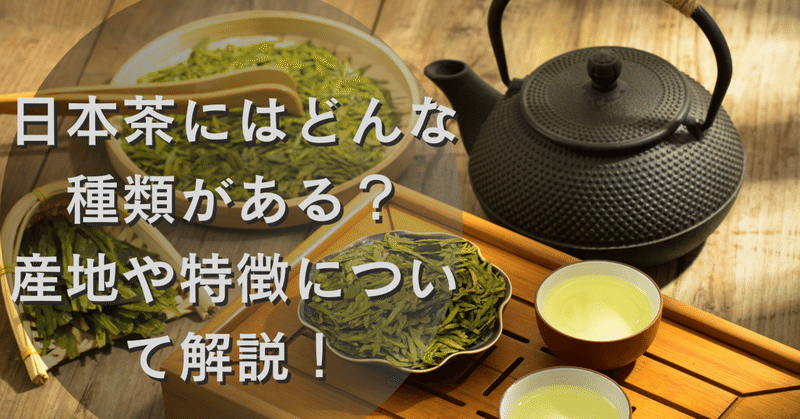
日本茶にはどんな種類がある?産地や特徴について解説!

日本人になじみのあるお茶といえば、やはり日本茶ではないでしょうか。
コーヒーや紅茶など、さまざまな飲み物がある中で、無性に飲みたくなってしまうこともありますよね。
「日本茶」と一言で言っても「ほうじ茶」「緑茶」「玄米茶」など、たくさんの種類があります。
この記事では、日本茶の種類や産地の説明だけでなく、それぞれのお茶がどのように分類されているのかについても解説します。
日本人として知っておいて損はない情報に触れているので、ぜひ最後までご覧ください。
日本茶のほとんどが緑茶の仲間

実は、日本茶のほとんどは緑茶の仲間です。
新芽のみを使ったり、茎の部分まで使ったりして味わいが異なることや製造方法の違いから、お茶の名称がそれぞれ違います。
それでは、どのお茶が緑茶の仲間になるのかをみていきましょう。
煎茶
煎茶は、一番身近でいわゆる「緑茶」としてなじみのあるお茶です。
たっぷり光合成した新芽を蒸気で蒸し、水分が均等になるように時間をかけて揉みます。
揉みながら熱風を当てて乾燥させ、茎などを取り除きながら針の形に整えて茶葉は完成です。
黄色みがかかった水色、苦味や渋みなどが程よいバランスで楽しめます。
玉露
玉露は、新芽が出始めたタイミングで日光を「寒冷紗(かんれいしゃ)」と呼ばれる化学繊維の布を被せて育てて作られます。
品質が良い玉露ほど、甘みや旨みが強く、香りも強く立ち、水色も透明色です。
ちなみに、「玉露」とは別に「玉露入り」という表示を見かけたことはありませんか?
原材料が玉露100%か数%かで表示が異なります。玉露数%入りのお茶が「玉露入り」です。
玉露は緑茶の中でもカフェインが多く含まれるので、飲みすぎには注意しましょう。
ほうじ茶
ほうじ茶は新芽ではなく、成長した茶葉を焙煎して作られたお茶です。
沸騰したてのお湯を注ぐだけで香り高く、色も茶色(飴色)をしていて、手軽に飲めるお茶といえます。
また、ほうじ茶はカフェイン含有量が少ないお茶なので、他の緑茶に比べると気にせず飲めます。
カフェインが少ない理由は、茶葉は成長するにつれてカフェインが少なくなることに加えて、焙煎する過程でもカフェインが減るからです。
玄米茶
玄米茶は、比較的安い緑茶や番茶の茶葉へ煎り米(炒り米)と呼ばれるお米を一晩水に浸けて蒸した後に煎ったお米を加えたものです。
煎り米を混ぜているため、茶葉の量が減りカフェインは煎茶の約半分、コーヒーの約1/6に抑えられます。
玄米の香ばしい香りが特徴で、浸出時間によっては煎り米から浸出する口当たりも楽しめます。
茶葉不使用のお茶

私たちの身近にあるお茶は、製造方法が異なるだけで緑茶の仲間であることがわかりました。
緑茶と何かを混ぜたブレンド茶や、「お茶」ではあるけれど、茶葉を使わないお茶もあるため、詳しくみていきましょう。
麦茶
麦茶は、焙煎した大麦を煎じたお茶で、香ばしくてすっきりとした味わいが特徴のお茶です。
身体を冷ましたり、血液をサラサラにする作用があるため夏バテ防止にもなります。
また、テレビCMの影響もあり「麦茶=夏に飲むお茶」として思い浮かべる人も多いでしょう。
カフェインが含まれていないため、安眠の妨げになることもなく、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い年齢の人が安心して飲めるお茶です。
麦茶を飲むことで得られる効果についても、すでに「胃粘膜保護作用」や「抗酸化作用」に期待が集まっています。
今後も注目度の高いお茶といえるのではないでしょうか。
黒豆茶
黒豆茶は、黒豆を焙煎したりに出したりして作るお茶で、身体に良いお茶として近年注目を集めています。
ポリフェノールの一種である「アントシアニン」を含んでいるため、抗酸化作用があり美肌やアンチエイジングの効果が期待されているお茶です。
この他にも、「高血圧・血糖値の改善」「肝機能の改善」といった嬉しい効果や、「むくみ・冷え性の改善」といった女性に嬉しい効果も期待できます。
黒豆茶も麦茶と同様、カフェインが含まれていないので寝る前に一杯飲んでリラックスするのもおすすめです。
日本三大銘茶

日本茶には、お茶の生産で有名な日本三大産地と上質なお茶、優れたお茶を指す日本三大銘茶と呼ばれるものがあります。
日本三大産地は、お茶の産地で有名かつ生産量の多い「静岡・鹿児島・三重」です。
しかし、日本三大産地と日本三大銘茶の産地が同じとは限りません。
狭山茶摘み歌の一節で『色は静岡、香りは宇治、味は狭山でとどめさす』とうたわれているのをご存知でしょうか?
狭山茶摘み歌の通り、日本三大銘茶は古くから「静岡・宇治・狭山」と言われています。
最近では、狭山茶の生産量が少ないことから、狭山茶に変わって鹿児島茶が加わることもあるため、以下4つの特徴について紹介します。
静岡茶(静岡県)
静岡茶は、日本三大産地である静岡県で栽培されているお茶です。
自然豊かな土地で育つ静岡茶ですが、とくに山間地で育つものは1日でうまれる寒暖差と程よい日照時間で、奥深い味わいをもつ茶葉に育ちます。
県内には、20を超える良質なお茶の産地があり、生産農家の大小もさまざまで多種多様な個性を持つお茶が楽しめることも特徴のひとつです。
宇治茶(京都府)
宇治は、玉露や抹茶の生産量が日本一で知られています。
日本茶の始まりの地とも言われており、千利休が始めたとされる茶の湯の歴史も深い土地です。
宇治茶の産地は、昼夜の寒暖差が大きいため渋みだけでなく、コクや甘さも味わえます。
また、香りも良く上品なお茶です。
狭山茶(埼玉県)
狭山茶は、茶摘みが年2回と制限されているため、生産量が日本全国8位と低いです。
しかし、茶摘み歌にもあるとおりコクがあって芳醇な味わいが楽しめることから、日本三大銘茶として数えられています。
狭山茶は、手もみ製法を用いており、蒸し焙炉に敷いた和紙の上で茶葉を揉み乾かして作られるのが特徴的です。さらに、「狭山火入れ」といった、伝統的な火入れをしているため、少ない茶葉でも味や香り、色に厚みを加えられます。
独特な製法が、お茶をコクと芳醇な味わいに仕上げているのです。
鹿児島茶(鹿児島県)
鹿児島茶は、生産している土地の中で1番南に位置しているため、日本一早い新茶を出荷できるのが大きな特徴です。
豊富な日照時間と、茶摘みの1週間前に黒色の資材でカブセをすることで、渋みと甘みの調和が取れたお茶が育ちます。
また、鹿児島では渋みと甘みの調和が取れたお茶だけではありません。
香り豊かなお茶も鹿児島県内北部で育てており、さまざまな味を楽しめます。
おわりに

私たち日本人にとって一番なじみのある「日本茶」について解説しました。
日本茶にはさまざまな種類があります。
製造方法や産地によって、香りや味わいも変わりますので、ぜひお気に入りのお茶を見つけて、有意義な時間をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
