
サブカル大蔵経34 永井和『西園寺公望』(山川出版社)
西園寺公望がなぜ<最後の元老>となったのか、その人物像や活躍ではなく、ただただ周辺の相談する順番を通して、元老から内大臣へ、天皇補佐の機構が移る過程を追うマニアックな本。
木戸幸一との絡みがなくて残念だが、大久保利通次男の薩摩閥・牧野伸顕と山形出身山県閥の平田東助との関係が濃密に描かれる。
政党と軍の関係がメインだと思っていた昭和政治史で、元老と内大臣の存在がクローズアップされるのは、ひとえに天皇の責任を守るためか。軍部に接近した近衛首相と木戸内大臣のコンビは西園寺逝去後、結局暴走。となると太平洋戦争の時、元老という抑えがいなかったということは、結構大きな問題だったかもしれないと、川田稔『木戸幸一』(文春新書)とさらに本書を読んで思った。元老政治の良さと元老政治を打破しようとした弊害が太平洋戦争に繋がったのだろうか。
平田内大臣から西園寺へ伝えたい事。
「清浦や山本などは、あるいは元老になる希望を持っているかもしれないが、それは断じていけないと思う。山県、松方の両元老が亡くなられ、西園寺公が唯一の元老となられた。中略 元老は西園寺公を限りとし、将来はおかないのが良い。原敬が生きておれば別だが、現状では元老の後継者は種切れである。」p.50
元老のふさわしさとは。なぜ山本権兵衛や清浦圭吾はふさわしくなかったのか。
天皇の大権君主制を、ぎりぎり紙一重の形式にまで縮小することによって、明治憲法を変更することなくして、日本においてもイギリス型の議会主義的立憲君主制を確立させようとしたのが西園寺であり、「1人元老制」「元老内大臣協議方式」はそのために必要な手立てであったと、肯定的に評価することもできる。その意味で西園寺流の「1人元老制」「元老・内大臣協議方式」に美濃部達吉の天皇機関説や吉野作造の民本主義と同等の位置づけを与えることもできよう。p.92
今の日本に元老はいるのか?中曽根、野中が死去した現在、森、小泉、青木、伊吹、大島、古賀あたりか?
実は、政界だけでなく、どんな世界でも、元老がいなくなった時ヤバいのでは?お年寄りに耳を傾けるのは、かっこ悪かったり、理論的でないかもしれないか、逆張りで、いいと思う。
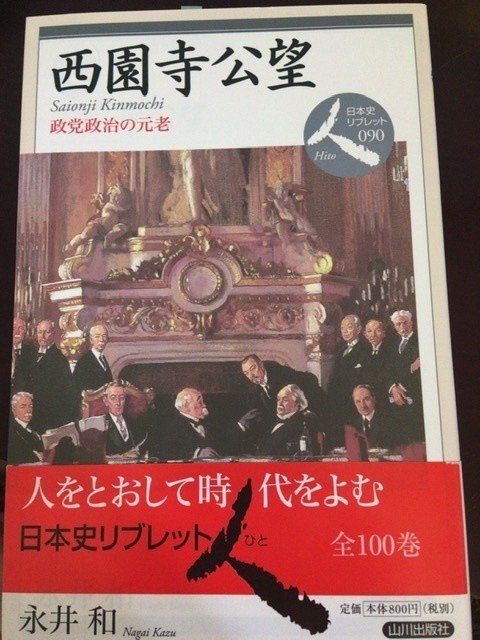
本を買って読みます。
