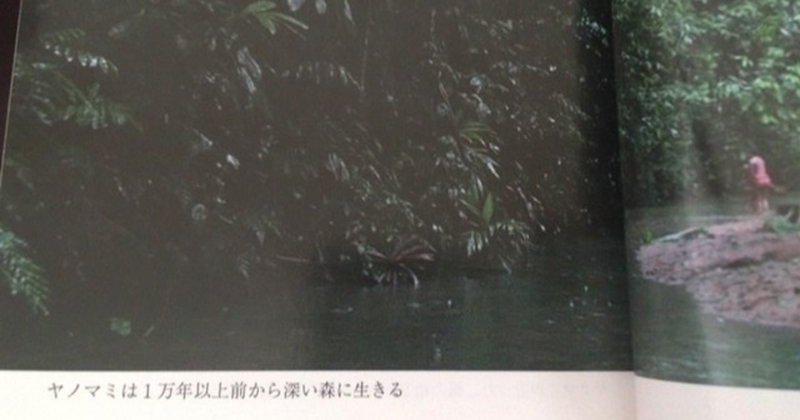
サブカル大蔵経72 国分拓『ヤノマミ』(新潮文庫)
現代の聖典。日本からNHKスペシャルの取材でブラジル奥地の少数民族ヤノマミを訪ねた作者。ヤノマミへの想いは片思いか、両思いか?日本はヤノマミになるのか?
ヘレアムゥとはいわば訓話のことでワトリキでは起床直後と就寝前の時間にほぼ毎日行われた。話すネタや話す場所も自由だった。p.73
日常でなされる言葉のアウトプット。
反復が非常に多いことだ。同じニュースが何度も繰り返し伝えられるのである。それは彼らが文字を持たないことと関係があると言う。p.75
お経もそうかもしれない。繰り返しは無駄なのか、培われたメソッドなのか。
ヤノマミには50を超える雨の言葉があった。アルマジロの雨、短い雨、紅い花の雨、川を叩く雨、木の匂いの雨、雨の数だけ匂いも違う。p.111
雨の言葉…。豊かな語彙と雨が生活に直結しているしるしか。
ヤノマミのしきたりでは、死者に縁のものは死者と共にも燃やさねばならない。そして、死者に纏わる全てを燃やした後、死者に関する全てを忘れる。名前も、顔も、そんな人間が言ったことも忘れる。彼らは死者の名前を決して口にしない。p.119
忘れるという供養。
ヤノマミでは4、5歳になるまで名前がない。男の子は「モシ」、女の子は、「ナ・バタ」とだけ呼ばれる。モシとは男性器、ナは女性器、バタとは、大きなとか、偉大。つまりナ・バタとは偉大なる女性器と言う意味だった。p.134
悪魔に名を呼ばれないためか。
余所者・流れ者・狩の名人パオロはこう答えた。「2度ほど結婚したがいいことなんて何もなかった。あいつらは働かない。働かないから、俺が働かないといけない。1人が1番良い。食べ物がない時は誰かがバナナをくれるから何も困らない。俺は1人がいい」パウロは断るごとに、女は面倒、女はこりごりだと言って、アハフーと笑った。p.139
異端児パウロに諭される日本人。
刃傷沙汰ルール。制裁の時、間男は抵抗してはならない、間男を殺してはならない、妻は制裁を受けない。p.142
なんか、最適な謝罪会見マニュアル。
通訳・モザニアル曰く、「これまでは、狩が1番上手い者か、精霊を最も知っている者が「バタムン(指導者)」になった。これからは、ポルトガル語が1番上手い者がバタムンになる。」p.158
言葉が武器になる、魔の道具。
「ホトカラ」は、死後に精霊となった人間が「第二の生」を送る場所。自分も死ねば同じ場所に行くのだ。子供は死んだのではない。生霊となってホトカラに行っただけなのだ。自分も死ねば生霊となってホトカラに行く。ホトカラに行けば精霊となった子供とまた逢える。女はそう信じていた。ホトカラとは女たちにとって再会の場でもあった。狩りの時もホトカラという言葉を聞いた。自分が仕留めた猿を自慢した後、僕たちが「今、その猿はどこにいるのか」と聞くと「ホトカラ!」と言って天を指差したのだ。そして、自分も死ねば同じ場所に行くのだと言った。殺した者と殺された動物が同じ場所で再会するのだ。p.195
ホトカラは浄土のような感じ?ブッダ→ホト+ケ→仏ホトケだよ?まさかサンスクリットか漢語がブラジルの奥地に?
ワトリキでは年に1度、死者を掘り起こして、その骨をバナナと一緒に煮込んで食べる祭りがある。死者の祭りと呼ばれるものだった。p.198
死者出汁。ウチにとりこむ。骨という残存物の有用性?見るだけでもなく、触るだけでもなく、食べるという選択。
深い森の中では、人間と動物、人間と精霊、そして生と死が、切り離されず一体となっている。それらは支え合い、時に殺し合いながら、どこかでつながり、最後はともに消滅する。p.201
皆、最後は消えていく。消えていく寂しさと幸せ。
ヤノマミの女は必ず森で出産する。ヤノマミにとって生まれたばかりの子供は人間ではなく精霊なのだと言う。精霊として生まれてきた子供は、母親に抱き上げられることによって初めて人間となる。だから、母親は決めねばならない。精霊として生まれた子供を人間として迎え入れるのか、それとも、精霊のまま天に返すのか。その時、母親はただじっと子供を見つめているだけだった。森の中で地面に転がっている我が子をじっと見つめているだけだった。p.204
実はこのくだり、ヨーロッパもアイヌも似ているような。
ワトリキは甘いユートピアではなかった。文明社会によって理想化された原始共産的な共同体でもなかった。ワトリキには、ただ「生と死」だけがあった。善悪や倫理や文明や法律や掟を超えた剥き出しの生と死だけがあった。1万年にわたって営々と続いてきた生と死だけがあった。思えば僕たちの社会は死を遠ざける。死骸をすぐに片付けられ、殺すものと食べるものとかが別人だから、何を食べても心が痛むことがない。だが彼らは違う。生きるために自分で殺し、感謝を捧げた後に土に返す。今日動物を捌いた場所で明日女が命を産み落とすことだってある。ワトリキでは死が身近にあっていつも生を支えていた。p.208
ただ生と死があった。現代はそれ以外に何があるのか?何かがあると思う幻想が苦しみも幸せも生み出している。
モシーニャは一点を見つめながら、子どもの亡骸の入った白蟻の巣を燃やし続けた。p.230
本当の埋葬だなあ。
精霊か、人間か、ワトリキでは母親が決める。どんな結論を下したとしても、周りの者たちは受け入れる。理由も聞かず、ただ受け入れる。そして、人間として迎え入れた子供両親は生涯をかけて育てる。男も何も言わず狩りの回数を増やす。p.240
物言わぬ男たち。
ローリはすっかりやつれていた。暗い表情のまま俯いていた。その傍らに子供が転がっていた。女の子だった。子供は手足をばたつかせていた。ローリの母親が来て、生まれたばかりの子供をうつぶせにした。そして、すぐにローリから離れた。子供の前にローリだけが残された。女たちの視線がローリに集まった。一瞬嫌な予感がしたが、それはすぐに現実となった。暗い顔をしたローリは子供の背中に右足を乗せ、両手で首を絞め始めた。とっさに目を背けてしまった。すると、僕の仕草を見て、遠巻きに囲んでいた20人ほどの女たちが笑い出した。女たちからすると、僕の仕草は異質なものだったのだ。失笑のような笑いだった。僕はその場を穢してしまったと思った。僕のせいで笑いなど起きるはずのない空間に笑いを起こしてしまった。p.251
手をばたつかせる儀式に目を背け、女な笑われた。その笑いこそが人間の深奥か。
その夜、ローリはハンモックには眠らなかった。出血が続いているようだった。ローリはハンモックに背中を預けながら、地面に腰を下ろしたまま一夜を明かした。夜明け前、囲炉裏から声が聞こえてきた。父親が何かをしゃべっていた。父親はこうつぶやき続けていた。森は大きい。歩けないほど大きい。p.253
森といのち。
精霊か人間か。女たちは一体何を基準に決断するのだろう。経済的な理由なのか、道義的なことなのか、答えは見つからない。女たちがその理由を決して語らない以上、僕たちには永遠にわからない。もしかするとローリ自身にも理由はわからないのかもしれない。p.254
私もこの基準を知りたいと思ったが、本人にもわからない。自力の世界ではない。
菅井カメラマンが白蟻の巣を見ながら「彼らは森を食べて、森に食べられるんだなぁ」と言った。明日を生きるために魚を獲る場所で、子供を納める白蟻の巣が激しく雨に打たれていた。彼らが生まれ、殺し、死に、土に還っていく円環を持った。彼らは体験的に自分がその円環の一部であることを自覚しているように感じられた。たぶん、彼らは全てを受け入れている。そう思った。森で生まれ、森を食べ、森に食べられると言う摂理も、自分たちがただそれだけの存在として森に在ることも、全てを受け入れていると思った。もちろん、それが正しいのか、僕にはわからない。僕にわかることがあるとすれば、これからも人は生まれ、猿も生まれ、ジャガーも生まれ、蟋蟀も生まれ、蟻も生まれると言う事だけだ。乾季と雨季が何度も繰り返すように、生も死も何度も繰り返す。生まれて、死んで、また生まれる。それだけのような気がした。p.258
食べられる私。私を食べてくれる森。
ローリは魚を追いながら、雨に煙る森の中に消えていった。すると、ローリが消えていった方向からアマゾンで最も美しいと言われるモルフォ蝶が舞ってきた。僕らは一緒目を奪われたが、女たちは誰1人、その青い蝶に関心を示さなかった🦋p.258
珍しい、というわれわれの視点。
ヤノマミの場合も最初の文明は宣教師によって持ち込まれることが多かった。宣教師にとっては一生を捧げるにふさわしい未開の地でもあった。p.279
「宗教」が文明を運び、文化を破壊するのか…。日本にとっての仏教もそうだったのかも。宣長や篤胤らの国学は、これを言っていたのか。
悲しき熱帯「先住民を教化するためには、まず、彼らの家を変えることだ。家は彼らの伝統や信仰と一体となっている。彼らの家を壊せば、信仰は失われ、伝道がやりやすくなる。」p.280
神棚と仏壇が日本の防波堤だったか。
長老シャボリ・バタの晩年の叫び。私の精霊がいなくなってしまった!私の精霊が死んでしまった!p.306
この「精霊」が見えなくなったとき、ヤノマミは終わるのかな。
長老たちはブラジル社会と戦っても武力では到底勝てない、言葉で訴えるしかないと考え、ポルトガル語の教育に同意した。言語教育の始まりと軌を一にして、ブラジル文化の流入が始まった。高カロリー・高タンパクの食べ物貨幣の意味を知り、様々な現代社会のシステムを知った。賃金をもらって保健所で働くようになり、狩りに行かなくなった。プライバシーの概念が持ち込まれた。20年前までは誰もパンツを履いていなかった。10年前までは誰もお金を見たことがなかった。今彼らは資本主義の入り口にいる。p.311
後日談。資本主義って…。
ヤノマミの居住区が保護区に指定された時FUNAIの総裁として陣頭に立ったシドニーポスエロ氏は先住民と文明との難しい関係についてこう語っている。「原初の世界に生きる先住民にとって最も不幸なことは、私たちと接触してしまうことなのかもしれない。彼らは私たちと接触することで笑顔を失う。モノを得る代わりに笑顔を失う。彼らの集落はどんなに小さくても1つの国なのだ。独自の言語、風習、文化を持つ1つの国なのだ。そうした国が滅んだり、なくなったり、変わってしまうと言う事は、私たちが持つ豊かさを失うことなのだ。」p.312
保護の名の下に破壊されるもの。
ポルトガル語で話しかけてきたハイムンドの最大の関心事はモノの値段だった。バナナ1房、Tシャツ、サンダル、時計いろいろなものを指差していくらかと聞いてくるのである。彼はテレビカメラを指差していくらか?とよく聞いてきた。さすがに本当の値段を言うわけにはいかないから、知らないと答えるしかなかった。p.326
値段という物差しが侵入した最後の地か。OSはあっという間に切り替わる。
東京に戻ってからも、体調は悪化する一方だった。食欲がなかったし、食べるとすぐ吐いた。10キロ以上減った体重はなかなか元には戻らなかった。外に出るとよく転んだ。あの日以来菅井カメラマンは子供に手をかける夢を見るようになったと言った。僕はそんな夢見なかったが、何故か夜尿症になった。善悪や規範だけではなくただ真理だけがある社会に生きる人間に直に触れた体験が僕の心をざわつかせ、何かを破壊したのだ。p.349
テレビマンの業は、未開を求める私たちの欲望に忠実。
加害者となる。あるいは加害者になってしまう。それは自分が最もそうなってはならないと絶えず戒めていたことだった。だから彼らが知らない物は、持っていかなかった。自分たちの習慣を消そうとした。番組や書籍を作る時も資料で知りえた情報を極力排し、自分が見てきたことだけを放送しようと思った。しかし番組が電波に乗り、書物が書店になるにつれ、それは無意味なことになる。結果として見世物となり消費されて忘れられていく。そしてその加害者は間違いなく自分なのだ。p.360
遅かれ早かれ、出逢ってしまったんだ。今もブラジルでのコロナ被害がアマゾン流域に広がって医療崩壊しているらしい。文明とともに疫病が入り込み免疫のない民族を根絶やしにする。これはインカ帝国と同じ道のりか。
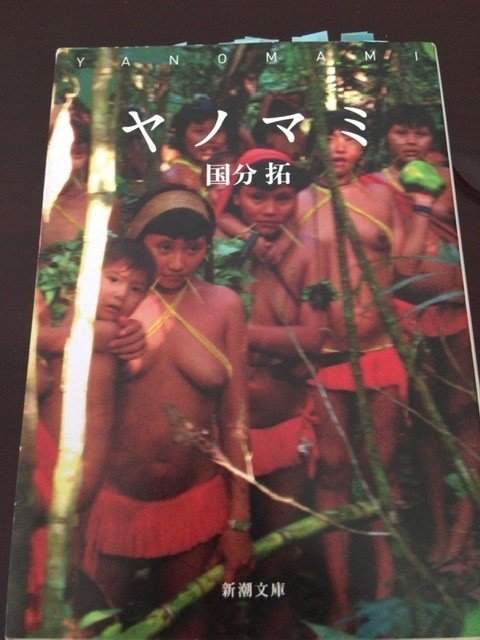
本を買って読みます。
