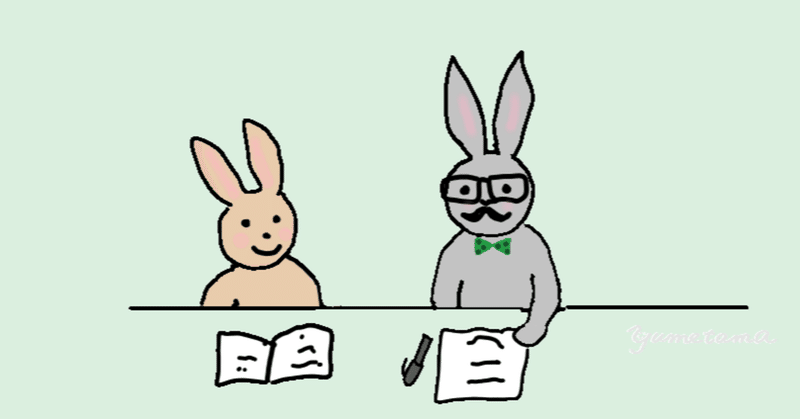
分数を知らなかった高校生の話〜家庭教師からみた軽度発達障がい児の教育〜
家庭教師歴、3年目。大学生になって最初に始めたアルバイトです。
家庭教師というアルバイトは私に非常にマッチしていたように思います。私は塾や予備校に行ったことが1度もなく、進研ゼミ信者でした。自分で計画を立てたり勉強法を考えたりマイペースにやるのが好きでした。他人からの強制を窮屈に感じるというのも理由のひとつです。そういうわけで自宅勉強あるあるも共感できますし、家庭教師を雇う生徒たちはみんな私と同じようなマイペースな性格をしているので気が合います。
現在は8人の生徒がいます。小3と小5の姉妹、中2、中3がふたり、高2がふたり、大学2年生がひとり。この中には発達障がいを持った生徒もいます。高2の男の子と、大学生の女の子です。
今日は4月から指導を始めた高2の男の子の話をします。週に2回2時間ずつ、まだ短い付き合いですが、随分と長い時間顔を合わせているような気がします。
4月某日、初回授業。机の上に並べられたのは、小4から小6までの国数英理社の教材と、中1から中3までの英語の教材。と、シャーペン1本。私は指導に授業用ノートを2冊と宿題ノートを1冊使うのですが、ノートは持っていないと言います。ノートだけでなく、赤ペンも消しゴムも持っていない。持っている筆記用具が「シャーペン1本」のみでした。
高校には行っていますが今まで勉強をしたことがなく、ついていけていないと言います。アルファベットは書けない。分数は知らない。本当に勉強をしたことがないようでした。アルファベットと分数の概念の説明から入りました。
ある日、学校からの宿題で単語の意味を記号で書くというプリントがありました。「fish」「egg」レベルの英単語だったのですが、彼は読めないから分からないと言いました。私が「フィッシュ」と読みます、と言うと、「さかな?」と答えました。そうそう!わかったじゃん!でも今度は、選択肢の「魚」の漢字が読めませんでした。漢字ノートと英語ノート、同時進行になりました。
今日は漢字ドリルに「南極」が出てきて、「南極とはなにか」を聞かれました。大陸の話をしました。「赤道」を知らなかった彼は、宇宙の神秘に目を輝かせて聞いていました。話は広がって「新大陸発見」の話、「人種」の話、「温暖化」の話、「戦争」の話。漢字ドリルの中のひとつの漢字だけで、彼の世界は驚くほどに広がっていきました。
彼は「大学進学」という夢ができて、勉強を始めようと思って家庭教師に教わることを決めたそうです。本人のやる気があるので、毎週だいぶん多くの量の宿題を出しているのですが、やってこなかった日はありません。スポンジのように吸収していく彼の指導は非常にやりがいがあります。
分数から始まった授業も、まだ穴は多いものの、数学は高校の内容を少しずつカバーしながら進め始めることができています。やる気がある人間って凄いなぁと思います。
最近は宿題に小4の国理社のドリルも追加して、穴になっていたところを解説してから授業に入るようにしています。まだ小3の復習の範囲なのですが、チョウは「サナギ」になるという話、モンシロチョウの幼虫は花の蜜を食べるわけではないという話、葉書では相手の名前を1番大きく書くという話、東西南北の話。勉強を始めた彼の世界は大きく大きく広がっていきます。
軽度の発達障がいを持っている彼は、小学校の頃に別教室で「通級」指導を受けていました。そこでは彼に合った授業を受けられる一方で、皆がいっせいに学ぶ授業内容は抜けてしまいます。彼の障がいは軽度であったため、その後「通常学級」に戻りました。しかし、既に勉強は大きく遅れていました。そのときから勉強に対して劣等感を抱き、もう追いつけないという気持ちのままで入った普通高校。周りの生徒に勉強ができないことを馬鹿にされてきたそうです。家庭教師のバイトでは、生徒のお悩みを聞いたりもします。
「学び」よりは「卒業資格」を与えられたらよいというその高校で、プリントをノートに丸写しする授業を受け、アルファベットもぜんぶ書けないままで大人になっていく所だった彼が勉強を始めようと思ったことはそれだけで大きく人生観が変わるきっかけになったのかもしれません。ひと月ほどでお父様から、「彼が変わった。ありがとうございます。」と言われ、とても嬉しかったです。
この生徒、集中力とやる気がすごくて5ヶ月で授業ノート4冊目、宿題ノートは6冊目になりました。私の類題をスピーディーに作る力もだいぶん上がってきました。
「俺は小学生以下」が口癖だった彼に「勉強に学年は本当は関係ない」ことを毎回説き、あえてざっくばらんに学習を進め、色んな話をしました。勉強をしたい、と彼が既に思っていたため、学習は非常にスムーズに進んでいます。理解力、記憶力はもしかしたら同級生より低いのかもしれませんが、個別指導ではペースを合わせられるのであまり関係がありません。彼は集中力は問題がないタイプなので、本当に今まで個別指導で学習をする機会がなかっただけなのかもしれません。
集団指導の弱点は、全員の歩幅を合わせなければならないということ。特に軽度の発達障がいを持つ児童や生徒は、集団の指示が通りにくかったりもう一歩詳しく説明をされないと理解が出来なかったりします。「家庭教師」という存在は、ひとつ解決のきっかけになり得るのかもしれないと感じます。お金がかかるのですが、保険を適用してもいいくらい療養的な側面もあるのではないかと思います。
専門的な知識もなく、いち大学生の家庭教師バイトの経験談になってしまいました。世界は色々です。高校生の頃、「分数の概念を知らない同級生」がいることは想像もしませんでした。周りにそんな子はいなかったからです。私たちは大きくなるにつれ、いつのまにか似ている層ごとに分けられています。そして、他の層と関わることがどんどんなくなっていきます。想像力も鈍ってしまいます。難しいことに、社会のシステムを作っているのは、しっかりと教育を受けた人、なのです。
いろんな人が同じ社会で一生懸命生きています。子供の未来は無限大です。発達障がいを持つ子供たちの未来も制限されるべきものではありません。色んな人がいる社会で、助け合って、みんなが幸せに生きていけますように。皆が人生を通して、学年を気にせずに学び続けられる、学び直せる社会になりますように。
社会人になってバイトをやめても色んな生徒と関わった経験を忘れないようにしたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
