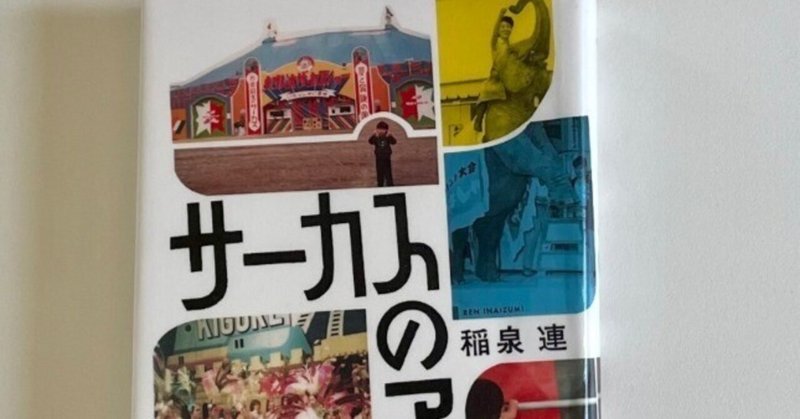
#読書感想文〜サーカスの子
サーカスの子(2023)稲泉連・著
講談社
著者は、1979年生まれ、26歳で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞している、気鋭のノンフィクション作家です。
タイトルから、サーカスで育った子供なのかと思いきや、著者自身は、サーカスの芸人ではありません。
ただ、母親がサーカスの炊事場で住み込みで働いていたため、幼少期に1年間だけ、サーカスで過ごした経験があります。
この本は、40歳を迎えた著者が、薄らいでいく自身の記憶を、確かめるように、当時のサーカスの団員たちにインタビューをして、書き上げたものです。
舞台は、キグレサーカス。
1942年に設立されたこのサーカスは、1970ー1980年代に、ピークを迎えますが、1990年代、バブル崩壊とともに、人気が衰え、2000年代に入ると、時代に合わせてその形態を変えることが出来ず、2010年に廃業します。
著者が、サーカスにいたのは、1983年頃、華やかな出し物が観客を魅了し、一番活気があった時代です。
2021年に行われたインタビューでは、現役でサーカスの芸人をしている人物は、すでにいなく、皆がそれぞれ、一般の社会で、職を得て生活しています。
この本で、著者が浮き彫りにするのは、サーカスの特殊性で、ある特殊な共同体としてのサーカスを描いています。
サーカスは、2ヶ月の公演をしながら、各地を巡業しますが、皆が、寝食を共に移動しながら生活する中、そこで結婚する人も多くいます。
そして、その中で子を産み、育てると、成長した子供はそのまま、サーカスの芸人になります。
昔はそれで、上手くいっていたのですが、だんだん転校を重ねながら、子供をサーカスで育てることに、親が不安や疑問を持ちはじめ、そうした親は、子供のために退団したり、あるいは、子供を祖父母に預けたりするようになります。
しかし、親がサーカスの芸人で、幼い頃にサーカスで過ごしていた子供の中には、サーカスが忘れられずに、学校を出たあと、またサーカスへと戻っていく子供が、少なからずいます。
それだけ、サーカスの世界には、人を魅きつけるものがあるのだろうと思います。
著者は、サーカスの世界を、現実とは隔絶された夢のような世界として書いていますが、そう感じるほど魅力的だったのだろうと思います。
特に子供の場合は、厳しい練習や、サーカスの運営のようなシビアな現実にも、全く関与しないので、おそらく楽しい思い出しかないのでしょう。
サーカスを出てから、一般の社会に馴染むのに苦労をした元サーカスの芸人たちは、「古き良きサーカスの時代」を懐かしみ、あの頃は幸せだったと皆が、口を揃えます。
一つの閉鎖的共同体の中で生活するのは、それほど安心感が得られるものかと、少々驚きましたが、そこから、外に出られなくなる危険性とは、表裏一体であることがよくわかりました。
時代の変遷に合わせて、形態を変えられなかった産業が衰退していく、モデルの一つが描かれていると感じました。
祭りのあとの、哀愁が漂う作品です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
