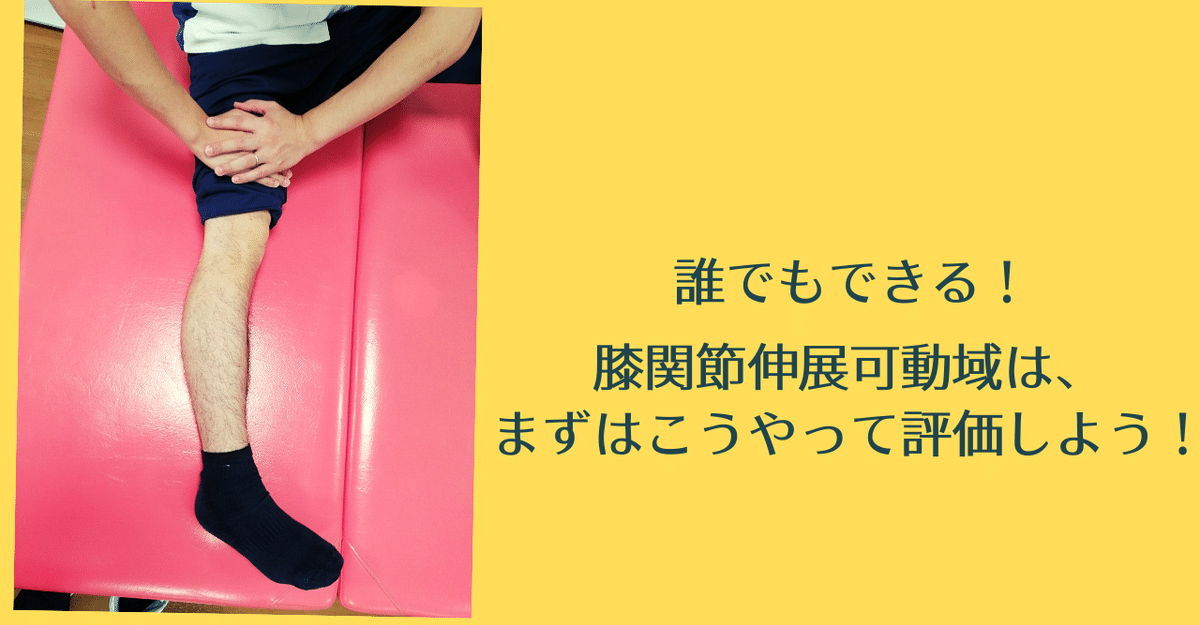
誰でもできる!膝関節伸展可動域は、まずはこうやって評価しよう!
こんにちは。茨城県で理学療法士をしています、宮嶋佑です。今回は,膝関節伸展についてです。
膝関節伸展可動域は、変形性膝関節症やTKAを始めとした膝関節障害の成績を左右するともいわれ、理学療法士だけでなく医師も気にしています。
「全然伸展出ていないぞ!」と怒られた事がある方も多いのではないでしょうか?
私はあります・・・
逆に言えば、伸展可動域をしっかりと出すことが出来れば、
・患者さんも良くなる
・医師からも評価してもらえる
事になります。
そうなれるように、
私なりの方法ではありますが、膝関節伸展可動域の評価方法について紹介したいと思います。
難しい評価方法は一切なく、だれでも出来る評価方法です!
伸展可動域制限の基本的な評価は、
①肢位を変えて可動域を比較する
②強制伸展してどこが緊張するか見る
③半膜様筋と大腿二頭筋短頭を疑う
の3つです。
更に、
④立位で膝が曲がる原因
を加えた4つを順に説明していきます。
是非、最後まで読んでいただき、自信をもって膝関節伸展制限に立ち向かってもらえたらと思います。
①肢位を変えて可動域を比較する
まず初めに行うのが、肢位を変えて可動域を比較することです。
これによって、2関節筋が膝関節伸展制限に関与しているかを評価することが出来ます。
図を用いながら解説します。

まず初めに長座位と背臥位で膝関節伸展可動域に差が生じるかを確認します。
長坐位のほうが制限が強くなる場合は、股関節伸展筋であるハムストリングによる制限を疑います。
この際に、長坐位の姿勢が骨盤後傾位にならないように注意します。
背臥位の方が制限が強くなるなら、股関節屈曲筋である腸脛靭帯、薄筋、または股関節伸展制限によって大腿が屈曲位になっている事を疑います。

内転位で増悪する場合は、腸脛靭帯、大腿二頭筋短頭(腸脛靭帯の裏の外側大腿筋間中隔から起始するため)
外転位で増悪する場合は、薄筋、半膜様筋(大内転筋と筋連結あり)を疑います。

底屈位の方が可動域が向上するなら、腓腹筋の影響を疑います。
以前は、背屈位VS中間位で比較していましたが、背屈位にすると大体の人は増悪してしまう為、中間位VS底屈位がおすすめです。
以上の評価を組み合わせながら、2関節筋が制限因子になっているかを推論します。
②強制伸展してどこが緊張するか見る
もし、どの姿位でも変化が見られない場合は
膝関節の単関節筋または関節包由来の制限が考えられます。
その際にどこが制限因子になっているかの評価方法として
膝窩部を触診しながら強制伸展する
という方法があります。

これを行うことで、膝関節後方の内側か?外側か?真ん中か?を確認することが出来ます。
膝窩部は靭帯、関節包、筋・腱などが多数に走行する場所なので、まずは後方の内側なのか?外側なのか?という大体の場所を確認することを勧めます。
内側か?外側か?については、もうひとつ簡単な評価方法があります。
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
