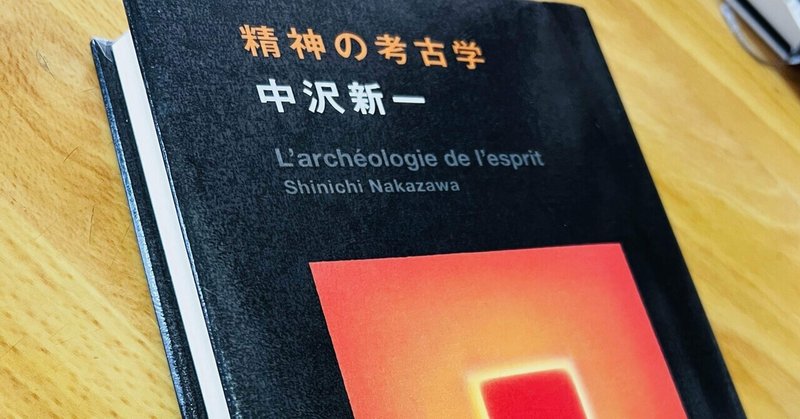
精神の考古学/中沢新一 -序盤-
第一部 ゾクチェンを探して
1 旅立ちまで
P19
神は世界に秩序を作り出す。したがって神には自由勝手な運動を阻止するための力が宿っている。ところが精霊は自由な流動の内部から自然にわきあがってくる。精霊は秩序をつくるのではなく、その背後で動いている力の流れをあらわしている。
この文章を本質的に物理現象として理解できる者、またそれを體現できる人間は今となってはごく僅かだろう。
この文章を読んでから5日が経ち、その意味がようやく今解った。
現在、集合意識の中には、既に精霊は居ない。精神に宿る流動性、精神が操るコトの流動性、仏教で言うところの「無常」だ。無常のサイクルは人によって異なる。
そう思うと、私の中には沢山の精霊が宿っているか、若しくは精霊の羽がまたたくことなく、コトを破壊させているかのどちらかだ。
私は無常のサイクルが非常に短い。
昨日と今日では自分は別人になっている。と自分では感じている。
その日のうちにその日の足場を無くしているからだ。
入って来たり、自ら湧いて来た「コト」も、その場で相殺させる。残したり、継続させることを私は嫌う。そもそも「コト」の循環が好きではない。だからもしかしたら私には精霊さえ居ないのかもしれない。
幼い頃より、御伽話やアニメに出てくる「天使」にとても違和感があった。神話の中の作られた偶像のようなものだと思っていたが、ようやく、「精霊」としての物理現象がわかりスッキリした。
精霊は嘗ては存在していた。現代では精霊の役目も要らないほど、精神も物質と化し、流動性がなくなった。個人の中では発見出来るときもあるのではと思う。
例えば、本物の壁を乗り越えるときに精霊は現れる。精神性が上がろうとしたとき、元いた此岸に別れを告げようとした時、自己否定をしたとき、そのようなときに精霊は現れる。
決して欲望成就の時に現れることはない。
それはウハウハ脳になっているだけで、そのとき現れるものは堕天使だ。所謂、魔が刺すとき堕天使は出現する。
故に現代の集合意識の中は堕天使に塗れていると言える。
また、本書のこの文章を読んで、やはり、神の力量はあると感じた。物理現象としては集合意識にある大きな秩序。自己が感じる世の中からの圧力であり、自己における妄想でもある。
P22
すべての人類がかつては非象徴、非交換、非増殖の「アフリカ的段階」に対応する心を持って生きていたのである。そこでは技術の発達はゆっくりしたスピードでしかおこなわれない。そのために物質文化に関してはじつに貧しい。しかし、精神(心)の内部をのぞいてみると、驚くほど豊かである。神ではなく精霊の力を中心とした高度な形而上学、考えられたものと生きられたものとの間の矛盾を解消する豊富な神話群、踊りや歌によって神話を補完する儀礼の数々によって、「アフリカ的段階」の心は豊かに世界を思考していたのである。
「アフリカ的段階」が精神の原始なのか、疑問に思うところでもあるが、縄文に文献がないから比較対象としてピックアップ出来ないのではという、歴史的精神性の背景も気になるところでもある。
この文面だけでは驚くべき精神の豊かさとはどのようなものであるかは分からず、本書を読み進めてみようとおもう。
豊富な神話をもとに数々の儀礼を通して体系化しなければならなかった、その時代背景の方が私には気になる。文献が残されている時点でその精神の有限性が窺える。
P25
ジャック・コーヴァンは、「新石器革命」と呼ばれる出来事が、まずは人間の精神(心)に起こった「象徴革命」として準備されていたことを強調している。野生の小麦や大麦の種子を品種改良して、収穫量の多い栽培種につくりかえるとき、将来農民となっていく人々の精神の中では自分たちの努力の結果が報われたときの状態が、想像力によって先取りされていなければならない。ここでは現実から乖離した、意味増殖がおこなわれている。───
それまでの固定した像をもたない流動体だった精霊が、テラコッタの像に表現され、儀礼や崇拝の対象になると、象徴化された神々となる。その結果、人々の宗教は象徴システムに移管されて、象徴の操作によって神々とのコミュニケーションは図られるようになる。
自己の精神の中にいた精霊を外に出して、流動性のない偶像を崇め、それらとコミュニケートするようになった。この偶像などにより象徴化された神々は縄文の土偶も同じ意味なのかも併せて気になるところである。
精霊を個々から追い出すことで集合意識の中にも流動性がなくなり、神と自己との隔たりが起こる。
神に与えてもらう個となり、
先生と生徒のような縮図となる。
時代が下ると、神さえいなくなり、支配者がその役目となる。先生と生徒のような関係という無理クリの大義を通して、暴力を正当化させているのだ。
またウンザリしてくるから次行こ。
P28
・増殖性をおびた脳の象徴能力。
現代は新石器革命に始まる。大「段階」の末期にある。ここからの脱出は、モーセの時代のエジプト脱出よりも、はるかに困難である。
象徴記号の増殖性は私たちの思考のきそに据えられており、知らず識らずのうちに私たちは世界を「増殖の相のもと」に見るように慣らされている。
P29〜
・1959年までゾクチェンはチベット外では知られざる思想のままであった。
・中国共産党と解放軍がラサへの一斉攻撃を開始した。インド、ネパール、ブータンへの脱出に向かったチベットの僧たちは、近隣国やヨーロッパ、アメリカへの亡命許可に従って分散していくことになる。
・「ゾクチェン」は、いっさいの象徴記号に頼らず、イメージを観想する瞑想技法にもよらず、ただ自然のままにして、人間の心の原初をあらわにする、特別な教え。
中国からの圧力を受けた、チベットの層たちだが、近隣諸国や欧米諸国に亡命した。
その歴史的動きがあったことは初めて知ったのだが、しかし、ここから先に私を萎えさせる文章があり、本書を読むのは辞めようかと思ったほどだ。
P32、33
最初の頃は訪れる人たちもまばらだったが、1960年代の後半に入り、欧米の若者を中心に「カウンターカルチャー」の運動が拡大すると、チベット僧たちの開いていた瞑想センターには、自分たちが生きている世界の中で行き場を失った若者たちが、たくさん集まってとかある。
そこで彼らははじめて「ゾクチェン」という言葉を知ったのである。人間の精神に真の自由をもたらすというその教えを、何人もの欧米の若者が学びたいと思った。しかし簡単にはゾクチェンの門戸は開かれなかった。厳格な錠前がおろしてあったのである。弟子入りを望んでも、その人の人格や知性の確かさを師が確認できるまで、数ヶ月も待たされることがあり、その間弟子入り志望者は師の身の回りの雑役に励まなくてはならない。入門が許されるようになっても、ゾクチェンの門戸を開くための「加行」を通過しなければならない。加行にはまた数ヶ月も要するこ動をはじめた。そうしてようやく錠前が外されて、ゾクチェンの門戸が開かれることになるが、気軽な気持ちで門を叩いた者たちの大半が、あきらめて元の世界に引き返していくこととなる・・・・・・それでもごくわずかな若い外国人だけが、それに耐えて、ゾクチェンを学ぶことができた。
こうした若者たちの多くは、私がゾクチェンを探してようやくネパールへたどりついた1979年当時には、修行際薬にしたがってインドやネパールの人里離れた瞑想小屋で、人との交渉をいっさい絶った「ツァム(隠棲裏想)」の修行にちょうど入っている時期にあたっていた。そのため、カトマンズ盆地にあるチベット寺院をいくら訪ね回ってみても、私のような新参者などが、ゾクチェンについての有意義な情報に出会える機会はほとんどなかった。
ヒマラヤの麓の盆地に目算もなく放り出された感のある私はあてもなく、いくつものチベット寺院を訪ね歩いた。
私たちは世界を「増殖の相のもと」に見るように慣らされている。とどこかに書かれていたが、「教えを乞うという相のもと」と「付加価値をつけなければ生きられない相」に見えるようにも慣らされている。
ゾクチェンが素晴らしいという付加価値を、欧米に逃げ込んだ僧侶自らが付け、他のものとの差別化をはかっている。自らが圧力をかけられ逃げて来たのにも関わらず、門下生にも同様の圧力をかけている。
私はこういった矛盾が大の苦手なのである。
教えの中身は素晴らしいものなのかもしれない。
しかし、資本主義的圧力が自身の中にある限り、自身の思想の中に欲望がある限り、精神に真の自由などないのだ。
ここに存在するのは、体系化された「真の自由を得るための教え」であって、真の自由を體現出来ているものは居ないと発覚しため、一旦、私の読書意欲は萎えたのだった。
この後の文章は、著者がゾクチェンに出会うために行動したストーリーが展開される。1970年代前後の時代背景も知る事ができ、面白い内容となっている。
第二部 ゾクチェンとの出会い
6 太陽を見つめるヨーガ
P59
そのとき私は、人間の魂には始源のときから光への憧憬があり、原初の暗闇から脱出しようという抑え難い衝動があったのだということを、理解した。大いなる夜がくると、万物は深いメランコリックな音調をとって、魂はすべて名状しがたい光への郷愁にとらわれる。それは閉じこめられた思いであって、原始人の眼にうかがわれるものであり、われわれはまた動物の眼にもそれをみる。動物の眼には悲哀があり、この悲哀が動物の魂と関わっているのか、まだ無意識のままでいる存在からわれわれに語りかけてくる胸を刺すようなメッセージなのか、われわれにはわかっていない。この悲哀はアフリカの気分と、その孤独の経験を反映している。それは母性的神秘であり、原初の暗黒である。したがって朝の太陽の生誕は、圧倒的な意味深い体験として───
「原初の暗闇から脱出しようという抑え難い衝動があったのだということを、」という文があるが、光を見た時の感動(暗闇から出て来たとき受け入れてくれた母性的神秘)も併せ持つ、この意識が人間の集合意識の中に宿っている。
私はというと、その感受性も勿論存在するが、相も変わらず、暗闇も光もない、無の中に帰りたいという想いだけである。。
引用が多かったからか、4000文字以上となりました。
60P/420P
まだ冒頭の域…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
