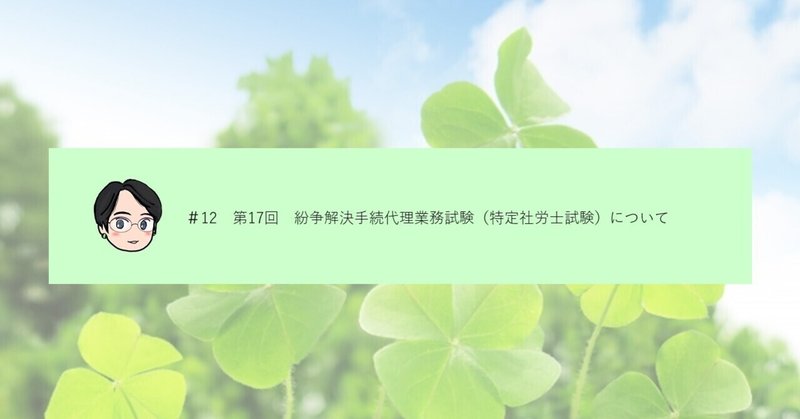
第17回 紛争解決手続代理業務試験(特定社労士試験)について
【はじめに 注意】
・第17回紛争解決手続代理業務試験、合格しました。試験に挑むにあたって、やったことの記録を残しておきます。もちろん個人の見解ですので、ご参考までに。
・グループ研修やゼミナールの進め方などは会場によって違います。参考文献も、人によると思います。
・申込時点で、人事労務歴16年。社労士合格は2010年。開業は2020年。実務経験はまあまああるけど、労働問題やあっせん事例にガッツリ触れたことはなく、法学部的な法律の素養もありません。
・「これから挑戦してみようかな」という方の参考になれば幸いです。
【1】第 17 回紛争解決手続代理業務試験結果 2021/12/4 開催
(1)受験者数 950 人
(2)合格者数 473 人
(3)合格率 49.8%
1.合格基準
100 点満点中、55 点以上、かつ、第2問 10 点以上
2.配点
(1) 第1問は 70 点満点とする
(2) 第2問は 30 点満点とする
・例年、第1問は労働問題あっせん事例の問題、第2問は倫理の問題です。
・私の得点は 第1問 44/70、 第2問 20/30 でした。
・どちらかと言うと倫理のほうが得意でした。
【2】スケジュール
(1)受験案内掲載
月間社労士 6月号
(2)申込要領 配布開始(事前に要領の請求をFAXか郵便で行う)
2021/6/16~
(3)申込受付期間(郵便振込、写真貼り付け、簡易書留)
2021/6/16~7/6
(4)中央発信講義(eラーニング)
2021/9/3~10/1 の間に視聴。
(5)グループ研修(地域ごと)
近畿は 2021/10/30、31、11/3 と少しタイトでした。
(6)ゼミナール(全国共通) 初日金曜日
2021/11/26、27、12/4
12/4の午後に紛争解決手続代理業務試験
(7)合格発表 2022/3/18
【3】試験に向けて読んだ本(よく見た順に)
(1)中央発信講義教材(全国社労士連合会発行)
(2)特別研修 グループ研修・ゼミナール教材(全国社労士連合会発行)
(3)過去問集 ※2022年版はこれから発行だと思います
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8590.html
(4)おきらく先生のノート ※2022年版はこれから発行されるそうです
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-03-21
この仕事をしていてなんですが、難しい文章が苦手で…。(1)と(2)の読み込みに苦労したのでわかりやすい説明を求めて購入。サブテキストとして使いました。
(5)判例集
(6)デイリー六法
(7)労働基準法解釈総覧
その他にも連合会から「参考文献」として指定された本がありましたが、私は読みきれないと思って購入しませんでした。
【4】学習方法
●7月下旬~8月 なんとなく勉強開始 過去問など @自宅など
・7月の終わりに過去問購入
・読み物としてぼちぼち読みながら試験の傾向を掴む
●9/5~9/21 eラーニングで中央発信講義受講 @自宅など
・9月初旬に【2】連合会発行テキストや、eラーニングの案内が届く。
・30.5時間あり、10/1までにすべて観ないと次の「グループ研修」に進めないので、理解できなくても真面目に観る。
・過去問も少しずつ手で書いて解いてみるが、はじめは丸写し。
・過去問の答えが納得行かないときもあるけど、模範解答ではないので参考までに。その答えに至った背景の判例や法令を確認できればいいかと。
●9/22~10/29 グループ研修の予習 @自宅など
・検討課題や、申請書、答弁書の作成課題が指定されているので、予習が必要。
・【2】の参考書を見ながら自分の考えをまとめる。
・倫理の勉強もする
・過去問も遅いペースで解き進む。
●10/30,31,11/3 グループ研修 @天満研修センター
・10人くらいの受験生+特定社労士のリーダーでひとグループ
①検討課題の議論
②あっせん申請書、答弁書の作成、提出
③倫理の確認
・細かい進め方、スケジュールはリーダーによるらしい。
・予習の有無や、申請書、答弁書の出来具合は合否には関係しない。
(ただ、準備不足だとグループ討論についていけないので気まずい)
・②の作成、提出をしないと次のゼミナールに進めない。
タイトなスケジュールだが、LINEグループを作り、みんなで意見を出し合いながら頑張って作る。
・いろんなバックグラウンドの社労士がいて、参考になった。
グループの組み合わせは運だけど、私は優しくてしっかりした方ばかりのグループでラッキーだった。
・15分遅刻で続きを受けられなくなるんだったかな?
体調と交通機関(台風の季節!)に気をつけて、遅刻をしないことが大事。
【持ち物】
①必須
・中央発信講義教材(全国社労士連合会発行)
・特別研修 グループ研修・ゼミナール教材(全国社労士連合会発行)
②あると便利
・判例集や六法
「重いから置いていこう」と持っていかないと使う…
③可能なら
・ノートパソコン
(②をまとめるのに便利。私は自宅と会場が近かったので持っていきました)
●11/4~11/25 過去問など試験の準備 @自宅など
・過去問
時間を計って書く練習。ボールペン決める
過去問は、全部で 16回分✕2周、最近の10回をもう1周やりました。
・足切りのある倫理のまとめ
倫理の過去問16回✕2問をエクセル一覧表にして以下のようにまとめました
①従前の事件のタイプ
②対応
③あとからの事件のタイプ
④備考
⑤結論 受任できる?できない?
⑥根拠
・エクセルに、あっせん問題の解答に必要な論点整理
(例)雇い止めに必要な要素は7つ
①更新基準の明確性
②雇い止め事由への該当性
③業務の客観的内容
④契約上の地位の性格
⑤更新を期待させる言動
⑥更新手続・実態
⑦勤続年数・年齢
自己流なので間違ってたらすみません…。
暗記が苦手なので、論点や倫理の法令はスマホのボイスメモに録音して、繰り返し聴きました。
●11/26,27,12/4 弁護士先生のゼミナール @天満研修センター
・グループ研修の10人が固まって座る。
・グループ研修で検討した課題や、提出した申請書、答弁書について弁護士の先生が解説。
グループの申請書や答弁書が突っ込まれても、専門家でもないのに完璧なものを作れているはずはないので気にしない。「勉強になるなあ」と拝聴する。
・ひとりひとり当てられるけど、分からないことは「分かりません」で何とかなったので、リラックスして弁護士の先生の話を聞いた。(優しい先生で良かった)
・とはいえ、ここで説明のあった論点が試験に出たので真剣に。メモを取り、ポイントを押さえながら聴きましょう。
【持ち物】
①必須
・中央発信講義教材(全国社労士連合会発行)
・特別研修 グループ研修・ゼミナール教材(全国社労士連合会発行)
・自分たちが作成・提出した申請書と答弁書のコピー
・六法
②あると便利
・判例集
パソコンはいらないと思う
●12/4 14時から試験
使用できるのはボールペンのみ
【5】試験のこと
第1問「あっせん事例」は、小問1~3が点数が取りやすいです。小問4と5は難しいですが配点が低いので、過去問集の解答例のようにつらつらと書けなくても動揺しなくて大丈夫。
小問1は定例文の丸暗記、小問2と3は問題文に書いてあることの書き出しなので、練習すればなんとかなります。
第2問の倫理は足切りがあるので注意が必要です。私は解釈が多様な「あっせん事例」よりも、理屈でかける倫理のほうが試験対策としては好きでした。
倫理、社労士法の条文暗記が初め大変ですが、やってくうちに慣れました。
受任できる、できないを決めたら一貫性をもって。結論が逆でも合格している方もいるので、論理の一貫性で「受任できる、できない」の2択の結論をカバーできるみたいですね。
【6】その他
うちのグループは試験のあと、飲み会にいきました。
リーダーの先生も見えて、有意義なお話を伺えました。
あと、同じグループの開業の先生で、興味のある分野を専門にしている先生がいらしたので、2月の終わりに個人的にお会いしました。
自分の業務に活かせるかはまだ構築中ですが、良いご縁があってよかったです。
個人的に、試験勉強に受かることだけを目標にしてしまった感があるので、「ちゃんと法律家としての知識を深めないとな」とグループ研修やゼミナールで感じました。
本業と並行しながら、長い研修をクリアして試験に挑むので、スケジューリングと体調管理が大事です。
皆さんの健闘をお祈りします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
