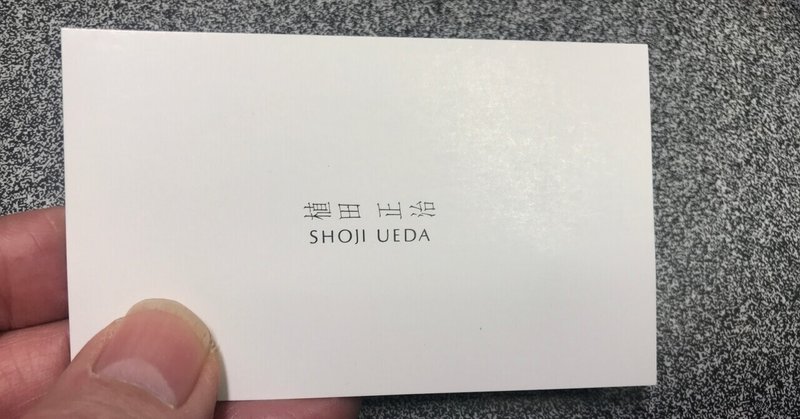
写真する幸せ / 植田正治に学ぶ
先日、ニッコールクラブの撮影ツアー「植田正治の世界を訪ねて」で山陰地方を訪れた。
山陰に生き、その風土を写し続けてきた植田正治(1913~2000)という写真家の存在は多くの写真愛好家もよく知っているはず。今回の撮影ツアーは植田さんの足跡をたどりつつ、植田正治写真美術館でのレクチャーや実際に砂丘で演出写真を撮るというところまでを網羅した。そこには、植田さんのご子息である植田亨氏やアシスタントを務めていた写真家の池本喜己氏のご協力があった。特に、植田邸を特別に御案内いただき、実際に植田さんが撮影したオブジェなどを見せていただいたのには感激した。

境港の水路がすぐそこに見える路地に静かに佇んでいる植田邸。玄関を開けると、まだ主がふいに出てこられるのではないか思わせた。針金でつくられたオブジェ、白く丸い固まり、ステッキ、帽子などのモノが発する美しさは、作家がこれに触れ、光を与え、レンズを向けたという創作のイメージが漂っているからだろう。さまざまなオブジェは玄関のみならず、居室兼台所などの隅々に、コラージュ作品のように雑多に置かれていた。四六時中、植田さんはそうしたモノに囲まれ、シャッターを押していたことを思うと、写真は理屈ではなく、手や目などを充分に動かしあれこれ試してみる以外に道はなしかと思えてくる。日本間に座り、植田さんの目線になってみたら、「まぁ、あわてないで、ゆっくり楽しく撮ればいいんですよ」などという声が聞こえてきそうだった。

ところで、植田正治というとやはり誰もが砂丘での人物写真を思い出すのだが、私にとっては、60年代の「童暦」や70年代から80年代の「小さい伝記」といったスナップショットへの思いが強い。特に「少年」を写したものに惹きつけられてきている。どうしてこう撮れるのか。昔から謎のひとつであった。評論家の草森紳一氏が植田正治の写真の魅力は「はかなさ」にあり、光景の中にふわっと入っていく「親和力」があると書いている。「世界なるものが、つねに忽然として決起してくるものであるとするなら、植田正治はその「世界」にカメラを持って構えた自分を照応させ、親和させる名手なのである。」(決起する光景---植田正治の親和力・草森紳一・植田正治の世界・平凡社コロナブックス)

草森氏が鋭く指摘したこの「親和力」こそ、スナップショット全般の根源としての力といえそうだ。そしてそれはカメラやレンズとの親和という問題にも関わってくる。山陰の地で、あくせくとカメラを構えることなしに、そこにいる人間に無理なく自然に接していく植田さんの身体のありようは、絶妙ともいえる距離感で表現されているのだが、昨今の広角系のズームレンズでなんでもかんでもぐっと踏み込んで撮ってしまうというパターンとはほど遠いレンズワークが生かされているように思える。そこに立ち会うことの必然、撮られることの必然、シャッターを押すまでに至るカメラとレンズのよき連携、そんなものがまさに歯車としてきれいに噛み合っていった時、写真することの幸せがそこに宿り、被写体は写されてしまったのではないか。これらは、折から植田正治写真美術館の企画展として展示されていた「童暦への道」をゆっくり鑑賞した結果得られた私の勝手な推察ではあるが、多分間違っていない。

植田さんはその写真生活のすべてに渡り、「写真することの幸せ」を感じながら生きてこられたとよくいわれる。オプジェに触り、さまざまなカメラ趣味に興じ、カメラを持ってふわっと人物に近づき、砂丘で最愛の奥様を最高に素敵な写真で飾り、子どもを肩車して、ファッションモデルを呆然と砂丘に立たせて、、、、そこには風土への愛情と誇りがあるのはもちろんだが、写真機という魔法の箱を子どもが手に携えているような趣も感じられる。いかに写すかでなく、どう写るのだろうか? そうした好奇心はなにもフイルムで可能、デジタルでは不可能ということでもないはずだ。それはすべからく心の反応に関わる。光や影やモノの形態や、人の愛おしいまでの美しさ。そうした被写体に寄せる水々しい心を私たちは失ってはいけないということなのだろう。
アサヒカメラ2015年1月号「魅せる写真 活きる写真 1」
古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。
