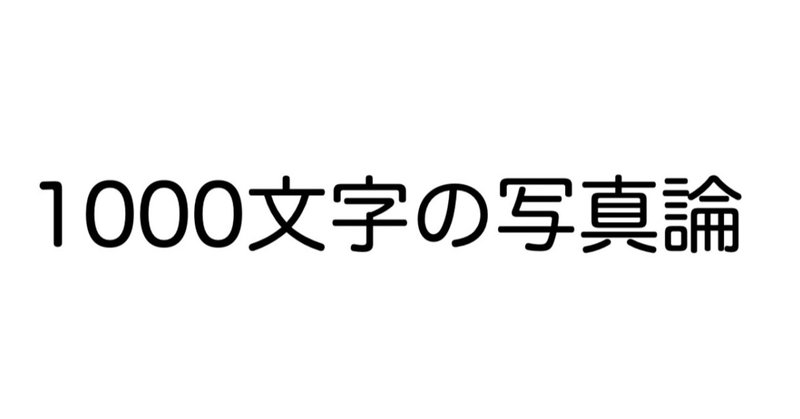
1000文字の写真論
今年「フォトコン」という雑誌に12回連載させていただいた短い記事「一千文字の写真論」の再録。本来、私は写真家ですから、黙って写真を撮っていていいのですが、写真を学んだ学校の校長が写真評論家・重森弘淹先生であったため、どうしても写真を考える機会が多く、それがずっと続いてきているだけです。2021年、改めて基本的なことをここで考えてみました。
1 「見ること」と「写すこと」
「写真論」はお硬い、面倒だという定説のようなものがあるかと思います。具体的に撮り方を教えてもらった方が実益に叶うというのもわかります。それに私も写真評論家ではないのでうまく書けないのは自明の理。しかし、改めて「写真」について考えてみるのは案外面白いものです。思わぬ発見もあれば、指針も見えたりします。第一、ほとんどお金もかかりません。渋みのあるお茶でもすするようにしばしお付き合いください。
さて、「写真論」と名打って書き始めるのも嫌なので、我が家にやってきた孫(男の子)の話から。
8歳になる孫は、これまで私の部屋に飾ってあったいくつかの古いカメラをオモチャのように触っていたものの、特に「写したい」という意思を示したことはありませんでした。先日、ちょうどインスタントカメラ(チェキ)にフイルムが入っていたので、「写してみるか?」と孫を誘いました。子どもの手にはちょっと大きなカメラですが、簡単な操作をすぐに覚え一緒に近所を歩きました。おじいちゃんにはうれしい散歩です。
しばらく孫が写している様子を見ていましたが、面白いことに気づきました。ファインダーのないカメラだからか、写すときにリアルタイムで見えている液晶画面ばかりを気にしています。写したいと思った「被写体」よりもカメラに映った「それ」に集中しています。これは何かに似ていると思ったら、彼らが大好きな「ニンテンドースイッチ」の感覚です。液晶画面での行いがすべての世界では、そこでの瞬発力や展開が結果を規定していきます。「作られた世界」であるから無理もないのです。一方、写真を写すという行いの上では、同じような画面は手元にあっても、「被写体」は「そこ」にあるのですが、孫にとってはそれが見えにくくなっている。画面上のリアルでしかないのではないかと思えてきました。本来は、そこにあるものをしっかり見て欲しいというのが写真家である私の期待したものでしたが。
「見ること」と「写すこと」には本来違いがあります。目の機能、視野などをレンズの描写性と照らしていきますと「見たものがそのまま写る」のが必ずしも写真ということでもありません。被写体を肉眼で「見る」ことよりも、液晶画面上だけ見ることに縛られているとなおさらそこにズレも生じ、結果として「見えなくなる」かも知れません。

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。
