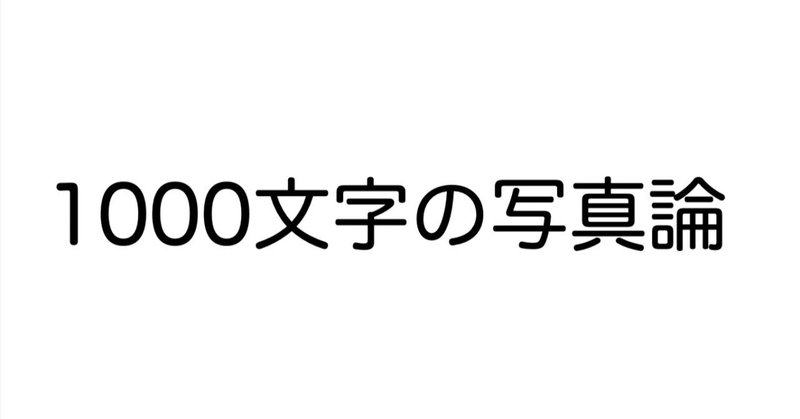
1000文字の写真論
10 被写体としてのモノ
写真論や写真批評を読んでいると、よく「モノ」という文字を見かけます。この「モノ」が「物」や「もの」であることは想像できるのですが、何故にカタカナで書かなくてはならないのかちょっと不思議に思われたことがあるでしょう。しかしこの「モノ、物、もの」の違いは多くの人が感覚的につかんでいるかもしれません。
「物」は人間が感覚として捉えることのできる形を持っています。八百屋さんの店先で「リンゴ」と「キャベツ」の違いも「物」として判別しています。「もの」はちょっと漠然としていたり、抽象的だったりします。例えば、「寒いので、なにか温かいものください」などと話したりします。「モノ」はさらに漠然とします。前号に書いた「ヒト」とも近い使い方です。ちょっと冷たそうで、素っ気ない感じもします。
写真の上で、被写体として「物」を撮ろうという時、形や色だけでなく、その「物」がどんな意味を持つもので、他の物とどう違うかなど概念やら知識やら情報やらを総動員して認知しようとします。広告写真などではそれらにより「商品」としてその存在意義が決定されます。一方で、どこかの荒野で見かけた自分の背丈と同じくらいの「岩」があるとしますと、「岩という物」であるが、ひよっとしたら自分が生まれる前からそこに在り、少しづつ風化している物体に見えたり、思えたりするかもしれません。岩がどの時代のものに属するか、素性はどうなっているかよりも、このただの「物体」としてという認識に立つ時、「物」は「モノ」に変わるのかもしれません。一つの「抽象化」ともいえます。
深い浅いはともかく「意味」を断ち切って、そこに「在る」という事実に注目する時、次第に「モノ」が立ち上がってきます。特別思想的、哲学的に考えなくとも、その「モノ」と私であるところの「人間」がそこで素朴に対峙し、対比されることもあるでしょう。
さらに厚みのある時間(歴史)や空間も関わってきます。そしてまた、その「モノ」をカメラで撮ることで写真という「モノ」も生まれます。この連環に表現としての価値を見出している写真家も古今東西います。そのようにして私たちのいる世界を改めて見つめてみるという行いはとても大事なことではないでしょうか。
「モノ」は「オブジェ」という言葉で言い表されたりすることもあります。今いる皆さんの部屋の中で「モノ」を探してみてください。

古くから様々な読者に支持されてきた「アサヒカメラ」も2020年休刊となり、カメラ(機材)はともかくとして、写真にまつわる話を書ける媒体が少なくなっています。写真は面白いですし、いいものです。撮る側として、あるいは見る側にもまわり、写真を考えていきたいと思っています。
