
世界のサバ事情
3月8日はサバの日。その日に向けて、「世界ではサバをどうやって食べてるの?」と知人に尋ねられ、そういえばどうなんだろうと思って調べてみました。サバは傷みが早いこともあって、私が台所探検で訪れるような地域ではなかなか出会わないんです。
日本では塩焼きにすることの多いサバですが、調べてみると世界には、その特性とおいしさを活かした本当に多様な楽しみ方がありました。
そもそもサバって?
① スズキ目サバ科、主にサバ属の魚の総称。サバ科の仲間には、サワラ・カツオ・マグロなどがいるので、これらの魚の親戚とも言える。
② 英語ではMackerel(マカレル)。
③ 鮮度が落ちるのが早いので、食用として流通させるには保存がとても重要。缶詰加工の技術や冷蔵インフラが普及する19世紀以前は、塩蔵や燻製にしていた。イギリスでは生で食べていたためしょっちゅう腐っていたらしく、フランスでは大量の塩で塩漬けにすることで全土に行き渡るようになった。
日本で食用にされるサバは主に三種類
世界には30種類以上のサバがありますが、日本で主に食べるのは3種類(マサバ、ゴマサバ、大西洋サバ)。マサバとゴマサバは日本近海でとれて、大西洋サバはすべて輸入。世界で漁獲量が多いのは大西洋サバで、脂が乗っていることから日本でも人気があり、ノルウェーサバと呼ばれることもあります。

画像出典:umito
日本は漁獲高世界一、輸出額は世界第3位(冷凍)
●サバ漁獲高上位国
日本 (537千トン), 中国(433千トン), インドネシア(400千トン), ロシア(311千トン)
出典:FAO(2018)
●サバ(冷凍)輸出上位国
中国 ($461M), ノルウェー ($431M), 日本 ($239M), オランダ ($148M)
出典:Observatory of Economic Complexity (OEC)
日本は、漁獲高も輸出量も世界有数。2006年以降は輸出が輸入を上回り、「サバ実質輸出国」になりました。輸入をしながら輸出もしているのは、大型で脂の乗った大西洋サバを輸入して、小型で国内では出回らないものを輸出しているから。

画像出典:nippon.com
ではそのサバはどこに輸出され、どのように食べられているのでしょう?
日本のサバ輸出先は、アジアからアフリカへと移行
2006年頃までの輸出先は、アジア諸国がその多くを占めていました。タイやベトナムへ輸出して委託加工され、缶詰などとして第3国へ再輸出されることが多かったのです。
しかし、近年は冷凍の小型サバが、食用直接消費用としてナイジェリア・エジプト・ガーナなどのアフリカ諸国に輸出されています。現在、日本のサバ輸出量の6割を占めるのはアフリカです。

画像出典:nippon.com
アフリカって海の魚食べるの?とちょっと意外に思う方もいるかもしれません。私も現地では淡水魚のティラピアばかり食べていたので、海の魚はちょっと意外です。魚を冷蔵や冷凍で流通させるには、そのための冷蔵設備を備えた輸送インフラが必要なので、それなりのコストと投資がいります。経済発展によって、タンパク質需要が高まると共に輸送インフラが整ってきたことが、アフリカの魚食を促している面もあるかもしれません。
アフリカは海に囲まれていますが、捕獲や輸送技術はまだ未熟で、魚は輸入に頼っています。サバ輸入元としてはかつての旧宗主国であるヨーロッパの国々からが多かったのですが、近年日本からの輸入が増加しています。
その背景には、ヨーロッパ諸国が資源保護のために大型のサバのみを漁獲するようになったことがあります。獲れる数が決まっているならば、大きく成長したものを獲る方が高く売れます。したがって、ノルウェー産などは大型で脂が乗って価格が高く、一方日本は国内市場で出回らない小型のサバを輸出しているので比較的安価。タンパク源としての価値から、アフリカでは安価な日本産が買い求められるようになっているのです。日本では様々な魚種の漁獲高が減少している中、サバはほぼ横ばいを維持しています。
アフリカはトマト煮!? 世界のサバ料理のぞき見
では本題。世界ではどのようにサバを食べているのでしょうか。
●アフリカ
日本の小型サバを輸入しているアフリカの国々。ネットで調べた範囲では、トマトと煮込んだ料理や燻製が多く見受けられました。たとえばナイジェリアの「サバのトマト煮」は土曜日の朝食の定番で、ヤム芋・米・パンなどどんな主食ともあうそうです。
サバはうまみ成分のイノシン酸を豊富に含むので、別のうまみ成分グルタミン酸を含むトマトと組み合わせることで、うまみの相乗効果が起こりいっそうおいしくなります。また、トマトの酸味は少しいたんだ青魚の匂いもカバーできます。北アフリカ〜ヨーロッパは、うまみ食材としてトマトを多用する地域ですが、サバ×トマトの組み合わせは、いろんな意味で理に適っていなあと思います。

画像出典:Nigerian Lazy Chef
ちなみにナイジェリアやガーナでは、サバ缶と言ったらトマト味がメジャーで、その7~8割を占めるのはGEISHA(ゲイシャ)というブランド。これは、日本の商社「川商フーズ」半世紀ほど前に発売開始した商品で、今や現地ではサバ缶の代名詞になっているのだとか。

●アジア
日本からの輸出の歴史も長く、自前の漁獲もあるアジア諸国。お国柄を感じるそれぞれの料理があります。レシピを見ていると、生のサバを使うものもありますが、材料に「サバ缶」と書かれたものも少なくありません。鮮度の低下が特に早い熱帯だからこそ、缶詰技術が普及する中で生魚より缶詰が重宝されるようになったのかもしれません(推測です)。
フィリピン
フィリピンのギナタン・マカレル(Ginataang Mackerel)という料理は、サバ(缶)とほうれん草をココナッツミルクで煮込んだもの。安い・早い・簡単ということで、ランチなどにも食べられるよう。

画像出典:PanlasangPinoy.com
ところで、フィリピンのサバ缶は水煮とオイル漬けがメインで、缶にはSABAと書いてあります。
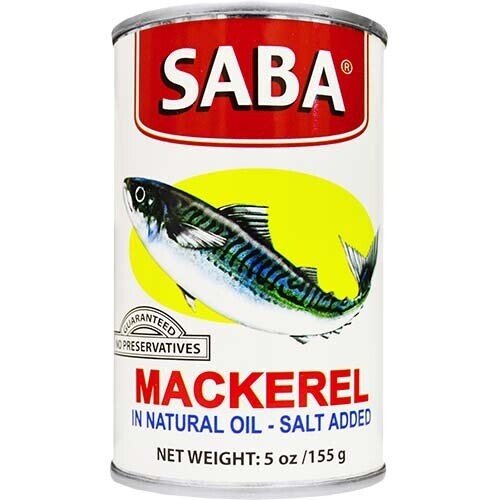
ただしSABAは鯖のことではなくブランド名なので、イカやマグロのSABA缶もあるのがややこしいところ。日本のメーカーではなく、現地企業のです。

東京のフィリピン食材店にて。ソウダガツオのココナッツクリーム煮SABA缶
タイ
サバは、最も大事な魚(fish of the nation)とされているそう。小ぶりなサバを蒸したものは、骨まで食べられる庶民的なもので、ねこの餌になっていたことも。しかし需要の増加に供給が追いつかず、近年価格は上昇。
ゆでサバに魚醤とチリをあえたシンプルな漁師飯としての食べ方や、中部地方ではトムヤム鯖がポピュラー。
韓国
ゴドゥンオチョリムは、国民的なおかずとされています。「サバと大根の煮付け」なのですが、唐辛子を使った真っ赤な一皿です。

画像出典:future dish
●ヨーロッパ
燻製や塩蔵のサバを用いたり、または生魚を香草とともにグリルすることが多いようです。これは缶詰が多用されるアジアとは対照的。19世紀以前から大西洋サバの産地として漁獲しており伝統的な保存方法(燻製・塩蔵)が定着していると考えられること、アジアと比べて気候も冷涼なので品質劣化の心配が比較的少ないこと、がその要因としては考えられそうです。それにしても調理法がシンプルなのはヨーロッパらしい。
ノルウェーの鯖缶Stabburは、サバのフィレをトマト煮にしたもので、このまま黒パンにのせて食べたりするようです。水煮はなく、トマト煮がオリジナル味。

画像出典:Stabbur
世界各地、多様なサバ食の世界
アフリカは小型魚をトマト煮、アジアは缶詰も利用して各国のフレーバーで、ヨーロッパは大型魚を塩蔵や燻製。歴史や気候を映した多様なサバの世界がありました。今までサバというと塩焼きやシメサバなどの”白いサバ”を想像していましたが、世界でメジャーな”赤いサバ”も、脳内レパートリーに加えたいと思います。
いただいたサポートは、 ①次の台所探検の旅費 または ②あなたのもとでお話させていただく際の交通費 に使わせていただきます。
