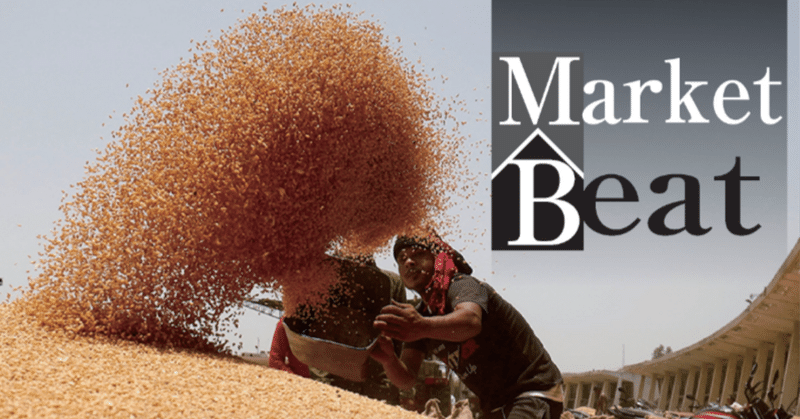
主要穀物価格が安値
ロシアのウクライナ侵攻直後に急騰した穀物価格が安値に沈んでいます。小麦先物、トウモロコシ、大豆など主要穀物はウクライナ侵攻前より安値となっています。世界各地の記録的な豊作が供給の懸念を和らげるかたちになりましたが、原油価格上昇など生産コストの上昇は、農家が割に合わない品目の作付けをためらう要因になります。農家が作付けを控えると価格高騰のリスクがあり、投機筋の空売りの存在が価格反転の引き金になる可能性があります。
マクロでみれば、穀物の価格は上昇トレンドにあります。その原因は、3つあります。ひとつは、世界人口の増加です。インド、中国、アフリカのような新興経済大国で食糧需給が爆発的に増えています。世界人口は80億人を突破し、2037年頃に90億人、2058年頃に100億人を突破すると予測されています。
世界の穀物および大豆の需要量は、総人口の伸び率を上回って増加すると予測されています。穀物価格上昇要因のふたつ目に、穀物は食用以外の新しい用途が出てきていることが挙げられます。今、最大のバイオ燃料の原料はとうもろこしで、アメリカが最大の生産国です。世界の30%を生産し、そのうちの4割がバイオ燃料用に加工されています。価格によっては、食用より燃料用が儲かれば、より燃料用にシフトすることも考えられます。
穀物価格上昇要因の三つ目に、気候変動が挙げられます。2023年10月のFAO(国連食糧農業機関)の報告によれば、この30年間で地球温暖化によって世界の食糧生産が3.8兆ドルの被害を受けたと言われています。干ばつの影響で生産が落ち込むリスクを世界は常にはらんでいます。
政治的要因も食糧需給に影響を与えます。ロシアのウクライナ侵攻で、西側諸国はロシアに経済制裁を課しましたが、ロシアの穀物収穫量は減少し、主な輸出先になっている中東やアフリカ地域への食糧需給が影響を受けています。米中貿易摩擦も、半分以上を占める米国産大豆の輸出先として中国の動向次第では米国産大豆の需給への影響は大きいと思われます。
これまでのところ、生産量が需要量を上回る状況なので世界の食糧需給に影響はないように見えますが、人口増加、バイオ燃料、気候変動の問題は簡単に解決できません。農作物の収穫量を増やそうとしても環境問題があり、天候や灌漑の影響を受けて生産は限界があります。
日本の食料自給率は38%と下げ止まらない状況です。食糧供給は海外からの輸入に頼らざるを得ないですが、日本の海外からの食糧調達力は以前より弱くなっています。為替の強い国や、人口の大きなインドや中国、人口成長が急速な新興国は食糧を大口で購入しますが、日本は海外のバイヤーと競争したときに必要量を買うことができなくなってきています。
しかし、日本の米の生産性は高いです。かろうじて米だけでみれば食糧自給率はほぼ100%です。日本の食糧自給を持続的にするのは、農家にとって米を作るのが効果的です。米の消費量が減り続けている中、食糧価格高騰の中でも米の価格は上がっていません。米は私たちの家計に優しい。そして、和食は健康にも良いと世界で認められています。
私たちができる食糧問題に対する貢献は、今、日本が基礎的食糧も世界で買い負けるような状態なので、米の消費を再生させることで日本の農業を再生させる大きな力にすることです。国産小麦や国産大豆にも目を向けて輸入小麦や輸入大豆より価格が高くても、国産小麦や国産大豆を使ったパンや豆腐などの価値を認め、購入することで応援することです。私たちひとりひとりが、そうすることで日本の食料自給率を反転させ、世界の食糧需給に圧力をかけないようにすることが大事だと思います。私たちが食のありがたさを認識し、少し行動を変えるだけで、日本の農業を下支えし、私たちの食糧を安全に保証することにつながります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
