
ダムタイプ感想とヒエラルキーあれこれ
ダムタイプ(だむたいぷ、Dumb Type, dumb type)は京都市立芸術大学の学生を中心に結成されたアーティストグループ。1984年に設立され、京都市立芸術大学在学中から海外公演を含めた活発な活動を行う。建築、美術、デザイン、音楽、ダンスなど異なる表現手段を持つメンバーが参加し、芸術表現の可能性を模索する。京都を拠点とし、海外公演を中心とした活動を行っている。1995年に中心メンバーの一人古橋悌二の死去後も、メンバーを変えながら活動は現在まで続いている。
ダムタイプ「アクション+リフレクション」の展覧会を観た。

(ダムタイプについては、この動画に詳しい)
わたしは、ダムタイプのことを知らなくて、
この展覧会をきっかけに初めて知ったのだけれど、面白かった。
舞台美術の展示ということもあって、作品の意図がどこまで理解できたのかはあまり自信がない。
(だから、記事にするのが少し遅くなってしまった・・・!)
ただ、エレクトロニックな雰囲気と、生と死や、男と女、などの、二項対立を乗り越えようとしていることは、どの作品にも通底しているように思った。
二元論的な捉え方一般に言えることだと思うけれど、そもそも、その対立軸が適切かということについて、わたしたちは考えていかないといけないのだよな、と思う。
たとえば、生物学的な性について、男か女かという区別を持ち出すことは、ある場面においては適切なのだけれども、その区別を持ち出すこと自体が、なんらかの効果を発揮しうる、というか。
(あまり展示と関係のない話ですが、フェミニズム的な文脈への対抗として、しばしばTwitterなどでは「男性への逆差別だ」という反論があるけれど、そもそも男女という対立軸に乗っかってしまって良いのか、というところから考えないと、結局、その分断からは逃れられないような気が、最近はしています。その舞台に乗ること自体が、既に本当に言いたいであろうことを言えなくさせてしまうようなことがありうるとおもう(また念のため言っておくけれど、わたしはフェミニズムが逆差別と結びついているとはあまり思っていない))
そういう二元論的な立場を超え出ようとしているのではないか、というような印象を持ちました。
(そういえば、作品の前提にもなっているデジタルは、語源からして二元論ですね。0と1の。)

《Playback》2018 パフォーマンス《Pleasure Life》(1988 年初演)をベースに、展覧会「Against Nature」(1989)のために制作されたインスタレーション《Playback》に基づいて制作された、リモデル版作品。16台のターンテーブル・ユニットの上で、本物のレコード盤が、当時の音源(80 年代初期ダムタイプの山中透・古橋悌二による音楽、英語教材の滑稽で風変わりな声、NASA の惑星探査機ボイジャーに搭載されていたレコードに記録された55 言語の挨拶)に加え、新たにフィールド・レコーディングした音素材をミックス再生するサウンドスケープ・インスタレーション。
これは、レコードがたくさん置かれていて、それぞれ違う声や音楽が、おそらく偶然的なタイミングで再生されている展示。
本来、まったく独立した文脈で録音されたであろう声や音楽が、こうして身体から離れて並べられると、それぞれが会話しているように見えてくるところが面白かったです。
逆に言えば、それほど身体がある、ということが会話にとって重要なことなのかもしれません。
(もし、これを俳優が立って同じ声で喋っていたとしても、モノローグに見えてしまって、会話しているようには見えないと思う。)
ほかにも面白い展示はたくさんあったので、興味のある人にはおすすめです。(東京の木場です)
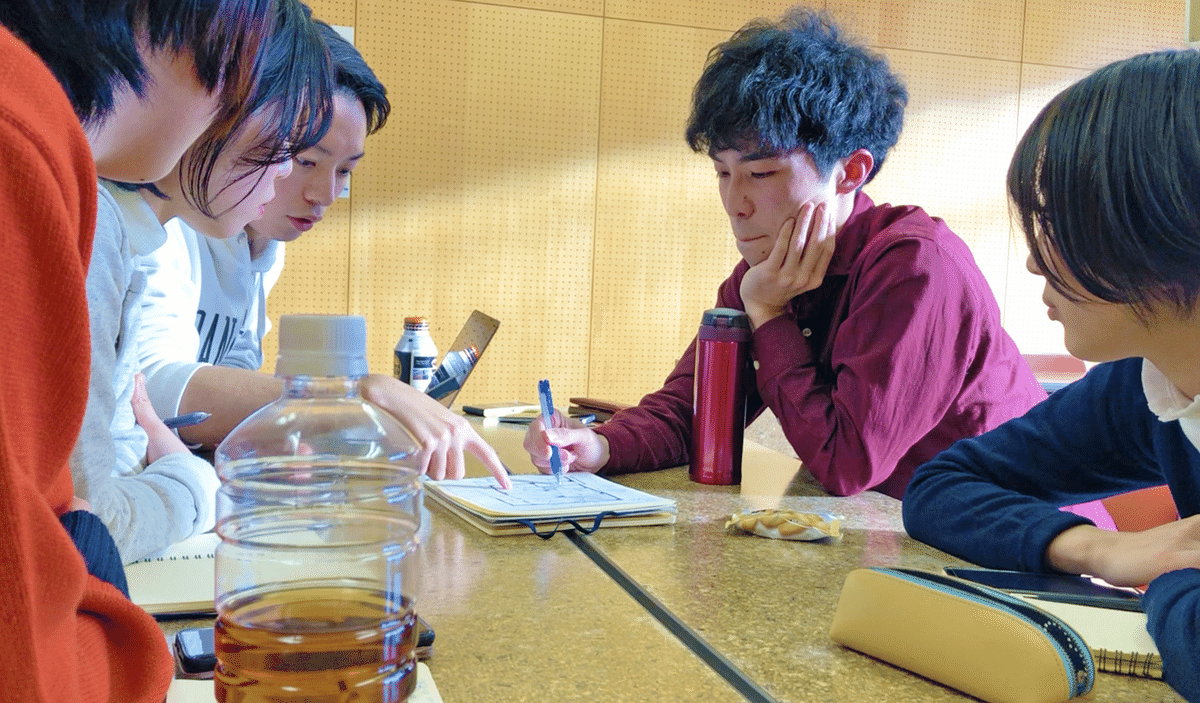
わたしがもうひとつ、展示とは別に興味を持ったのが、ダムタイプの創作方法で、いわゆる集団創作的な作り方をしているようでした。
メンバーには、建築家・美術家・デザイナー・プログラマーがいるようで、それぞれの強みを活かして創作にあたることで、ヒエラルキーのない集団を実現している、とのこと。
(このあいだ見た、「目」もそういう作り方らしかった)
劇団とヒエラルキーについては、わたしも、いち制作者として、しばしばあれこれ考えてしまう。
青年団という劇団の平田オリザさんは、「現代口語演劇のために」のなかで、集団論について詳しく述べている。
たとえば、劇団内のヒエラルキーの形成によって劇団が腐敗しないために、中間管理職的なポジションを設けず、主宰と劇団員が一対一で向き合うことのできるような環境を作るようにしている、というように。
たしかに、過度な分業制は、ヒエラルキーを生みかねないし、それは集団を腐敗させるとわたしも思う。
その一方で、ダムタイプのような集団創作の在り方を見ていると、必ずしも、分業性がヒエラルキーに結びつくというわけでもないのかな、とも思う。
平田さんも指摘しているように、たぶん重要なのは、各自が持つ専門性に応じて、その責任と自由の範囲を明確に定め、それを集団内で共有するということ、なのかもしれない。
ダムタイプは、おそらく、プログラミングのエラーについて建築家は干渉しないし、脚本についてデザイナーは干渉しないだろう(たぶん・・・)。それは、各自の自由と責任の領域を決めているということだ。
関連して大切なのは、事実として情報が共有されているということではなくて、共有されているという事実が共有されているということ、このことだと思う。
実際、情報が事実として共有されているだけでは、ヒエラルキーは形成せざるを得ない気がする。
たとえば、俳優Aのギャランティだけが不当に高いことは、事実として誰しもが知っている(事実として共有されている)が、共有されているということが共有されていない(公然化されていない)ために、誰もそのことについて議論することができない(言ってよいのかな、となったりする)。それゆえ、情報を公然化する力を持つ人が、結果として情報や議論の土台を操作することができてしまう、(がゆえに、権力構造が再生産され強いヒエラルキーが形成される)というように。
一般的に、分業がヒエラルキーと結びつきやすいのは、分業の結果の報告が公然化されていないがゆえに、事実としてその情報をみんなが持っていたとしても議論ができないということが、理由の一つとしてあるような気が、わたしはしています。
(もちろん、かならずしも、このことだけにヒエラルキーが生まれる原因がるとは思わないけれど・・・)
これを防ぐためには、(チープな解決策かもしれないけれど)今はクラウドサービスが普及しているから、誰しもが、その日のお金の周り方や、会議の進みを、スマートフォンを通して見られるようにすることが大切かもしれない。
(クラウドサービスと、メールでの個別配信の違いは、たとえば、クラウドサービスは誰しもがそこにアクセスできることを誰しもが知っているが、他方で、個別配信の場合は、仮に全員に配信されていたとしても、その情報が自分しか持っていない可能性を排除できないがゆえに、情報が公然化されない事態が生じてしまう、ことがあると思う。)
ちなみに、情報の公然化については、
3人の囚人の話がわかりやすいです。
つまり、互いが動き出さないことを、互いが互いを見回していることを示し合うことによって公然化することで、自分の帽子の色が分かる、という。
事実として、個人個人が知っている情報は増えていないのに、情報が公然化されることで、それぞれの行為が変わってくるということが、この話の面白いところだと思います。(場を共有した、といったほうがもしかしたらわかりやすいかもしれません)
だから、ぺぺぺの会では、劇団に関する会議(議事録や録音)や、お金の動きは、全て共有のGoogleドライブにアップロードして、劇団員であれば誰もが見られるようにしようにしています。
このことは、ただ欠席した人が情報を見られるというだけではなくて、その情報が公然化されることで、いろいろなことを対等に議論することができるようになると思うからです。
そうだとしたら、代表者を決めなくても、うまくいくことは多いんじゃないかな、なんて。
ダムタイプ「アクション+リフレクション」展は、東京都現代美術館で、2/16まで開催しているようです。
興味を持たれた方いましたら、ぜひ。おすすめです。
読んでくださってありがとうございます。 みなさまのコメントやサポート、大変励みになっております。
