
和歌山県の社会人サッカーを見に行った話
先日初めて和歌山県社会人サッカーのゲームを観に行った。来季からチームを率いる身として本来ならもっと早くに観に行く必要があったのだが、如何せんコロナウイルスの影響がありなかなか時間がかかってしまった。(和歌山県はコロナウイルスのワクチン摂取率が日本で一番高い等、感染防止対策に力を入れている県でもある。)
今回訪れたゲームは下記の3ゲーム。
・KSL 1部 アルテリーヴォ和歌山 vs ポルベニル飛鳥
・クラブ選手権和歌山県予選 CLASSICS vs 岩出FCアズール
・クラブ選手権和歌山県予選 ソラティオーラ和歌山 vs 海南FC
まずは県内トップチームであるアルテリーヴォ和歌山のゲームを観て、今一度関西サッカーリーグ1部のレベル、和歌山県でトップに立ち続けているチームを再度確認すること。ここではゲームの内容だけでなくコロナ禍におけるホームゲーム運営についても確認したい部分もあった。
そしてその後は和歌山県リーグ所属チームのゲームを2試合。リーグ戦は試合数が多くないのでタイミング合わなければなかなか県リーグチームのゲームを見ることは出来ない。和歌山県社会人3部リーグからスタートする身として、来季以降確実に対戦するであろうチームのゲームを観ないわけにはいかない。更に各都道府県リーグのレベルも全然違うことから、一体どれほどのレベルなのか?という部分も再確認しなければならない。
和歌山県のトップチーム
まずはアルテリーヴォ和歌山のホームゲーム。
試合前のW-UPなどゲームに持って行く雰囲気を久しぶりに感じ取れたのは良かった。月並みな感想だがやっぱり試合前の雰囲気は心地よく来季以降楽しみになった。知っている選手やスタッフにも後輩がいるなど、少し試合後に話が出来たことも良かった。
いつかこのチームともゲームがしたいし、ライバルだなんて思って頂けるように歩んでいかなければならないと強く感じた。和歌山県で14年ほどトップに立ち続けているチームにリスペクトを持って進んでいきたい。
とりわけ一つのサッカー観戦としても楽しめた。また関西サッカーリーグの他チームのゲームも見に行こう。
忘れていたようなこと
直近且つリアリティを感じられるのはここから。
CLASSICS(和歌山県2部) vs 岩出FCアズール(和歌山県1部)のゲーム。
岩出FCはジュニア年代のチームもあるので名前は知っていた。そこのトップチームである。対するCLASSICSは仕事との両立でサッカーも取り組んでいるという一般的な社会人サッカーチームだろうか。両チーム監督やコーチなる人物は不在でベンチメンバーもいないに等しい。
これぞ社会人サッカーだと感じるところがあった。
面白かったのは高卒の若い選手が想像以上に多かったこと。平成10年〜14年生まれ(23歳〜19歳くらい)が多く、大学には進学せずに地元で就職してサッカーを楽しんでいる選手が多かった。強豪高校から大学へ進学する選手も多いが、それらの選手はサッカーをキッパリ辞めてしまうケースも多い。当然大学サッカーの想像以上の壁を感じる選手もいるだろうし、大学に進学することで成長が止まってしまう選手もいるだろうと感じる。
しかし高卒の彼らは純粋にサッカーを楽しんでいた。そしてチームでは安定的にゲームにも出れることから、ゲームに出ていない選手以上に成長も出来るということ。
もちろんサッカーにおいて勝ち負けは大切ではないとは思わないが、究極は生涯スポーツとしてのサッカーを大切にすることが、文化形成の面においても重要である。育成年代だけでなく社会人サッカーもグラスルーツだと思えば、和歌山県はこの役割を果たしていると思えた。
選手も審判も運営も、皆が協力して1つのゲームを完成させる。その中で楽しむ。殺伐とした雰囲気はこのゲームには無く、少し自分が忘れていたものを思い出せたような気がした。
カテゴリーとチームレベルは比例しない
続いてはソラティオーラ和歌山(和歌山県3部) vs海南FC(和歌山県1部)
海南FCは和歌山県において紀北蹴球団に並び歴史あるチームだということは知っていた。先程のゲーム以上に強度が高く、観ていても面白いゲームだった。
最も驚いたことは選手のレベルの高さだ。
正直このレベルの選手がいるのか。。。と。
地域リーグクラブと関わっていたりもするが、私の見立だと恐らく地域リーグ1部〜2部。しっかりと自分がフィットするチームを選び、更に成長できればJFLも射程圏内だ。より一層サッカー選手がステップアップして行くのは選手の実力以上に、タイミング、出会い、運が大きいなと感じる。
選手自身が、自身の特徴を理解すること。そこから自身が適応しやすいチームを選ぶこと。(言うまでもないが適応能力やコミュニケーション能力の高い選手は何処に移籍をしても最終的にはスタメンでゲームに出られるケースが多い。それの日本トップクラスの選手が長友選手や岡崎選手、長谷部選手なのだろう。)
また県3部といっても侮ってはいけない。
ソラティオーラ和歌山には海南FCのOBが多いらしく、平均年齢こそ高いもののしっかりとした技術を持っている選手が多かった。「昔は凄かったんだぜ!」と話せるような選手が多いイメージだろうか。
特にここ1〜2年はコロナ禍もあり、新しいチームが出来たり逆にチームが消滅したりとリーグとして安定していない。カテゴリーによってレベルがある程度区分されているはずが、和歌山県リーグは各カテゴリーでチーム数も少ないのでよりカテゴリーとチームレベルが比例していない。
その感覚を掴めたことも大きかったと言える。
来季一番の仕事とは
来季に向けてチームとしては色々なことを準備中だ。
ただリーグとしての難しい課題に立ち向かわなければならない可能性がある。
それが棄権だ。
サッカー選手にとって一番精神的に辛いことが、ゲームに負けることではなく、棄権によりゲームが無くなってしまうこと。相手チームが棄権すれば確かに勝ち点3を得られるかもしれないが、それで選手のモチベーションが上がるわけもない。更にサポーターやファンを少しづつ増やしていく目標があるとして、観戦できるはずだったゲームが無くなる落胆はかなり重い。
しかし棄権するチームが悪いとは微塵も思えない。社会人として仕事とサッカーの両立は簡単ではないし、全てのチームが勝ち負けに拘っている訳でもない。更にはコロナ禍でチームの活動も難しくなっている。
自分たちのクラブが異種分子であることを理解しなくてはならない。
自分のやるべき仕事はモチベーションとチーム内競争の維持。そして思わしくないことが起きてしまった時の対応策とカバー。ただこのような部分も新規チームを立ち上げるからこそ経験できること。楽しんでいきたい。
時間が経ち、その現場を訪れることで、より鮮明に物事がイメージ出来た。
残された時間は半年弱。
スピード感を上げて取り組んでいく。
ここから先は
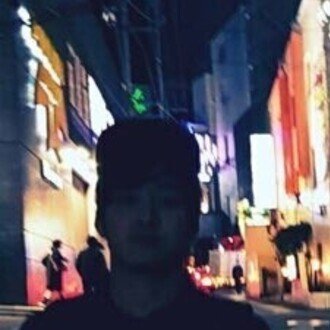
キャリアゼロからJリーグを目指す監督note
トップカテゴリーでの指導経験が全く無い人間が、[監督]として成功できるのか? 奮闘する毎日の中で考えていることや想い、クラブの道筋を覗いて…
これからも自分以外の【誰か】や【何か】のために、少しでもその方々にとって有意義なものを作っていきたいと思います。楽しみましょう!
