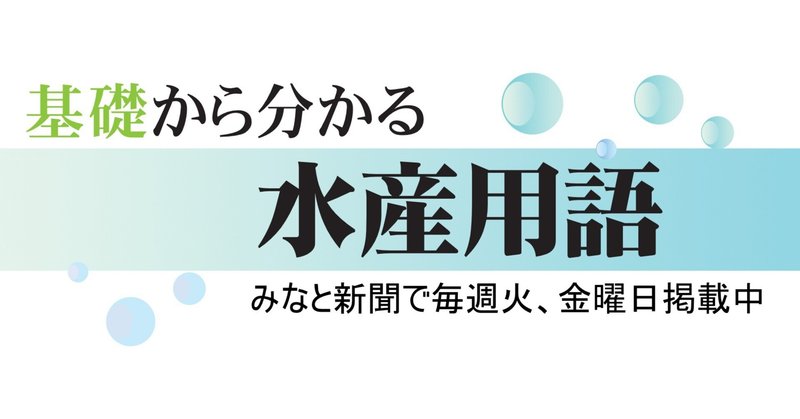
【無料】基礎から分かる水産用語<27> 巻網漁業とは
みなと新聞で毎週火・金曜日に連載している「基礎から分かる水産用語」を公開します。
みなと新聞の専門記者が、漁業、流通・加工、小売など水産で使われる一般用語から専門用語まで、分かりやすく説明する連載です。
巻網漁業とは
網で魚群を囲い込み、魚を獲る漁法。主にアジやサバ、イワシ、カツオ、マグロなど浮魚が対象となる。効率的に多くの魚を獲ることができる国内の主力漁法の一つ。
巻網漁業の種類には、沖合・遠洋で操業する「大中型まき網漁業」(大臣許可漁業)、沿岸・地先沖合で操業する「中型まき網漁業」(知事許可漁業)、「小型まき網漁業」(同)がある。農水省の2021年漁業・養殖業生産統計によると、海面漁業漁獲量319万1400トンのうち、巻網は134万200トンで全体の約4割を占める。
巻網漁業の中核を担うのが大中型まき網漁業。全国まき網漁業協会によると、大中型は操業方法により1そう巻と2そう巻があり、集魚灯の使用が認められている場合もある。網を積んだ本船、魚群を見つける探索船(または灯船)、獲った魚を収集して運ぶ運搬船などで船団を組む。
網の大きさは魚種や漁場状況などで異なり、1そう巻は長さ約1・6~1・8キロ、2そう巻は長さ約1キロ、深さはいずれも100~250メートル程度ある。探知機などで魚群を見つけ、投網。魚群を網で囲い、運搬船に積み上げて漁獲する。現在は約100カ統の大中型まき網漁業船団(海外まき網漁業含む)が操業。21年の漁獲量は約92万トン、水揚金額は海面漁業全体の約1割となる約940億円だった。
