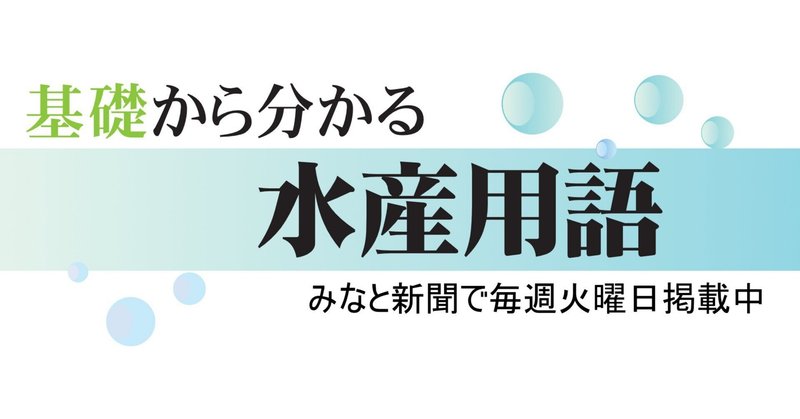
【無料】基礎から分かる水産用語<204> 魚礁とは
みなと新聞で毎週火曜日に連載している「基礎から分かる水産用語」を公開します。
みなと新聞の専門記者が、漁業、流通・加工、小売など水産で使われる一般用語から専門用語まで、分かりやすく説明する連載です。
魚礁とは
多くの魚が生息する場所や漁場として用いられる場所のこと(「水産・海洋辞典」から)。水産総合研究センター(現水産研究・教育機構)の公式ホームページ(HP)では魚礁に魚が集まる理由として、「魚が生きるために必要な機能が備わっている」ためと説明する。
同HPによると、魚礁の機能には、小型魚が大型魚に襲われた際に身を守る「隠れ場」▽流れが速い所で泳ぎ続けることが難しい時に休息する「休み場」▽産卵に必要な海藻に多くの種類や大きさの違う魚が集まる「産卵場」▽カニやエビ、フジツボなどの餌生物が生息する「餌場」-がある。
農林水産省によると、魚礁には天然の岩でできた「天然礁」とコンクリートブロックや鉄骨などで人工的に造った「人工魚礁」がある。同省は「磯焼けの影響などで天然礁は減少傾向にある」と説明し、「藻場を増やして天然礁を維持する他、人工魚礁に切り替える場合もある」と話す。
同省は沖合の排他的経済水域(EEZ)に人工魚礁を整備する「フロンティア整備事業」を2007年から実施し、計5カ所で人工魚礁の整備を進めている。うち、長崎の五島西方沖地区(総事業費92億2200万円)は15年10月に、島根・鳥取の隠岐海峡地区(総事業費55億円)は20年12月にそれぞれ完成した。
みなと新聞本紙2024年5月14日付の記事を掲載
