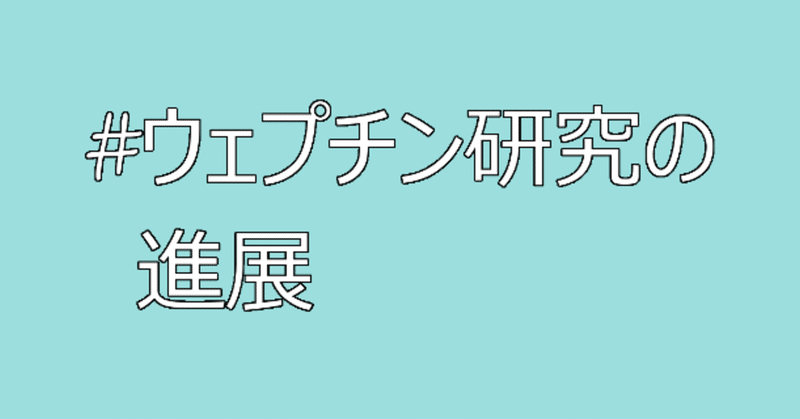
ウェプチンは何らかの生産方法で、その評価は精度・性能と簡単さしかない
おはようございます、那由他でございます。
今回は「ウェプチンの研究」に進展があったので、その報告になります。
事の発端
事の発端は僕が先月からYouTubeにはまってしまって、短時間でnoteを書く方法を合成できないか考えたことにあります。
いつも近日中にアップした数回分のnoteをチェックしてから、その続きを書くようにしていたんですが、そのときにTechnical Abstractsの説明文を整理していたら、ウェプチンのある共通点に気がついたんですね。
1つ目の発見:ウェプチンは何らかの生産方法である
ウェプチンは日本語で表すと「成長因子」で、もともと何らかの技術を想定していたんですが、過去にサンプリングしたウェプチンのデータを見直してみると、それが「何らかの発想を実現するための技術、方法」であることがはっきりしました。
そこでまた、あることに気づいたんですが、それが、
2つ目の発見:その評価は、精度・性能と簡単さしかない
ということです。
皆さんの手元にはウェプチンのデータはないかもしれませんが、有名な発想法で「オズボーンのチェックリスト」というものがあって、それで発想した結果にも同じことが言えるので、良ければあてはめてチェックしてみてください。
じゃあ、新しいものとは何か?
「でも、それって新しいことには言えないんじゃない?」と思われた方がいるかもしれません。
ですが、これは以前からも何度か説明してきたように、新しいものは目的をかえることで生まれます。(ラテラルシンキング)
ApB的には、「A(テーマ、目的)が唯一無二な発想は新しい」と表すことができ、それにp(大切なこと)とB(大切なことを得る方法)がとりあえずついている状態で、それらがこの精度・性能と簡単さで評価できます。
例えば、僕が以前に考案した「立方技」(※コートの角をゴールにして立方体を敷きつめていく)というスポーツを例に挙げると、根本的に「立方体を用いたスポーツ」というA(テーマ、目的)が新しいので出てくる発想も新しくなります。
この構図は破壊的イノベーションに似ている?
新しいものが誕生すると、最初は性能や精度が低いんですが、業界ができ複数の企業が改良を重ねて徐々に精度が上がり、やがてオーバーシュート(過剰に精度に改善が加え続けられている段階)に達します。
このウェプチンの精度・性能と簡単さという評価項目は、それ(オーバーシュート)が簡単で新しい発明によって破壊され革新が起きる破壊的イノベーションと似ています。
プロジェクトでもよく「成長と革新は同じこと」と言っています。
ここで話をもどすと
ここで話をもどすと、この評価(精度・性能、簡単さ)から「短時間でnoteを書く方法」や成長を逆算できることがわかります。
1.精度や性能を高めるには?:その技術によって精度・性能は高まったか?
2.簡単にできないか?:その技術によって簡単になったか?
例えば、僕もYouTubeコンテンツは1日に5件ずつアップしていたことがありますが、その簡単さをnoteに移植できたら革新的な手法になります。
短時間でnoteを書く方法
これはYouTubeのゲーム動画で考えるとわかりやすいんですが、「ブロガー100の質問」みたいな問題集を常にストックしておくことです。
ゲームには、常に何かやることがあります。
noteもそれと同じで、常に「解かなくてなならない問題」、「答えなければならない質問」があれば、短時間で書くことができます。
また以前には、ゲームを自作してアニメーション、CMメーカーとして利用していたこともありましたが、アプリにすれば簡単に動画にすることもできます。
謙虚でポジティブに続けていきたいと思っています!応援よろしくお願いします^^
