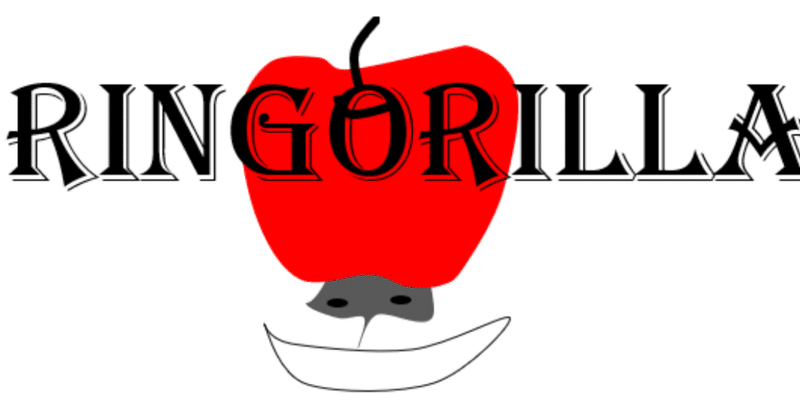
リンゴリラ #7
月島アークホテル
月島アークホテルは閑散としていた。田村と磯田の死体を取り囲んでいる5人の警視庁の本部長クラスの人間は、ホテルに大量にたまった死体の処理をどうするか検討している最中だった。
通報者が誰なのかも分からず、挙句現場にいた刑事二名は拳銃で撃ち合い死亡、残る一人は豊洲のアパート前で死んでいた。この事件が露見すれば、警察の無能ぶりが糾弾されることは間違いない。
「いや、ここは隠蔽でしょう」
「隠蔽するには死体が多すぎる」
ロビーのソファで缶ビールを飲みながら、議論が続けられる。今日は特高警察の生き残りのお偉方の誕生日を祝う会だった。こんな事件でもなければ、家に帰って鼾をかいているところだ。全員しらふではない。重鎮に気を遣って朦朧となるまでしこたま飲んだ後に、こんな事後処理の電話だ。五人はそのことだけで面白くないのだ。
「カエルに任せたのが失敗でしたね」
誰かがそう言った。それに別の誰かが答えようとすると、その人物の顔が次の瞬間消えていた。
開栓。
一瞬、さっきまでの宴会のバカ騒ぎが思い返された。そこでは派手にドンペリニヨンが開栓され、勢いよく中身があふれ出た。
だが、いま彼らの顔に降りかかってくるそれは、ドンペリニヨンではなかった。
メガネが血で曇って見えなくなった一人がメガネを外そうとした。だが、外そうとするにも、彼には腕がなかった。
一人が騒ぎ出した。騒ぎ出した男は下半身と上半身が分離していた。腕だけではそんな遠くに行けるはずもない。
二人はその事態を呆然と立ち尽くして見ていた。
酒を飲みすぎたのも手伝って、二人はその場に嘔吐した。
吐き終えてすっきりしたところで、二人の首はなくなった。
現場には腕のない刑事と上半身だけの刑事の呻き声だけが響いた。
《庭師》は腕のない刑事の首に縄をつけ、床に倒した。
それから、上半身だけの刑事の首にそのロープの反対端を巻きつけた。
「足を使わない刑事と、拳銃を握らない刑事。この国にお似合いだと思わないか?」
刑事は答えなかった。
「でもどっちかだけでいい」
《庭師》は二人に、反対方向にロープを引き合うように命じる。強かったほうが生き残ることができる。上半身だけの刑事に比べれば、腕のない刑事に利があった。
《庭師》は勝負の行方をしばし見守ったが、勝負は分かりきっていた。腕のない刑事が、泣きじゃくりながらロープを引き、上半身だけの刑事の首の骨が折れる音が鳴った。
「優勝トロフィーの代わりに、お前の腕をやろう」
《庭師》は刑事に二本の腕を投げて渡す。
「まだうまくくっ付けられるかもしれない」
だが、刑事にはそれを抱える腕がない。腕のない刑事は、二本の腕を足でちょこちょこ蹴りながら逃げていく。だが、彼がエントランスまでたどり着くことはなかった。
伸縮高枝バサミを最長まで伸ばし、《庭師》は刑事の首をはねた。
《庭師》は、二階に上がり、エレベータから最も遠くにある部屋に入った。室内には死体はなかった。明かりはつけずに、丁寧にベッドメイキングされたベッドに座ると、静かに時計の針を目で追った。
時計が四時五九分から五時に変わると、《庭師》は窓際に立った。
その窓からは、月島神社が見下ろせた。
そして、窓の外には両手を手錠でつながれたままのルーベンスの姿があった。神社の鳥居に立ち、月島神社が祭るウサギの銅像を見つめている。
その光景は、破壊を継続してきた男の最後の場所としてはいささか奇妙な気がした。
《庭師》は、伸縮高枝バサミを握り直した。
月島神社
鎮守の杜のざわめき。
獣たちの声。
木々の隙間から見える群青色の空には、まだ太陽の姿は見当たらない。その杜のなかに続く石段を歩き、ルーベンスは境内に辿り着く。
ルーベンスは、左右に配置されているウサギの石像に目を留める。
これまで、ルーベンスは仕留める対象を「ウサギ」と形容することがあった。そういうとき、ルーベンスの頭には、ターゲットそのもの以上に、ふわふわとした白い毛に覆われたウサギが浮かんだものだ。それと同時に、ルーベンスが敬愛する画家のブリューゲルの『雪中の狩人』が浮かぶ。『雪中の狩人』にはウサギは登場しない。だが、ルーベンスのなかで、狩人が追っているのは間違いなくウサギなのだ。彼らはウサギを追っている。あるいは、覆われた雪は、これまで彼らが殺してきたウサギを象徴しているのかもしれない。
ルーベンスはしばしばその絵画の狩人に自分を重ね合わせてきた。これまで殺してきた人間の数は三ケタでは足りないかもしれない。ドストエフスキーが長い小説を書くように、自分もまだまだ死体を重ねなくてはならない。重ねる行為自体はしんどい作業ではない。問題は、それをどこで終わらせるか、だ。
『雪中の狩人』の狩人にも、恐らくそれが分からないのだ。
だから、彼らは途方に暮れている。
いまルーベンスはウサギの石像をみて何らかの奇異な印象を抱いた理由を考える。結論に時間はかからない。ウサギは逃げるものだ。それが逃げずにこちらを見つめているのが奇異なのだ。
ルーベンスは背中に回された両手を動かしてみる。手錠は抜けない。掌の骨を折れば、簡単に抜けるだろう。だが、まずはカホリに逢ってからだ。
五分経過。
後方でカラスが鳴きながら杜から飛び立つ。ゴミ回収所に出稼ぎに向かうところだろう。カラスにとっては東京全体が食料庫だ。その意味で、ルーベンスとカラスは、同じ穴の狢だ。
背後から足音が聞こえてくる。
だが、その足音は女のものではない。
ルーベンスはとっさにウサギの石像の影に隠れる。
相手もプロなのか、その際のわずかな気配を見逃さない。
足音が止まる。
「ジンジャエールはどこだ」
あまりうまくはないが、外国人のなかでは流暢な部類だろう。デーヴ・スペクターレベルだと、ルーベンスは思う。
「ワタシは両手に一挺ずつセミオートマチックピストルを持っている。お前が一発撃つとこっちは二発お前に撃ち込むことになる」
男は圧倒的優位性を説く。チャイナ・マフィアか、とルーベンスは思う。
「ルーベンス、それがお前の名前だ。そうだな?」
相手はどうやらこちらを調査済みらしい。ルーベンスは背中で組まれた両手をぎちぎちと外そうと試みる。だが、外れない。
「ワタシは寛容な人間だが、尋ねられて返事をしない奴は好きになれない」
「ラオチュー(鼠)が何の用だ」
「ジンジャエールを返してもらう。それで後腐れなしだ」
「ジンジャエールはここ数年飲んでない。もっぱらウィスキー党なんだ、悪いな」
「お前、分かってないね。いまどれだけの脅威がお前を狙ってると思う?」
「…二挺の拳銃だろう? 分かってるさ」
「それはワタシの持ってるピストルの数だ」
ルーベンスは鎮守の杜を振り返る。
ほの暗い杜の木々が、すべて拳銃に見える。
これは相手のハッタリか。
それとも……。
「我々はお前を許さない。お前があと五秒でジンジャエールを解放しなければ、お前の爪一本地上には残さないよ」
「爪一本」というフレーズをルーベンスは気に入った。実に刺激的で破壊的な発言だ。
カウントが始まる。
5
ルーベンスはこのとき、なぜか先ほどタクシーのなかで見た夢を思い出す。犬だ。犬を自分は抱いていた。自分で首をへし折った犬を抱きながら泣いていた。
4
夢を見たのは本当に久しぶりだった。犬を飼ったことのない自分が、犬を抱いて泣くというのは奇妙だが、これも何らかの分析のしようはあるのだろう。
3
ルーベンスは両掌を強く押し付け合い、小指の骨を折った。
激痛。だが代わりに、手錠は難なくはずれた。
2
チャリン、と音がして、手錠が地面に落ちる。
落ちる前に、骨折した掌が腰の拳銃を引き抜く。
1
だが、ルーベンスが石像の影から飛び出そうとするより早く杜の中からマシンガンが撃ち込まれる。一挺や二挺ではなさそうだ。
鎮守の杜に狩人たちがいる。その事実にルーベンスはひどく興奮する。自分がヘチマのように穴だらけにされるところを想像するだけでひどくドキドキし、下半身が反応しはじめる。
ルーベンスは考える。ここからどう動くべきか。そして、動く必要があるのかどうか。ここまでよく走ったじゃないか。どこかで死の沸点は必ずやってくるのだ。それが今であってはいけない理由はどこにもない。待ちに待った最高のエクスタシーを迎えるときがきたのではないのか? これはご褒美だ。それが《庭師》ではなく予想外の敵によるというところが何とも刺激的じゃないか。神の粋な計らいだ。十九歳で初めてルーヴル美術館を訪れたときにさえ得られなかったほどの感動が胸に去来するのを、ルーベンスはどうすることもできない。
しかし、もう一方で、いや、まだだ、と否定する自分もいる。
そうだ、リンゴを手にするまでは。
カホリと逢って、奴があの文豪から奪ってきたリンゴを手にするまでは死ぬわけにはいかない。
ルーベンスはカホリを使ってリンゴを手に入れた。この月島神社でカホリからリンゴを受け取ることになっている。実際には、事前にカホリを消すつもりでいた。そのためにパンツとウォンを月島アークホテルに送り込んだ。
だが、計画は失敗に終わった。
カホリはすでにホテルから姿を消していた。
理由は分からないが、カホリは危険を察知したのだ。そして、カホリのためにルーベンスが用意した隠れ家、第二豊洲アパートメントでウォンが首なし死体となって発見された。ウォンはカホリがそこにいることを嗅ぎつけ、挙句殺された。同行していたパンツは、それをルーベンスの仕業だと思い、今もルーベンスを追跡している。
首を刎ねたのは《庭師》だろうが、爆破したのは《庭師》ではない。《庭師》が火薬系の武器を使用するとは考えにくい。恐らく、カホリ自身だろう。
そこから先、カホリの手がかりは完全に途絶えてしまったため、ルーベンスとしては、ここへ来ざるを得なかったのだ。そして、カホリが潜入していた中国マフィアの組織もまた、カホリを追って月島神社にたどり着いた。
ルーベンスは、一瞬の眠りのことを思い出す。
自分が眠っていたあのわずかな間に、世界は変わった。こんな物騒な世の中では瞬きすらできないのに、自分はあの状況で眠りに落ちた。一瞬の眠りが、歯車を狂わせた。
中国マフィアたちはカホリを自分たちの商品と勘違いしている。そういう連中だ、それは仕方ない。言って分かる相手ではない。いったん火がついたら、とりあえず皮を引ん剥くまでは気が済むはずがない。
「いいだろう。彼女を渡そう」
「もう遅い。我々で探す」
再びマシンガン。
ルーベンスの頭ひとつ上にあるウサギの像が根元から崩れ落ちる。
落下するウサギ。頭から転がり、柔らかな土にさかさまに刺さったウサギを、ルーベンスは足で転がした。
「そいつはムリだ。彼女の居場所は俺以外誰も知らないんだぜ?」
マシンガンがやむ。
「あの女はサイコ―だ。そう思わないか?」
男は答えない。
「あの女がサイコーな理由を考えるに、それはゼッタイに俺たちの思い通りにならないってところじゃないかと思うんだが、どうだ? どんなにおとなしくフェラチオしているようでも、それは彼女が従順だからじゃない。アイツがそうしたいからだ。もし気が変われば、こっちがイくイかないに関わらず途中でやめちまう」
「お前、何の話をしている」
「いい女の条件ってのは、男の大事なモンをとことん台無しにできるってことなんだな」
「お前、本当に分かってないね」
ルーベンスは笑った。ルーベンスの性的対象は人間ではない。もちろん動物でもない。いわば、状況なのだ。たとえば今、このひりひりするほどの生の脅かしに、耐えられないほどの興奮を感じている。だが、これはちょっと説明しづらい。
シュウウウウウウウ
その時、奇妙な音がしたかと思うと、辺りが光った。
鎮守の杜がオレンジ色に輝いた。
轟音。
大樹の隙間から火達磨になった人間がもがきながら現れる。
ルーベンスはようやくウサギの影から現れ、杜から出てくる動く炎を順に撃とうとした。だが、炎の前に立つ男が、ルーベンスよりも先にその影を撃っていく。先ほどから対話をしている中国人の男だ。杜にいるのは彼の味方ではなかったのだ。そいつを仕留めるために、中国男は焼夷弾を杜に放ったらしい。
「ナイショの話をしたいからね」
振り向いた中国男の左目は洞穴のようにぽっかりと空洞になっている。
そして、ポケットから一つ目玉を取り出し、それを洞穴に埋め込む。
「スペアはこれで最後だ」
ルーベンスは男に銃口を向ける。
男もほぼ同時にルーベンスに銃口を向ける。
「マーマの魅力は、絵画的曲線美にある。それと乳首。ピンク色に輝く先端、葡萄の一粒は、まさに画竜点睛」
「中国では絵画鑑賞も裸でやるのかい」
ルーベンスは笑い、引き金を引く。だが、弾がない。終わった、とルーベンスは思う。ついに終わりがやってきた。
中国男はルーベンスに近づくと、右手に握ったセミオートマチックピストルでルーベンスの顔面を殴りつける。ルーベンスは笑いながら後方に倒れる。男はそのままルーベンスの上に跨ると、ルーベンスの口を手で無理やり開かせ、その口内に自分の義眼を取り出してくわえさせた。
「飲み込め」
食道の幅とほぼ直径が同じ球体を飲めばそれだけで窒息するのは目に見えている。万一うまく腹に収まったところで、それは焼夷弾だ。爆破するのは時間の問題だろう。
すると、中国男は奇妙なものをマジシャンのように指の間から取り出す。それは──爪楊枝だった。
「飲み込めないなら、お前の目と取り替えっ子だ」
爪楊枝の先端がルーべンスの左目に接近する。ルーベンスは両腕を動かそうとするが、男の両腿にしっかりと挟み込まれて動かない。中国男は、その小さな躯体からは想像できないほど硬く、重たかった。まるで墓石だ、とルーベンスは思った。
背中に、冷たい土の感触が心地よく広がる。ルーベンスは目を閉じるつもりもないのに、勝手に閉じようとしている目の自然な運動に驚いた。そして、当然ながら中国男はその働きを阻止した。上下の目蓋を指で押さえて閉じないように固定し、爪楊枝を勢いよく振り上げると、一思いに振り下ろしルーベンスの左眼球を爪楊枝が貫いた。
痛みは想像通り。だが、流血は想像以下だった。ほとんど血は流れなかった。中国男は、たこ焼きでも食べるときのように、手際よく指を動かして、左眼球を掬い上げると、それを口に頬張った。眼球と肉体をつなぐ神経が長く伸びる。中国男は、それを歯でうまく噛み切った。そして、代わりに空洞になった左目のあった場所に、ルーベンスの口に突っ込んでいた義眼をはめ込んだ。
「この義眼がお前を救ってくれる日も来るだろうさ」
中国男は立ち上がろうとした。とどめを刺すつもりはないらしかった。ルーベンスは、この間、一声も発しなかった。痙攣とともに訪れた恍惚に酔いしれていた。そして、自然反応で射精した。
直後に異変が起こった。中国男の影はゆっくりと後方に倒れた。一瞬、自分の射精が相手を撃ち抜いたような愚かな錯覚に囚われた。
急いで、倒れた男の下に近寄って確かめる。
首の骨が百八十度ねじれている。
仰向けに倒れているのに、顔だけが地面を向いているのだ。
後方の杜の炎は、いよいよ激しくなり、神社に火が燃え移るのも時間の問題だ。ルーベンスは、ウサギから狩人へと再び復帰する。死体多き火中の狩人に。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
