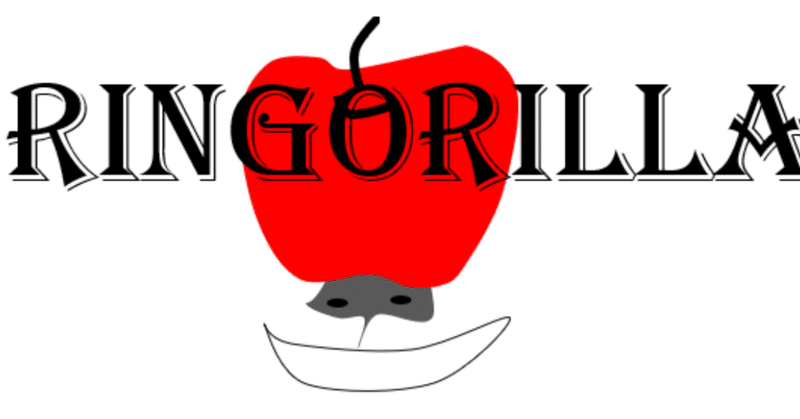
リンゴリラ #5
同じく第二豊洲アパートメント周辺
パンツは左腕で生首を抱え、右腕を使って這い進んでいく。月の光がよそよそしいのは今に始まったことではない。だが、今宵はやけに冷笑的だ。
やっとの思いで大きなビルの裏手に入り込んだ。公衆電話から闇治療をしてくれる医師のところに電話をかけるためだ。
《鈴》と呼ばれるその医師は、ルーベンスとつながっている。もしかしたら、命取りになるかもしれない。だが、それはある意味で好都合だ。この体たらくではルーベンスを殺しにいくこともままならない。いっそ向こうから出向いてくれたほうが助かるというものだ。
「その声はパンツ君だね、いまどこにいる?」と《鈴》は少しロボットを思わせる口調で尋ねる。人体をモノと捉えて生きている人間に特有の無機質な調子だ。
パンツは自分の場所を正確に伝えた。
「分かった。すぐに迎えを寄越す」
《鈴》の言ったことは嘘ではなかった。いかつい看護師の女がフェラーリに乗って登場すると、生首を抱えたパンツを見ても悲鳴ひとつ立てずにパンツを抱え上げ、車の後席に乗せた。
「毛布をかけるよ、見つからないように」
看護師は毛布をかけた。パンツはそのまま眠った。だが、人生にはたとえ、それが暖かいカプチーノと暖炉つきだったとしても眠っていはいけないときがある。パンツにとっては、この時がまさにそうだったのだ。
どれくらい経ったのか。
目覚めたとき、パンツは自分の足に違和感を覚えた。
「てめえ、何しやがった!」
ベッドの脇にいた《鈴》は、ゆで卵のような白い肌をつややかに輝かせ、ブランデーを片手にパソコンに向かい合っていたが、そのパンツの声に驚き、振り向いた。
そして、自身が作り上げたモンスターの産声に狂喜と畏怖の入り混じった表情を浮かべ、薄ら笑いを浮かべながら後方へ退いた。
「動こうとしても無駄だよ。きちんと鎖で固定されてるんだからね」
《鈴》──人畜無害そうな丸い顔で、笑い声ばかりが甲高く耳障りなためにこう呼ばれている。
《鈴》は白い肌をきらきらと輝かせ、ぷるぷる震えながら、それでも顔には勝者の笑みを浮かべている。
パンツの失われた左足には、ウォンの生首が縫い合わせてあった。
「ふざけた真似しやがって」
「面白いかと思ったんだけど、ウケ悪かったね。アハハハ」
パンツは拳銃を探したが、手近に置かれていないようだった。
「拳銃? ここだよ」
パンツの口の中に拳銃が押し込まれる。
「悪いね、使えなくなった殺し屋は好きにしていい契約なんだ」
汗を拭き拭きニタリと笑う。
「使える使えないは医学的判断に任せるって言われてる。医学的判断ってのは、つまり判断は僕任せってこと。医学の判断イコール医者の判断という現代人の陥りがちな誤謬を、君のボスも犯したんだ。医学の判断なんか、本当は医学自身にしかできない。医者ができるのはしょせん個人的判断さ。つまりつまりつーまーりー、医学的判断ってのは、医学を学ぶ医者による個人的判断の略というわけ。こんなの誰も誰もだーれも知らないけどね」
《鈴》はそう言って笑った。
「面白いものを見せてあげるよ」
《鈴》はいかつい看護婦に合図した。
看護婦は一度部屋から出て行ったあと、カチャカチャと音を言わせながら何者かを連れてきた。それは小学生くらいの男の子だと思われた。だが、頭部だけが犬になっている。それも、頭部だけやけに膨張した不細工な犬に。
「顔面に大やけどを負った子でね。治らなかった。ハンサムな子だったんだけどね。親がこんな醜い子は要らないっていうんで、貰い受けたんだ。どう? これなら親御さんも喜んでくれると思わない?」
少年の頭部は、白い毛並みをして、映画の「ネバー・エンディング・ストーリー」のファルコンみたいに耳が長く垂れ下がっている。そして、目は涙をためたみたいにうるんでいる。
「脳みそと眼球は元気だったからそのまま使った。あとはうちの犬。こんなこともあろうかと保存しておいて良かった」
《鈴》は犬少年を抱きしめた。
「お前は僕の大切なファミリーだよ」
パンツは自分の左脚の付け根にくっつけられたウォンの顔を見た。ウォンの顔はわずかに微笑んでいるように見えた。
バタンと大きな音がした。
わずかに身を起こすと、床に《鈴》が倒れていた。
その脇に、鉄パイプをもったいかつい看護師が立っていた。看護師は何度も繰り返し《鈴》を叩き、そのたびに《鈴》の体がぴょんぴょんとゴム人形のようによくはねた。
「コイツのせいで私は勝手に男にされちまったんだ」
一連の暴力的行為への解説書。パンツはうなずき返すしかなかった。
その後、犬少年が近づいてきて、パンツの体に巻きつけられた鎖をほどいてくれた。
「ばお、ぐーば、ぶふくふ」
「声帯まで犬にされてるから、まだうまくしゃべることができないんだ」と横から看護師が添えた。
パンツはうなずき返すしかなかった。パンツが身を起こすと、ウォンがわずかに窮屈そうな顔になった。看護師がパンツに拳銃を渡した。
「どこへ行きたい?」
パンツは想像した。男性ホルモンを注射されたいかつい看護師と、犬の顔をもつ子供をつれて、どこかのモーテルで朝食を食べている様子を。それはそれで、ひとつのゆがんだ幸せの肖像といえなくはないような気がした。
「とりあえず、ここを出よう。金はあるか?」
「コイツのカードをもらっていく。暗証番号は知ってるから」
「そりゃあいい」
そんな二人のやりとりの間、犬少年は《鈴》の顔面に噛み付いて、頬の肉を引きちぎって遊んでいた。
三人の怪物たちは、診療所を出た。
これも、第二豊洲アパートメント周辺
「お前の話を聞きたい」と爪楊枝が切り出した。
庵月はカウントを止める。
「寝かせ屋はどんなことをやる?」
「人を寝かせる。殺し屋が人を殺すように、寝かせ屋は人を寝かせる」
「それで、お前はかなり腕のいい寝かせ屋というわけだ」
「依頼人は多い。値段が安いせいもあるが」
「お前の信条は何か?」
「信条?」
庵月は聞き返した。
「信条のない奴、いい仕事人にならない。お前の信条何か言え」
庵月はしばらく黙った。それから呟くように答えた。
「殺すより寝かせろ」
一瞬間を置いてから、爪楊枝は笑った。
「エコロジーな標語だな」
「眠らせてコントロールしたほうが何かと便利だ。警察も死体が上がれば騒ぐが、寝てるだけなら騒がない」
庵月はそこまで喋って窓の外を見た。まだ息をしていることに感謝するべきかもしれない。
「お前の利用価値をワタシに売り込む気か?」
「さあ。あんたがそう思うなら」
庵月は手を膝に置いたまま、トランペットを吹くときのように指を動かした。『うずくまる女』。これまでで一番感じが掴めている。音楽というのは、ある危機的な状況において非情に個人的なものになる。あるいはそれがスライの言うところの「お前がクソ何者なのか」を記すということかもしれない。
庵月は言葉をつないだ。
「俺が言いたいのは、俺は俺の信条に嘘はつかないということさ」
「どういうことだ?」
「ジンジャエールとやらが殺されたというなら、やったのは俺じゃない」
「だが、お前は奴の居所を知っている」
「買いかぶり過ぎだ。それより、なぜそこまでしてそいつの居場所を追っているのか、教えてもらえないか?」
「旦那、そんな奴の話をいつまで聞いてる気ですか?」
運転席の肉塊が会話に割り込んできた。
それだけで車内の気温が一、二度上がる気がする。
「もう限界ですよ。そろそろ食べさせてもらわないと…」
最後の「と」の部分は半音で切り上げられた。フロントガラスが真っ赤に染まり、前のめりになった肉塊のせいでアクセルが全開になった。そしてそのまま前の車に突っ込んだ。完全に衝撃が収まるまで待って、庵月は立ち上がった。首の筋を違えたのか、肩から首にかけて激痛が走る。一方の爪楊枝は何一つ問題がないようだった。
開きにくくなったドアをガチャガチャ動かして何とか外に出た爪楊枝は、反対側に回って、庵月側のドアを開いた。
「なぜ殺した?」
「第一に、ワタシはエコロジストじゃない。第二に、ワタシは我慢強い人間しか信頼しない。無条件に信頼できるのは、冬の乾燥した土地に生まれた人間だけ」
「じゃあ、この国の人間は全員失格だ」
「さもありなん」
手を引っ張って庵月を引きずり出す爪楊枝に、庵月は三、四語の中国語を発した。
その言葉を聞いた瞬間、爪楊枝は卒倒した。
「ときには自分の信条も疑ったほうがいい」
庵月は爪楊枝のこめかに指を当て語りかけた。
「で、何を探してる?」
混濁した意識のなかで爪楊枝が答える。
「……リンゴだ」
「リンゴ。それは何らかのメタファーか、あるいはリンゴそのものか」
「両方だ。それはメタファーであり、リンゴそのものだ」
「それをジンジャエールが奪って逃げた。少なくともあんたらはそう考えてるわけだ」
「それが、彼女の任務だからだ」
「つまり、あんたらが彼女にそれを命じた。ところが途中からうまくいかなくなった。月島アークホテルから彼女は失踪してしまった」
「そういうことだ」
「いろいろ話してくれて助かった。もうすぐ警察が来るだろう。警察が来たらパトカーの中でいびきをかいて眠るといい。あんたの人生にはたぶん質の良い睡眠が足りないんだ」
庵月は立ち上がった。
前方ではスポーツカーの後席シートがぐちゃぐちゃになっている。
なかでは運転席の男がフロントガラスに顔を突っ込んで死亡している。ぐちゃぐちゃになった後席では、殆ど全裸の男女の体が手足の絡まった状態で、解きがたい惨状を呈している。カーセックスの最中だったのだろう。運転席の男がどういう立ち回りだったのか、気になるところだ。
庵月は空を見上げる。それから、再び爪楊枝に話しかける。
「《殺すより寝かせろ》が俺の信条だと言っておいたのに」
「違いない」
「あんたの大事な商品を殺したのはルーベンスという男の組織だ。俺じゃない」
「ルーベンス……」
「知ってるか?」
「画家だ」
ルーベンスの一行が追っているものと爪楊枝たちが追っているものは同じだろう。《リンゴ》だ。そして、恐らくジンジャエールと呼ばれる女の失踪とリンゴの消失には深い関わりがある。
そして──彼女は何らかの理由で、庵月がトランペットを吹かなくなった理由を知っている。奇妙な話だ、と庵月は思う。まるでプラトニ・カルキの小説の暗示的プロローグみたいではないか。
「はじめにリンゴがあり、次にそれをかじるゴリラが現れる。このゴリラはラッパを吹くことができない」
庵月は月を見上げる。そこにはいつもと同じ月がある。プラトニ・カルキの小説のようなドラマティックな現象は起こらない。ここは現実だ、と庵月は考える。ここは誰かの書いた小説なんかではない本物のリアルな世界だ。
庵月はトランペットを吹く手真似をする。深く、軽やかな音が出そうだ。だが、その音色はどこにも届かない。失われた音楽は、どこにもない空間をぐるぐると回り続ける。
庵月はポケットからGPS探査を取り出す。
依頼人の復讐は、まだ終わっていない。
第二豊洲アパートメント焼け跡
ルーベンスが第二豊洲アパートメントに着くと、焦げ臭い匂いが周囲に立ち込めている。まだ消防車は到着していないらしく、アパートの周りにはパジャマ姿のやじうまが数名。炎は、いよいよ強くなりつつあった。
しばらくして消防車が到着し、ホースを撒き散らした。火はすぐに落ち着き、その後で救出作業が始まった。201号から203号の住人が死んでいるのが発見された。他は皆避難できたらしい。
そして、204号室からは首なし死体が発見された。
それがウォンであることは、その長身さから察することができた。
なるほど、これがパンツの言っていた「仕打ち」かとルーベンスは得心がいった。これは確かにひどい「仕打ち」だ。誰がやったかは明確だが……。
消防車のあと、遅れて現れたのは小暮だった。小暮は部下を連れておらず、ルーベンスの顔を見るなり、ビクリとしたようだった。
「さっきの電話のことは忘れろ。いいな」
小暮の首根っこを掴むと、ルーベンスは開口いちばんそう告げた。
「旦那、ご無事で……」
首を絞められているせいか、本当のガマガエルのような声になった。
「忘れるんだ。お前はあんな電話は受けていない。俺は誰一人お前に売ったりはしていない」
「もちろんでさぁ、これまでの付き合いを考えてください」
「俺は付き合いで物事を推し量ったりはしない」
ルーベンスはパトカーのバンパーに小暮の顔面を押し付けた。カエルの河童焼き。
「よしましょうよ、旦那。人が見てます」
「警察手帳を寄越せよ」
小暮は胸ポケットからそっと警察手帳を渡した。ルーベンスはそれを高く掲げて見せる。
「警察だ。射殺するぞ」
その一言で野次馬はさっと身を引く。
「いなくなったぜ」
「警察の地位向上にご協力感謝します」
どんなときにも軽口を叩けるのは、この男のひとつの処世術なのだろう。
「いいか? 月島アークホテルを襲ったのはあの二人じゃない。月島アークホテルの一件は一切俺たちは関係していない」
「もう遅いですよ」
「何だと?」
「さっきあの二人を指名手配する連絡を回しちまったところです」
ルーベンスは小暮から離れた。小暮を殺すことにメリットを感じなかった。警察がパンツを追うことを止められなかった。ただそれだけのことだ。ルーベンスに害が及ぶものではない。それなのに、この何ともいえない釈然としない気持ちは何だろう?
ルーベンスはもう一度現場を確かめることにした。パンツの現在の居場所を知る手がかりがあるかもしれない。それに、失われたウォンの首も探し出さなくては。そもそも、奴らは何故このマンションに辿り着いたのだ? どうしてたどり着くことができたのだ?
階段を駆け上がる。
だが、204号室のドアの前に立ったとき、ルーベンスは、背後に冷たいものが突きつけられるのに気づいた。ルーベンスは両手を高く掲げた。ルーベンスの首には冷たい、よく研がれた金属が当てられている。最大何メートルまで伸びるのだっただろうか、とルーベンスは考える。もしかしたら奴は隣のそのまた隣の建物の屋根あたりから伸縮自在の枝きりバサミを伸ばしているのかもしれない。いずれにせよ、それはルーベンスの見えない後方に広がる世界の奥行きである。
「俺は部下を殺せとは言ってないぜ? 掃除屋の代わりにナメた真似をしてる兄ちゃんを殺すよう頼んだんだ。違うか?」
返事はない。それほど遠くにいるのだろうか。一体このハサミはどこまで伸びるのだろう。まさか二十メートルも伸びたりはしないはずだが……。
「そうか。お前はものすごく遠くにいるんだな?」
やはり返事はない。
ルーベンスは急におかしくなって笑い出した。全身にみなぎる死への恐怖。これぞ《庭師》を雇った甲斐があるというものだ。今日までの日々は今この瞬間のためにこそあるような気がした。
なぜか下半身が反応し、勃起した。
こんな偶然の、無作為に選ばれた一夜に、このような快楽が待ち構えていようとは…。ルーベンスは今に感謝した。ルーベンスにとって勃起と性衝動は完全に分離されている。勃起をセックスによって処理しようと思ったことはない。勃起とは、生の漲りであり、それはその状態を限りなく維持することの悦びを味わい尽くすべき現象なのだ。
「お前に俺の幼い頃好きだったことを話したかな?」
勃起状態の恍惚に酔いしれながら、ルーベンスは言葉を紡ぐ。
「俺はその昔、知らない家に忍び込むのが好きだった。手に持っているのはゴルフクラブだけだ。誰もいない家のなかで手当たり次第壊して回る。それだけの遊びさ」
両手の感覚がなくなってきた。緊張と興奮でアドレナリンが体内を逆流しているせいだ。
「そうやってぶんぶん振り回してるとな、世界の外側に立ったような感じだ。振り上げてるときの俺は鬼、振り下ろしたあとは仏。そんな極限を行ったり来たりしていると、自分がどんどん精神的な高みにいくのが分かるんだ。シャンデリア、食器戸棚、デッキチェア。なんでも叩き割ったよ。俺が思うに、一つも物を壊したことのないやつの破壊衝動なんてたかが知れてる。破壊衝動ってのは育ててやらなきゃ大きくはならない。そして大きくならなきゃ、その意味には気づけない。人生と一緒だ。大事なのは、とにかくモノを壊し続けるってことさ」
ルーベンスはここで唾を飲み込む。喉がからからなのだ。
「だが、継続にも終焉はくる。あるときだ。留守だと思ってゴルフクラブをいつものようにぶんぶんやっていたら、目の前にその家の主が立ってた。一瞬俺は何が起こったのか分からなかった。迷わずぶった切るべきだったんだろうな。ところが、一瞬判断が鈍った。そしたら、そいつ、ショットガンを俺の腹に撃ちこみやがった。それで、何と言ったかわかるか? 『このショットガンはお前にくれてやる』そう言ったのさ。『ただし、ここから這って帰れ』男は俺をゴルフクラブでさんざんぶち、ショットガンの弾を一つだけ装てんしたショットガンを俺に持たせた。一週間後、俺はソイツをショットガンで撃ち殺した。そのときの気持ち悪さったらなかった。まるで自分が使われた感じだ。面白くもなんともない。俺は明らかにその男に使われた。そのことを思い知ったんだ」
ルーベンスをドキドキした。
ときめきの渦に飲まれ、その麻薬に溺れた。
「今の状況は、あの頃と違う。忍び込んだのが俺なら、ショットガンをぶちこむのも俺さ。そしてお前が俺のただ一つの弾だ」
待った。時が過ぎ、自分の体と、首とが切り離される瞬間を。
そのためにお前はいる。ルーベンスはそれを《庭師》に分からせたはずだった。だが、目をつぶり呼吸をしているにも拘らず、それは来なかった。もっとも、ハサミがルーベンスの体を二分するとき、そのことに自分が気づける自信はなかったが。
Q1:首と体がつながっている間に、あと何回生唾を飲み込むこことができるか?
これはとても面白い問題だ、とルーベンスは思う。これまでルーベンスに殺されたいくつもの命も、消される直前にはこんな風に生唾を無駄に何度も飲み込んだだろう。過去の惨殺の風景は個別のものであるはずなのに、総合的に見れば似たり寄ったりのイメージになる。もちろん、それはルーベンスがそれだけの数をこなしたという意味でもある。
「俺は破壊の対象を人間にシフトした。始末した人間の数を考えれば、戦争をした軍人と同じくらいは殺したことになるかもしれん」
命乞いをするために喋り続けるのか、命があるから喋っているだけなのか、恐らく両方だろう。ルーベンスはまだ客観的に自分を分析できた。圧倒的死の局面であっても客観的でいられる精神を身につけただけでも、四十数年生きてきた甲斐がある。八十点。ルーベンスは自分の人生に点数を下す。決して悪い点数ではない。残りのマイナス二十はリンゴを手にしていないからだ。
「いろいろ話せてよかった。もういいぞ」
ルーベンスは目を閉じ、首が裁断されるのを待った。自分が一本の枝になったように、じっと動かずに。
「なら後ろに手を回してくれ、旦那」
小暮の声だった。後頭部につきつけられた銃口が冷たい。
「ガマガエルか……」
「いいから後ろに手を回すんだよ、旦那。今の俺は北極熊とだってセックスできそうな気分なんだ。あんまりノロノロしてるとケツの穴が3つになるぜ」
ルーベンスは小暮の言うとおりに手を背中に回した。小暮は、その手に慣れた手つきで手錠をかける。
「俺を逮捕して何になる?」
「終わりにするのさ。何十年か続いてきたカーニバルを」
「終わり?」
「そう、エンド・オブ・バイオレンスだ。そして俺は警視総監になる。いい計画だと思わんか?」
「その計画の要は何だ?」
「要? 決まってるだろう、俺がカミさんのところに早く帰れるようになるってことさ。そうすればカミさんに海外ドラマを見せないよう教育しなおすことだって夢じゃない。こんな愉快な話はないだろ?」
ルーベンスは笑った。小暮も笑った。
だが、三秒後に笑っていたのはルーベンスだけだった。
ルーベンスは真っ赤に染まったスーツと少ない髪の毛の後始末のことを考えていた。背後に倒れた首なし死体と、通路に転がったカエルの生首を見やり、それから手錠の鍵を求めて、背中に回された手で、ガマガエルのポケットをまさぐった。だが、鍵はどこにもなかった。
三秒後の世界は分からない。《庭師》の気配も今はもうない。
血腥くも静寂な世界で、鍵を求めてしゃがみこんでいる。
「昨日までは考えられなかった現在に佇む男の肖像」とルーベンスは呟く。
そのとき、聞きなれない電話の音が鳴り響く。素っ気ない電子音。
それは小暮の胸ポケットで鳴っている。
全部で27回鳴ってようやく電話は切れた。
だが、再び鳴り始める。しつこく、繰り返し。
ルーベンスは、室内の突き破られた出窓に近づく。
まだ電話は鳴っている。
その音を聞きながら、ルーベンスは出窓から落下した。
台場第一オペレーションセンター
台場テレフォンサポートセンター内にある台場第一オペレーションセンターには夜勤の人間が三人いて、うち二人は眠っている。ここは、電話回線のトラブルに二十四時間対応するために設置された、電話会社のオペレーションセンターだ。
「電話回線のトラブルについて電話でかけてくるってのもバカらしい話だよな」とコウモリは言う。
「そうでもないさ。人間の葬式は人間が出す」
庵月は答える。
コウモリとは、かつて庵月が消費者金融系のオペレーターをやっていた頃に知り合った。株で一生あっても使いきれない金を稼いでいるため、時間を浪費することを目的にオペレーターを続けているというコウモリとは、時折どちらからともなく連絡を取り合う。
「あと二十分ほどすると見回りが来る。その前には出て行くんだろうな?」
コウモリは、度の強いメガネの向こう側から小さな細い目で庵月を見て言う。
「あまり歓迎されてないらしいな」
「なぜ俺の非番の日を選んでトラブルを起こさないんだ?」
「勘が悪いんだ、だから株もやらない」
「株をやらないから勘が悪いんだ」
「どっちでもいい」
庵月は電話番号を表示してみせる。
「この番号の主が何者なのか教えてもらいたいんだ」
「安い用事だな」
コウモリはPCに番号を打ち込み、顧客検索をかける。
「小金井竜一、1960年生まれ、ルーベンスと呼ばれている。おい、お前ヤバイことに顔突っ込んでるんじゃないだろうな?」
「突っ込んでるのが顔なのか足なのか分からなくて困ってる。だが、とにかく依頼人は死んだ。中国人の娼婦だ」
「死んだ依頼人のために動くなんて、今頃私立探偵だってやらないぜ?」
「それはハードボイルドが死んだせいだ、俺の問題じゃない」
庵月はコウモリを改めて見る。相変わらず血色が悪く、あと二ヶ月で死ぬのだと言われても信じることができそうだ。
「知ってたか? ここは、隠れた国家の生命線なんだぜ。国民全体を監視するなら、全回線を盗聴するのが早いからな。で、その国家の生命線に直接データをもらいに週に一度やってくる男がいる」
「それがルーベンスか」
「ああ。何をやっているのか知らないが、とにかく国家機関に出入りしているわりに、国家の匂いがまるでしないところがどうもな…」
「株で養ったお前の勘が、危険信号を出しているというわけだ」
「省庁というのは、表に出せる国家機関だ。表に出せない国家機関は、公的名称がつかない。そもそも存在自体が闇である必要があるからな」
庵月は、コウモリの言葉を咀嚼する。コウモリが何を言おうとしているのか庵月にはある程度理解できる。暴力の背後には国家がある。だが、それは庵月にとって驚くべき事柄ではない。
「ルーベンスのここ一ヶ月の通話記録を出してもらえないか?」
「プリンターに記録が残るから、見るだけにしてくれるか?」
コウモリはそう言ってキーボードを叩く。
打ち出された画面にはずらりと番号と時間が表示されている。
庵月は、その中から見知った番号を探す。
そこで庵月は、ある番号を目にする。
この三日の間に、その番号から五度も連絡が来ている。
庵月は、自分の携帯電話を取り出す。そこにある電話番号と一致している。
「アニマリック……」
庵月はそう呟く。もう一つ調べてほしいと言いかけたとき、通路を歩いてくる者があった。
「まずい、警備員が来る。しゃがんで出口Bまで走れ」
コウモリは出口のサポートセンター地図を庵月のポケットに入れる。奇妙なことだった。ルーベンスの部下たちも、何かを探していたからこそ大量虐殺に及んだはずだ。それがもしもリンゴを探していたのだとすれば、彼らもまたあの女を追っていることになる。だが、そのボスであるルーベンスは、地下鉄にいたあの女とコンタクトをとっている。
何故だ?
「幸運を祈る」
庵月は、それ以上の調査を諦めて出口Bへ向う。
思ったよりも闇は深く、まだ夜は明けそうにない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
