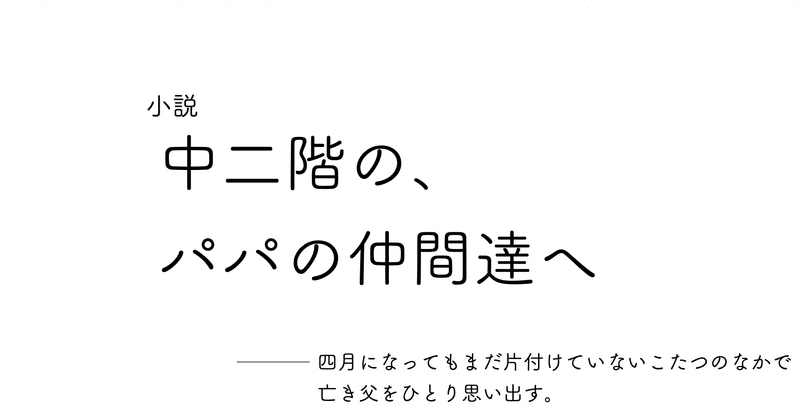
中二階の、パパの仲間達へ
私がここで暮らし始めて早二年となる。
二年前の三月、私の高校入学を目前に死んだ父親は、私と母親という仲の良くない二人を置いてあちらへ行ってしまった。高校入学前ということもあり判が必要であったからしばらくは仕方なく二人で過ごしたが、どうでもいい印鑑という本人確認の慣習につきあわされる事もなくなり学校にも慣れた七月、私が、父親の生前から仲の良かったまだ四十手前の父親の妹、つまりは私の叔母に「母親と別れて暮らしたい」と頼んだのが私の一人暮らしの始まるきっかけだった。
その少し前、世間では新生活を前に自分を変えるきっかけをつかもうとする人らが溢れるその年の春も、本来はその人らにまぎれるつもりだった私にとってはいつにも増して重く苦しいものであった。
父親の葬式は、開ける時にすぽっと音がする筒に入ったあの卒業証書とやら紙切れをもらってから一週間ほどたった後に行われた。やはり世間の浮き足だった雰囲気はとても斎場まではとどかず、私は同級生に一人置いてけぼりを食らったようであった。葬式の次第はともあれ、生前の父に罵声を浴びせ、彼の心をえぐりつづけた母親から発せられる父への感謝の言葉は、七歳の時に冷蔵庫の奥にあった腐りかけのソーセージを食べた時よりも気持ちが悪く、寒気が止まらなかった。それを聞いて泣いている、おそらくは四親等以上の親戚らにはもはや同情の念も浮かばず、ただただあきれただけであった。
葬式屋に母親の素性を少しは話そうとも思ったが、金を払っている―と言うよりも社会的に「払わされている」―のは母親なので、何を言っても取り合ってもらえないだろうと思い、やめた。
その選択は正しかったのだろうが、「鴛鴦夫婦のお別れ会」を演出しようとする葬式屋にもまたあきれずにはいられなかった。
逆に事情を知っている一親等や二親等の親戚らは私と似たような感情を覚えたのか、式中もその後の食事会でも気まずそうにしていた。父方の親戚は、父親の生い立ちについては周りにたくさん聞かせてやっていたものの、その話の中で母親との出会いから先が語られる事はなかった。
そういえば、一連の流れの最後に父が火に入る前、彼の顎の下に横向きの一本の碧色のあざを見つけたが、今思えばそれは彼が何かをしようとした跡なのだったのかもしれない。死因は未だに詳しく聞かされていないが、どんなときでも笑顔を絶やさずにいた彼が一ヶ月の間にみるみる痩せ細っていったのには深い理由があるに違いなかった。二年以上たった今でも死因を隠し通そうとしているように見える母は、やはりこの家族を端から引き裂こうとしていたヴィランなのだろうか。
二年前に越してきたこの部屋にも、一枚だけ家族写真がある。私がまだ二歳の頃、不安も何もなさそうな両親が私を間に挟んで大きな山をバックに写真に映っている。その大きな山はきっと今は無くなり、跡形も無くなっているのだろう。知らず知らずのうちにそんな意味の分からないことを考えてしまいそうになるほど、そこに映る彼らの顔には今では信じられないくらい幸せそうな笑顔が貼り付いていた。それは幼稚園の時に使っていた手で塗るクリーム状ののりなんかではなく、小さい歯磨き粉のケースのようなチューブから出てくる瞬間接着剤で強力に貼り付けられたような正真正銘の笑顔であった。
その写真を眺めながら葬式の事を思い出しているとどうもまたあの寒気がよみがえるようでいけないので、
私はそれを鍵付きのピンク色の小箱に入れた。小さな時から私のそばにあるこの宝箱だが、一人になってからはその写真を除いてほとんど何も入っていない。
それを閉じる時にふわっと私の鼻にやってきた香りは、少しツンとする木とピンク色のペンキのにおいのように感じた。父親が数枚の木の板からこの箱を作ってくれた日のことが思い出されるようだった。
私は四月になってもまだ片付けられずにいるこたつに入って、その上に広がっている書類の山から今度提出するレポートのためのメモを取り出した。背中を自分で光らせる薄気味悪いパソコンも同時に開き、ネタを集め出した。テーマは「死とお金」である。
そういえば、父親の残したものたちはどうなっているのであろうか。
母親は葬式以来父の事に関しては何も手をつけていなかったが、親戚の人がやってくれているのだろうか。
以前、父の古い日記が出てきたことは叔母から聞いたが、結局未だに見られていない。
人の日記を覗き見するのはどうも気が引ける。しかし、もしかすると彼なりの人生の葛藤がみられるかもしれない。もしかすると、彼はそれでも「のほほん」と生きていたのかもしれない。
どちらにせよ、その内容が面白くないはずがない。
何せ彼は、二十年間、ただ原稿用紙に「嘘」を書き続けることを仕事にしていたのだから。世間の中二階で静かに暮らしてきた彼に、それ以上の事が出来たとは思えない。しかし「それだけの事」でも、その紙の上に落ちる幾千の涙とその紙から生まれる幾万の希望が、少なからずこの世界の中二階を生きる彼の仲間達にリビングルームへ行く勇気を与えることができたのだ。
きれい事を並べてリビングルームの方から誘うより、多少表現は劣ろうとも中二階で一緒に楽しい話で盛り上がる時間を作る方が大切なのだと彼は教えてくれた。
そうしてみると、彼が唯一その時間を作る事を忘れていた相手が母なのかもしれない。中二階から無理矢理引きずり下ろそうとした彼女にも非はあるが、そこで彼女を中二階へ誘えなかった彼は、それだけ彼女に惚れ込み、自分の特技も忘れる初々しい彼だったのだと、彼らの映った写真は示してくれている。
<いつからか崩れ始めた二人の間>を取り持てなかった彼の「嘘」も、本当は役に立つものなのだと彼女に教えてあげなくてはいけない。その責任を果たせるのは父が残した私しかないのだと自分でも分かっていた。
そう思った時にはもうこたつから足は出ていた。身支度をして家を出た私はまだ肌寒い春の陽気に少し鼻先を赤くしながら、桜のはなびらが散る川沿いの道を十五年間住んだ「我が家」へ向かって歩き出した。
今度は<中二階へ上がってしまった彼女>との楽しい時間を、私が作る番なのだ。
2020
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
