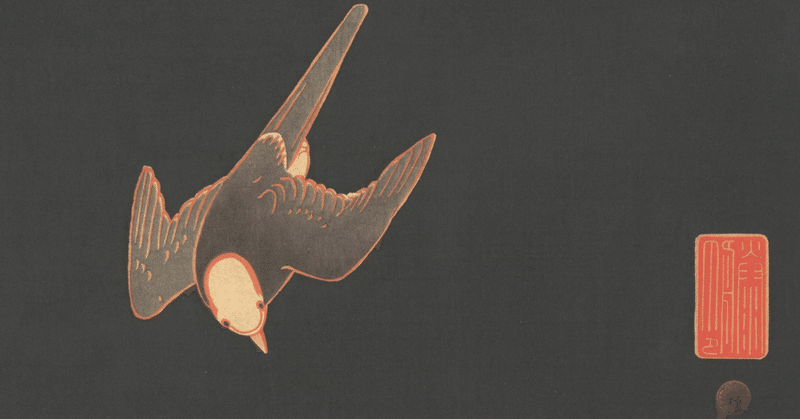
シェアハウスのリビングに飾ってある1枚の絵

この絵、見つけて購入したのは確か20代の半ば頃です。随分長い間、みけ子と共にいました。引越しの度に丁寧に梱包し新居に運びました。部屋に飾っていた時もあったし、どこにも飾る場所が無くて仕舞いっぱなしだった時もありました。
この絵は書画を扱う京都の骨董店の店頭で見つけた額装画です。

着物を纏って藤の花の枝を持ち、踊る若い女性を描いた絵。藤娘なのでしょう。紙本の日本画で、簡略化された線ながら、女性の生き生きした感じや躍動感が表現されています。
この絵は初めて見た時、何か絵から滲み出るような情感が感じられて、一眼で気に入りました。ただ、格式の高い京都の書画骨董のお店です。店頭のウインドウに飾ってある絵が自分に買える値段なのかどうか。(値段は表示してあったのかなぁ?)お店に入るまで何度かお店の前を行き来しました。1週間程の滞在を予定していたので、何度もそのお店の前に行って絵を見ていました。
だけどその絵、みけ子が決定的に「買おう❗️」と思った理由がありました。絵の右端に書かれたサインの名に覚えがあったのです。

絵には「テルヲ作」とサインがありました。あ、知ってるこの人❗️京都画壇で大正から昭和初期にかけて活躍した「秦テルヲ」の描いた絵でした。
みけ子は絵や美術が好きで、履歴書の趣味の欄には「美術鑑賞」と書いていたこともありました。お目当ての美術作品を見るために遠くまで出かけたりも良くありました。中でも大正から昭和初期にかけての日本画が大好きで、当時画集も何冊か持っていました。その中の1冊にあった「秦テルヲ」の名前を覚えていたのです。
大正期は、明治期に西洋から流入してきた文化を受け入れ、その時代における「日本人としてのアイデンティティ」を若い芸術家たちが表現し始めた時代でした。
長い伝統を持つ日本画においても、その若い芸術家たちの表現が西洋文化と混ざり合い、独自の表現となって開花した時代であったのです。
秦テルヲは、絵を志して画家として生涯を終えた人。反骨精神に満ちていて一般受けするような絵はほとんど書いていなかったようです。芸術家として生きるのが難しい時代で、漂泊の末に困窮を極め、亡くなられたようです。
20代の自分は、思い切って格式高そうな京都の美術骨董店に入店し、応対に出て来た店主らしき人に「表に出ている絵が欲しいんですけど」と伝えました。すると「どうぞお好きな物をよって(選んで)下さい」との返答が。店頭には額装されていない、古い日本画が1枚1,000円程度で箱に沢山重ねられていました。店主はその絵の事を言ったのです。「いえ、それではなくて額装されている、あの絵なんですが」そう伝えて、旅行中なので家まで送って欲しいと言う事も申し添えました。
店主はちょっと驚いた風でしたが、東北の仙台から来た事を聞いても、送料は結構です、との事。確か値段は5万円ほどだったと思います。自分にとっては当時は少し思い切らないと払えない金額でした。(いえ、現在もです)でもその時の自分には何故か買わない、という選択肢はなかったんです。そうしてこの絵は自分の所有になりました。
現代でさえ芸術家として生きて行くのは簡単ではありません。それなのに大正〜昭和の激動の時代、そして戦争へ突入せんとしている時。自分の信じる絵を描き、芸術を貫き通す難しさを思います。彼はかなりの個性派画家で、市井の地を這うようにしていて生きていた人々をモチーフにすることが多かったみたいです。
この絵には「テルヲ」の名前の下に「漂」の文字が書き加えられています。「漂泊」の漂です。時代に翻弄され、画家として生きる自分をどのように見ていたのでしょうか。1枚の絵からさまざまな事を考えてしまいます。
縁があって自分の所有になった1枚の絵。個性派の秦テルヲの絵にしては「藤娘」と言う踊りや絵の題材としてはよく見られる、一般受けするものです。誰かの発注によって描かれたものなのでしょうか。もっと彼の描いた絵を見てみたいと思います。こんな風に絵を見つめながら、あれこれと思考を巡らしたり意識を宇宙の彼方に(笑)飛ばしたりするのが、自分なりのリラックス法の一つだったりします。
古い日本家屋のリビングの一角に飾られた1枚の絵。飾られるに相応しい場所を得て輝きを増したような気がします。
↓1枚の絵を飾るだけで、部屋の雰囲気が一変することがあります。木馬に乗った騎士を形どった玩具の版画。川上澄生の作品です。愛らしく素朴な雰囲気で見るものを和ませます。
サポートをいただけるならば、それはそれは大感激です❣️毎日発信を続けることが、自分の基礎トレーニングだと思っています。サポートを励みに発信を続けます💓
