
江戸と東京をめぐる無駄話#03/立農主義の物理的限界
徳川幕府は対為す二つの両輪で回っていました。
前両輪が、天下普請と参勤交代制という公共事業です。この二つが経済の循環をもたらしていた。
後両輪が、米本位制度と全国共通通貨による貨幣経済です。稲作をコアとした立農国家とし、その流通の支えとして貨幣を用いた。
これが徳川幕府です。
立農を確立するために「農民」なる地位を固定したのは織田信長/豊臣秀吉です。平安時代以降、自然発生的に生まれた「武器を持つ武士」なる人々は「農民」と混然一体化していた。源氏も平氏も根本は農民です。
こうした「武装する農民」は中央集権化が進むと、著しく天下統一を阻害していたのです。なので織田信長/豊臣秀吉は、基本政策の一つとして「農民の非武装化」を取りました。彼らは、農家が武装しなくてもよい立農制の確立を目指したのです。それが小農自立政策です。「太閤検地」と呼ばれるものです。
「太閤検地」以前の農家は「惣村」という集団でまとまっていて「惣村請」という形で領主に年貢を払っていました。
なぜそんな形を取っていたかというと、年貢を徴収する「領主」なるものが単一でない場合が多々あったからです。もちろん「惣村」がそれを歓迎していたわけはない。否応なしだった。その否応なしにパワーバランスをもたらすために「惣村」は武装化するしかなかったのです。
「天下統一をした」豊臣秀吉は、こうした複数領主に年貢を納めるという行為を是正することで小農自立を可能にし「惣村」の武装解除と農業に専念出来る体制を目指したのです。所謂「自作農撫育/年貢皆済」です。農民が夫婦単位の単婚小家族で自作農を行い生活できる体制の確立です。歴史の本で「小農」と言われるものですね。これを目指した。そして武装自営しなくていい理由として、自作農化が不作凶作などで困窮した場合、直該領主が「御救(おすくい)」を行うという体制です。複数領主による搾取「やらずぶったくり」が起きない体制を作ろうとしました。
徳川家康はこれをそのまま踏襲し「自作農撫育/年貢皆済」をベースとした「幕藩体制」を確立した。
すなわちこれは徳川家を頂点として日本を/土地を分割し、夫々を徳川直領地、部下である大名/旗本/公家/社寺などが支配するという体制です。この幕藩体制によって、徳川家は農家の完全管理を目指し、稲作をベースとした立農国家の確立を可能にした。これが徳川幕府の長期安定をもたらしたのです。
しかし・・この経営方法は抜本的な問題を抱えていた。はじめは表面化しなかった抜本的な問題です。
それは日本国が四海に囲まれた限られた広さしかない・・という問題です。
同じような立農国家はチグリス・ユーフラテスにもエジプトにも、イタリア半島ポー平原(ローマ帝国)にも中原(中華)にも誕生しています。しかし彼らは物理的に閉ざされていなかった。したがって常に拡大していくという道へ進めた。拡大していくことで、次第に生まれる内部矛盾を抑え込んでいけたのです。日本国は・・徳川幕府は、それが出来ませんでした。
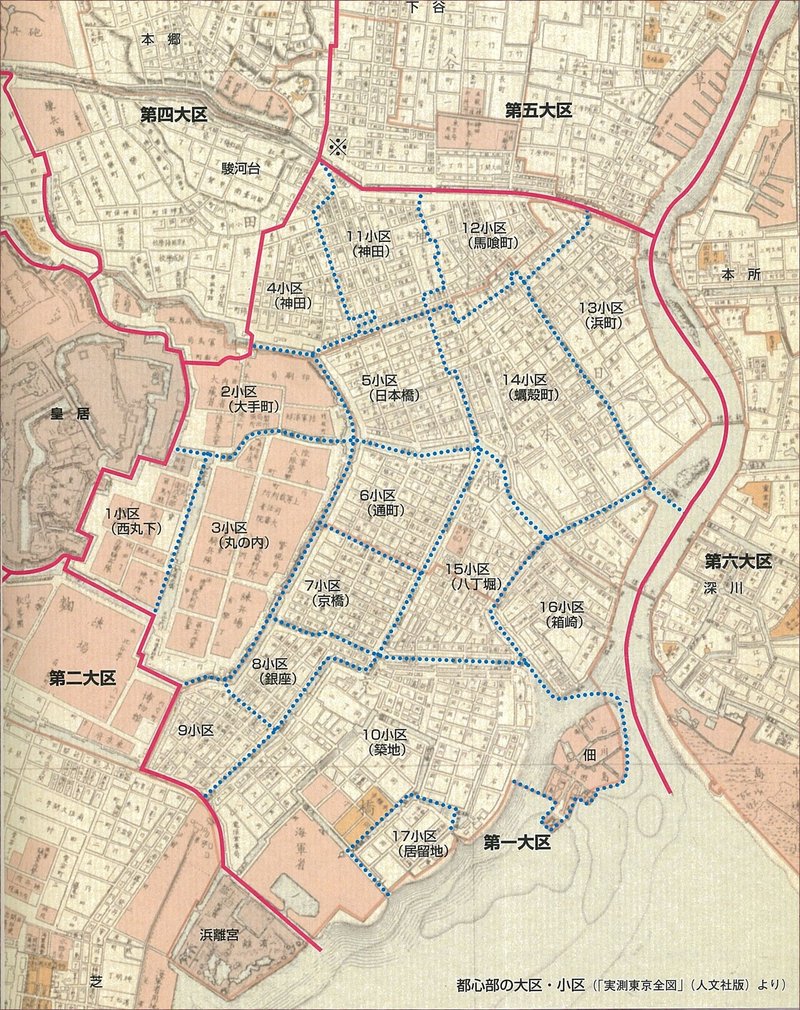
無くてもいいような話ばかりなんですが・・知ってると少しはタメになるようなことを綴ってみました
